
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
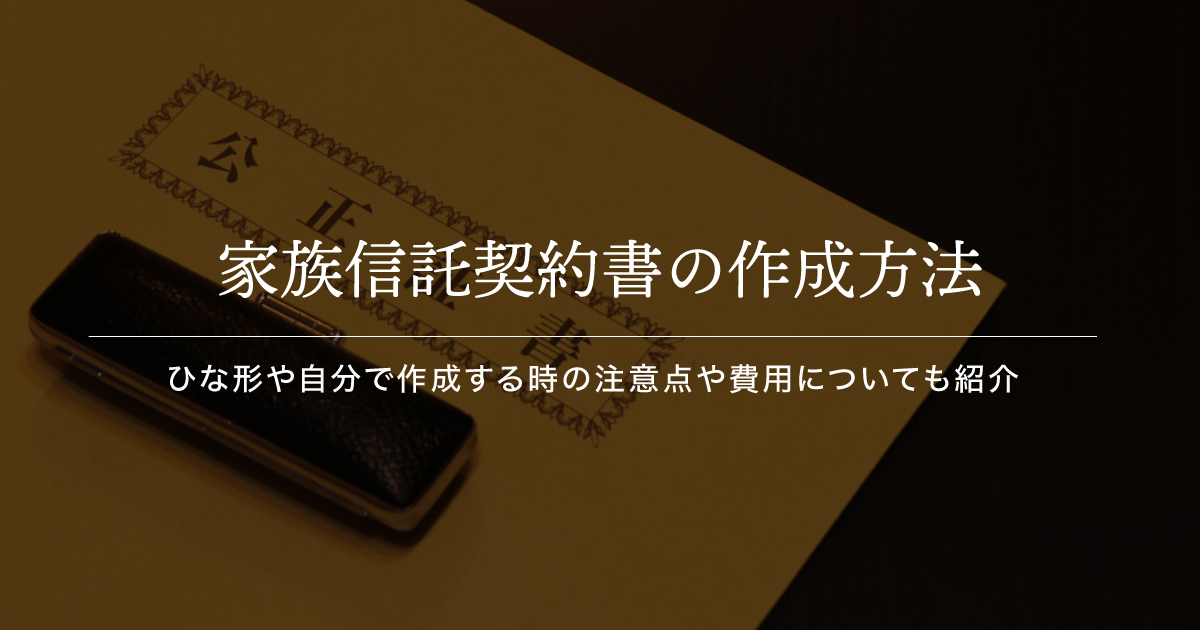
家族信託は老後の有益な財産管理方法として注目されていますが、活用にあたっては家族信託契約書を作成しなければなりません。
そこで、本記事では家族信託の基本知識を解説しながら、契約書を作成する場合の手順や注意事項、メリット・デメリットなどを解説します。
家族信託契約書の作成を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリット、必要性についてわかりやすく解説

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

家族信託は、書面の契約書がなくても家族間の取り決めだけで実行できます。しかし、口約束だけでは将来トラブルになる可能性は大きくなります。
家族信託では、契約内容を公的に証明するために契約書の作成が必要です。契約書は自分で作成できますが、将来のトラブルを防ぐためにも専門家に依頼することをおすすめします。
また、家族信託の専用口座を開設する場合にも、家族信託の詳細を明記した契約書を公正証書で作成したものの提出が必要になるでしょう。

前述した通り、家族信託の契約書作成は、自分で行うのではなく専門家に依頼することが望ましいです。
その際、あらかじめ契約書に記載される項目について理解を深め、事前に情報を整理しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
ここでは、家族信託の契約書には一般的にどのようなことが記載されるのか、項目別にご紹介します。
なお、ここで触れていない契約書に書くべき具体的な内容についてはご家族の状況ごとに異なるため、専門家に相談する際に併せて確認するようにしてください。
契約書ではまず、契約の当事者が誰であるかを最初に明記します。
先に述べたように、家族信託の契約は基本的に委託者と受託者の二者間の契約です。契約書の冒頭で「委託者と受託者がそれぞれ誰であるか」といった形でフルネームが記載されます。
例えば「委託者 ●●●● 及び受託者 ■■■■ は、本日以下のとおり信託契約を締結する」のような記述です。
信託の目的とは「信託の設定によって達成しようとする基本的な目的」のことです。委託者はこれを自由に定めることができます。
信託の目的は、信託において一番大事な部分といっても過言ではありません。受託者の信託事務処理の指針になったり、信託契約を変更する際の限界を画する役割があります。
信託目的は委託者が自由に決められるため、信託契約ごとに異なります。例えば以下のような事項が記載されます。
他にも、不動産の管理が目的の場合には「委託者の不動産を管理し、収益を受益者の生活に必要な資金として分配するため」などと書かれることもあります。原案を作成する際には、受託者に確認しつつ事前に考えておくようにしましょう。
信託の対象とする「信託財産」を特定します。
家族信託では、委託者の財産の全てを信託する必要はありません。どの範囲の財産を信託するかは、委託者が自由に設定できます。
このとき「何が信託財産であるか」きちんと特定ができるような記載をしなければなりません。信託財産がたくさんある場合には、信託財産目録として紙にまとめておくと良いでしょう。
特に信託財産に不動産が含まれる場合には、登記上表示を正確に特定しておく必要があります。
あらかじめ法務局で登記事項証明書を取得しておくようにしましょう。
受託者は契約書の冒頭にも記載しますが、本文の条項にも明記されます。記載事項は住所、氏名、生年月日など当事者を特定する情報が必要になります。これは受益者についても同様です。
また、当初の受益者が死亡した場合に、別の人が受益権を引き継ぐ「受益者連続型信託」の設定も可能です。そのため、この信託を検討している場合には、二次受益者となる人の住所、氏名、生年月日も調べておきましょう。
なお、受益者連続型信託では、三次受益者以降を指定することもできます。ただし、信託設定後30年経過した時点における、受益者が指定した次の受益者が最終の受益者となる期間制限があります。
家族信託では、信託財産の管理方法や信託財産から得られた利益の扱いについて、委託者が自由に定めることができます。
受託者は、家族信託の契約書に記載されたこれらの内容に基づき、財産の管理などを行います。
以下のような事項を記載することが一般的です。
信託の目的を達成する上で非常に重要な項目となります。事前に家族で話し合いながら、受託者にどのような権限を持たせるのかを明確にできるようにしましょう。
信託法149条1項に定められているとおり、信託契約は関係当事者の合意で変更できるように設定することも可能です。
また、終了時の手続きについても定めた方が良いため、あらかじめ考えておくようにしましょう。
信託の終了事由については信託法163条に定められていますが、これと異なる内容を家族信託の契約内で定めることも可能です。
信託終了時の残余財産の帰属先についても指定します。
家族信託では、信託終了時に残った信託財産の帰属先も事前に定めておくことができます。
信託終了時の受益者を帰属権利者にしてもかまいませんし、信託財産が複数ある場合には、それぞれの財産について帰属先を別に定めることも可能です。
なお、残余財産の帰属権利者の決め方によっては税金がかかることがあるので、注意しておかなければなりません。
例えば、受益者と委託者が同一のケースで、受益者が生存している間に信託が終了した場合、受益者以外の人に残余財産を帰属させると贈与税がかかってしまいます。

家族信託の契約書は雛形などを利用して自分で作成できます。
しかし、信託財産の管理・運用方法については指定できるものの、家族に託した後に起こるトラブルを想定することは、専門家でも難しいのが現状です。
家族信託の契約書は、法的に有効である、税務上の問題がない、契約書の不備がない、など高度な専門的な知識が必要になるため、専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の契約書は専門家に依頼するのが一般的ですが、自分で契約書を作成する場合は、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
まずは、家族信託の契約書を自分で作成するメリットから見ていきましょう。
契約書を自分で作成するメリットは、費用がかからないことです。契約書の雛形などを利用すれば、基本的に契約書の作成は無料です。
契約書の作成を専門家に依頼すると、一般的に10万円前後の料金がかかります。その他、事前に相談料や着手金などの諸経費がかかる場合もあるでしょう。
契約書を変更する場合にも、自分で作成した契約書であれば随時無料で変更が可能ですが、専門家に依頼する場合は、変更する度に費用がかかることもあります。
家族信託の契約書を自分で作成する2つめのメリットは、外部に財産やその他の個人情報が流出しないことです。
家族信託を契約することを知らせたくない家族には、知らせないままで契約書を作成することもできるので、委託者にとっては好都合といえるでしょう。
また、専門家に依頼すると、家族信託の設計のために信託財産に関連する情報を詳細に伝えることが必要になりますが、自分で契約書を作成すればこうした手間も省けます。
次に、家族信託の契約書を自分で作成するデメリットについて見ていきます。
家族信託では、あらかじめ信託財産の内容や管理・運用方法などの設計が必要です。契約書を自分で作成すると、設計に含まれていない財産などが出てくる可能性があります。
契約書に記載のない財産をめぐって相続人の間で争いが生じたり、信託の終了時の残余財産の帰属先がわからずに家族間で揉めることにもなりかねません。
家族信託の契約書には、特定した信託財産、信託財産の管理方法、信託の開始から終了、残残余財産の帰属先などを詳細に漏らさず記載することが重要です。
家族信託では、信託財産と受託者個人の財産を分けて管理するために、金融機関で専用の口座(信託口口座)を開設する必要があります。
信託口口座を開設するためには、専門家が作成した法的にも有効な契約書の提出を求められることが多いです。自分で作成した契約書では、信託口口座を作成できない可能性が高いでしょう。
そのため、受託者名義の信託金銭管理用の口座を開設する必要があります。
家族信託の契約書では、信託財産の設計内容を適切に法的に表現することが必須である他、契約の内容が信託法に違反しないことが重要になります。
信託法など法的知識や経験がないまま契約書を作成すると、記載内容が曖昧で契約の効力が発生しない、あるいは信託法に違反して契約自体が無効になってしまうこともあるのです。
信託法では「受託者連続型信託」の設定をした場合、設定後30年もの長期間効力が持続します。契約書の作成は専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の契約書は、公正証書で作成することが一般的とされています。 公正証書とは公証人に依頼して、公文書として作成してもらう書類のことです。契約書を公正証書にすることで、より証明力の高い文書となります。
ここでは、家族信託の契約書を公正証書で作成するメリットや公正証書にする方法、実際にかかる費用などを解説します。
家族信託の契約書を公正証書にした方が良い理由は、以下のような点が挙げられます。
契約書を公正証書にするときには、公証人が立ち会い当事者の本人確認や意思確認を行います。
「契約書に記載された日付時点で、当事者双方の合意があった」という証拠になるため、契約の有効性を疑われるような事態を防止できます。
公正証書の原本は「公文書」として公証役場で20年は保管されます。
仮に手元にあるものを紛失してしまった場合でも、謄本を再発行してもらえるため、契約書の中身を第三者の手によって偽造・改ざんされるおそれもありません。
公証人は法務大臣に任命された法律知識のある専門家です。
公正証書作成時には契約書の読み合わせをするなど、一項ずつ内容を確認してもらえるので、契約書の不備により、信託が無効になる可能性は低いといえます。
信託財産は、委託者や受託者固有の財産と区別して管理する必要があります。金銭を信託する場合には、家族信託専用の信託口口座を開設しなければなりませんが、その開設の際に公正証書での信託契約書の作成が条件となることがあります。
公正証書を作成する際は、公証人と契約内容に関する事前打ち合わせを行う必要があります。 そのため、あらかじめ信託財産に関する資料(不動産の登記事項証明書など)を提出し、専門家と相談の上、公正証書に書く内容も決めておきましょう。
公証人との間で内容の確認が取れたら、契約締結の日時を予約して、契約の当事者全員で公証役場に出向きます。
そこで当事者の意思確認や契約内容の読み合わせなどを行い、問題がなければ当事者と交渉人が書類に署名押印するという流れになります。
なお、公正証書作成当日には、運転免許証などの本人確認書類と認印(または印鑑証明書と実印)を持参する必要があるので注意しましょう。
公証役場は全国に約300か所設けられており、基本的には近くの公証役場に依頼します。病気などで公証役場に出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。
このテンプレートは基本構成に基づいていますが、実際の契約に使用する際は、司法書士や信託専門家に必ずご相談ください。

家族信託は契約内容を自由に決めることができますが、契約する上で注意しなければならない点があります。
家族信託の契約は、委託者が意思能力を喪失した後では組成することができません。意思能力がない人が締結した契約は無効になってしまうためです。
利用を検討している方は、認知症などになり手遅れになる前に、早めに契約手続きを進めると良いでしょう。
家族信託の契約では、財産管理に関することしか定められません。成年後見制度のように身上保護権が与えられていないのです。
身上保護とは、 本人の生活を維持するための仕事や療養看護に関する契約などのことです。
そのため、本人の認知症発症後に、家族に介護施設に入所する契約や入院に関する手続きなどを任せたい場合には、別途任意後見契約を結ぶ必要があります。
家族信託には、直接の節税効果はありません。
委託者と受益者が同一でない場合、贈与があったものとして受益者に贈与税が課税され、納税の義務が発生します。また、遺留分侵害額請求を免れることもできません。

家族信託を契約すると、実際にどのようなケースで役に立つのでしょうか。 ここでは、家族信託の活用例を契約内容と共にみてみましょう。
老齢で、将来自分で生活費などのお金の管理ができるか心配な場合は、家族信託が有用です。
上記のように家族信託の契約を締結しておくことで、自身に万が一のことがあった場合でも、家族が代わりに預金を管理し、生活費や医療費などを支出できるようになります。
障がいのある子どもがいる家庭では、多くの場合「親が亡くなった後に誰が子どもの面倒を見るのか」という不安を抱えているでしょう。
上記のような形で家族信託の契約を締結すれば、自分が生きているうちは自分のために、自分の死後は子どものために財産を使ってもらうことができます。
自社株のほとんどを持っている中小企業のオーナーが子どもに事業を引き継ぎたいといった場合も、家族信託の活用がおすすめです。
こうすることで後継者にスムーズに事業継承ができ、さらにオーナーが元気な間は自分に経営権を残し、実質的なオーナーの地位を維持することも可能です。
不動産を親子共有名義で所有している場合、家族信託を活用することでトラブルを未然に防ぐことができます。
通常、共有名義の不動産を全部売却するには共有者全員の同意が必要となります。もし、親が認知症などで意思能力が低下してしまうと、不動産の管理や処分をすることが難しくなってしまいます。
その場合、以下の内容で信託をすることで、管理・処分は受託者1人の権限で行うことができるようになります。不動産の処分について委託者の認知症などの影響を受けることはありません。

家族信託の契約書の依頼先は、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などの士業がありますが、それぞれに対応できる領域が異なるため注意が必要です。
税理士は、税務処理を専門としていますが法律全般の専門家ではありません。家族信託の法務に対応しづらい場合もあるでしょう。
行政書士は、契約書などの書類作成ができます。ただし、法務局で契約書の登記はできませんし、紛争には関与できません。
司法書士は、登記申請を専業とし契約書の作成も可能です。信託財産に不動産がある場合は適任でしょう。
弁護士は、法律業務全般を行うことができます。契約書の作成から登記、また紛争になった場合には裁判まで対応が可能です。
これらの士業の中から、家族信託に精通した専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の契約書を自分で作成する場合と専門家に依頼する場合では、費用が異なります。それぞれの費用を見ていきましょう。
自分で家族信託の契約を作成する場合には、以下の費用がかかります。
自分で契約書を作成すれば費用は無料ですが、必要書類を取得する際の費用がかかります。
戸籍謄本または抄本は一通450円、固定資産税評価証明書は一通300円、登記事項証明書は一通600円、印鑑証明書は一通450円です。これらの必要書類は、家族信託の内容や信託目的によりそれぞれ異なるため注意が必要です。
公正証書を作成する際には、信託の対象とする財産の価額に応じた公証人手数料がかかります。
公証人手数料の額は公証人手数料令で決まっており、全国どこの公証役場でも共通です。公証人手数料の額は、具体的には次のように定められています。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
| 3億円超10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
| 10億円超 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
なお、上記の金額の他、公正証書の枚数に応じた謄本手数料などの手数料がかかることがあります。
信託財産に不動産がある場合は、契約書を作成した後に不動産の信託登記を行わなければなりません。
信託登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.3%〜0.4%です。固定資産評価額が高くなれば、信託登記の登録免許税も高額になります。登録免許税がいくらなのか心配な方は、事前に調査しておくことをおすすめします。
専門家に依頼した場合の報酬基準は、家族信託の目的や信託財産により大きく異なりますが、主に以下の費用がかかります。
家族信託契約書の作成を専門家に依頼した場合、専門家の種類により報酬料が異なります。信託財産に不動産があると100万円以上の費用がかかることもあるでしょう。
ただし、コンサルティング料は契約書作成時のみならず、作成後のサポートも含まれる場合もあります。事前に専門家に確認しましょう。
契約書の作成を専門家に依頼した場合でも、信託財産に不動産があれば、契約書の作成後に信託登記を行わなければなりません。
信託登記の登録免許税の他に登記手数料の費用がかかります。信託登記報酬の相場は、約11〜16.5万円とされています。報酬基準は異なりますのでやはり事前の確認が必要です。

では家族信託の契約書作成を専門家に依頼すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
まずは、家族信託の契約書を専門家に依頼するメリットについて見ていきましょう。
家族信託の契約書は、信託財産や家族構成、親族間のトラブルなどを想定して作成する必要があり、自分で作成するには大きな負担がかかります。
専門家に契約書作成を依頼するメリットは、それぞれに応じた適切な信託設計のアドバイスを受けながら、契約内容に不備や誤りのない契約書を作成できることです。
家族信託に精通した専門家からサポートを受けることで、将来のトラブルを回避することもできるでしょう。
家族信託の契約書は、作成して保管しておけば終了するわけではありません。契約書を作成した後にも、様々な手続きが必要になります。
例えば、信託財産が不動産であれば、契約書の作成後に不動産の名義変更をしなければなりません。金銭であれば、信託口口座の開設が必要になります。
家族信託の契約書作成を専門家に依頼すれば、契約書作成後にも様々な手続きや相談に対応してもらえます。また、より良い信託設計を提案してくれることもあります。
次に、契約書の作成を専門家に依頼するデメリットについてみていきましょう。
専門家に契約書の作成を依頼すれば、報酬などの費用がかかります。
専門家により報酬の基準も変わりますが、信託財産の1%程度を報酬として設定しているのが一般的です。報酬の下限を30万円としている専門家も多いことから、30〜100万円の費用が相場といわれています。
専門家も士業の種類や精通している分野により様々ですが、家族信託の内容に適した専門家を選ぶには、事前にリサーチをする必要があります。
信頼できる専門家を探すには、時間や手間がかかることもデメリットとなるでしょう。初回のみ無料で相談できる専門家もいるので、まずは相談してみることをおすすめします。

家族信託の契約書は自分でも作ることができます。
しかし、専門的な知識が必要であり、法的に要求される要件を満たすことが必要です。そのため、自分で作成することはおすすめできません。
家族信託契約書には、信託目的、信託財産、信託受益者等等、重要な条項が含まれています。 これらの条項を適切に記載し、信託契約書が法的に有効であることを確認するためには、弁護士などの専門家に相談することが必要です。
家族信託の公正証書化には、専門的な知識や経験が必要であり、自分で行うことはできません。
公証人によって行われる手続きです。公正証書化には、公証人に対して、家族信託契約書の内容を確認し、署名や印鑑押印などを行ってもらう必要があります。 公証人は、法律や条令に基づいて業務を行う公的機関であり、信託の公正証書化に関する専門的な知識を持っています。
公証人に依頼することで、公的な証明力を持つ信託契約書を作成することができます。
家族信託の変更は、原則的には委託者、受託者および受益者の合意によって行えます。ただし、信託内容の変更は受益者の判断能力がなくなるとできなくなるため注意が必要です。
あらかじめ受益者の判断能力がなくなった時にも、成年後見人と受託者で信託の変更ができる、など具体的な対応策を条項に入れておくことをおすすめします。
家族信託では信託期間の制限がないため、契約書を作成する場合でも有効期限はありません。ただし、何代も先の受益権者を指定できる「受託者連続型信託」を活用する場合には、30年経過後の最後の受益者で契約が終了する「30年ルール」があるため注意が必要です。
契約書作成には専門家のサポートを受けることをおすすめします。

家族信託は老後の財産管理を行うための最適な方法として浸透し始め、自分で契約書を作成しようか検討している人も多くなりました。しかし、信託契約書は高度な専門知識を必要とするため、専門家に依頼して作成することを強くおすすめします。
ファミトラでは、家族信託の相談をいつでもお受けしています。お気軽にご相談ください。

田中 総
(たなか そう)
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

田中 総
家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。