
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

信託財産とは家族信託において、信託目的に沿って受益者のために管理・運用・処分などを行う財産です。
本記事では、信託財産のルールや具体例と注意点を解説します。本記事を読むと、家族信託の信託財産とは何かがわかるようになります。
信託できる財産とできない財産の具体例と注意点についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

家族信託とは、ある人が自分の所有する財産の全部あるいは一部を信頼できる人に託して、託された人は財産を一定の目的に従って管理処分し、その運用利益を特定の人が受け取る仕組みです。
託された財産は託された人の名義になり、元の所有者の財産と切り離されます。
これを信託財産といい、不動産・現金・株式などが主なものです。
財産を託す人を委託者、財産の名義人となり運用する人を受託者、託された財産から利益を受け取る人を受益者といいます。
それぞれ以下で詳しく解説します。
財産の所有者で財産を信託し、信託の設定をする人です。
委託者は、信託の目的・信託の期間・受託者・受益者を決め、自分の所有する財産を受託者の名義に移します。
委託者になるのに特に資格は必要ありませんが、家族信託は契約であるため判断能力があることが前提です。
受託者は、委任者から委託された財産の運用管理をする人です。
受託者は、財産の管理をする際に信託の目的に従う必要があります。
家族信託という名称ではあるものの、受託者には家族以外の第三者でもなることでき、個人ではなく法人でも構いません。
法的な資格は特にありませんが、未成年者は欠格事由に該当するため受託者になれません。
また、業として受託者になるには官庁の許可が必要になります。
受益者は、信託された財産から生み出された利益を享受する人です。
受益者が持つ信託財産から生み出される利益を受ける権利を受益権といいます。
受益者に特に資格はなく、委託者自身、委託者以外の人、株式会社等の法人、権利能力なき社団等が受託者になることができます。
また、胎児や現在存在しない子や孫でも受益者になることができます。
受益者は複数人でもよく、受益権を順次承継させることも可能です。

家族信託における「信託財産」とは、文字通り信託する財産のことです。
信託財産の内容は信託契約によって決められるため、必ずしも全ての財産が信託財産になるわけではありません。
信託財産は受託者名義になりますが、受託者自身の財産になるわけではありません。そのため、受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する必要があります。
信託法第2条第3項では「信託財産は受託者に属する財産で信託によって管理・処分すべき一切の財産」である旨が規定されています。
以下では、信託財産の範囲の明確化の必要性と、登記手続きの必要性について解説します。
信託の設定時には、何が信託財産になるのかを明確に特定しておく必要があります。
信託財産が多い場合には、信託財産目録を作成することで信託財産の範囲が明らかになり比較的容易に信託契約書の作成が可能です。
信託法第14条では「信託の登記をしなければ財産が信託財産に属することを第三者に対抗できない」旨の対抗要件が規定されています。
信託設定の登記をすることで、信託された不動産を受託者が第三者との関係においても運用・管理することが可能になります。
また、信託財産が不動産であれば、信託設定の登記をすることは受託者の分別管理義務の内容にもなっているため登記手続きは必要です。
信託契約締結後に新たに追加したい信託財産が生じれば、委託者と受託者の合意があれば追加が可能です。
追加したい信託財産が金銭であれば、信託契約書に金銭の追加信託の条文を加えた変更契約を両者の合意により行うことで追加できます。
事前に金銭の追加を想定している場合には、信託契約に両者が合意すれば信託財産の追加が可能との条文があれば信託契約書の変更手続きは不要です。
不動産を追加したい場合には、信託契約書を変更するとともに信託設定の登記が必要になるため注意しましょう。

家族信託では、基本的に財産的価値のあるものは信託財産にすることが可能です。
ここでは、信託財産にできるものについて具体例を挙げて解説します。
現金は、信託財産として活用される代表的なものの1つです。
現金を信託財産としておくと、委託者が認知症などにより判断能力が低下した後も介護費用などとして柔軟に活用できます。
現金が信託財産となっていない状態で委託者が認知症になると、信託された不動産に発生する税金など、信託に関連した支出が必要な場合に支払いができなくなります。
家族信託の利用に際しては、現金を信託財産にしておくことは有効な方法です。
土地・建物などの不動産も信託財産として活用される代表的なものの1つです。
特に収益不動産などを所有している場合は、長年にわたり管理・運用を続けていくのは容易なことではありません。
不動産を信託財産として受託者に管理させることで、委託者の判断能力が低下した後でも、賃料の回収や建物の修繕などを行うことができます。
株式や国債などの有価証券も、家族信託の信託財産にできます。
ただし、後述するように、上場株式を信託財産にするのは実務上難しいため、株式は非上場株式に限ります。
委託者の有する債権も信託財産となります。
家族信託でクレジット債権が信託財産となることはほとんど考えられませんが、個人で金銭の貸し付けをしている場合には、貸付債権を信託財産とすることが可能です。
貸付債権の返済が長期にわたる場合などは、信託財産とすることで返済中に委託者の判断能力が低下してしまったとしても、受託者が債権の請求をすることができます。
委託者が発明品の特許権や小説などの著作権を有している場合には、信託財産として受託者に管理・運用を任せることもできます。
特許権者や著作権者は、侵害行為があると適切な対応を取らなければなりません。信託財産とすることで、受託者が侵害行為への対応などを行えるようになります。
宝石や絵画、車、ペットなどの動産も信託財産にできます。
ただし、現在の実務では管理の問題もあり、動産を信託財産とする例は少ないです。
信託財産として活用されることが多いのは、現金、不動産、上場していない株式の3種類です。それ以外の活用例は多くありません。
今後、実務での運用が続くことで、動産の活用例も増えていくことが考えられるでしょう。
信託財産とすることは法律上は禁止されていませんが、実務上信託が困難な財産に、上場株式と農地があります。
上場株式は証券会社が家族信託に対応しておらず、事実上信託財産とするのが困難です。
上場株式は証券会社を通して取引を行いますが、証券会社によっては受託者の注文を受け付けることができない場合があります。
前述のとおり、土地は信託財産とすることができますが、登記地目が田や畑、あるいは現況が農地の場合は信託財産にすることは難しいといえます。
農地(田や畑など)は原則として農業委員会の許可がない場合には、贈与や売買ができず信託財産にできないためです。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
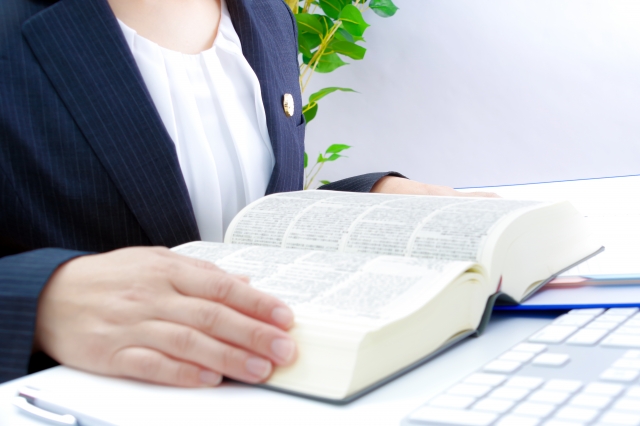
法律上では、信託財産とできるものに制限はありません。
しかし、財産的価値のないもの、財産的価値で評価できないものは信託財産とすることはできません。
個人の生命・名誉は、財産的価値で評価することはできないため、信託財産とすることはできません。
委託者の生命や名誉について、受託者が管理・運用するなど考えられないので、当然のことといえるでしょう。
借金や保証債務など、マイナスの財産については、財産的価値がないため信託財産とすることはできません。
年金の受給権など、委託者の一身に専属する権利についても信託財産とすることはできません。
つまり、受託者が委託者に代わって年金の受取人となることはできません。

家族信託では、「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者がそれぞれの役割を果たします。
以下では、それぞれの権利について解説します。
家族信託契約を締結すると、信託財産の管理・運用・処分権は信託契約に規定された範囲で受託者に移ります。
受託者は委託者が定めた範囲内において、上記の権利を行使することが可能です。
信託財産から生じた収益は、受益権を有する受益者のものです。
収益不動産の賃料や売却代金、信託された金銭などから生じた収益は受益者のものになります。
なお、基本的には、資産の所有者であった委託者が受益者を兼ねることが多いです。
信託財産で受託者が取得する所有権は、一般的な所有権の獲得を意味するものではありません。
一般的な所有権は、自由に所有物の使用・収益・処分をする権利であり、その権利を行使して得た収益は所有者のものです。
しかし、家族信託の受託者は、家族信託の目的に沿って権利を行使する必要があり、また権利行使によって得られた利益は受益者のものになります。

家族信託を検討するに際して、どの財産を信託財産とするのかは重要な問題です。
同じ不動産であっても家族が置かれた状況によって、信託財産とすべきか否かは異なります。
ここでは、信託財産として検討すべき財産の具体例を紹介します。
委託者が1人暮らしをしている場合、認知症などで施設に入所することになれば、現在の家は空き家となってしまいます。
この場合に家を管理・処分する権利のある人がいなければ、家を売ったり、貸したりすることができず、空き家のまま放置することになってしまいます。
さらには、空き家の管理費用の立て替えを迫られる可能性もあるでしょう。
委託者が元気で判断能力も正常なうちに信託財産としておけば、いざという時には、受託者が家を管理・処分できるため安心です。
自宅を売却することができれば、委託者が施設に入る際の費用をねん出することができるかもしれません。
相続人が複数いる場合には、相続によって不動産が共有となる可能性があります。
不動産が共有となると、売却や賃貸には共有者の同意が必要となるため、管理・処分が難しくなります。その結果、意見の異なる共有者間でトラブルとなることも多いです。
家族信託を利用すれば、不動産を信託財産として1人の相続人に管理・処分を任せることができます。
受託者は、他の相続人の意見に左右されることなく不動産の管理・処分を行うことが可能です。
また、信託終了時には特定の者に財産を承継させることとすれば、共有の問題を未然に防ぐことができます。
ただし、相続人のうち1人を受託者とする場合には、他の相続人を予備的な受託者とするなど、他の相続人が不満を持たないよう配慮する必要があるでしょう。
相続の対象となった不動産は、相続人が自由に売却できます。
家族信託では土地を信託財産としながらも、受託者に土地の売却権限を与えないことが可能です。
この仕組みを利用することで、受託者は土地を相続しても売却することができなくなります。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

実際に家族信託を開始するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、家族信託で財産を家族に託す場合の手続きの流れを解説します。
家族信託は、委託者、受託者、受益者のみの話し合いで内容を決められます。
しかし、家族信託を開始するにあたっては、当事者とならない家族も含めて話し合うことが重要です。
法律上は問題のない手続きであっても、話し合いに参加していない家族がいると、後になってトラブルとなる可能性があります。
家族信託の内容について、できる限り家族全員の合意を得ることが手続きのスタートです。
話し合いで家族信託の内容が決まったら、信託契約書を作成します。
信託契約書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けるべきです。
家族信託は歴史も浅く、市販の書籍やインターネット上の情報だけで正確な契約書を作成するのは難しいです。
専門家のアドバイスを受けて、法的に問題のない契約書を作成するようにしましょう。
信託契約書は、公正証書の形式とするのが望ましいです。
特に、信託財産に不動産が含まれるような場合には、公正証書による作成が必須といえるでしょう。
信託契約書を作成したら、契約書の内容に従って信託財産の名義変更の手続きを行います。
現預金は、受託者の口座に振り込む以外に手続きは必要ありません。
不動産は信託登記をして、受託者の財産とは分別管理することが法的義務となっています。
信託財産に現金や預貯金が含まれる場合、受託者は信託財産を管理するための預金口座を開設する必要があります。
受託者は、信託財産を受託者自身の財産とは分けて管理しなくてはなりません。
現金のままで管理していると、自身の財産と分けて管理することが難しく、記録も残りません。そのため、専用の預金口座で管理する必要があります。

家族信託する信託財産を決める時に注意すべきことがあります。
何を信託財産にするかにより注意すべき点が異なるため、それぞれの場合について解説します。
銀行に預けている預貯金を信託財産にする場合、そのまま信託財産にできない点に注意してください。
銀行に預けている預貯金は「預貯金債権」と呼ばれ、預貯金債権を第三者に譲渡できないと決められています。
そのため、預貯金を信託財産にする場合、信託財産を管理する専用の口座にあらかじめ送金しておくなどの対策が必要です。
次に、不動産を信託財産にする場合に注意すべき3つの点について解説します。
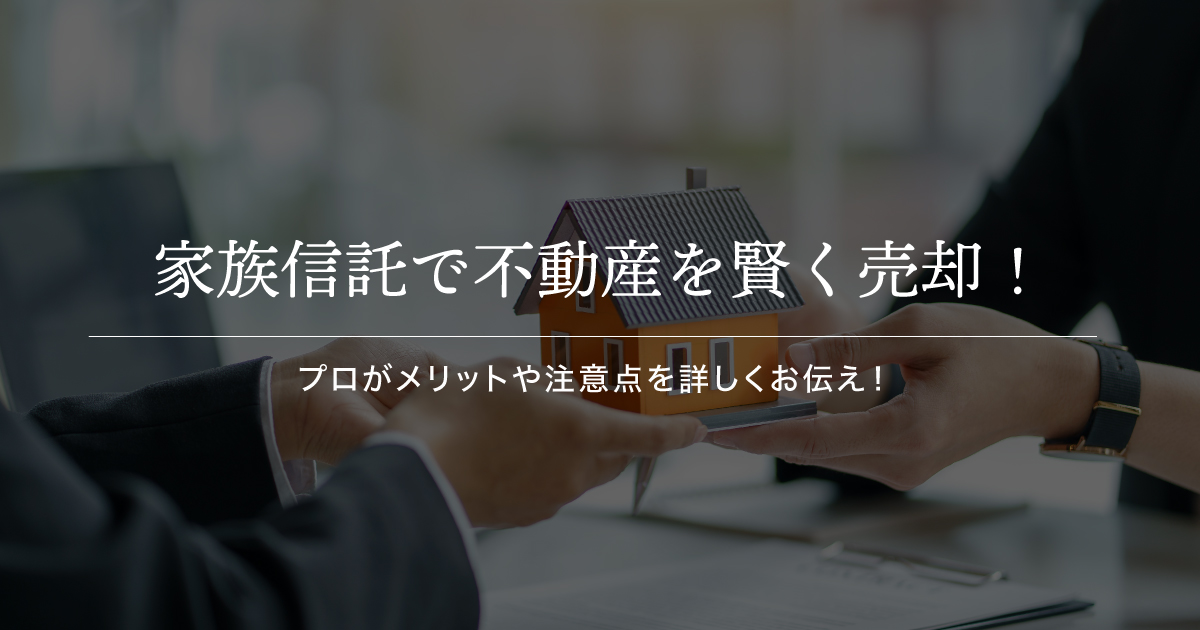
不動産を信託財産にする場合、所有権移転登記と信託登記をしなければいけません。
所有権移転登記とは、信託財産の名義人を委託者から受託者へと変更する登記です。
厳密には所有権移転登記の義務はありませんが、登記手続きをしなければ第三者に権利を主張できなくなるため、必ず手続きするようにしてください。
また、信託登記とは、不動産が信託財産であることを登録するために行う登記です。
信託登記は所有権移転登記と異なり、必ずしなければならないため注意してください。
不動産の中でも、収益不動産を信託財産とした場合、家賃管理の対応もしなければなりません。
信託財産の管理は受託者が行うため、収益不動産の家賃も受託者が管理する必要があります。
委託者が自分で管理している収益不動産であれば、家賃が委託者に振り込まれるため、入居者に振込先を信託専用の口座に変更してもらう通知を送ります。
一方、管理会社が収益不動産を管理している場合は、管理会社に家賃が振り込まれるため、入居者に通知を送る必要はありません。
しかし、管理会社から委託者に振り込まれるお金の振込先を、信託専用の口座に変更してもらう必要があるため、管理会社に通知を送る必要があります。
信託財産である不動産を売却する可能性がある場合には、契約時に決めておく必要があります。
具体的には、信託契約で不動産の売買に関する項目が含まれていて、その旨が不動産登記に反映されていたら、信託財産でも不動産売却ができます。
ただし、不動産に抵当権が設定されたままである場合、不動産は売却できません。
金融機関から融資を受けている場合、返済を担保するために抵当権を設定していることがあり、売却するためには抵当権を外してもらう必要があります。
認知症が進行している場合、繰り上げ返済が認められず、抵当権を外してもらえない可能性もあります。あらかじめ金融機関に確認するようにしてください。
株式や投資信託を信託財産にする場合に注意すべき6つの点について解説します。
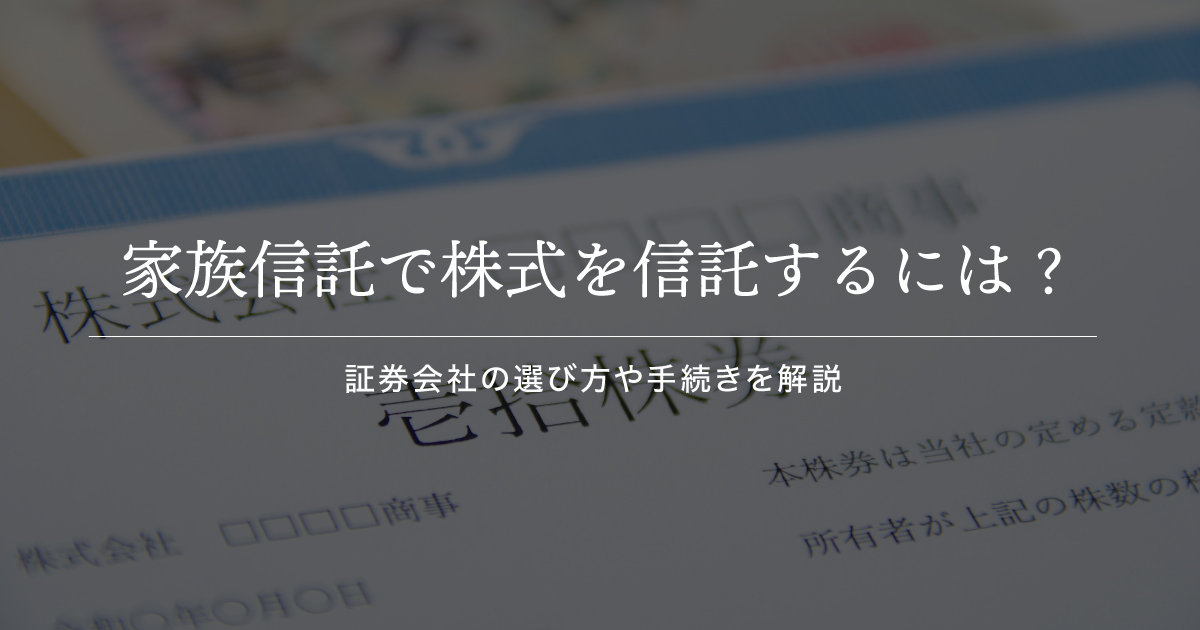
株式を信託すると、株主名簿には受託者名義で新しく登録されるため、保有期間がリセットされます。
株式の保有期間がリセットされると、株主優待の保有期間も当然リセットされるため、株主優待を受けられなくなる可能性があります。
とはいえ、株主優待は廃止される傾向が広がっているため、期待しすぎるのはおすすめしません。
証券会社によっては特定口座を利用できず、一般口座を開設しなければいけない可能性もあります。
同じくNISAも利用できない可能性があります。
一般口座を開設することになると、確定申告が必要です。
そのため、特定口座やNISAでは必要なかった手間が増えてしまう点がデメリットだといえるでしょう。
税務署に信託計算書の提出が必要になる点にも注意してください。
有価証券の配当がある場合、受託者が信託計算書と信託の計算書合計表の2つを毎年1月31日までに税務署長に提出しなければいけません。
確定申告の他に、信託計算書や信託の計算書合計表も提出しなければいけないため、かなり多くの手間がかかるでしょう。
信託計算書や信託の計算書合計表の提出が必要な場合とそうでない場合があるため、税理士に確認するようにしてください。
投資信託を信託財産とする場合、専用の口座に他の金融機関で預かっている投資信託を移管できます。
しかし、全ての場合で投資信託を移管できるわけではなく、信託専用の口座を作る証券会社でも取り扱っている商品でなければ移管できません。
もし、移管したい投資信託がある場合、専用口座を作る証券会社でも取り扱っているのかの確認が必要です。
株式を売却するときには、譲渡所得の他に株式委託手数料がかかります。
株式委託手数料とは株式の売買が成立した際に、金融機関に支払う手数料のことです。
このように、株式を売却すると売却益を全て手に入れられるわけではないため、注意してください。
投資信託を売却するときには、信託財産留保額がかかることがあります。
信託財産留保額とは、投資信託を解約する時にかかる費用で、基準価額に対する割合として解約代金から差し引かれる形で支払います。
差し引かれる金額は一般的に0.3%ほどです。種類ごとに異なり、差し引かれない場合もあるため、確認が必要です。

信託財産が相続財産に含まれるかどうかという議論があります。
以下では、信託財産は相続財産になるかという点について見ていきましょう。
家族信託では、信託した財産は委託者の財産ではなくなります。
信託財産は受託者に所有権が移転し、受託者が信託財産の管理・運営・処分を行います。
信託財産は所有者である委託者の財産でなくなるため、委託者が死亡時に行う遺産分割協議の対象財産にはなりません。
委託者が作成した遺言の対象財産からも除外されます。
信託財産から給付された金品は、受益者固有の財産です。
受益者の財産であるため、受託者が死亡した場合には遺産分割協議や遺言の対象財産になります。
具体的には信託契約が「信託財産から受益者に対し毎月一定額を給付する」などという内容であれば、受益者に給付された金品は受益者の固有財産です。
したがって、受益者に相続が生じれば、遺産分割の対象になります。
受益権とは、受益者が信託行為に基づいて生じた信託利益を受け取る権利のことです。
受益者が亡くなった時点で、受益権は相続財産となり相続税の課税対象の財産になります。
相続税が課税されるタイミングは、受益者が亡くなったときです。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

信託財産とは受託者が委託者と信託契約を結び、その信託目的に従って受益者のために管理・処分などをする財産のことです。
信託財産は受託者名義になりますが、受託者による自由な処分は認められず、受託者の固有財産とは区別される財産です。
銀行の抵当権付き不動産を信託する場合、銀行の同意が必要です。
銀行が同意しない可能性もありますし、名義を取得する者に債務を引受けさせる条件を設ける場合もあります。
抵当権付き収益アパートを信託する場合でも、抵当権は存続します。
信託により生じる法的リスクを最小化するために、信託特有の性質を把握した上で銀行側と相談しながら進める事が望ましいです。
信託財産は、委託者・受託者・受益者の三者の合意があれば変更できます。
信託目的に沿わないことや受益者の利益に合うことが明らかであれば、より簡易的な方法でも変更できます。
しかし、信託契約に変更不可と決められている場合は、合意があっても変更できません。
もし、信託契約で変更不可と定めている場合は、契約内容自体を変更しなければいけなくなるため、注意してください。
信託契約で必要な条項を備えておけば、現在の受益者の同意がなくても変更できます。
しかし、新しく受益者になった人は贈与税が課税されてしまう点に注意してください。
前の受益者から新しい受益者へ贈与されたとみなされるため、贈与税が発生するのです。
なお、法律上は受益者を同意無しで途中で変更できますが、前の受益者からは反発が出ることが容易に想像されます。人間関係を平穏に保つためのフォローが必要になるでしょう。
信託の当事者には、委託者・受託者・受益者の三者が存在します。
それぞれが破産した場合の信託財産への影響は下記のとおりです。
委託者が破産すれば信託の終了事由に該当し、家族信託は終了します。(信託法第163条第8号)
信託開始後に委託者が破産しても、信託財産への影響はありません。信託開始時において、信託財産が受託者へと移転しているためです。
受託者が破産すると受託者の任務の終了事由に該当し、受託者の任務は終了します。(信託法第56条第1項第3号)
ただし、受託者が破産しても任務が終了しないようにすることは可能です。受託者を辞めさせるかどうかの判断は、当事者間で決めることができるためです。
受託者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、信託財産は影響を受けない旨が信託法に規定されています。(信託法第25条第1項)
ただし、信託財産となっている預金は、差し押さえられる可能性があります。信託専用口座は外形上受託者個人の預金であるためです。
受益者の破産によって、家族信託が終了するなどの影響はありません。受益者の持つ受益権は差押えの対象になります。
信託財産の中で融資を受けることを信託内借入といいます。
信託内借入を行った場合には、信託財産が破産する可能性が生じます。
たとえば、信託内借入により、信託財産の土地の上に賃貸マンションを建設したものの、収益が想定を大きく下回った場合には、当該借入が返済不能に陥ることもあるでしょう。
上記のような場合には、信託財産が破産する可能性が高くなるといえます。

信託財産にできるものの例として現金・不動産などがあることや、財産的価値のないものが信託財産にできないものであることなど、具体的に紹介しました。
また、信託財産を決める際の注意点としては、不動産を信託財産にするためには所有権移転登記と信託登記手続きが必要であることなどが挙げられます。
信託財産の管理について興味をお持ちの方は、認知症対策としても注目されている家族信託を検討されてみてはいかがでしょうか。
ファミトラでは相談者とご家族の想いや状況・要望を整理して、専任の担当者と専門家が対応していますのでお気軽にご相談ください。
無料で詳しい資料をお取り寄せいただくことも可能です。ぜひ一度、資料をご請求ください。

家族信託に精通した専門家が、お客様の相談を受け付けております。
ファミトラでは、家族信託に限らず相続対策や成年後見制度にまつわるご相談など幅広く対応することが可能です。

さまざなお客様のケースに対応してきた経験豊富な家族信託コーディネーターが、お客様一人ひとりのご状況に合わせて親身にサポートいたしますので、「まずはお話だけ…」という方もお気軽にご相談ください。
\ 24時間いつでもご相談可能 /
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。