
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
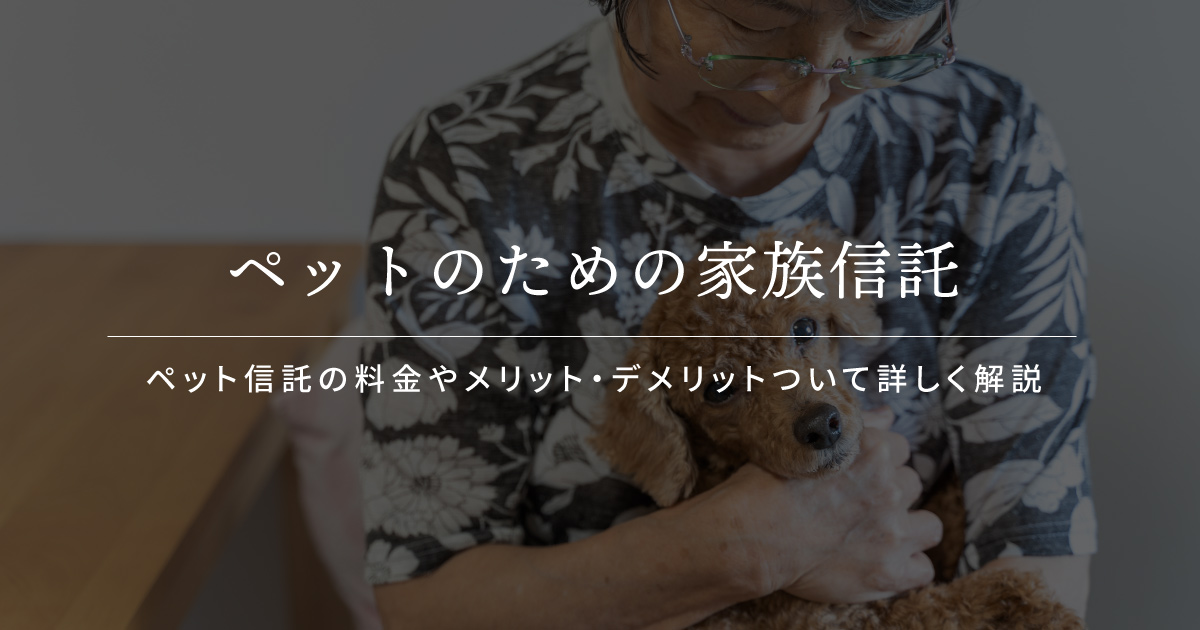
独り身でペットを飼っている高齢者なら誰しも「自分の死後、ペットの世話はどうしたらいいのだろう?」と考えたことがあるのではないでしょうか。
この記事では、飼い主が亡くなった後、ペットが安心して暮らせる方法を解説しています。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリット、必要性についてわかりやすく解説

田中 総
(たなか そう)
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

田中 総
家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

家族信託といえば、認知症発症後の財産管理のための方法だと思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、家族信託は自分が認知症になった時やペットを遺して亡くなった時に、ペットを守る方法としても活用できるのです。
「ペットに財産を残したい」と考える飼い主は多いと思います。しかし、ペットは民法上、遺産を受け取ることができません。
民法上、権利義務の主体になれるのは「人」に限られるからです。
遺言書に「飼い猫○○に財産を相続させる」と記載しても、その部分は無効になります。
こういった場合、ペットに財産を残すのではなく、ペットのために財産を使ってくれる人に託すことが考えられます。
具体的には以下の3つの方法があります。
ペットの世話をしてくれる人に遺言でペットの飼育を条件に財産を残します。
この場合、気を付けなければいけないことがあります。
1つは、ペットも財産に含まれるということです。
世話をしてくれる人にペットを相続させる、あるいは遺贈する旨を記載しましょう。
もう1つは、必ずしもその人が遺贈を受けてくれるとは限らないことです。
遺言書を作成する際に、ペットの世話をしてくれる人に再度確認しましょう。
ペットの世話をしてくれる人に、飼い主の死亡を原因とした負担付贈与をします。
契約なので負担付遺贈と違い、遺贈の放棄はありません。
家族信託の仕組みを利用し、ペットの飼育のために財産の管理・運用をしてもらいます。
以下、詳しく説明します。
家族信託とは、財産のある人(委託者)が、自分の財産を信頼する人(受託者)に託します。受託者は財産から生じる利益を受け取る人(受益者)のために、その財産を管理・運用する仕組みです。
ペットのための家族信託では、委託者はペットの飼い主、受託者は財産の管理をしてくれる人、受益者はペットの飼育をしてくれる人になります。
受託者には家族や信託事務代行業者などが、受益者にはペット飼育業者、里親紹介団体、獣医などが選ばれることが多いようです。
ペットのための家族信託で注意すべきことがあります。
それは、ペットの飼育をする人と財産の管理をする人を別の人にすることです。
家族信託では、受託者と受益者が同一人物の場合、1年で家族信託が終了してしまうためです。

家族信託は、委託者が意思表示をできなくなった時に備えるための仕組みです。
したがって、次の場合にその効果が発揮されます。
認知症や病気などによりペットの世話が難しくなったときに、ペットの飼育と財産管理を任せるように信託を組成しておきます。
そうすれば、委託者の望むタイミングで信託が開始されます。
高齢者がペットを飼っている場合、自分が亡き後のペットの行く末が気になる人も多いと思います。
ペットのための家族信託を組成しておけば、飼い主の死後、ペットは受益者である飼育者の元へ引き取られ、受託者からペットの飼育に必要な金銭を受け取ります。
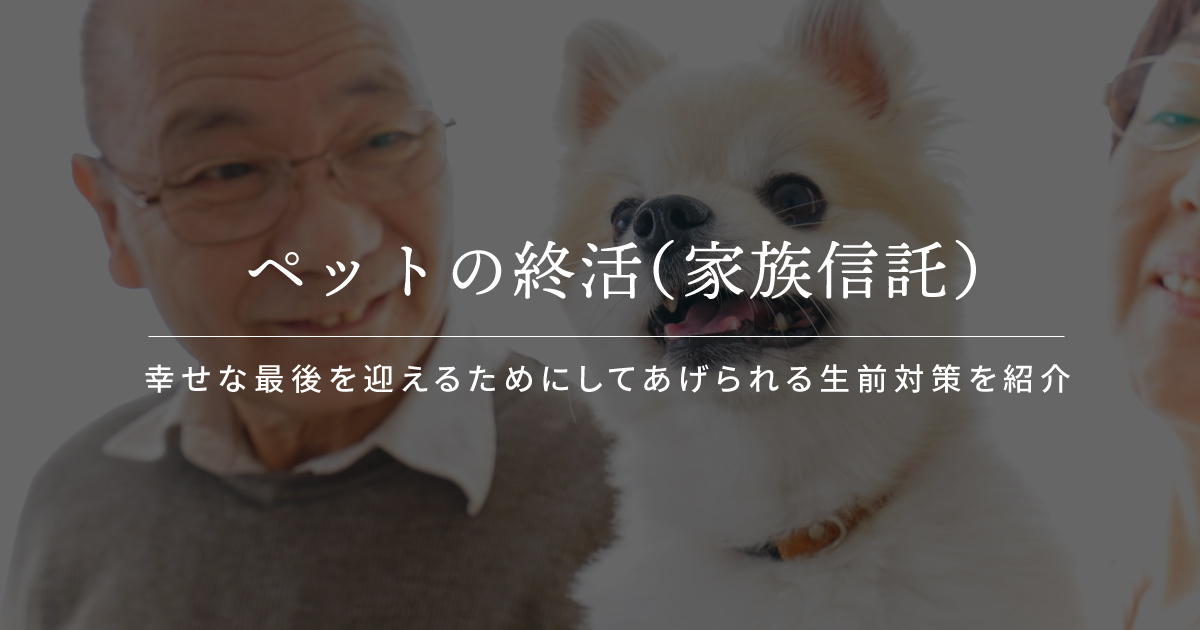

ペットのために家族信託を利用する最大のメリットは、ペットのために確実に財産が使われることです。
家族信託の場合、託された財産は信託財産となり、信託契約で定められた目的以外に使えなくなるためです。
したがって、ペットの飼育を目的としておけば、財産をペットの飼育以外には使えなくなり、ペットのために確実に財産を残せます。
また、信託監督人を選ぶことで受益者がきちんとペットを飼育しているかチェックすることができます。
負担付遺贈・負担付死因贈与契約の場合、遺産は受遺者の自由に使うことができます。
確実にペットに使われているのか、きちんと飼育されているのか第三者がチェックできないことが最大のデメリットです。
家族信託の場合、飼い主の死後、相続でもめても信託された財産は信託財産として遺産とは別に確保されるため、ペットの飼育費用は確保されます。
また、信託監督人がいればペットの飼育状況と飼育費用の管理について監督をするので、ペットの生活は確実に保障されるのです。
負担付遺贈や負担付死因贈与契約の場合、財産だけ受け取ってペットを他人に譲ったり、最悪のケースでは、ペットを遺棄したりすることも考えられます。
上述したように、信託監督人のような第三者によるチェック機能がないので、ペットの生活が保障されるとは限りません。
これらの点を考慮すると、ペットの生活を守るためには家族信託を使うことをおすすめします。
家族信託は契約なので、その内容は柔軟に設定できます。
飼い主が現在飼育している状況をできるだけ再現できるよう、契約内容を細かく設定することが可能です。
ペットの信託の場合、以下の事柄を決めておくこともできます。
上記のことは、負担付遺贈や負担付死因贈与契約ではできないことです。
負担付遺贈や負担付死因贈与契約の場合、誰にどの財産を相続させるのか決められるのは、一代限りです。
例えば、負担付遺贈で息子にペットの世話を条件に財産を相続させると、その財産は息子のものになります。その先は誰に相続させるのかは息子の自由です。
家族信託は、二次以降の相続についても委託者が決められます。
ペットが亡くなり、ペットのための家族信託が終了した後、残った信託財産を家族に相続させる、あるいはペットの世話をしてくれた人に相続させるなど、柔軟な承継が可能です。

Aさんは、現在85歳で、猫のX(5歳)と暮らしています。
最近、認知症の兆候が出始めて、自分の今後とともに、猫の行く末も心配しています。
Aさんには遠くで暮らす娘のBさんがいますが、ペット飼育不可のマンションに住んでおり、Aさんに何かあってもXの世話ができません。
幸い、かかりつけの獣医Zが、Aさんに何かあったらXの世話をしてくれるといっています。
Bさんも、できることがあれば協力するといってくれています。
上記の例で、家族信託を組成してみましょう。

ペットのための家族信託にかかる費用の分類は以下の3つです。
自分で信託設計する場合は費用がかかりませんが、家族信託の設計には高度な法律の知識が必要になるため専門家に依頼するのが一般的です。
弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼した場合、相場は50万円〜100万円程になります。
一般的に、信託財産が高額になるほど費用は高額になります。
信託契約書作成にかかる費用は、15万円〜30万円程になります。
所有権移転登記は一般の人には難しいため司法書士に頼むことになります。
費用の相場は、5万円〜15万円程です。
所有権移転登記の際、必ず払う税金です。
費用は不動産の評価額によります。
弁護士や司法書士などの専門家を信託監督人にした場合、月々の費用が発生します。
相場は、1万円〜2万円程です。
猫の例で説明します。
| 費用内訳 | 費用 |
|---|---|
| ①ノミやダニの予防接種 | 15,000円 |
| ②トリミングなど | 40,000円 |
| ③トイレの砂・ペットシーツ代 | 60,000円 |
| ④獣医への通院費 | 60,000円 |
| 合計 | 175,000円 |
ペットの費用の他に、ペットの世話をしてくれる受益者に感謝の意味でも、謝礼を払いましょう。
そうすれば、大切なペットを一層かわいがってくれるでしょう。

ペットのための信託の6つのデメリット・注意点を解説します。
前述したように、民法上、ペットは権利・義務の主体にはなれません。
したがって、家族信託の受益者にはなれないのです。
ペットのために財産を使用するには、ペットの世話をしてくれる人を受益者にして、ペットのためにお金を使ってくれるように家族信託を利用する以外ありません。
一年間でペットの飼育にかかる料金は、猫で17万円〜20万円、小型犬で20万円〜25万円、大型犬だと30万円〜35万円です。
それに、それぞれの平均寿命から現在の年齢を引いた数をかけた額を、一括で信託財産として支払う必要があります。
大型犬だと、数百万円を一括で支払うケースもあります。
ペットの飼育費用は、ペットの種類や何歳であるかによって異なるため、よく調べて不足することのないように支払いましょう。
ペットの飼育を引き受けるにはそれなりの覚悟が必要です。
そのため、なかなか受益者になってくれる人が見つからない場合もあります。
何とか見つかったが、動物が好きなわけでもなく謝礼目当てという人だったという可能性もあります。そのような人に大切なペットを任せることはできません。
受益者がペットの飼育に不適切な人物だった場合の対策として以下2つの方法があります。
信託監督人に信託財産がペットのために使われているのか監督させるとともに、受益者が信託契約の内容に沿ってペットを飼育しているかチェックさせます。
チェック機能を強化するために、信託監督人には弁護士や司法書士などの専門家を選任しましょう。
専門家を選任すると報酬が発生しますが、それだけの働きをしてくれるはずです。
信託設定後に、複数いる受益者を1人にする場合や受益者が不適格などの理由により受益者を変更する権利を受益者変更権といいます。
受益者変更権を信託監督人に設定しておけば、受益権がペットの飼育に向いていない場合、よりふさわしい人を受益者に変更できます。
ペットのための信託は比較的新しい仕組みで、ペットのための信託を専門的に扱っている業者は少ないのが現状です。
そのため業者同士の比較が難しく、それぞれの業者の強みや特色と飼い主である委託者のニーズに合うかどうかが基準となってきます。
無料相談を行っている業者も多いので、いくつかピックアップした業者に無料相談を申し込み、その上で慎重に決めましょう。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に民法上認められた、被相続人の財産を最低限相続する権利のことです。
信託財産は他の財産と切り離された独立の財産となりますが、遺留分を侵害することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、ほぼ確実に遺留分侵害額請求を行います。
相続を機に家族がバラバラにならないように、信託財産は遺留分に十分留意しながら設定しましょう。
ペット信託においては、受益者だけでなく受託者もなかなか見つからないことがあります。
受託者はその負担や義務が大きいことが、受託者が見つからない理由です。
特に帳簿などの作成・報告・保存義務は受託者にとって大きな負担となります。
受託者の負担を減らすことが、受任に繋がる可能性があります。
受託者の負担を減らすには以下の3つの対策が有効です。
金銭以外の財産、特に不動産は家賃や地代が発生する場合も多く、管理が難しいです。
これら管理の難しい財産を信託財産に含まないよう組成することで、受託者の負担を軽減します。
家族などの身内が受託者になった場合、無償というケースも多いですが、受託者は負担や義務が大きいので、報酬を支払うよう信託契約を結びます。
受託者の労力に見合う報酬を設定すれば、引き受けてくれる可能性は大きくなります。
弁護士や司法書士などの専門家を信託監督人に選任し、受託者にアドバイスなどをしてもらい、受託者の負担を減らします。

ペットのための家族信託契約をご自分ですることも可能です。
しかし、家族信託を組成するには法律に関する高度な専門知識が必要になります。
一般の方が家族信託を組成する場合、以下のデメリットがあります。
お金はかかりますが、弁護士や司法書士などの専門家や家族信託のコーディネーターなどに相談の上、依頼することをおすすめします。
家族信託という名称ですが、受託者を家族以外にすることは可能です。
本来、民事信託というところを、わかりやすく家族信託と言い換えているのです。
家族信託の受託者には、未成年者以外であれば個人・法人を問わずなることができます。
また、複数の受託者を設定することも可能です。
ただし、弁護士や司法書士、税理士などの士業従事者は、信託業法上、受託者にはなれません。
受益者が高齢でペットが長生きな種の場合、受益者の方が先に亡くなる可能性もあります。
ペットを最後まで確実に飼育してほしい場合、第二受益者を設定しておくことをおすすめします。


家族信託はペットの飼い主が認知症の発症や死亡などの不測の事態が起きた際に、非常に有効な仕組みです。
大切なペットが最後まで安心して暮らせるように、家族信託を利用することをおすすめします。
ただし、家族信託を自分で組成する場合、契約の不備などで信託が無効になるケースが多く見られます。
ファミトラでは、弁護士や司法書士といった法律の専門家が無料相談を受け付けています。
ペットのための家族信託に興味のある方は、一度、ファミトラにご相談ください。