
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
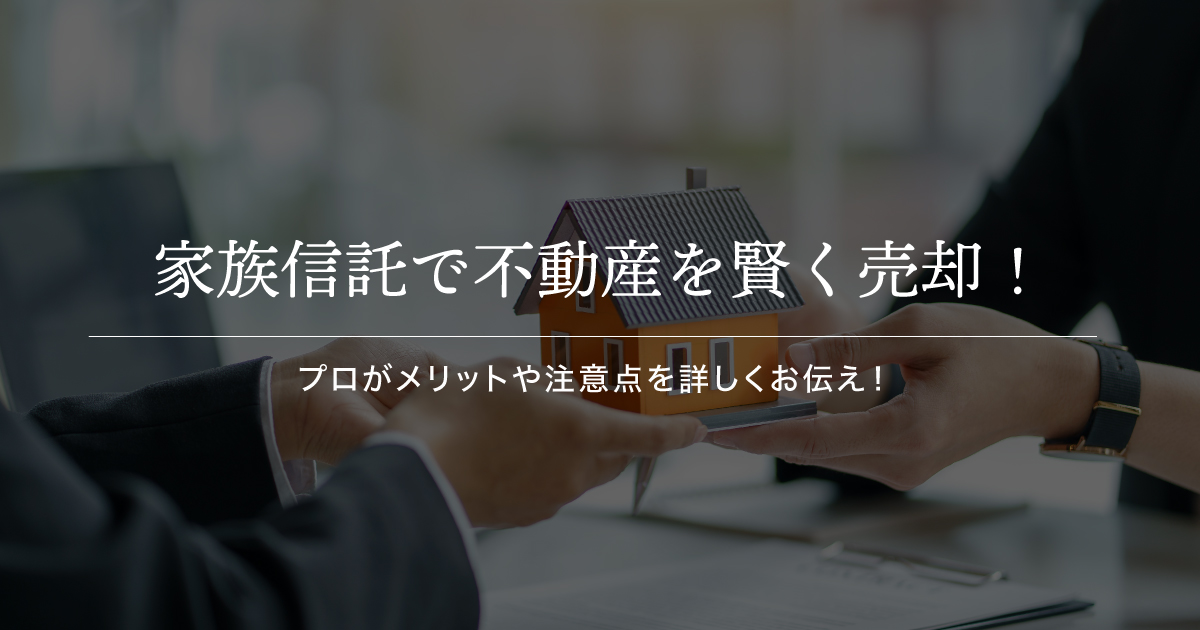
家族信託では「どのようにして不動産を管理・売却したら良いのだろう」と思われている方もいるのではないでしょうか。
家族信託を利用して不動産を売却する方法は、不動産自体を売却する方法と受益権を売却する方法の2つです。
本記事では、家族信託で不動産を管理・売却する仕組みとメリット・デメリットを解説します。本記事を読めば、家族信託で不動産を売却するときの注意点がわかるようになります。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリット、必要性についてわかりやすく解説

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
急いで概要だけを掴みたい方はこちらの動画をご覧ください。この記事の内容を2分でまとめた解説動画です。
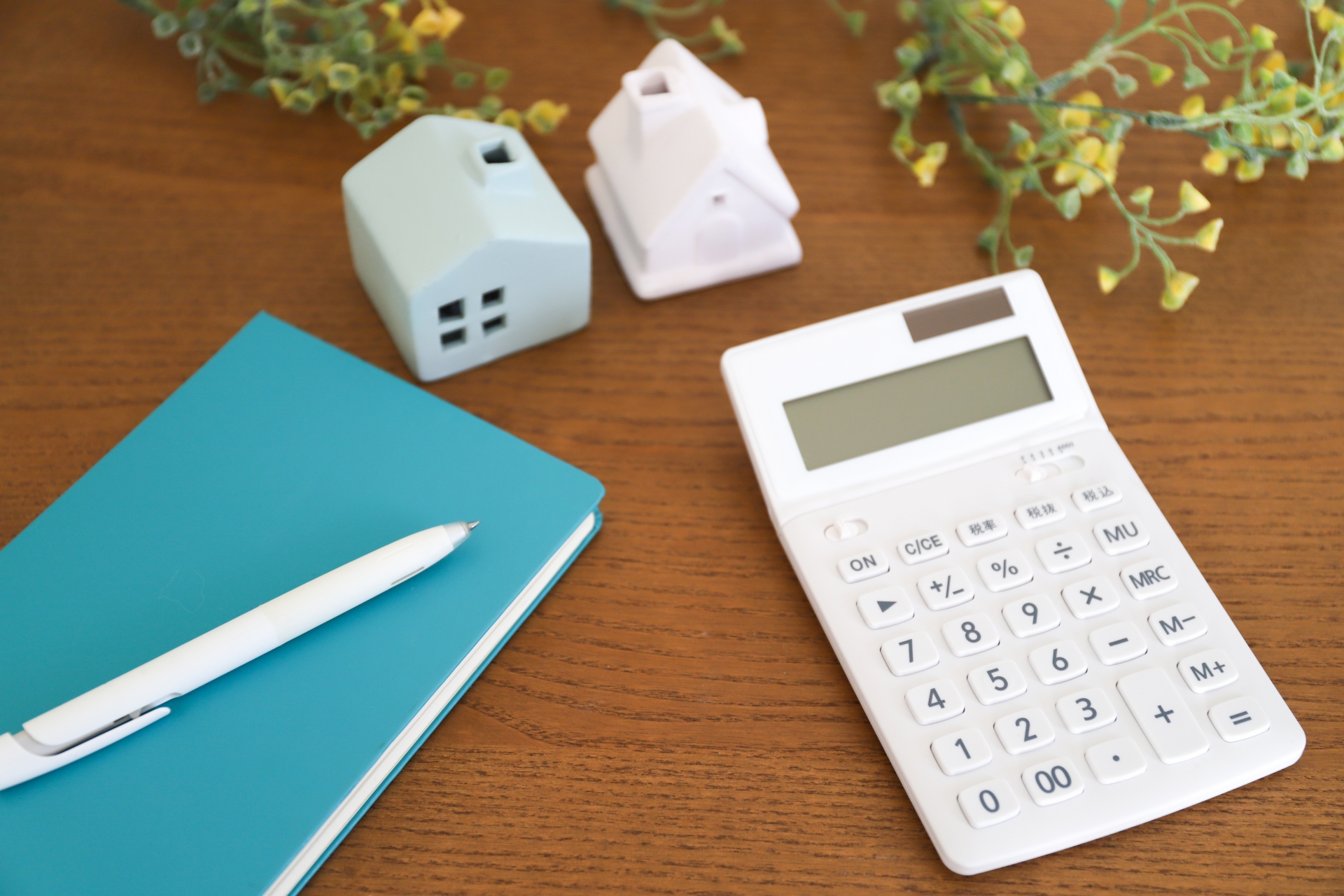
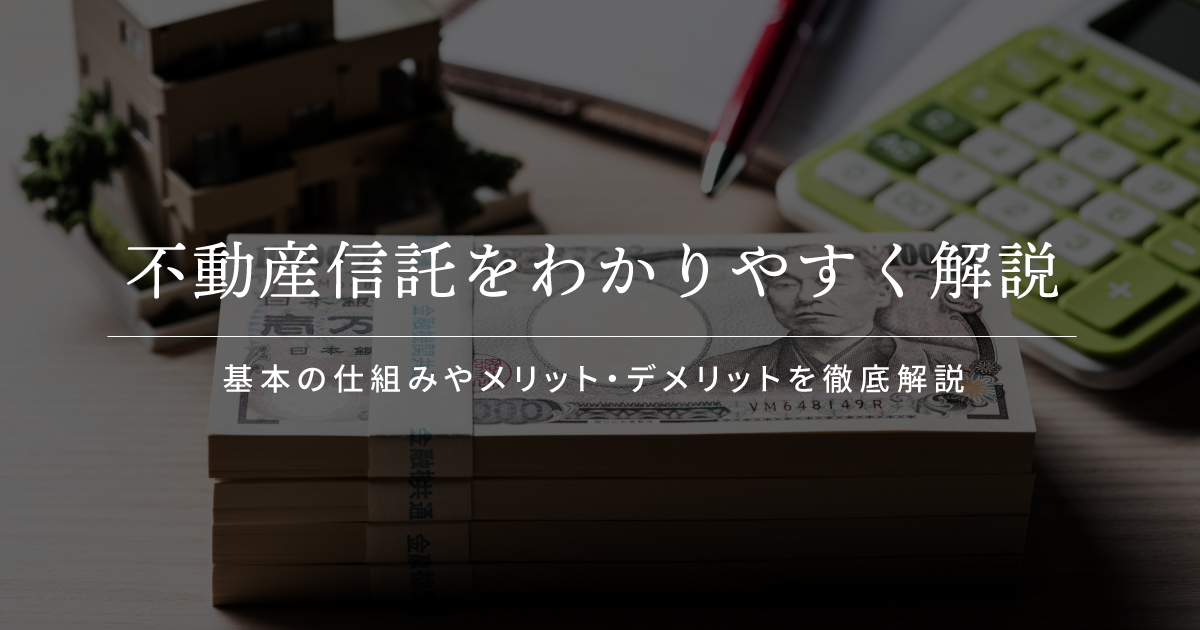
家族信託は、主に以下の三者によって構成されます。それぞれの役割は次のとおりです。
家族信託で不動産を管理する場合、委託者・受託者・受益者はそれぞれどのような役割を果たすのでしょうか。
三者の役割を1つずつ解説します。
委託者は、不動産の持ち主で資産を預ける人のことです。
委託者になるための資格などはありません。ただし、家族信託では契約を締結するため、判断能力が低下していると利用できません。
委託者の権限は契約内容で決まるため、一概にはいえませんが、委託者の判断能力があるうちは受託者の監督もできる場合が多いでしょう。
受託者は、委託者から不動産を預かる人です。不動産を管理したり運用したりします。
家族信託では、家族や友人など委託者が信頼を置いている人物が受託者になります。
受託者の権限は契約内容で決められるため、信託契約書に書かれていないことはできません。
不動産の管理や運用に関することしか契約書に書かれていない場合は、金銭の管理や運用はできないのです。
受益者は、不動産から生じた収益を受け取る人です。一般的には、委託者と受益者は同一人物で、不動産管理のみを受託者に依頼しているケースが多いです。
しかし、委託者以外が受益者になることも認められています。例えば、障害を抱えた子どもが就職できなくても生活に困ることのないように、不動産から出た収益を受け取れるようにすることも可能です。
家族信託を利用した不動産管理を行う場合、委託者が自身を受益者として管理や運用を受託者に委託することになります。
受託者が不動産を管理することになるため、テナントや居住人は受託者と賃貸借契約を結びます。そのため賃料も、受託者に支払われることになるのです。
受託者が受け取った賃料は、委託者兼受益者に信託配当という形で渡します。
信託した不動産の所有者は受託者です。信託後、不動産登記の所有者には受託者の名前が記載されます。
不動産の名義人が受託者である以上、売買や賃貸の主体も受託者です。不動産売買に際して必要な意思の確認は、受託者に対してなされます。
受託者の意思が確認できる限り、委託者や受益者に判断能力がなくても契約の成否に影響を与えません。
しかし、受託者の所有権は形式的です。実質的な所有者は、受益者といえます。
不動産売却代金や賃料など、利益を受け取るのは受益者だからです。

不動産の所有者が認知症になってしまった場合、その管理はかなり面倒になってしまいます。
場合によっては、成年後見制度を利用することになり、裁判所に許可を求める手続きをしなければならないでしょう。
そのため、認知症対策として家族信託を利用して備えることがおすすめです。
家族信託とは何かを知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

家族信託では本人の判断能力が確かな間に、不動産の管理を家族に託すことができます。
託す相手は、「信頼に値する人物か」「委託者の意図をくみ取ってくれるか」といった要件を満たすことが望ましいです。
親族であれば誰でも良いわけではありません。
信託する不動産の管理・運用・処分能力だけでなく、自分のことを大切にしてくれるかを基準にして、受託者を選ぶ必要があります。
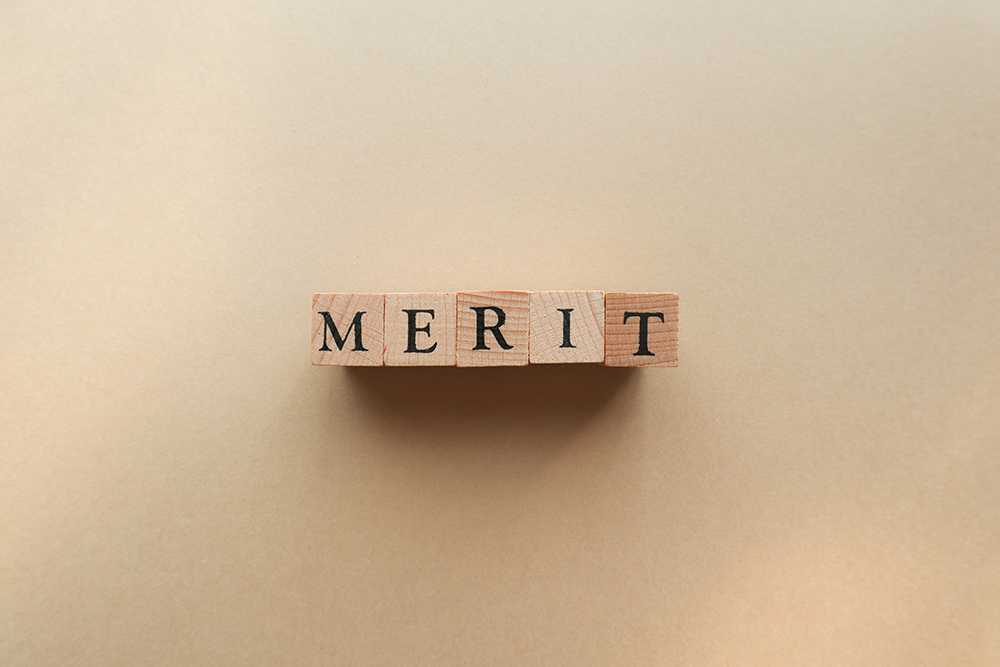
家族信託では、信託契約で受託者に権限を定めておけば、不動産の売却なども可能です。
そのため、将来、様々な費用が発生するときに備えておくことができます。
受託者に対し、不動産の管理・運用・処分についての幅広い権限を与えておくことで不動産の処分も可能になり、費用面で負担をかけずにすみます。
認知症を発症して正常な判断能力が失われると、不動産の賃貸・売買などの契約行為ができなくなります。
委託者が元気なうちに、親族を受託者として家族信託契約を締結しておくことにより、受託者が不動産の賃貸や売却などを含む管理・運用・処分をすることが可能になります。
日本では、年々少子高齢化が進んでいます。家族信託を利用することは、認知症の発症リスクに対する有効な対策の1つになると考えられます。
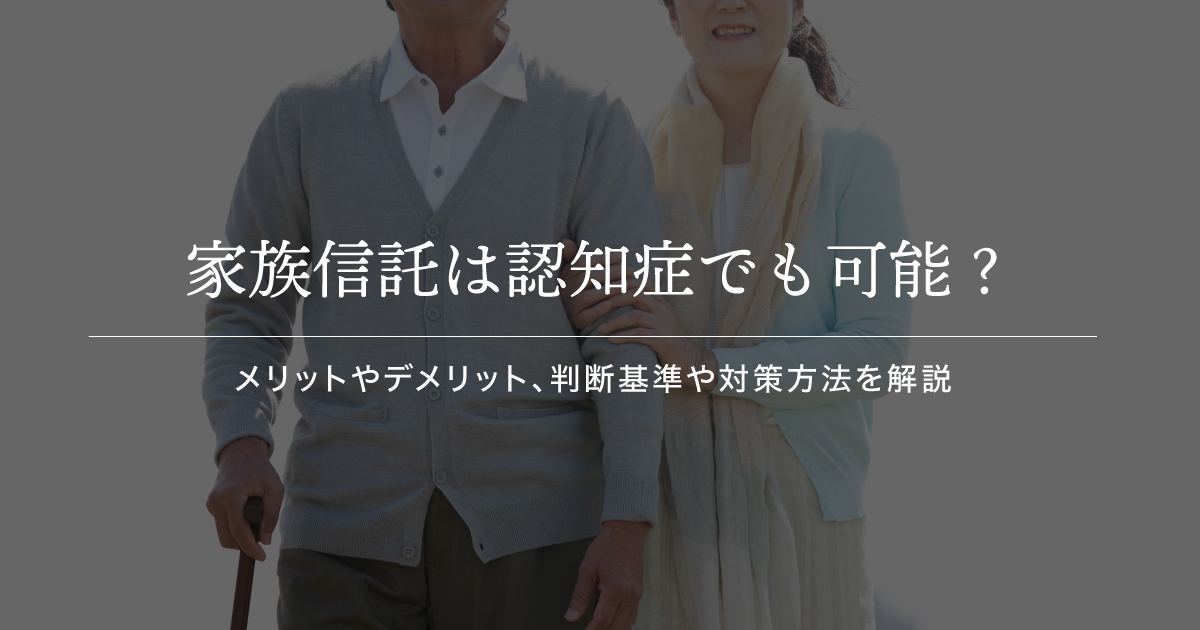
家族信託を利用すると、不動産の管理を他人に任せつつ、不動産が生む利益を享受できるようになります。
自らを委託者兼受益者として親族に受託者になってもらえば、不動産管理をしなくても、賃料収入を確保できます。
高齢になり不動産の管理に不安を感じる方は、家族信託を検討しましょう。
家族信託の活用により、健康に不安が生じた場合でも、問題なく不動産管理を継続できます。
遺言による不動産相続の場合、親は子どもへ相続させることはできます。しかし、孫の世代まで相続先を決めることはできません。
家族信託では、不動産の承継を子どもだけでなく、孫世代まで指定することができます。
家族信託は、子どもが死亡した後に孫に不動産を渡すことまでを選択肢とできる柔軟性の高い手法です。
不動産を共有名義にすると、共有者全員の同意がなければ不動産全体の売却処分をすることができません。
相続により不動産を共有することになった場合、共有者間の意見の相違により、本来得られるはずの収益を手にすることができないなどのトラブルが発生する可能性があります。
家族信託を利用して1人を受託者として選び、不動産の管理・運用・処分を任せれば不動産共有によるトラブルを回避できます。
家族信託と似た制度に任意後見制度があります。
任意後見制度は本人の判断能力が低下した場合、あらかじめ本人が選んだ任意後見人に対して、代わりにしてもらいたい行為を契約で決めておくものです。
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
介護施設への入居費用など急な出費が必要になった場合でも、任意後見制度を開始するには家庭裁判所での審判が必要です。
その点、家族信託では急な出費が必要な場合には、不動産を信託の目的の範囲内で管理・処分できるため、管理や運用の自由度が高いといえます。

不動産を家族信託することで、全てが上手くいくというわけではありません。
以下では、主なデメリットを8つ挙げて解説します。デメリットも十分に考慮した上で、家族信託の利用を考えてください。


家族信託の契約内容に建物が含まれている場合には、受託者に対し建物を適正に管理する義務が生じます。
特に、一定の年数が経過した建物であれば管理を怠れません。
建物の老朽化による倒壊などで、歩行者に怪我をさせることのないよう定期的なチェックを行うといった「管理面での手間」がかかります。
また、信託契約書の作成などを専門家に依頼する場合、専門家に支払う費用が発生します。
費用について現在のところ統一された報酬基準は設けられていませんが、決して安いものではありません。
家族信託にかかる費用については後述します。
不動産を信託するためには、適切な不動産の運営・管理・処分を行う能力のある家族や親族がいなければなりません。
安心して自身の財産を託すためには、信頼できる親族の中に不動産の管理能力を持った人がいるかどうかは重要なことです。
将来の相続の発生も見据えて、親族から受託者を選定した方が望ましいといえます。
親族に適任者がいなければ、任意後見制度を利用し、専門家に対応してもらうなどの方法を検討することになります。
不動産を信託する場合、家族のうちの誰かが受託者として任されることになります。
信託契約をした際に「家族全員が説明を聞かず受託者だけが理解していた」ケースでは、家族間でトラブルになりやすいです。
また、不動産の管理・運用・処分を適切に行ってはいたが「家族に事前に報告するなど説明をせず、意志疎通が取れていなかった」ケースでも、トラブルに発展する可能性があります。
トラブルを発生させないためには、受託者以外の家族が信託内容について十分に理解していることや、受託者と家族とのコミュニケーションが取れていることが必要です。
これらの点について専門家から家族に説明してもらうことも大切です。
家族信託において、受託者が職務に就く期間は長いです。契約の終了時期は、委託者の死亡時に設定される場合が多いためです。
また、受託者の責任は重く、かつ広範囲です。報告義務や損失填補責任など、受託者には様々な責任が発生します。
責任の重さや拘束期間の長さを曖昧にしたまま受託者を選んでしまうと、後でトラブルになりかねません。
不動産所得は所得金額の計算をする上で、損失が生じた場合には損益通算の対象となる所得です。
しかし、不動産所得のある方が家族信託を選択した場合には、収益性が下がって損失が生じたとしても、他の不動産所得との損益通算を行うことができません。
なお、損益通算ができないのは、同じ家族信託内の不動産と家族信託外の不動産の組み合わせです。
1つの信託契約で信託財産に含まれる不動産同士の損益通算は可能です。
1つの家族信託契約で不動産Aと不動産Bの管理を息子に任せている場合、不動産Aと不動産Bは損益通算できます。
不動産Aと家族信託に含めなかった不動産Cとの損益通算はできません。
家族信託を締結する前に、税理士などの専門家と相談しておくことをおすすめします。
家族信託を利用しても、直接的な節税効果は見込めません。家族信託で相続財産の価値が減少するわけではないためです。
家族信託は相続税対策には繋がらないため、注意が必要です。
もっとも、家族信託で間接的に、相続人の負担を減らす結果に繋がる可能性はあります。
家族信託を利用すると、(将来の)被相続人の財産の積極的な運用・処分が容易になるためです。
家族信託契約を根拠に実家を売却し、売却代金を老人ホームの入居費用に充てれば、相続人の負担は軽くなるでしょう。
家族信託では、委託者の意図にそぐわない形で財産が処分される可能性があります。
委託者の意図とは違う方向で、受託者が処分権限を行使する場合があるためです。
思わぬ結果を生まないためにも、家族信託契約の内容を決める際は慎重になる必要があります。信託の目的や受託者の権限の範囲など、入念な設計が求められます。
予期しない結果を避けるためにも、契約内容には敏感になりましょう。失敗を避けるためには、専門家への相談がおすすめです。
家族信託は近年使われるようになった制度です。2006年の信託法改正で利用されるようになりました。
信託法改正後、家族信託を取り扱う専門家は、増加しています。
しかし、家族信託契約の締結準備から財産管理に至るまでを一貫して経験した専門家は少ないです。
家族信託の全ての場面に対し、対応可能な専門家は限られています。
家族信託の取扱い件数の多い専門家や、家族信託の実務を担当する家族信託専門士として積極的に活動している専門家に相談する方が良いでしょう。
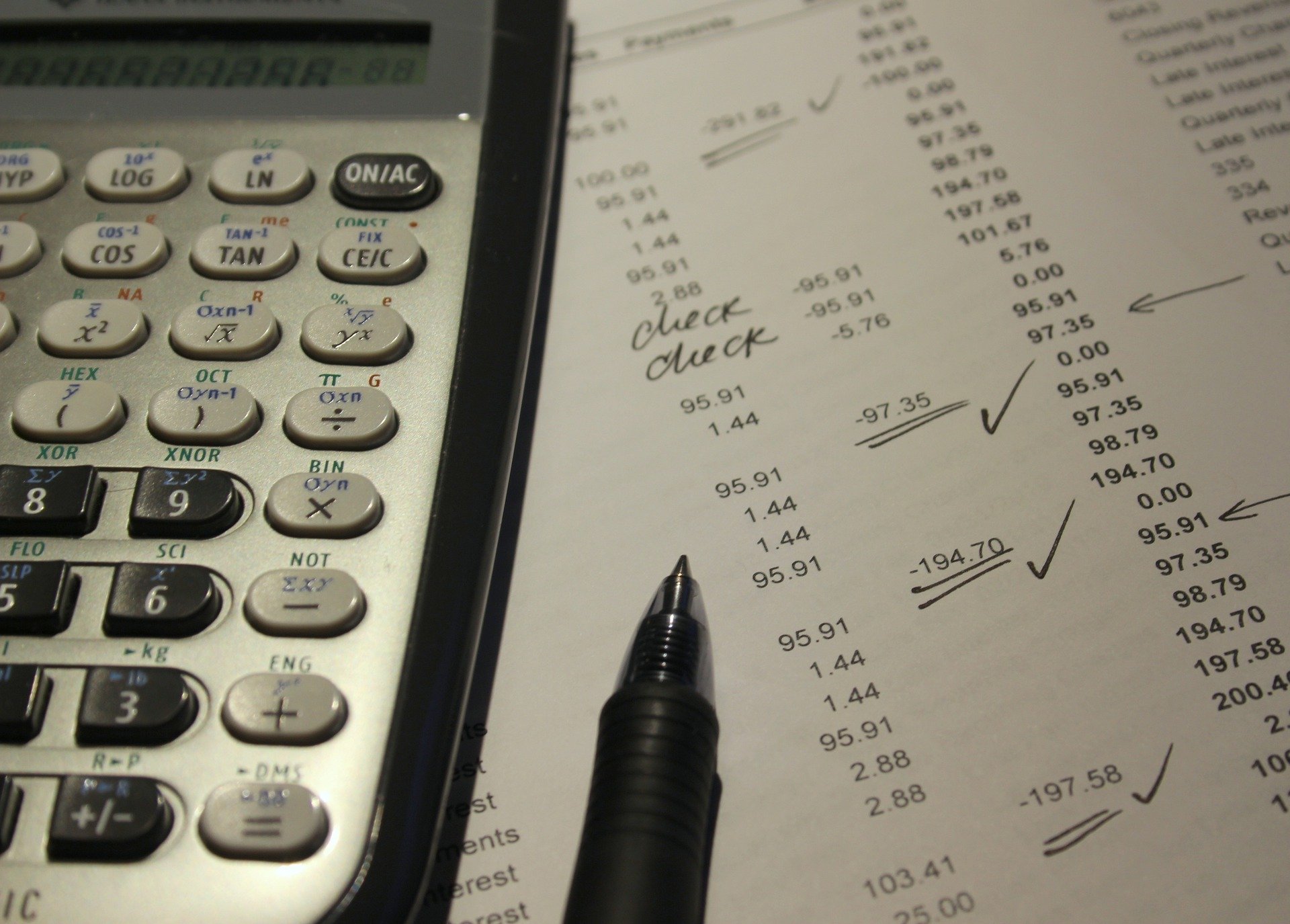
税金は、利益に着目して課税されるものです。
ここでは、家族信託で不動産を信託財産とした場合に発生する税金について説明します。
委託者・受託者・受益者のそれぞれに課される可能性のある税金について、順番に紹介します。
課税される可能性は個々の事例により異なるため、税務署の判断となります。ここでは参考に留め、少しでも疑問があれば税理士に相談してください。
家族信託では、委託者に対し課される税金はありません。
ここでは、委託者が関係する「自益信託」と「他益信託」の事例について簡単に説明します。
自益信託(委託者と受益者が同一人物の信託)の場合、信託の効力が生じた前後において、信託財産から利益を受ける人が変わらないため、利益の移転はなく、受益者に贈与税は発生しません。
他益信託(委託者と受益者が同一人物でない信託)の場合、信託の効力が生じた前後において、信託財産から利益を受ける人が異なるため受益者に利益が移転しているとして、贈与税がかかります。
受託者には、次の2種類の税金が課される可能性があります。
不動産が信託財産に含まれている場合は、不動産について「信託による所有権移転及び信託の登記」を行うことになります。
信託の登記では最初の登記時点で課税され、信託を終了する時点でも不動産を受け継ぐ人に対して2度目の課税がされます。(信託不動産を受託者から引き継ぐ人に対しての所有権移転登記が必要なため)
毎年1月1日現在の不動産所有者に対して課税されます。
不動産が信託財産に含まれている場合は、受託者が形式的な所有者となるため、受託者に対し課税されることになります。
受益者には次の4種類の税金が課される可能性があります。
(委託者と受益者が同一人物である場合には、委託者は受益者として課税されます。)
委託者と受益者が同一人物である場合は、基本的には課税されません。しかし、場合によっては課税されることもあるので専門家への確認が必要です。
相続が発生した時点において、受益者の地位を継承する二次の受益者に対し課税されます。
受益者が受益権を売却した場合は、発生した利益に対し課税されます。土地や建物の譲渡による所得では、他の所得と合計せず「分離課税制度」となります。
収益性のある不動産からの賃貸収入などに対し課税されます。

ここでは、不動産を家族信託にすべき人がどんな人かを解説します。
所有している不動産を、後世まで残したいと考える人には家族信託がおすすめです。
孫やその後の代まで不動産を守りたいと考えていても、子どもが不動産を相続したら、すぐに売却して現金化されてしまう可能性があります。
しかし、家族信託を利用すればその心配はありません。孫の代まで相続する旨の信託契約をしておけば、少なくとも子どもの代で売却されることはありません。
自分もしくは親が認知症になってしまったら、認知症になった本人の財産は自由に利用できなくなります。
しかし、判断能力があるうちに家族信託を利用しておけば、定めた目的の範囲内であれば財産を自由に利用できます。
そのため、自分や親が認知症になった際に、本人の財産をある程度自由に使えるようにしておきたい場合は、家族信託がおすすめです。
障害などにより財産管理ができない子どもがいる場合、親の死後の生活が不安になるでしょう。
そこで、親が収益不動産を有しており財産管理のできる子どもがいる場合、財産管理のできる子どもを受託者にし、どちらの子どもも受益者となる家族信託を締結します。
そうすることで、収益不動産からの収益が安定的に受け取れるようになります。

ここからは、不動産を家族信託する流れについて解説します。
認知症への対策、障害のある子どもの生活を支える、不動産の承継先を決める、など家庭によって家族信託の目的や形は様々です。
目的が不動産の承継である場合は、先祖代々譲り受けてきた土地に対する思い入れが強いことも少なくないでしょう。
信託に関わる家族全員で話し合い、合意を得ることが必要です。
家族信託では、公正証書により信託契約書を作成します。
いわゆる私文書による契約書でも契約は成立します。しかし、信託専用口座の開設や、不動産売却時に備えて公正証書による作成が望ましいです。
信託財産や依頼内容により必要書類は異なりますが、公正証書作成には一般的に以下の書類が必要になります。
これらの書類は、以下の手続きでも必要となるものです。
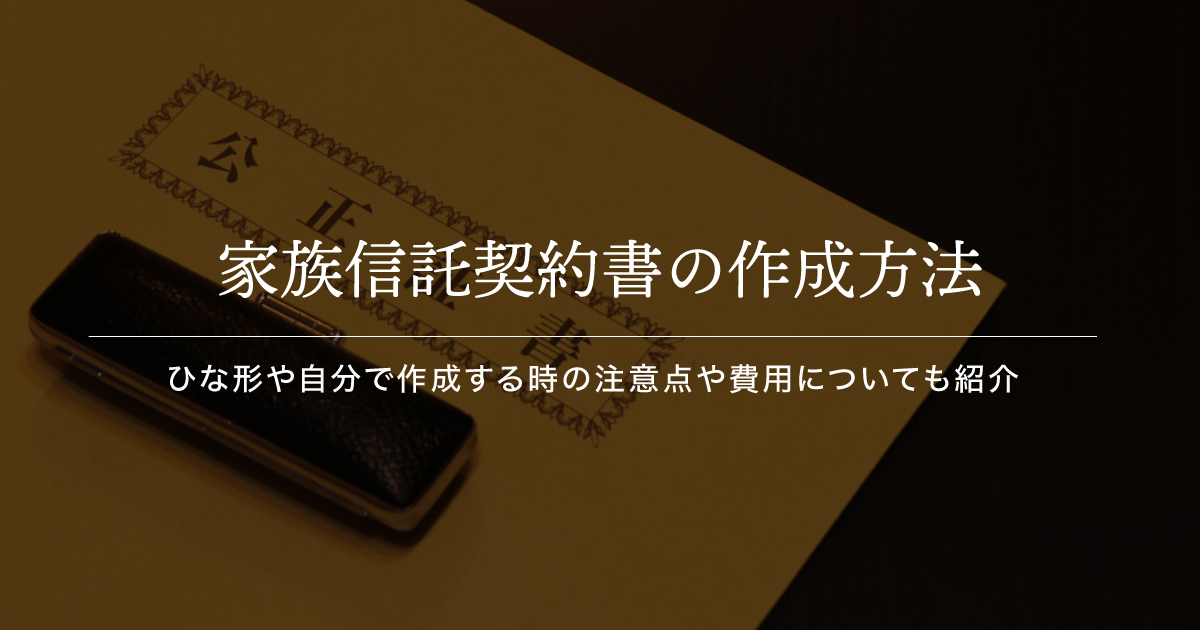
信託契約書を作成した後、不動産の名義を委託者から受託者へと移すことになります。
不動産が信託された旨の「所有権移転及び信託登記」を法務局に申請します。
申請時には、どの不動産の名義変更を行うのかがわかるように、信託財産の一覧表である「信託目録」を作成しておきます。
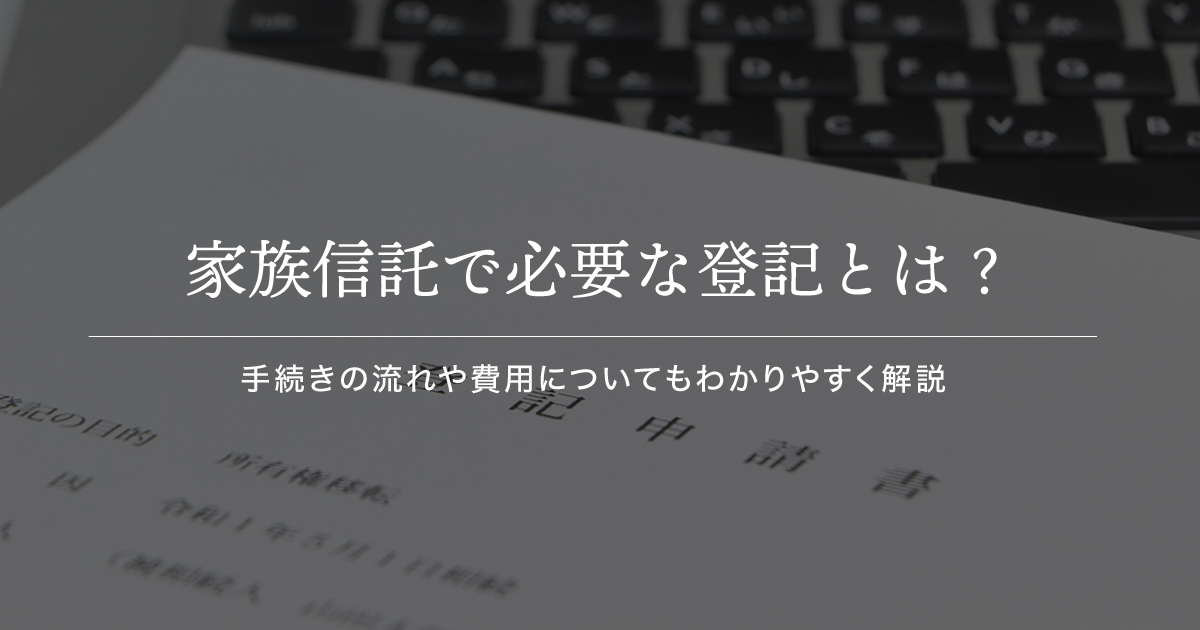
家族信託では、財産管理のための専用口座を開設し、開設した口座に信託財産を入金して分別管理します。
家族信託する不動産が収益性のある不動産であれば、賃料などの振込先口座も信託用の口座に変更しなければなりません。
また、該当する不動産の名義変更を行うことにより、信託した固定資産税の納税義務者も受託者に変わります。
固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)時点の所有者です。
登記が終了した翌年には受託者宛に納税通知書が届くようになります。受託者は、信託財産から納税資金を用意することになります。
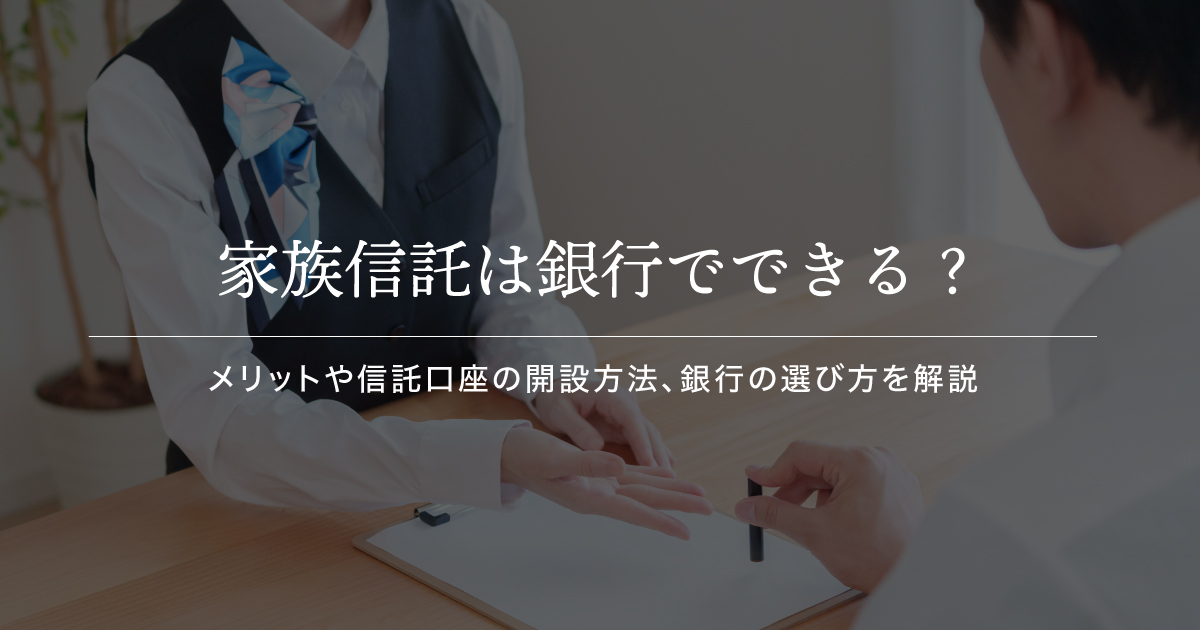

不動産の家族信託に関する手続きを自力で行うことは簡単ではないため、外部に手続きを依頼したいと考える方もいるでしょう。
そこで、不動産の家族信託の手続きを依頼できる人について解説します。
弁護士・司法書士は、信託契約を結ぶ前から契約を結んだ後までワンストップで相談できるため、安心して家族信託の手続きを進められます。
特に、家族信託はできてから間もない仕組みであるため、最新情報を仕入れ続けている専門家に依頼するのが良いでしょう。
弁護士・司法書士は、自身の専門分野にかかわる法制度については、常に最新情報を取り入れているため、家族信託にも精通している場合が多いです。
そのため、家族信託の手続きを安心して任せることができるでしょう。
また、不動産を信託財産に含む場合、信託登記が必要です。
信託登記は弁護士・司法書士しか代理できない業務です。弁護士・司法書士に依頼すれば、信託登記も含めて対応してもらえるでしょう。
不動産を管理すれば良いだけであれば、弁護士・司法書士でも十分です。
しかし、不動産を運用する予定がある場合、弁護士・司法書士は不動産運用のプロではないため、依頼するのが適切ではない場合もあります。
そこで、おすすめなのが不動産会社です。不動産会社は不動産運用のプロであるため、相談内容にも的確に答えてくれます。
手続きに関しては不動産会社内で対応できる場合もあれば、外部の弁護士・司法書士に依頼できる場合もあるため、適切な選択肢を選ぶと良いでしょう。
家族信託を利用しようと考えているけれど、どこから手を付けたらよいか判断に困る場合もあるでしょう。
その場合は、家族信託コーディネーターに依頼することも検討してみてください。
家族信託コーディネーターとは、家族信託の専門家との橋渡しをしてくれる存在です。家族信託についての説明や、家族信託に必要な物事を的確に教えてくれます。

まずは家族信託コーディネーターに相談し、家族信託への理解を深めることで、家族信託を利用すべきか、利用する場合はどのような契約にすべきかなどがわかるでしょう。
ファミトラでは、家族信託コーディネーターが窓口となって、皆様の家族信託を組成するお手伝いをしています。
家族信託の内容を決める際は、複数回の話し合いを行うなど家族が納得のいくまで協議を重ねることで、家族信託の契約内容で揉めることが少なくなるでしょう。
また、信託契約書の作成は弁護士に、信託登記は司法書士に依頼することで、安心して手続きを進められる環境も整えています。
家族信託についてどうしたら良いかわからなくても、一からお伝えしていきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

家族信託を司法書士・弁護士などの専門家に依頼した場合は、約50~100万円の費用がかかるといわれています。
目的や財産内容によっては100万円を超えることもあります。
| 内訳内容 | 費用 |
|---|---|
| 相談、コンサルティング料、契約書作成費用 信託財産の価格によって異なります。 | 約30~80万円 |
| 公正証書作成手数料 | 約3~10万円 |
| 登録免許税 信託財産に不動産が含まれている場合 | 不動産価格の1,000分の4に相当する額(相続の場合) |
| 信託登記を依頼する場合の報酬 | 約10~15万円 |
家族信託の手続きを弁護士・司法書士に依頼する際、家族信託の内容から考えてもらう場合にはコンサルティング料が必要です。
家族信託では、信託契約書に記載されている内容しか受託者は対応できません。そのため、抜けや漏れがあるともう一度契約し直さなければいけません。
もし、抜けや漏れが判明した際に委託者の判断能力が低下していると、契約を結び直すことができません。そのため、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
コンサルティング料の相場は約30〜80万円です。相場の幅が広いのは、信託財産の価格によってコンサルティング料が変動することが影響しています。
家族信託の契約書は、公正証書で作成するのが一般的です。
公正証書で作成しておくことで、契約書に信頼性をもたせられるため、後々トラブルに発展することを防ぐ効果があります。
公正証書は、公証役場に行き公証人に作成してもらうことになります。その際に手数料が必要です。
相場は3〜10万円ですが、信託契約の内容や信託する財産額によって変動します。
信託財産に不動産が含まれている場合、信託登記が必要です。
信託登記とは、不動産の名義人を委託者から受託者に変更する手続きのことです。
信託登記は自身で行うことも可能です。
しかし、信託登記は他の登記に比べても難しいため、専門家に依頼することをおすすめします。
費用は、8〜12万円が相場であると理解しておきましょう。
なお、登記手続きの代理は、弁護士か司法書士しかできません。家族信託に詳しい弁護士・司法書士に依頼しておけば、信託登記も含めて一括で対応してもらえます。
信託登記をする際には、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税の算定方法は以下のとおりです。
固定資産税評価額が1億円の土地を信託する場合、30万円を登録免許税として納めることになります。

家族信託後に不動産を売却するには、次の2つの方法があります。
ここでは、それぞれの方法について具体的な内容を解説します。
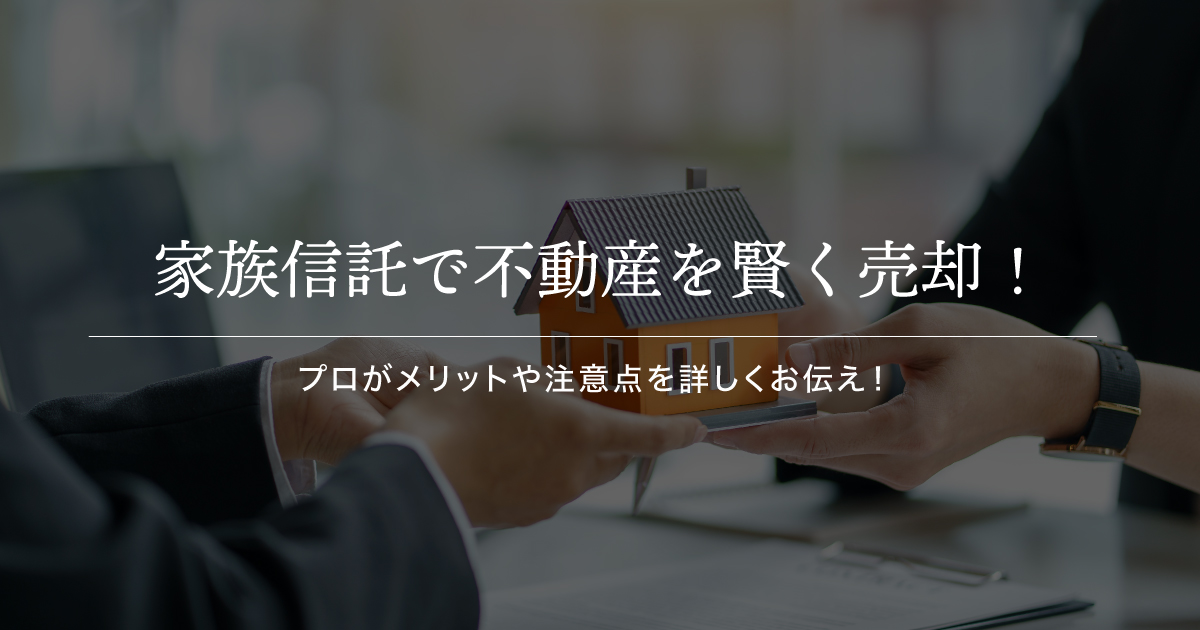
不動産自体を売却する場合は、通常の不動産の売却とほぼ同じ手順です。
所有者である委託者が売主でなく、受託者が売主となる点が異なります。不動産の売却で得た利益は、信託財産となります。
前提条件として、信託契約条項に信託不動産の売買が含まれていれば、信託の目的に沿って信託不動産を売却することが可能です。
受益権(財産権)とは、信託財産の管理・運用・処分から得られる利益を受ける権利です。
一例として、委託者である親の賃貸マンションを、受託者である子どもが管理をすることで発生した利益を享受する権利です。
受益者が売主となって、受益権(財産権)の対価として信託不動産の売買相当額を金銭で得ます。
受託者は、売却後も信託財産を引き続き管理しますが、信託財産から得られる収益は受益権(財産権)を持つ買主へ渡すことになります。
相続対策などの一環として、不動産自体ではなく受益権を子どもや同族法人へ売却する場合があります。
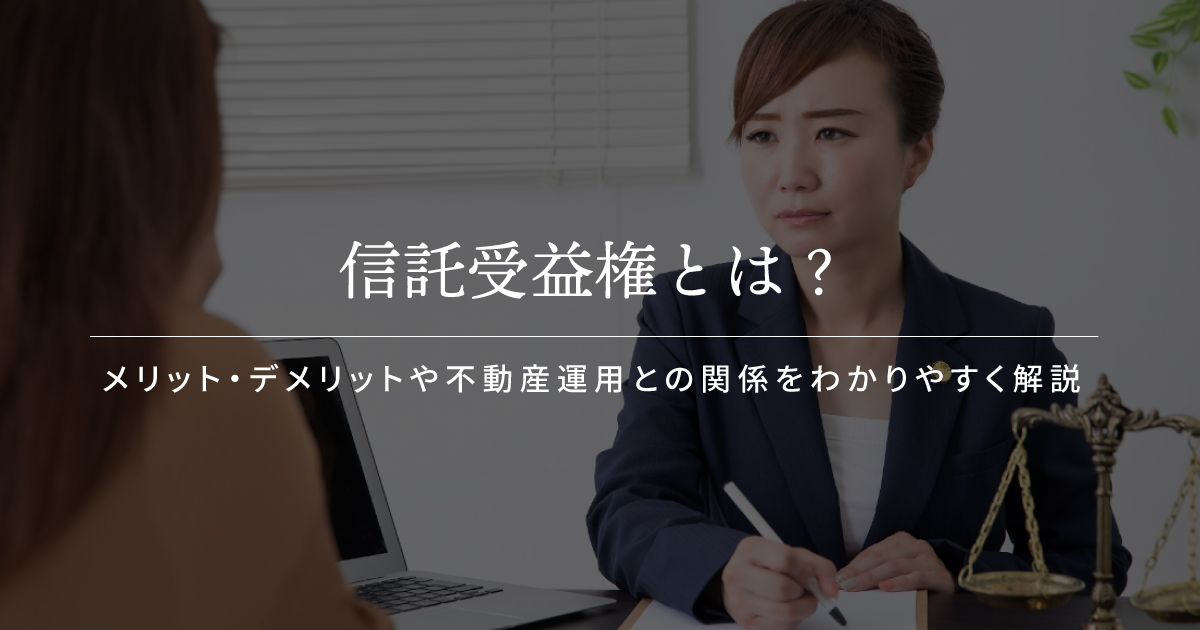

信託財産である不動産を売却しても、当然ながらその売却代金は信託財産のままであり、受益者のために用いるべき資産です。
信託不動産の売却代金により、新たに不動産を購入してもその不動産は信託不動産になります。
信託財産は、受託者が信託契約に基づきその権限内において管理・処分を行うのであれば、不動産や金銭といった形態を問わず信託財産のままです。
また、信託不動産を売却する際の売主は受託者ですが、通常どおり宅地建物取引業者に依頼して不動産を売却することが可能です。
信託不動産を売却する場合には、いくつかの注意点があります。
以下では、信託不動産に抵当権が設定されている場合と信託契約書の契約条項に関することの2つについて解説します。
家族信託した不動産を売却する場合、売却前に不動産登記の内容を確認しておく必要があります。
金融機関から融資を受けたことがあれば、物的担保として金融機関が抵当権を有していることがあるためです。
金融機関が抵当権を有している不動産の場合は「金融機関の承諾を得ることなく、担保不動産を第三者に移転できない」旨の条項が入っていることが通常です。
この場合、金融機関に相談し同意を得なければ契約違反であり、金融機関とのトラブルになりかねません。
抵当権を消滅させる条件は、金融機関・融資金額により異なることがあります。
判断できない場合には、専門家へ早めの相談をおすすめします。
信託不動産を売却する場合、家族信託の契約条項に″売買″の条項が必要になります。
″売買″の条項を定めることで、売買の権限を受託者に移すことができ、信託不動産の売却が可能です。
信託契約時には売却するつもりがなくても、将来的に売却する可能性があれば″売買″の条項を入れておくのがおすすめです。
委託者本人の判断能力があれば、家族信託の契約内容を変更する方法と、家族信託の契約を一旦解除し、委託者本人が売買する方法の2通りの解決策があります。
委託者本人の判断能力がない場合は、信託契約の変更や解除を行えません。
その場合は、信託終了事由の発生まで待つ必要があります。
信託終了事由には、例えば以下のようなものがあります。
委託者本人の判断能力がない場合は、不動産の売買が非常に困難になります。
そのため、″売買″の条項を入れた信託契約を締結することがおすすめです。

信託不動産を売却するときには、受託者が不動産業者に対して行うべき3つの手続きがあります。
信託不動産の売却手続きは、一般的な不動産の売却と変わりありません。
ただし、信託不動産の所有権は、信託契約により委託者から受託者に移っています。
そのため、委託者ではなく、形式的な所有者である受託者が不動産売却の手続きを行います。
不動産業者には、受託者自身に信託不動産の売却権限があることを知らせる方が良いでしょう。
上述のとおり家族信託は2006年の信託法改正で利用できるようになった新しい制度であるため、委託者による手続きが必要と考えている不動産業者がいるためです。
不動産業者には下記の2点を確実に伝えておく必要があります。
不動産の売買に当たっては、不動産売買契約書などを始め多くの書類への記名捺印が必要です。
契約書などの名義人欄には委託者の名前を書かずに「〇〇(委託者名)信託受託者 氏名」と記載しましょう。
単に受託者の氏名のみを記載すると信託契約上の契約行為でなく、受託者個人としての契約行為と間違われる可能性があるためです。
全ての関係書類には「〇〇(委託者名)信託受託者 氏名」と記載する必要があります。

信託不動産はどのように売却すれば良いのでしょうか。
ここでは、信託不動産を売却する手順を5つのステップに分けて解説します。
まずは、不動産仲介会社に売却の依頼をします。
不動産仲介会社に依頼せず、自分で売却先を探すことも可能ですが、多くの時間を要してしまうことが考えられます。
また、売却先が見つかっても、売却が完了するまでに様々な手続きが必要です。これらを自分で行うのはかなり大変でしょう。
不動産仲介会社に依頼すれば、これらの面倒な手続きも一任できるので、不動産仲介会社の利用をおすすめします。
買い手が見つかったら売買契約を締結します。
売買契約の締結も不動産仲介会社のサポートを受けながら進められます。
もし、契約締結後に家族内で揉めて売却を取りやめると、契約解除となり手付金の倍の金額を支払わなければなりません。
そのため、契約締結前に委託者や家族に伝えておくのが望ましいでしょう。
売買契約が締結できたら不動産を引き渡します。
不動産の引き渡しと同時に、売却代金の受領を行うことを理解しておきましょう。
この際、不動産の名義変更の登記手続きも行います。
ほとんどの場合、司法書士が手続きを代行してくれるため、必要な書類を用意するだけで問題ありません。
不動産の名義変更の登記手続きと同時に、信託抹消の手続きも必要になります。
不動産を信託状態ではなく、通常の状態に戻して引き渡しをするために必要な手続きです。
こちらも、名義変更の登記手続と同様、司法書士に代行してもらいましょう。
引き渡しの際に受領した売却代金を信託専用口座に入金します。
不動産の売却代金も、信託財産の売却によって得られたものなので信託財産になります。
信託財産は分けて管理する必要があるため、受託者が日常的に使用している口座ではなく、信託用の専用口座に入金することを忘れないようにしましょう。
万が一、受託者が日常的に使用している口座に入れてしまった場合は、トラブルになる可能性が高いので注意してください。

受託者は家族信託で管理している財産で不動産を購入できる場合があります。
ここでは、家族信託で管理している財産で不動産を購入する方法を解説します。
受託者が家族信託で管理している財産で不動産を購入するには、契約条項に″購入権限″の条項が必要です。
反対に、契約条項に″購入権限″の条項がなければ、基本的に家族信託で不動産を購入できません。
不動産を購入する際に信託金銭が足りないときには、融資が受けられる場合があります。
その場合は、融資を受けられる点や、その手続きについて信託契約書に規定をしておくようにしましょう。
信託契約書に融資の規定を置く際には、担保提供や借入金の返済方法など融資を受ける際の細かい条件まで記載するべきです。
追加信託とは、信託契約締結後に信託財産へ財産を追加することです。
綿密な計画の上で信託契約を締結しても、想定していなかった財産を信託財産に追加する必要が出てくる場合もあるでしょう。
一般的に不動産は、土地であれば路線価の変動に伴って価格が変動します。人気の物件であれば価格が高騰することもあるように、価格の変動リスクが伴います。
不動産購入時には、場合によっては資金不足となることもあるでしょう。
資金不足に備えて家族信託契約書に追加信託が可能な旨の条項があれば、信託財産への財産の追加は問題ありません。
家族信託を利用して不動産を購入する際には、以下の3つの流れが重要です。
家族信託で不動産を購入するには、まず信託契約書に不動産購入の権限が受託者に与えられているかを確認します。この権限が明記されていない場合、契約書の修正が必要です。また、購入に必要な資金が信託財産に十分にあるかを確認し、不足している場合は追加信託や金融機関からの借り入れを検討します。
不動産購入の手続きは、通常の不動産購入と同様に行われます。具体的には、購入の申込み、重要事項説明、売買契約の締結、手付金の支払い、残金の支払い、不動産の引き渡しが含まれます。これらの手続きは受託者が単独で行うことができます。
購入が完了したら、不動産の所有権移転登記を行う必要があります。家族信託の場合、通常の所有権移転登記に加えて「信託財産の処分による信託」の登記も必要です。これにより、購入した不動産が信託財産であることが公示されます。

任意後見制度と家族信託は、共通する部分はあるものの、お互い別の制度です。
目的に沿って、2つの制度を使い分ける必要があります。
任意後見制度は、本人の財産と生活を守る制度です。任意後見制度を利用し、任意後見人に本人の不動産を管理させることで、財産の毀損を防げます。
任意後見制度の特徴は、財産の保全に重きが置かれる点にあります。任意後見人は、本人が所有する財産の価値が目減りしないよう努めなければなりません。
投資などの財産の価値が減少する可能性のある行為は、認められていません。
保全の範囲内でしか財産を管理できない点で、任意後見人の権限には限界があります。
そのため、任意後見制度で与えられる任意後見人の権限は、限定的であるといえるでしょう。
ただし、任意後見制度は財産のみならず、身上保護までカバーします。
財産以外の生活部分の領域まで含む点で、任意後見制度は家族信託と異なる存在価値を持ちます。
任意後見制度で実現できる不動産管理は、家族信託よりも限定的です。
任意後見制度では難しい不動産管理の事例として、次のものが考えられます。
将来的に本人に利益をもたらす可能性のある不動産管理・処分であっても、財産保全の目的に反するおそれがある以上、任意後見制度では制限がかかります。
利益獲得を目的とする積極的な財産管理は、任意後見制度では難しい点を押さえておきましょう。
任意後見制度と家族信託は併用できます。任意後見制度と家族信託は、別目的の制度だからです。
双方の弱点を補えるため、ケースによっては任意後見制度と家族信託の併用はおすすめです。
家族信託を利用すると、任意後見制度よりも積極的な財産管理が可能になります。
しかし、家族信託の受託者には身上保護はできません。
財産管理のみならず身上保護まで望む場合は、任意後見制度との併用で、目的を達成できるでしょう。

不動産の信託には家族信託の他、信託銀行や信託会社に管理を任せる信託方法があります。
不動産収益のアップを目指すなど、より専門的な運用を期待する方は信託銀行や信託会社を通した信託方法も視野に入れると良いでしょう。
不動産管理の委託方法として、家族信託の他、信託銀行などの専門機関に依頼するパターンもあります。
信託銀行や信託会社などの専門家を通す財産管理は、商事信託と呼ばれます。
商事信託と家族信託の大きな違いは受託者です。
商事信託では、信託銀行や信託会社など専門家集団の手によって不動産が管理されます。家族信託と異なり商事信託ではプロが不動産を運用するため、運用利益を期待する方にとって商事信託はメリットが高いといえるでしょう。
家族信託では受託者を自由に選べます。
しかし、不動産管理に長けた人間が周囲にいるとは限りません。単なる管理にとどまらず、不動産を運用し収益を得たい場合は、商事信託の検討をおすすめします。
商事信託における、信託会社は2種類あります。管理型信託会社と運用型信託会社です。
管理型信託会社と運用型信託会社の違いは、信託会社に与えられる裁量の程度にあります。
管理型信託会社は、裁量が狭い会社です。
管理型信託会社は、自らの判断で不動産を運用するわけではなく、委託者の指示に従うのみです。
一方で、運用型信託会社の裁量は、管理型信託会社よりも広く設定されます。
運用型信託会社は、委託者の指示がなくとも自らの判断で不動産を運用できます。
商事信託を利用する際は、管理型信託会社と運用型信託会社の2種類がある点を押さえておきましょう。
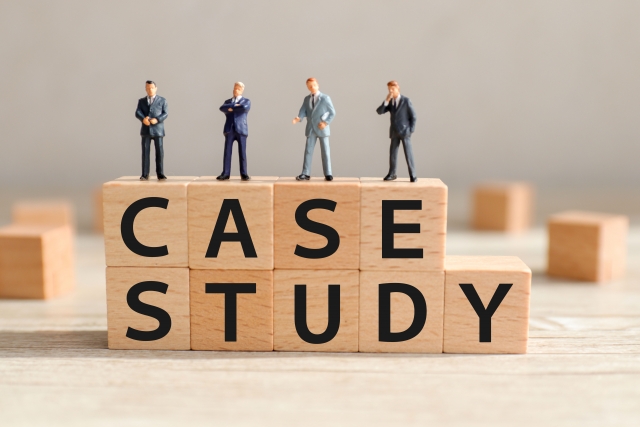
ファミトラの家族信託サービスをご利用いただいたお客様の中には、親の介護費用捻出のため自宅を売却した事例もあります。
ファミトラに相談いただくことで、関連会社の株式会社ファミトラリアルティで相続関連の不動産を中心とした総合的なご提案もあわせて行うことができます。
お客様のお手間を取らせることなく一括したソリューションでサービスを提供することも可能です。
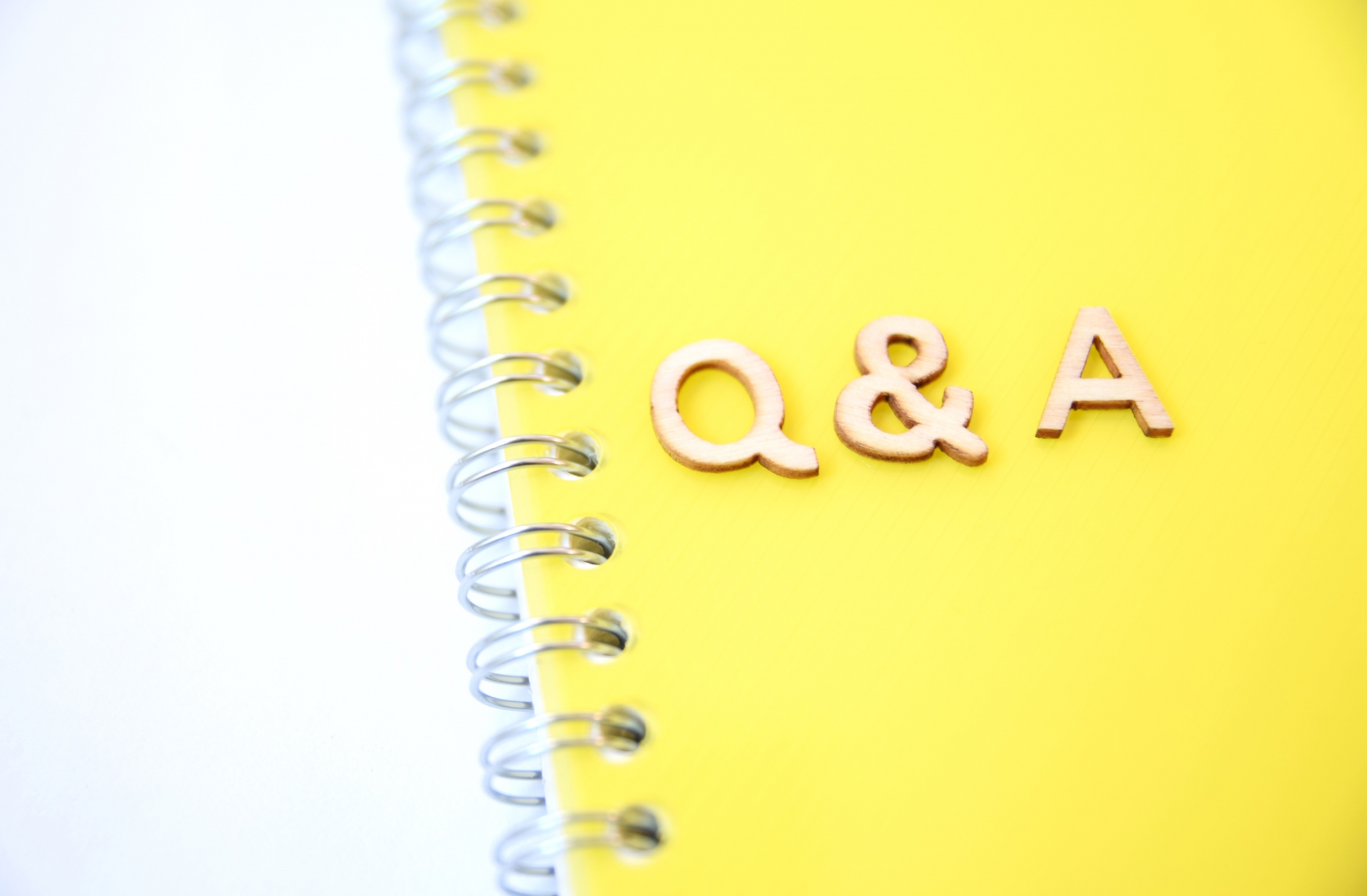
最後に、不動産の家族信託に関してよくある質問を9つ紹介します。
家族信託契約を結んでも、不動産を売却することは可能です。
ただし、家族信託契約に基づいて信託財産の管理・使用・売却などが規定されている場合は、それに従う必要があります。
また、売却に際して所得税などの税金が発生することもあるため、家族信託を組成したコンサルタント、法律専門家や税理士などの助言を受けることをおすすめします。
家族信託契約を結んだからといって、それだけで委託者に税金が課される事はありません。
ただし、自益信託を選択した場合には、委託者は受益者として税金がかかります。
詳細は家族信託を組成する際に、しっかりとコンサルタントや専門家に聞いておきましょう。
不動産だけの家族信託も可能です。
家族信託で信託する財産は、信託契約で任意に決められるため、不動産だけを信託しても預金口座だけを信託しても問題ありません。
とはいえ、一般的に不動産だけを信託するメリットは多くないでしょう。
不動産の信託が必要であれば、固定資産税の支払に必要なお金だけでなく、日常生活に必要なお金も信託しておく必要がないのかなども検討することをおすすめします。
自宅の家族信託も可能です。
もし、施設へ入所することになると、多額の保証金を用意しなければならない場合もあります。
施設へ入所すれば自宅に住む人はいなくなるため、自宅を売却することで保証金を賄おうと考えても、すでに判断能力が低下していれば自宅を売却できません。
そのため、保証金を用意できなくなってしまうことも考えられるでしょう。
自宅を家族信託しておいて必要な場合には売却し、資金を用意できる状態にしておくことがおすすめです。
不動産信託受益権とは、家族信託された不動産で得られた収益を受け取れる権利です。
家族信託には、不動産の所有者である委託者、不動産を管理する受託者、不動産から得た利益を得る受益者の三者がいます。
不動産の管理や運用は受託者が行い、それにより発生した利益は受益者が受け取るため、不動産信託受益権は家族信託における受益者にあります。
信託不動産の固定資産税は、受託者名義で払います。
不動産登記名義人のもとに、固定資産税納付書が届く仕組みになっているためです。
不動産を信託すると、不動産名義人が委託者から受託者へと変更されます。不動産名義人が受託者である以上、固定資産税は受託者名義で課税されます。
しかし、信託で利益を受けるのは、受託者ではなく受益者です。不動産から利益を受け取らない受託者が固定資産税を支払うのは不合理といえるでしょう。
そのため、信託契約で固定資産税の支払いは受益者がすると定めた上、受託者が信託財産(金銭)を用いて納税するのが一般的な流れです。
信託不動産で収益が発生した場合、受益者が確定申告を行います。
家族信託で利益を受け取る主体は受益者である以上、利益を受け取る受益者が納税手続きをする必要があるためです。
不動産オーナー(委託者兼受益者)が息子に賃貸管理を任せる場合、確定申告をするのは受益者たるオーナーです。
収益不動産を含む家族信託で確定申告をするのは、不動産から収益を受け取る受益者である点を確認しましょう。
家族信託契約書の内容に記載漏れや誤りがないか注意することです。契約締結前のチェックを怠ると、希望していた運用ができない可能性があります。
特に不動産の運用や売却に関することや受託者が行使可能な権限の範囲については、入念に確認しておきましょう。
また、家族信託の契約書として内容が適正であるかの検討も必要です。
たとえば、相続における遺留分に抵触する場合は、後に相続人との間でトラブルになる可能性があります。
信託財産の不動産を全て売却しても、原則として、家族信託は終了しません。
不動産を売却しても、信託財産の形態が不動産から金銭へと変化するだけだからです。
ただし、信託契約の内容で「信託財産の不動産の売却により信託が終了する」旨の定めがあれば、家族信託を終了することも可能です。
家族信託を行う目的を第一に考えて、家族信託を継続することと終了することのどちらが受益者にとって有益かを良く検討した上で家族信託を組成しましょう。

本記事では、家族信託を活用した不動産管理・売却について様々な視点から解説しました。
家族信託を利用して不動産を管理すれば、委託者が認知症などにより判断能力を失っても不動産の管理や売却が可能です。家族信託の利用は、認知症対策や相続対策にも繋がります。
ファミトラでは、家族信託についてのトータルサポートを行っています。不動産の売却など財産管理について興味のある方は、専任の担当者と専門家が対応していますので、お気軽にご相談ください。
24時間メールフォームから無料相談を受け付けています。ぜひ一度お問い合わせください。

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。