
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
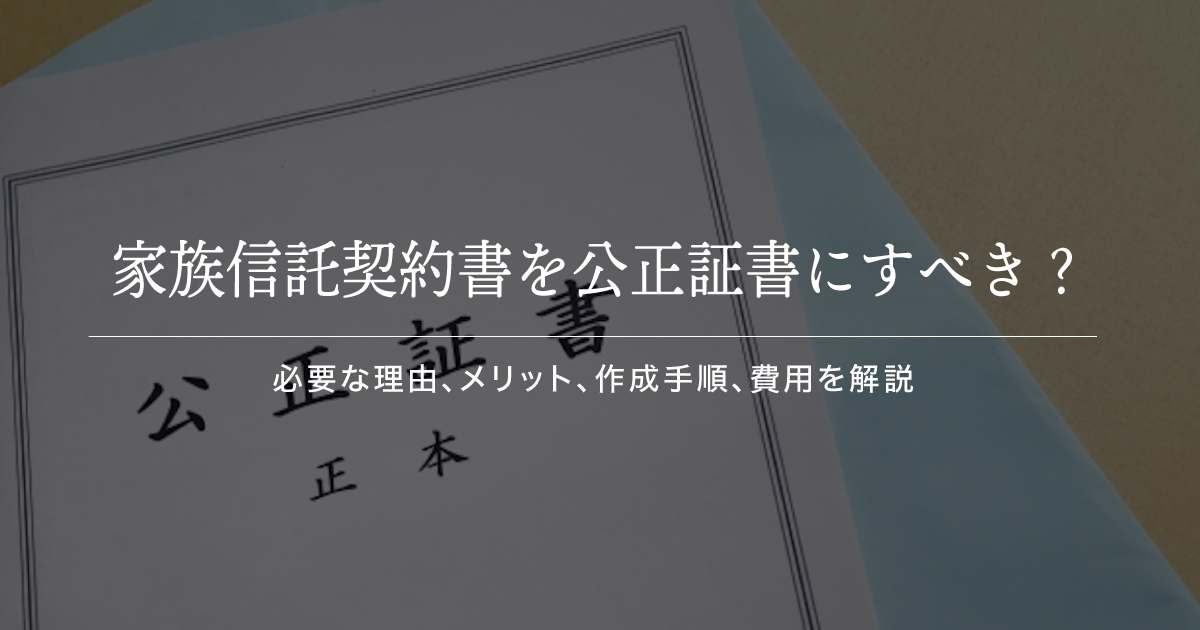
家族信託における契約書は公正証書で作成されることが多いです。しかし、契約書の公正証書化にはお金がかかります。
公正証書化せず、契約書を作成したいと考える方もいるかもしれません。
この記事では、公正証書で家族信託を組むべき理由や、公正証書の作成手順・費用などを解説します。家族信託契約書の作成方法が気になる方は、参考にしてみてください。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリット、必要性についてわかりやすく解説

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

家族信託は、第三者に財産にかかわる権限を与えて、財産を管理する仕組みです。
家族信託は、以下の三者で構成されます。
財産管理を委託する本人を委託者と呼び、管理を任される人を受託者と呼びます。財産が生む利益を受け取る人は受益者です。
受託者は、家族信託の契約内容に沿って、財産管理を進めます。契約内容が曖昧だと、受託者をうまくコントロールできず、委託者の意図しない結果を招くでしょう。
契約の定め次第で、家族信託がもたらす結果は大きく異なります。家族信託契約書の作成は、家族信託の根本部分といえます。
家族信託を組むにあたっては、家族信託契約書が必要です。
通常、契約は口頭のみでも成立します。
しかし、現実的には、契約書の作成なしでは手続きが進みません。
家族信託では信託専用口座の開設が必要になりますが、契約書なしで口座開設を認める金融機関は皆無に等しいためです。
家族信託を組むからには、契約書の作成は必須といえるでしょう。
ただし、家族信託の契約は、盛り込むべき内容が多く複雑になりがちです。家族信託で失敗しないために、契約書の作成にあたっては、専門家を頼ることをおすすめします。
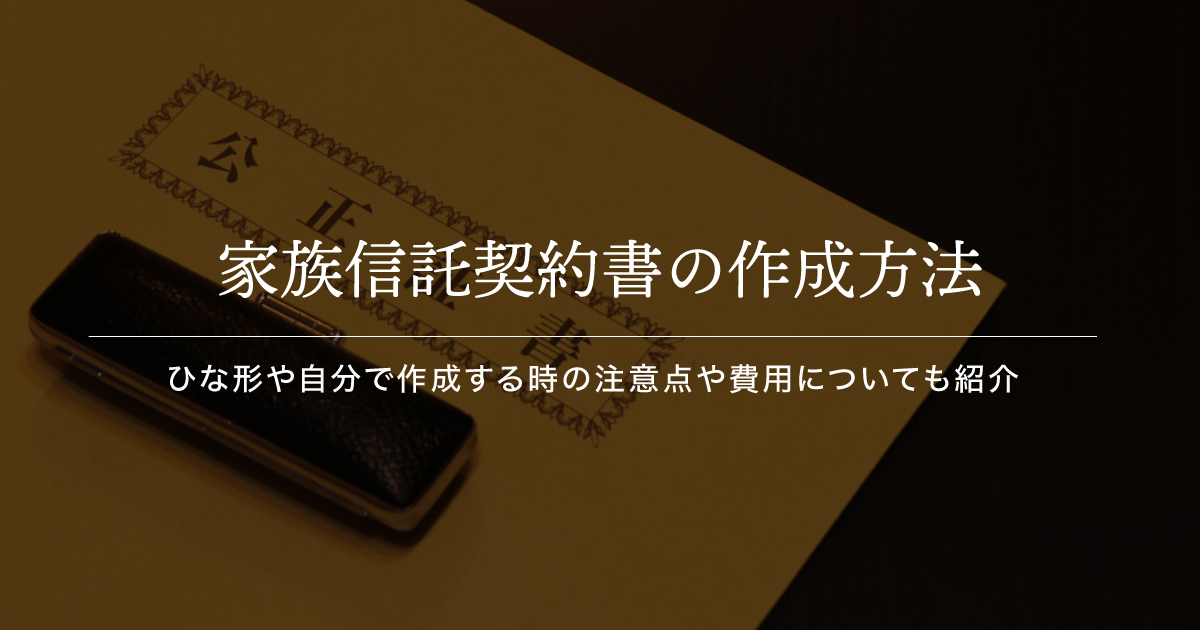
私文書の契約書で家族信託を組んでも、家族信託は有効です。
家族信託に関して、公正証書で契約すべきとする法律の規定はありません。
しかし実際のところ、家族信託契約書は、私文書ではなく公文書で作成することがほとんどです。
具体的には、公正証書で家族信託契約書を作成します。
公正証書は公証人が作成する公文書で、信頼性の点で私文書よりも優れています。
様々なトラブルが想定される家族信託では、契約書を公正証書化し公文書にするケースが通常です。

公正証書とは、公証人という公務員が、依頼を受けて作成する公文書のことです。
公証人は、元裁判官や検察官といった法律の専門家であり、作成される公正証書は信用性と証明力に優れています。
家族信託では委託者は家族とはいえ、自分の財産管理を別の人(受託者)に任せることになります。

不備や不明確な点があると契約が無効になって受託者が財産管理できなくなったり、契約の有効性について、他の相続人とトラブルになったりする可能性があるのです。
公正証書で作成しておけば、契約が無効になったり、相続人の間でトラブルになる心配が少ないため、家族信託を組成する際に有効といえるでしょう。

家族信託で契約書を公正証書化しておくメリットはどのような点にあるのでしょうか。
主なメリットを5つ解説します。
公正証書は信用性や証拠としての力(証明力)が高く、後に偽造や改ざんなどを理由に無効になる可能性が低いです。
家族信託では、委託者の子どもなど一部の相続人が受託者になるケースが多いです。
公正証書にせず当事者のみで契約書を作成した場合、相続が生じた際に契約書の不備や偽造などを理由に他の相続人から有効性を争われることが少なくありません。
公正証書の場合、法律の専門家である公証人が作成した公文書であるため、契約書の不備や偽造を争われる可能性は低く、契約の有効性をめぐるトラブルを回避できるのです。
公正証書で家族信託契約書を作成すると、契約当事者間の認識違いを防げます。
公正証書で契約を作成する際は、公証人が当事者の面前で契約内容を読み上げてくれるためです。
家族信託の契約内容は複雑であるため、書面のみの確認だと当事者が読み飛ばす可能性もあります。
読み飛ばしがあると内容の認識違いを招き、トラブルに繋がるかもしれません。
しかし、公正証書の場合、読み上げのプロセスがあります。
第三者である公証人が内容を読み上げることで、契約内容を漏らさず確認できるようになるでしょう。
家族信託契約書を公正証書で作成すると、改ざんの心配がなくなります。
公正証書で契約書を作成した場合、契約書の原本は、公証役場に保管されるためです。
私文書と異なり原本を第三者が保管するため、改ざんの恐れがなくなります。
私文書は個人が保管するため、紛失や改ざんのリスクがつきまといます。
改ざんを防ぎ、契約内容の確実な遂行を可能にする点で、契約書の公正証書化はメリットが高いといえるでしょう。
公証人からは公正証書の原本を受け取ることはできず、渡されるのは正本や謄本と呼ばれる写しのみです。
公正証書の原本は公証役場で保管されるため、仮に渡された正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行を受けられます。
家族信託は、人の生前の財産管理から死亡時の相続、内容によっては次世代の資産承継先を決めることもあり、10年以上続くケースも少なくありません。
当事者だけで契約書を作成した場合、長期の保管自体が難しい上に、相続人が保管場所を知らされなかったため想定していた資産承継を実現できない、といったこともあります。
公正証書は少なくとも20年間は公証役場で保管されるため、長期にわたって再発行ができる体制となっているのです。
万が一なくしてしまっても簡単に再発行できるため、公正証書で家族信託契約書を作成するのが良いでしょう。
信託口口座とは、受託者が信託財産を管理するために作成する専用の口座のことをいいます。
家族信託では、受託者は自身の財産と信託財産を別々に管理することが求められています。信託口口座は、受託者自身の預金と信託財産を分けて管理する上で便利です。
信託口口座を作るには金融機関で手続きを行う必要がありますが、ほとんどの場合、公正証書化を求められます。
また、不動産が信託財産に含まれているときは、信託財産になっていることを他の人に主張できるようにするために信託登記をする必要があります。
信託登記をする際は、登記の項目と公正証書に記載されている項目が一部重複するため、登記申請をスムーズに行うことができるのです。

公正証書で作成しない場合に、具体的にどのような問題があるのでしょうか。
特に把握しておくべき注意点を4点解説します。
家族信託契約書を有効に作成するには、信託法や民法などの法律知識、課税関係に関する税務知識などの専門的な知識が必要になります。
また、思い通りの設計を実現するには、金融機関などの当事者以外の関係者にも認めてもらえるように実務上の取扱いを知っておくことも必要となるでしょう。
専門知識や実務経験に乏しい本人が作成した場合には、契約書の不備などに気づかず、契約が無効になったり、金融機関に受け付けてもらえなかったりする可能性があります。
私文書での家族信託契約書の作成には、紛失や盗難のリスクがつきまといます。
家族信託契約は、継続期間が長期間続くため、契約書の紛失や盗難のリスクはとくに高いです。
契約書が紛失してしまうと、契約内容を証明する材料が消失し、事実上、契約は無効の扱いになります。
あらためて家族信託契約を締結する方法もありますが、本人がすでに認知症になっていた場合、家族信託は契約できません。
一方、公正証書で家族信託を組んだ場合、契約書の原本は公証役場に保管されます。公正証書にしておくと、個人で保管する必要がないため、紛失や盗難の心配はなくなります。
当事者間で契約書を作成する場合は単なる私文書ですので、後で有効性について争いが生じる可能性があります。
例えば、高齢の親が委託者で、何人かいる子どものうちの1人が受託者となり、相続時には受託者であった子どもが受益権を取得できるような信託契約を結ぶ場合です。
このような場合、後で相続人となる他の子どもから親の判断能力がなかったことを理由に信託契約の無効を主張され、契約書の有効性が問題となることが少なくありません。
家族信託契約書について、まずは当事者間のみで作成しておき、必要になったタイミングで公正証書化しようと考えている人もいるでしょう。
しかし、適切なタイミングを逃すと、公正証書化できなくなることもありますので、注意が必要です。
例えば、公正証書を作成する際には公証人による本人の意思確認が必要になります。本人が認知症により判断能力がなくなっている場合には作成できません。
当事者で家族信託契約書を作成した時点で判断能力があったとしても、公正証書を作成するときに判断能力がなければ公正証書化はできませんので、気を付けましょう。

家族信託契約書を公正証書化することで生じてしまうデメリットはあるのでしょうか。
注意すべきデメリット3点を説明します。
公正証書は、専門家である公証人に作成してもらう証明力の高い公文書であることから、作成してもらうには手数料が必要です。
具体的な費用は、信託財産の評価額に応じて違います。詳細は後述しますが、例えば、評価額が3,000万円の場合、2万円〜3万円程度必要です。
当事者間で作成する契約書であれば、かかる費用としては収入印紙代とその他の実費くらいなので、作成費用がかかることはデメリットといえるでしょう。
公正証書で契約書を作成すると、当事者のきめ細かい要望が契約内容から抜け落ちる可能性があります。
ひな形が使用される結果、当事者の契約内容が一般化されるからです。
公正証書は、公証人が当事者の話をまとめることで完成します。
話を文章化する際、公証人はひな形を使用する場合があり、当事者の契約内容もひな形に沿った内容にカスタマイズされるかもしれません。
契約内容がカスタマイズされると、当事者の細かい要望が反映されなくなるデメリットが生じます。
公正証書を作成するためには、公証役場へ赴いて公証人と契約内容などについて入念な打ち合わせをする必要があります。
そのため、当事者のみで契約書を作成する場合と比べて、作成までにどうしても手間と時間がかかってしまうのです。
もっとも、最終的な本人の意思確認以外の事前の打ち合わせなどは、司法司書や弁護士などの専門家に代理して行ってもらえば、手間を減らすことができます。
また、公正証書で作成することのメリットを考えれば、手間や時間をかけてでも公正証書で作成すべきといえるでしょう。

自分で公正証書の作成手続きを行う場合の流れは以下のとおりです。
誰に、どの財産を信託し、どのように管理するのか、などについて入念に決めておきましょう。
後のトラブルを避けるために、契約当事者にならない家族にも、信託契約の内容を話しておくことが望ましいです。
※公証役場とは
打ち合わせは複数回にわたることがあります。
事前に必要な書類や費用を確認しておけば、手続きをスムーズに進めることが可能です。
公証人との打ち合わせで準備が整ったら、公正証書を作成してもらいます。
当日は、公証人による本人確認、契約内容の読み上げを行います。
問題がなければ、公正証書となる書面に本人と公証人が署名・押印を行い、作成費用を支払って手続き終了です。
公証人に依頼して、公正証書の写し(正本、謄本)を交付してもらいます。
専門家に依頼して公正証書の作成手続きを行う場合の流れは以下のとおりです。
初回の面談時には、家族信託の実務経験が十分にあるかどうかや、必要となる費用について確認しておきましょう。
専門家に希望を伝えて信託契約の素案を作成してもらいます。
打ち合わせの前に、自分の希望を整理しておくと、専門家に伝わりやすいでしょう。
公証人との打ち合わせは専門家が行ってくれるため、本人が出向く必要はありません。
専門家と公証人が打ち合わせをして作成した公正証書の原案を、本人が確認します。
専門家に依頼する場合でも、作成日当日は専門家だけではなく原則として本人も公証役場に出向く必要があります。
当日の手続き内容は本人が作成手続きをする場合と同じです。
交付請求手続きも専門家に頼めば行ってくれる場合が多いです。
公正証書作成にあたっては、公証人に出張してもらうこともできます。
公正証書を作成する際は、公証役場に出向くのが基本です。
しかし、委託者が身体障がい者であるなど、当事者が公証役場まで出向くのが難しい場合もあるでしょう。
当事者が出向けない際に備えて、公証役場は出張サービスを実施しています。
費用は割り増しになりますが、公証役場に出向けない方にとっては便利です。
出張サービスを利用する方は、契約内容の確認など事前の準備をしておきましょう。準備することで、現場での手続きが円滑に進みます。
なお、出張サービス利用の際は、公証役場の管轄をチェックすることも必要です。管轄によって、出張可能な範囲が異なるためです。

家族信託契約書の公正証書化でかかる費用を解説します。契約書を公正証書化する際は、事前に発生する費用を確認しましょう。
公正証書化の手続きは専門家に依頼できますが、専門家に支払う報酬が別途発生します。
委託者と受託者それぞれの本人確認書類と印鑑、公正証書の作成費用が必要です。
求められる本人確認書類の組み合わせは下記のとおりです。
上記の組み合わせのうち、いずれかを準備しておけば問題ありません。
認印の代わりに実印を持っていくことも可能です。
公正証書を作成する費用は、信託財産の評価額によって変わります。
具体的な金額は下記表のとおりです。
| 信託財産の評価額 | 費用(手数料) |
|---|---|
| 〜100万円 | 5,000円 |
| 100万円超え 〜200万円 | 7,000円 |
| 200万円超え 〜500万円 | 11,000円 |
| 500万円超え 〜1,000万円 | 17,000円 |
| 1,000万円超え 〜3,000万円 | 23,000円 |
| 3,000万円超え 〜5,000万円 | 29,000円 |
| 5,000万円超え 〜1億円 | 43,000円 |
| 1億円超え 〜3億円 | 43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円を加えた額 ※例えば、評価額2億円の場合 69,000円(=43,000円+13,000円×2) |
| 3億円超え 〜10億円 | 95,000円+超過額5,000万円までごとに11,000円を加えた額 ※例えば、評価額4億5,000万円の場合 12,8000円(=95,000円+11,000円×3) |
| 10億円超え | 249,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加えた額 ※例えば、評価額15億円の場合 409,000円(=329,000円+8,000円×10) |
公正証書の作成手続きを、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。専門家に依頼した場合の相場は、10〜15万円程度です。
10〜15万円のお金は専門家に報酬として支払う費用であり、実費は別に発生します。
コストはかかりますが、専門家に手続き依頼した場合、公証人との打ち合わせも含めてお願いできます。
公正証書で契約書を作成するときは、契約書に定めたい内容を公証人に上手に伝えられるかがポイントになります。
弁護士や司法書士であれば、契約書の作成に慣れているため、公証人とのやり取りもスムーズに進むでしょう。
公証人の出張を求める場合の費用を紹介します。
費用の内訳は、次のとおりです。
公証人費用は、通常の1.5倍の金額になります。具体的な金額は、既出の表を参考にしてください。
文書料は、紙の枚数によって変わり、1枚あたり250円で算出します。
日当は1日あたり20,000円です(4時間以内の場合は10,000円)。
交通費は前もって料金が決まっておらず、現場までの距離や公証人の交通手段によります交通費を安くするためにも、現場からの距離が近い公証役場を選びましょう。
証人を手配する方は、手配料として6,000〜9,000円が発生します。
なお、本人の意思確認のために病院や自宅に公証人が出張した場合や、正本、謄本を取得する場合は、別途出張日当や、正本などの交付手数料が必要となることがあります。

家族信託契約書はどのような場合でも公正証書で作成すべきなのでしょうか。
特に、公正証書で作成すべき3つのケースをご紹介します。
あらかじめ家族・親族間でトラブルが予想される場合には、公正証書によって家族信託契約書を作成しておくべきでしょう。
例えば、父が委託者兼受益者、複数人いる子どものうちの1人が受託者となる信託契約において、父の死亡により相続などで受託者である子どもだけが受益権を取得する場合です。
他の子ども(すなわち、受託者の兄弟姉妹)が事前に契約内容を知っていないと、「父は認知症で契約書の作成能力はなかった」「契約書は偽造されたものだ」などとして後から有効性を争われかねません。
相続人となりうる家族には事前に内容を伝えて契約書を作成すべきですが、伝えることが難しい場合は、特に契約書を公正証書で作成するのが良いでしょう。
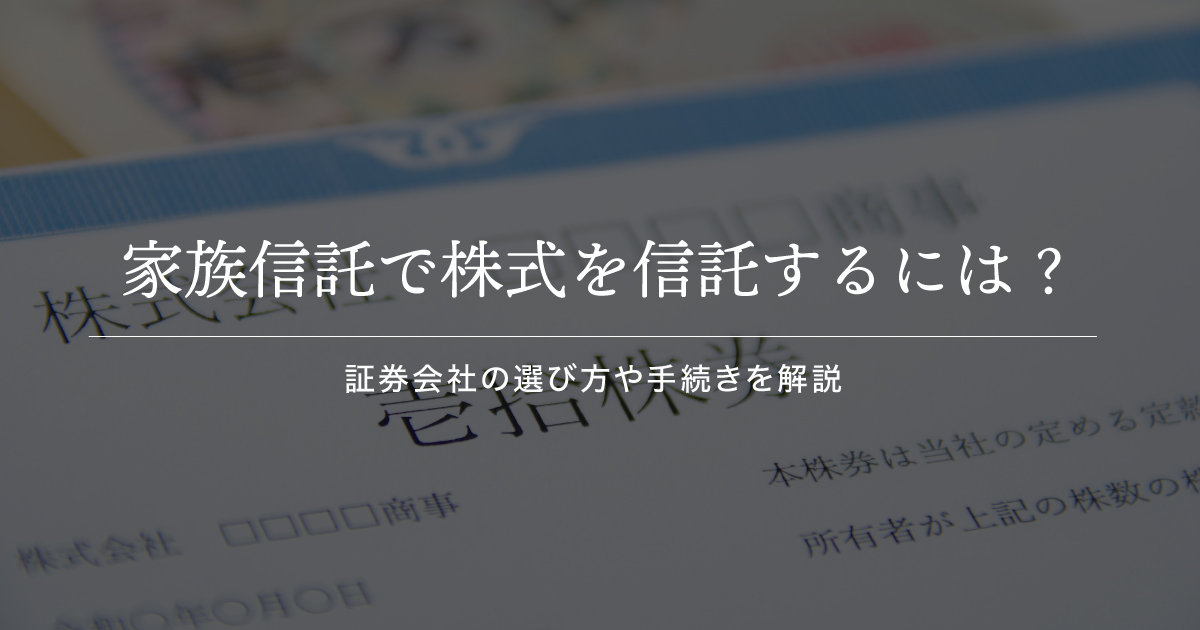

銀行や証券会社といった金融機関が関係するときは、ほとんどの場合、公正証書による作成を求められます。
例えば、信託財産に株券があり証券会社とやりとりをする必要がある場合や、信託財産である不動産を担保に入れて銀行から融資を受ける場合などです。
金融機関では、家族信託契約書の有効性を確認するために、社内規定において公正証書であることを取り扱う要件としていることもあります。
そのため、公正証書で作成しておかないと、金融機関に有効な契約書として扱ってもらえないといった事態になりかねません。
そういった事態を避けるためにも、株券や不動産が信託財産に含まれるなど、金融機関が関係する可能性があるときは、公正証書で作成しておくべきでしょう。
自己信託では、公正証書での契約書作成は必須です。
自己信託の場合、原則として、公正証書での契約書作成が契約の効力要件となっています(信託法4条3項)。
自己信託は、委託者と受託者が同一人物になる信託契約です。
委託者が自己所有の財産を、第三者(受益者)のために自ら管理する場合、自己信託となります。
信託契約は、委託者と受託者の間で交わされるのが通常です。
しかし、自己信託に限っては、委託者=受託者となるため、公正証書で契約書を作成しなければ効力が発生しない決まりになっています。
自己信託を組む際は、公正証書での契約書の作成が必須である点を、押さえておきましょう。
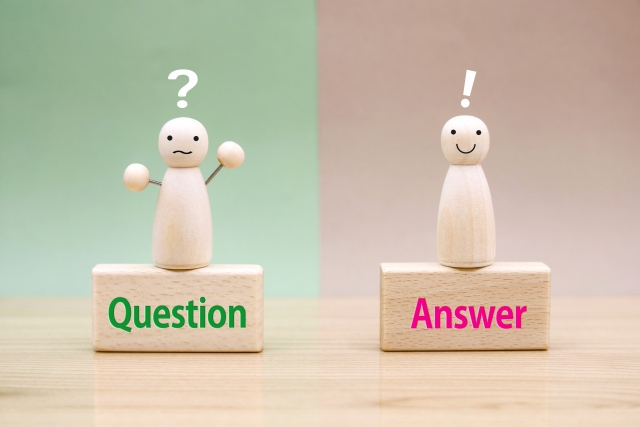
ここでは家族信託契約書の公正証書化に関して、よくある質問に回答します。
代理人が出席して作成することも可能ですが、本人が出席する方が望ましいです。
公正証書を作成する際は、基本的に本人が公証役場に出向く必要があります。
公証人が本人の意思を確認した上で、署名押印などの公正証書の作成手続きを行う必要があるためです。
司法書士や弁護士などの専門家が代理人として公証役場へ出向くことで、本人が出席しないことも例外的に認められています。
もっとも、公証役場によっては代理人のみによる出席を認めない場合もありますので、原則通り本人が出席しておく方が無難といえるでしょう。
目安として1週間から1カ月程度の期間がかかります。
公証人は、当事者が作成した家族信託契約書の草案について、契約の有効性に問題ないかなど法的なチェックを行います。
そのため、事前に必要書類などの準備が十分できていたとしても、早くとも1週間程度はかかることが多いです。
また、契約内容が複雑な場合や必要書類に不備があった場合、公証役場が他に多くの案件を抱えているような場には、1カ月以上待たされることもあります。
1週間から1カ月程度というのはあくまでも目安ですので、余裕をもった準備を心掛けましょう。
利害関係のある方は、公正証書作成の現場に立ち会うことができません。
利害関係人が公正証書作成の現場に同席すると、契約当事者に何らかの圧迫を与える恐れがあるためです。
親族が利害関係人に該当するか否かは、ケースバイケースです。
しかし、親族は信託財産の帰属先に指定される場合が多く、利害関係人に該当する可能性が高いです。
公正証書の内容が立ち会う親族に不利益に働く場合、立ち会った親族は自分に有利になるよう契約内容の変更を求めるかもしれません。
そのため、親族が立ち会える可能性は低いと考えて良いでしょう。
公正証書作成時の判断能力は、公証人が判断します。医師の診断で決まるわけではありません。
契約当事者の判断能力が備わっていると公証人が判断すれば、公正証書の作成が認められます。
公証人が判断するポイントは様々ですが、一般的には、以下のポイントがチェック項目とされています。
上記項目は、あくまで目安です。最終的には、公証人の判断に委ねられます。
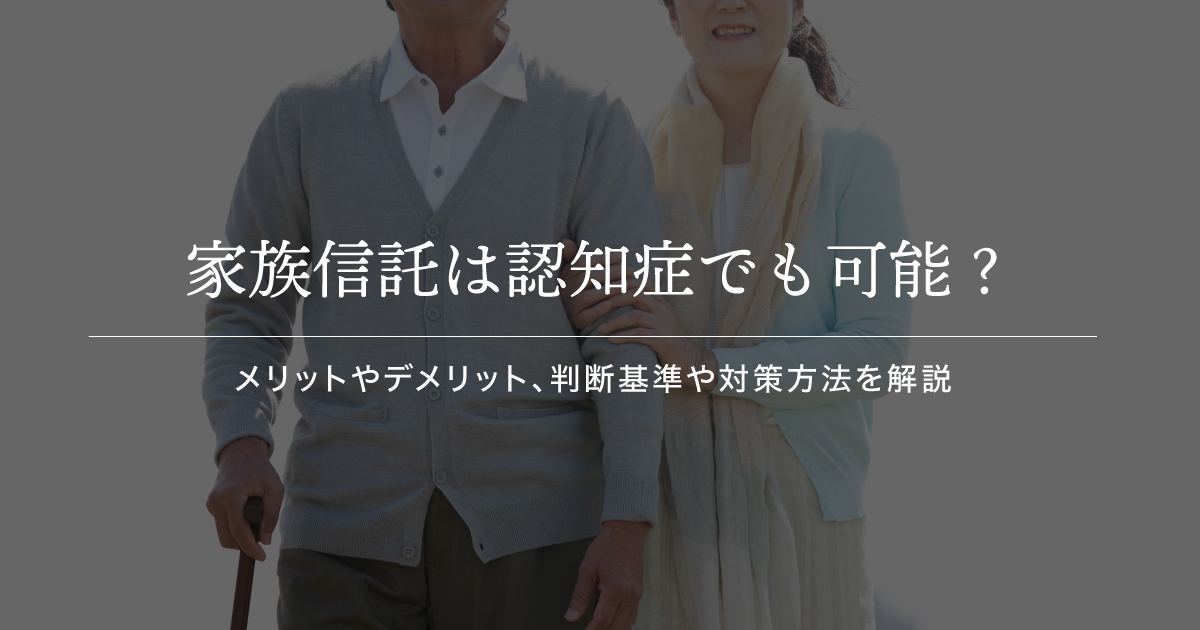

公正証書で家族信託契約書を作成すると、契約の有効性が増します。私文書で家族信託契約書を作成すればコストは安くすみます。
しかし、家族信託は契約の継続期間が長く、他の契約類型にくらべて、紛失や盗難のリスクが高いです。
この点、公正証書で契約書を作成すれば、公証役場に原本が保管されるため、紛失や盗難のリスクを防げます。
家族信託の内容を確実に遂行してもらうためには、公正証書による契約書の作成は欠かせません。
ファミトラでは家族信託の無料相談を実施しています。家族信託の契約書作成で気になる点があれば、ファミトラまでご相談ください。

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。