
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中


活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
認知症保険は高齢化社会の進行に伴い、認知症に備えて加入する保険です。認知症になった場合に、保険金や給付金を受け取ることができます。
保険会社により商品内容は異なりますが、一般的に公的介護保険や民間の介護保険で対応できない部分に特化したものが多いといえます。
本記事では認知症保険の特徴や必要性、メリット・デメリットをわかりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

認知症保険は、認知症になった場合に備えて加入する保険です。認知症保険には、他の介護保険にはない様々な特徴があります。
ここでは、認知症保険の役割や特徴を具体的に解説します。
認知症保険は、その名のとおり認知症となった場合に、保険金や給付金を受け取れる保険です。何をもって認知症と判断するのかなど、保険金の支払条件は保険会社によって異なります。
認知症になると介護のために高額の費用が必要です。また、認知症が原因で第三者に損害を与えてしまうことも考えられます。
認知症保険は、認知症を原因とする出費に備えるための保険です。
認知症になった場合に利用が想定される保険として、認知症保険の他に介護保険があります。
認知症保険と介護保険の大きな違いは、認知症保険の受給要件が「認知症と診断されたこと」であるのに対し、介護保険の受給要件は「要介護と認定されたこと」であることです。
また、認知症保険は任意保険のみであるのに対し、介護保険は公的保険と任意保険が存在する点も異なります。介護保険は、40歳以上の人は加入しなければならず、介護保険料を納める必要があります。一方、認知症保険は任意保険のみであり、必要のない人は加入する義務がありません。
介護保険では、要介護認定や所得によって異なりますが、介護サービスを1~3割負担で受けることができます。
よって、認知症になり介護が必要となった場合、介護保険の自己負担分を自己資金で賄えるのであれば認知症保険に加入しなくても良いと考えられます。
認知症保険は歴史の浅い保険であり、加入条件や保険金の支払条件も保険会社によって様々です。
そのため、認知症保険の特徴といっても、全ての認知症保険に当てはまるものではありません。
ここでは、多くの認知症保険に共通する特徴について解説します。
認知症保険では認知症と診断されると、保険金や給付金などを現金で受け取ることができます。
公的な介護保険や医療保険では、介護サービスや治療などを受けることはできますが、現金の給付はありません。認知症になると、介護保険や医療保険ではカバーできない費用負担も発生します。
認知症保険と公的な保険を併用することで、介護サービスや治療を受けられるだけでなく、日常生活や介護で発生する費用について準備することができます。
認知症保険は保険金の支払基準が統一されておらず、保険会社によって支払基準は様々です。
支払基準を大まかに分類すると次の3つに分けられます。
非連動型は、保険会社が独自の支払基準を設定している保険のことです。一方、連動型は、公的介護保険の認定基準に従って支払基準を設定している保険のことです。
公的介護保険では、被保険者の症状によって、要支援1・2、要介護1〜5の7段階で等級認定をしています。
連動型保険は要介護1以上と認定されれば保険金を支払うなど、公的機関による認定に合わせて保険金を支払います。
一部連動型は公的介護保険の認定基準と保険金の支払基準を連動させながら、それに加えて保険会社独自の支払基準を設定する保険です。
つまり、支払基準は保険会社によって厳しいものや、緩やかなものがあります。
保険料や保険金の額なども比較考慮しつつ、どの保険に加入するのかを検討する必要があります。
指定代理請求制度とは、あらかじめ被保険者が指定した代理人が保険金の請求を行える制度のことです。
被保険者が認知症となった場合には、被保険者が自ら保険金を請求するのは難しいでしょう。
そのため、認知症保険では指定代理請求制度を活用し、あらかじめ保険金請求の代理人を決めておくことで、問題なく保険金請求ができるようにしています。
なお、指定代理人が被保険者と同居していない場合などは、保険金請求が必要なときに請求ができるように、指定代理人とスムーズに連絡が取れるようにしておきましょう。
家族間で誰が指定代理人であるのかを共有しておくことが重要です。
認知症保険で給付される保険金には、主に下記のものがあります。
以下で詳しく解説します。
認知症診断一時金は、認知症になったときに保険会社が定める一定の条件を満たすことで、一時金を受け取ることが可能です。
認知症になると多くの費用が発生するため、認知症と診断された場合に一時金で備えておきます。
保障内容や申し込み可能な年齢などは、保険会社により異なりますので問い合わせが必要です。
認知症介護年金は、介護に必要な費用を一時金でなく年金として受け取るタイプです。
特約として年金で生涯受け取ることや、重度の認知症の場合には年金額が加算されるものもあります。
保障内容は所定の要介護状態が継続したり、公的介護保険制度の要介護度によって特約年金額が支払われたりするものなどがあります。
上記の一時金や年金タイプ以外にも、様々なその他の給付金があります。
主なものは下記の通りです。
上記の予防給付金を利用して、認知症の前段階のMCI(軽度認知障害)のリスクを調べることができるものもあります。
認知症保険の保険金給付条件は、保険会社や保険商品により様々です。
具体例を挙げると、以下の給付条件に該当する場合には、給付対象となる商品が多く見受けられます。
認知症と診断されるだけで保険金を受け取れるのではなく、保険会社が定める上記のような保険金給付条件を満たさなければなりません。
認知症保険の保険金給付条件は保険会社により異なるため、加入に当たっては十分に検討しましょう。
損害保険会社が取り扱っている認知症保険もあります。
認知症になったことが原因で第三者に怪我を負わせるなど、損害を与えた場合の個人賠償責任を補償する認知症保険です。
また、認知症による徘徊で行方不明になったときの捜索費用補償などもあります。
認知症によるトラブルは予想がつきにくいものが多いため、人的・物的なトラブルへ対処する保険として使用されます。
一部の自治体では認知症高齢者による賠償事故のリスクに鑑み、認知症の住民の賠償保障や被害者への補償を行うところも増加しました。
この場合、自治体が契約者となり、被保険者が認知症の住民です。多くの場合、自治体が保険料を負担します。

ここまで認知症保険の特徴を中心に解説しました。
高齢者が認知症になるリスクは高く、認知症になれば多額の費用がかかります。
以下では、高齢者の認知症リスク・認知症で必要な介護費用・認知症保険の加入率について見ていきます。
厚生労働省の「簡易生命表」によれば、令和4年(2022年)の日本人の平均寿命は以下の通りです。
平成2年(1990年)の日本人の平均寿命は男性75.02歳、女性81.90歳であったことからすると、日本人の平均寿命の延伸が進んでいることがわかります。
一方で、令和4年(2022年)の合計特殊出生率は1.26%で過去最低となり、少子化が進んでいることがわかります。
つまり、日本は少子高齢化が進んでおり、高齢者の割合が増加している状況なのです。高齢者の割合が増加すると、高齢化に伴う認知症患者の割合も増加します。
認知症患者が増加すれば、認知症になった場合に備えて保険に加入しておきたい人が増えます。
このように、日本では少子高齢化が進むに伴い、認知症保険が普及していったのです。
日本では少子高齢化が進んでおり、人口に占める高齢者の割合は増加を続けています。
平均寿命も伸びているため、「高齢者」として過ごす期間も短いものではありません。
厚生労働省の統計によると、2020年の時点では65歳以上の高齢者のうち、約600万人が認知症となっています。
さらに2025年になると、認知症患者の数は約700万人にまで増加し、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症は、高齢者であれば誰の身にでも起こりうる重大な問題であるといえます。
自分は大丈夫と考えるのは危険です。誰にとっても認知症に対する備えは必要です。
介護に要した費用のうち、毎月支払っている費用は平均8.3万円です。年間で約100万円かかります。他に一時的な費用として、住宅改造費・介護ベッドの購入費などの合計額は約74万円です。
一方で、個人年金保険加入世帯の基本年金額の年額の世帯合計額は、97.1万円となっています。
介護費用には、世帯の基本年金額の年額が充てられるほどの多額の費用が必要です。
また、認知症介護では、通常の介護に比べると常に付き添う必要もあり、多くの介護サービスを長時間にわたって受けることで介護費用の負担が増加する可能性もあります。
多額の費用の心配をしたくない方には、認知症保険は検討材料の1つといえるでしょう。

公益財団法人生命保険文化センターによる2021年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、認知症保険の加入率は6.6%となっています。
一般的な医療保険の加入率が93.6%であることからすると、かなり低い数字といえるでしょう。
認知症保険の加入率が低い理由としては、認知症保険が歴史の浅い保険で一般的な認知度も低いことが挙げられます。今後、高齢化がますます進み認知症患者の数も増えてくると、認知症保険の加入率も上昇する可能性は高いでしょう。

認知症保険には、当然ながら保険料の支払いが生じます。
保険料を支払う価値があるのか判断するためにも、認知症保険への加入が有効な場合を知っておくことは有効です。
認知症保険に加入すれば、費用面で手厚いサポートを受けることが可能です。認知症にかかる費用は、思いのほか広範囲にわたります。医療費や介護施設費用のほかにも、費用が発生します。
介護施設費以外にかかる費用の具体例は、次の通りです。
介護には、様々な費用がかかってきます。公的な医療保険や介護保険ではカバーできない内容も含まれます。
いざ認知症になった際に、費用面で手厚いサポートを受けたい方は、認知症保険の加入を検討しましょう。認知症保険は、公的な医療保険や介護保険ではカバーできない費用にも対応できます。
家族や周囲の人への損害に備えたい場合も、認知症保険はおすすめです。家族が認知症になると、家族や親族に、介護費用の負担が生じるからです。認知症は、家族の経済状況に悪影響を与える可能性があります。
認知症でかかる費用は、本人の預貯金や財産で賄うのが基本です。しかし、本人に十分な預貯金がない場合、家族の経済的サポートが必要になります。
介護サービスを頼れるほどの経済力が家族にない場合、本人介護のため、家族の誰かが仕事を辞めなければならないケースもあるでしょう。
しかし介護保険に加入し、家族に頼ることなく介護費用を支払える体制を整えておけば、周囲に迷惑をかけずに、経済的負担に対応できます。
介護費用に不安を感じる方にも、認知症保険の加入はおすすめといえます。介護には、予測できない費用がかかる可能性があるからです。
介護にかかる費用をあらかじめ試算しておく作業は、認知症対策の基本といえます。認知症になってから介護費用のことを考えても、手遅れの場合が多いからです。
しかし、資金計画を立てても、必要な介護費用が予想額を超える場合もあるでしょう。
介護施設は民間施設か公的施設かで大きく異なります。また同じ公的施設でも、サービス内容によって費用に開きが生まれるでしょう。
認知症になった際の本人の状況により、最適な入所施設は変わります。当初予定していた介護施設とは異なる施設を選ばざるを得ないケースもあるでしょう。
この点、認知症保険に加入しておけば、予想していた介護費用を上回る場合にも対応できます。

ここでは、認知症保険の役割や特徴を踏まえた上で、より具体的なメリットやデメリットを解説します。
認知症保険の加入を検討するには、メリットとデメリットの両方を知った上で行いましょう。
認知症保険に加入するメリットとしては、次の3点が挙げられます。
以下では、それぞれのメリットを具体的に解説します。
認知症保険は、若いうちから加入できる商品も多いです。
若いうちから認知症保険に加入することで、月々の保険料を抑えつつ老後の不安に備えることができます。
少子高齢化の進行により、老後の不安を抱えている方も多いでしょう。認知症は老後の不安のなかでも大きなリスクであるため、若いうちから備えることができるのは認知症保険のメリットといえるでしょう。
認知症保険に加入できる年齢は、保険会社の商品によって様々です。年齢の低いものでは15歳から、高いものでは85歳でも加入できる保険があります。
早いうちから保険に加入すると、月々の保険料は安くなります。
認知症の危険を身近に感じ始めてから加入することもできるため、ニーズに合わせたタイミングで保険に加入できます。
認知症保険という名称の商品であっても、認知症以外の病気も保険金の支払対象となる商品も多くあります。
ガンや糖尿病から骨折に至るまで、様々な病気やケガに対応した保険に加入することで、認知症以外のリスクにも備えることができます。
認知症保険では、指定代理請求制度が利用可能です。
指定代理制度の存在により、被保険者が意思表示できない状態でも、保険金の請求ができるようになります。
認知症になると、被保険者の意思表示が認められず、事実上保険金を請求できない状態が想定できます。本人が意思表示できなくても保険金の請求が可能になる指定代理制度があるのは、認知症保険のメリットといえるでしょう。
契約内容に沿ってあらかじめ指定代理人を定めておけば、認知症患者本人の意思表示がなくても、指定代理人のみの意思表示で保険金が受け取れます。
指定代理制度があるおかげで、認知症による判断力の低下を気にすることなく、確実に保険金が受け取れる仕組みになっているのです。
保険料の安さも、認知症保険のメリットの1つです。認知症保険の保険料は、他の保険に比べて、安価に設定されているケースが多くあります。保険料が安いのは、保険の適用が、認知症に限定されているからと考えられます。
しかし認知症が原因で介護に繋がる確率は高く、内閣府のデータによると、要介護になった理由の2割近くが認知症です。
保険の適用範囲が認知症に限定されるとはいえ、認知症が原因で介護費用の負担が発生する確率は高いのです。その意味で、保険料が安い認知症保険は、コストパフォーマンスの高い選択といえるでしょう。
もっとも、認知症以外の原因で、介護が必要になる可能性があるのも事実です。
その場合は、オプションで、認知症以外の病気もカバーできるようにしておくと良いでしょう。保険会社によっては、特約で認知症でなくても保険金が受け取れるタイプの商品が用意されています。
認知症保険に加入するデメリットとしては、次の5点が挙げられます。
以下では、それぞれのデメリットについて具体的に解説します。
認知症保険での保険金支払基準は、保険会社や商品によって様々です。
多くの認知症保険では、認知症と診断されてもすぐには保険金を受け取ることができません。
例えば、公的介護保険と連動型の認知症保険では、医師に認知症と診断されても介護認定を受けるまでは保険金を受け取ることができません。
他には、医師による認知症の診断を受けてから、その状態が一定期間継続することを支払条件とする商品もあります。
このような場合にも、期間の経過を待つ必要があります。
認知症には様々な原因や症状があります。認知症保険は、全ての認知症を給付対象としているわけではありません。
例えば、アルコール依存などを原因として認知症を発症するケースは珍しいことではありません。しかし、アルコールを原因とする認知症は給付対象から外している商品も多いです。
保険を選ぶ際には、どの範囲での認知症が給付対象となるのかを十分に確認しておく必要があるでしょう。
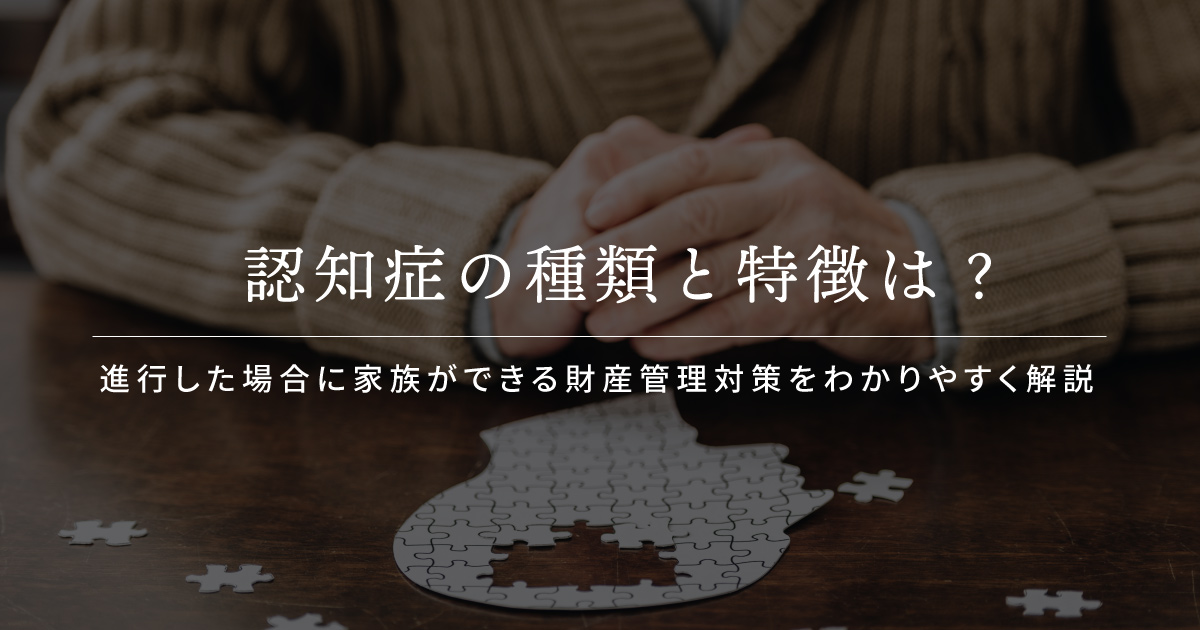
認知症保険のほとんどは掛け捨て型です。契約の途中で解約することになっても、解約返戻金はありません。
若いうちから認知症保険に加入する場合には、認知症が発症する恐れのある年齢まで保険金の支払いを続けられるのかを十分に検討する必要があります。
認知症保険の保険料は、比較的高額になりやすいといえます。高齢になってから、認知症保険に加入するタイミングが多いためです。
2025年になると、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると予測されています。高齢で認知症保険に加入すれば、保険料の負担が大きくなるでしょう。
また、様々な特約を付帯するなど保障を手厚くすれば、保険料は高額になりやすいといえます。
一般的には認知症保険に免責期間がある点には、注意しなければなりません。
免責期間とは、保険加入後の一定期間に認知症になった場合でも、保険金や給付金が支払われない不担保期間があるということです。
保険会社により免責期間の長さは異なるものの、180日から2年間程度で設定されているものが多く、期間中に認知症と診断されても保険金や給付金が支払われません。
認知症保険を検討している方は、免責期間のリスクを避けるため、早めに加入した方が安心といえるでしょう。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

認知症保険は、加入すべきケースと加入しなくても良いケースがあります。以下では、どのような場合に認知症保険に加入すべきか、または加入しなくてもよいかを解説します。
認知症保険に加入すべきケースは主に以下2つのケースです。
それぞれのケースを見ていきましょう。
自分や家族が認知症になったときの介護費用が心配な場合、認知症保険に加入すべきです。
医療費や介護費は、医療保険や介護保険である程度負担を軽減することは可能です。しかし認知症になると、医療や介護にかかる費用の他、以下のようなさまざまな費用がかかる可能性があります。
自分や家族が認知症になったときに多くの費用がかかると見込まれるケースでは認知症保険に加入しておくべきでしょう。
認知症によって周りの人に損害を与えてしまうようなケースでは、認知症に加入すべきでしょう。
認知症になると、判断能力の低下により夜中に徘徊するなどの予測不可能な行動を取る場合があります。また、感情を理性でコントロールすることができなくなり、誰かに暴力をふるったりする場合もあります。
このように他人に損害を与えてしまった場合、損害賠償を請求されるケースがあります。
認知症によって周りの人に損害を与えてしまう場合に備えたい人は、認知症保険に加入しておくべきでしょう。
一方、認知症になった場合に上記のような費用を自己資金で賄える場合には、認知症保険に入らなくても良いでしょう。
保険はあくまで自分が支払えないほどの費用や損害が発生した場合に備えるための制度だからです。
まとまった自己資金があれば、認知症になった後にバリアフリー化が必要になった場合でも保険に頼る必要はなくなります。
また、万が一他人に損害を与えてしまった場合でも、自己資金で賠償することが可能です。

これまでにも説明したとおり、認知症保険には様々な商品があります。その中から自分に合った保険を選ぶのは簡単ではありません。
ここでは、自分に合った認知症保険を選ぶためのポイントを解説します。
認知症保険は、商品によって持病の有無や年齢での加入条件が異なります。
持病があると加入できないものや保険料が高くなるものもあるため、健康状態によっては加入できる商品が絞られてしまいます。
また、年齢が若いうちから加入すると保険金額が安くなるものや、高齢であっても加入できる保険など、年齢によっても選ぶべき商品は変わるでしょう。
認知症保険は商品によって支払基準が様々です。
認知症の程度が重度のものでなければ保険金が支給されないものもあれば、比較的軽度の認知症でも保険金が支給されるものもあります。
「重度の場合だけで良いので、しっかりとした金額を受け取りたい」「金額は少なくても良いので、軽度の認知症でも保険金を受け取れるようにしたい」など、自身に合ったニーズの保険を選ぶようにしましょう。
保険金の受け取り方としては、まとまった金額を一度に受け取る「一時金」形式や、月払いなどの分割で受け取る「年金」形式があります。
認知症となった場合に、保険金を介護施設などへの初期費用に充てたいのであれば、「一時金」形式が良いでしょう。月々の生活費や入居費用などに充てたいのであれば「年金」形式が合っています。
このように、保険金の利用目的に合わせて受け取り方を選ぶようにしましょう。
認知症保険では、認知症以外の病気に対応しているものもあります。
認知症以外の病気について、他に加入している保険で対応できる場合には、認知症保険で対応する必要はないでしょう。そうでない場合には、認知症以外にも対応した保険を選ぶのも選択肢の1つです。
保険を選ぶのに最も重視されるのは、内容と料金のバランスです。
必要な最低限度の保障を受けることができ、できる限り安い料金で加入できる保険を選ぶようにしましょう。
過度な保障を受けるために高額の保険に加入する必要はありません。また、保険料の安さのみを重視して、いざというときに必要な保障を受けられなければ意味がありません。
所定の状態になったとき、保険料の払い込みが免除される場合があります。
保険会社により異なりますが、下記のような条件で保険料の払い込みが免除となる場合があります。
不測の事態での保険料の払い込み免除の有無は、認知症保険を選ぶポイントの1つでしょう。
保障期間から見れば、認知症保険には定期型と終身型の2つのタイプがあります。
定期型は保障期間があり、契約時に定めた期間を終えると契約の保障内容が終了するものです。
終身型は一生涯にわたり保障が続きます。そのため、定期型よりも保険料は高くなります。
終身型は保障が生涯続くため安心ですが、保険料と収入のバランスから自分に合ったタイプを選ぶようにしましょう。
保険の受け取り方法によって、自分に合った認知症保険を選ぶアプローチもあります。
保険金の受け取り方は、保険商品によって異なります。認知症保険を選ぶ際は、ご自身に合った保険金の受け取り方ができる商品を選ぶと良いでしょう。
一般的に、保険金の受け取り方は、一時金タイプと年金タイプの2つに大別されます。
一時金タイプは、一度に全額を受け取ることができる保険です。一方で、年金タイプは老齢年金のように、分割で保険を受け取れます。一時金タイプと年金タイプ、どちらの選択が正しいかは使い道等によって変わります。
例えば、保険金を入所施設の入居一時金など、初期費用に充てたい方は、一時金タイプがふさわしいでしょう。
また、一時金タイプか年金タイプかは、支払う税金にも影響を及ぼします。保険会社等で試算してもらい、納める税金がより低くなる年金受け取り方法を選ぶアプローチもあります。
他の保険にも加入している方は、保障が認知症保険と重複していないかチェックすることが必要です。
保険会社や保険商品にもよりますが、認知症保険の中には認知症にかかわる保障だけでなく、医療保障や死亡保障がついているものもあります。
現在加入中の保険と認知症保険の保障内容の重複をチェックすれば、保険料を抑えることにも繋がります。
認知症保険には、認知症に関連した情報提供を行ってくれるものや、相談窓口が設置されているものもあります。付帯サービスで選ぶのも1つの方法です。
保険会社によっては、認知症予防のアプリや見守りサービスまで付帯されているものもあります。
各種サービスが無料で提供されているものもあるため、他社商品と十分に比較検討して、自身に合った商品を選ぶことも大切です。

認知症保険に加入するタイミングは、いつが良いのでしょうか。
加入可能な年齢は40歳から75歳、20歳から80歳など、保険会社により異なります。ご自身の年齢で加入できるのか、事前のチェックが必要です。
認知症保険は上記の通り加入する年齢が幅広い傾向にあり、一般的に加入するタイミングが早ければ保険料も安く済みます。
認知症対策をしっかりしておきたいとお考えの方は、早めの加入を検討するのが良いでしょう。
健康状態によっては加入できない場合もあるので、認知症に備えたい方は健康なうちに検討すべきです。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

認知症保険に加入したら、家族や親族に保険内容などを伝えておくことが重要です。
この際、保険請求が必要となったときに指定代理請求制度を活用できるよう、指定代理人についても家族内で共有しておくようにしましょう。
認知症保険は、被保険者が認知症となった場合に保険金請求を行う保険のため、被保険者が保険金請求をできる状態ではないことも多いです。
家族が認知症保険の存在を知らなければ、せっかく保険に加入していても、請求しないままになってしまう可能性もあります。
請求漏れを起こさないためにも、認知症保険に加入したことは、家族内で確実に共有しておくことが重要です。

認知症保険の加入以外に役立つ、認知症対策について紹介します。
認知症対策になると預金口座が凍結される等、財産の流動性が失われます。預貯金や不動産の売却で介護費用を捻出しようと考えている方は、あらかじめ対策を施しておかないと、損失を被ってしまうかもしれません。
家族信託は、受託者に財産の管理を委託し、財産の管理・運用をする方法です。
家族信託は、認知症対策として機能します。家族信託を組んでおけば、本人が認知症になっても、意思能力を気にすることなく財産の管理を継続できるからです。
認知症が引き起こす問題の1つに、預金口座の凍結があります。
本人の認知症を把握すると、銀行は預金口座を凍結します。いったん凍結になると、家族であっても本人の預金を引き出すのは容易ではありません。
しかし家族信託を組み、受託者に預金管理の権限を与えておくと、凍結リスクの回避に繋がります。
口座凍結対策のほかにも、家族信託により認知症後も意思能力を気にすることなく不動産の売却をできるようにしておくことが可能です。
任意後見制度も、認知症対策になります。任意後見制度を利用すると、認知症後は、任意後見人が本人に代わって財産管理を行えるからです。
任意後見は本人が元気なうちに、任意後見契約を締結し成立します。
任意後見制度と似た制度に成年後見制度があります。しかし任意後見は成年後見と異なり、本人が希望する人物が後見人になる可能性が高く、財産の管理内容も比較的自由に設定できます。
ただし、任意後見は家族信託に比べて積極的な財産運用ができません。より柔軟な財産運用を希望する方は、家族信託も併せて検討しましょう。
生前贈与も認知症対策になります。生前から財産の所有権を家族に移しておけば、本人の認知症発症後でも、家族が譲り受けた財産を自由に使えるからです。
生前贈与をする際は、110万円の壁に注意しましょう。110万円の壁というのは、年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるというものです。
多額の財産を生前贈与で家族に移す場合は、長期目線で取り組みましょう。ただし、途中で認知症になってしまうと、意思能力との関係で、生前贈与を継続できなくなる恐れがあるため、注意が必要です。
なお相続時精算課税制度を利用する場合は、年間110万円を超える贈与でも、非課税枠を超えない限り贈与税は課されません。
遺言書を作成しておけば、死後の財産の行方を指定できます。
ただし遺言書の効力が発生するのは、死亡時です。認知症になっても、遺言の効力は生じません。その意味で、遺言書の作成は認知症対策としては不十分です。
遺言書を認知症対策として取り入れる際は、家族信託や任意後見制度との併用がおすすめです。家族信託や任意後見制度は、生前に効力が発生するからです。
なお遺言書の作成は、認知症になる前に作成する必要があります。認知症発症後に作成した遺言書は、効力が否定される恐れがあるため注意しましょう。

認知症保険は認知症対策の1つとして有効ですが、その他にもさまざまな認知症対策が存在します。
ここでは認知症対策として有効な制度である「家族信託」「任意後見制度」「生前贈与」「遺言書」の4つを取り上げて解説します。
家族信託とは、自分の財産を家族などの信頼できる人に託し、管理・運用してもらう仕組みです。家族信託において本人の財産を管理・運用する人を受託者といいます。
家族信託を利用することにより、自分が認知症になった後、自分の財産を家族などに管理・運用してもらうことができます。
よって、認知症になった後に自宅の改修工事が必要になったり介護のための費用が発生したりする場合であっても、受託者が本人の財産を管理して支払いを行ってくれるので安心です。
家族信託を利用するためには、認知症により判断能力が低下する前に家族信託契約を結んでおく必要があります。よって、認知症になった後は利用できない点に留意しておきましょう。
任意後見制度とは、成年後見制度の1つです。認知症になる前に任意後見受任者との間で任意後見契約を結び、認知症になった後に任せたい事務の内容を決めておく制度です。
任意後見契約を結んでおけば、将来自分が認知症になった場合に任意後見人が自分の財産を管理してくれます。
自分の財産を管理してくれるという点は家族信託と共通しますが、財産の積極的な運用はできない点に留意しておきましょう。
また、家族信託と同様、認知症になる前に任意後見契約を締結する必要があり、認知症になってしまった後は利用できません。その場合、法定後見制度を利用することになります。
生前贈与とは、文字通り生前に自分の財産を他人に贈与しておく方法です。贈与された他人のことを受贈者といいます。生前贈与をしておくことにより、自分が認知症になった後の費用や損害の支払いを受贈者に任せることができます。
認知症になった後の費用を自己資金で賄える場合、認知症保険に加入しなくても良いことをお伝えしました。しかし、認知症になった後は判断能力が低下しているため、自らが自己資金から費用を支払うことなどが難しくなります。
生前贈与をしておけば、認知症になった後でも受贈者が代わりに費用を支払ってくれるでしょう。
ただし、受贈者には認知症後の費用の支払いを代わりに行う義務はありません。受贈者に認知症後の費用の支払いを依頼する場合、負担付き贈与をする必要があります。
ただし、多額の贈与を行うと贈与税がかかる場合がある点には注意が必要です。生前贈与と贈与税の関係は別の記事で詳しく解説しているので、気になる方はそちらの記事もぜひご覧ください。
遺言書とは、自分が死んだ後、誰にどのような財産を残したいかを書き記した書面のことをいいます。
遺言書に財産の分配方法を記載しておけば、自分が希望する人に財産を残すことができます。よって、認知症になり死亡した後の財産の配分を生前に決めておくことが可能です。
自分が希望する人に財産を残せる点で生前贈与と共通しますが、遺言書は本人の死亡後に効力が生じます。よって、本人が存命中は効力が生じません。
自分の死後の事務費用の支払いを任せるために遺言書を作成しておくことは有効ですが、認知症になった後の対策をしておきたい場合、他の制度を併用する必要がある点に留意してください。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

ここでは、認知症保険についてよくある質問に回答します。
認知症保険と公的介護保険との大きな違いは、保障に対して提供されるのが現金なのか、介護サービスなのかという点です。
連動型の認知症保険を除くと、支払条件も公的介護保険とは異なります。
公的介護保険は、公的な機関での等級認定に従いサービスが提供されますが、認知症保険では商品によって様々な支払基準が設定されています。
なお、民間の介護保険の場合には、認知症保険と同じく保険で支払われるのは現金です。
支払条件は、基本的に介護保険と連動しており、一定の等級認定を受けたことを条件に保険金が支払われます。
認知症は誰の身にも起こり得ることで、高齢者への備えは誰もがしなくてはならないでしょう。
認知症保険に入るべき人は、公的介護保険や民間の介護保険などの保障では不十分なので、より手厚い保障を受けたいと考える人。万が一の場合に介護サービスではなく、現金を受け取ることで認知症に備えたいと考える人。などが挙げられるでしょう。
認知症保険を含め生命保険には告知義務があり、入院歴や持病があると加入できない場合があります。
認知症保険の多くは、健康状態が良好で日常生活を支障なく送ることができる方が加入対象です。
過去に入院歴などがある方でも、現時点が健康状態が良好であれば、加入できる場合があるので保険会社に問い合わせてください。
70歳以上や80歳以上の方でも、認知症保険に申し込みは可能です。
ただし、認知症保険の中には契約上限の年齢が75歳や79歳などの保険商品もあるので、高齢になるにつれて商品選択の幅が狭くなります。
また、一般的に加入年齢が高齢になれば、保険料も高くなります。

認知症保険の加入率は6.6%と低いものの、今後も高齢化が進むことから認知症患者の絶対数は増加します。
多額の介護費用に備えるために、認知症保険の必要性が高くなります。認知症対策として有用ですが、加入に当たっては必要性をしっかりと見極めたいものです。
認知症対策には、他に家族信託などの方法も考えられます。認知症保険と併せて検討してみてはいかがでしょうか。
ファミトラでは、本記事で解説したような認知症保険の活用事例など、お客様の状況に最適な方法を幅広く提案・サポートいたします。家族信託に興味のある方は、ぜひご相談ください。
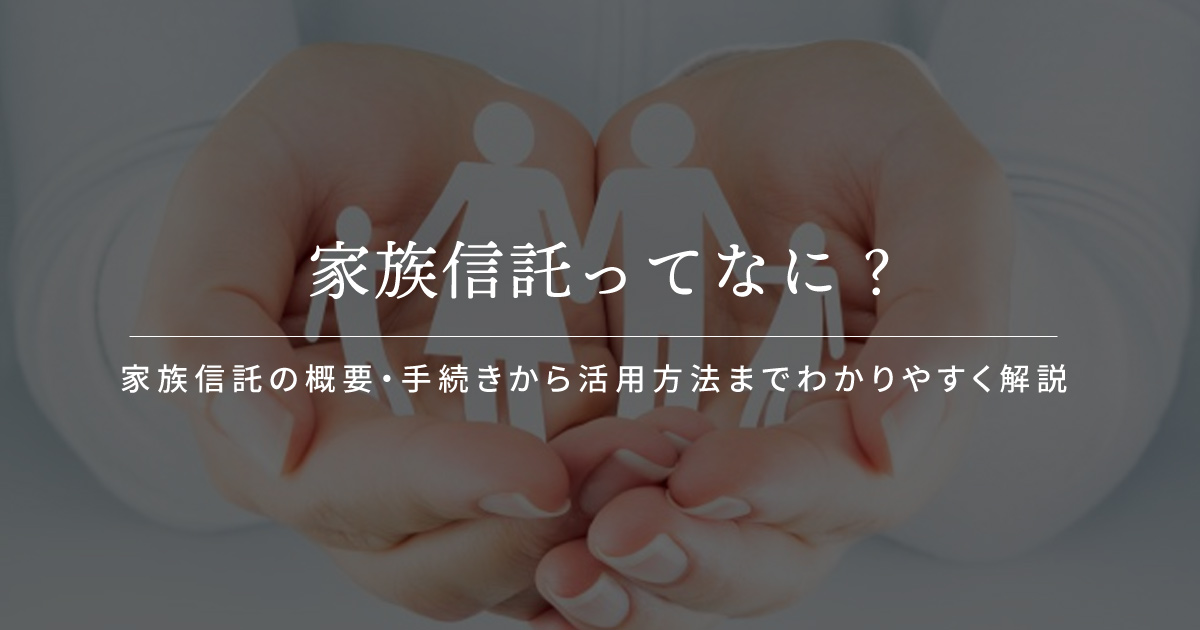

家族信託に限らず、本記事で解説したような認知症保険を活用した事例など、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。