
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
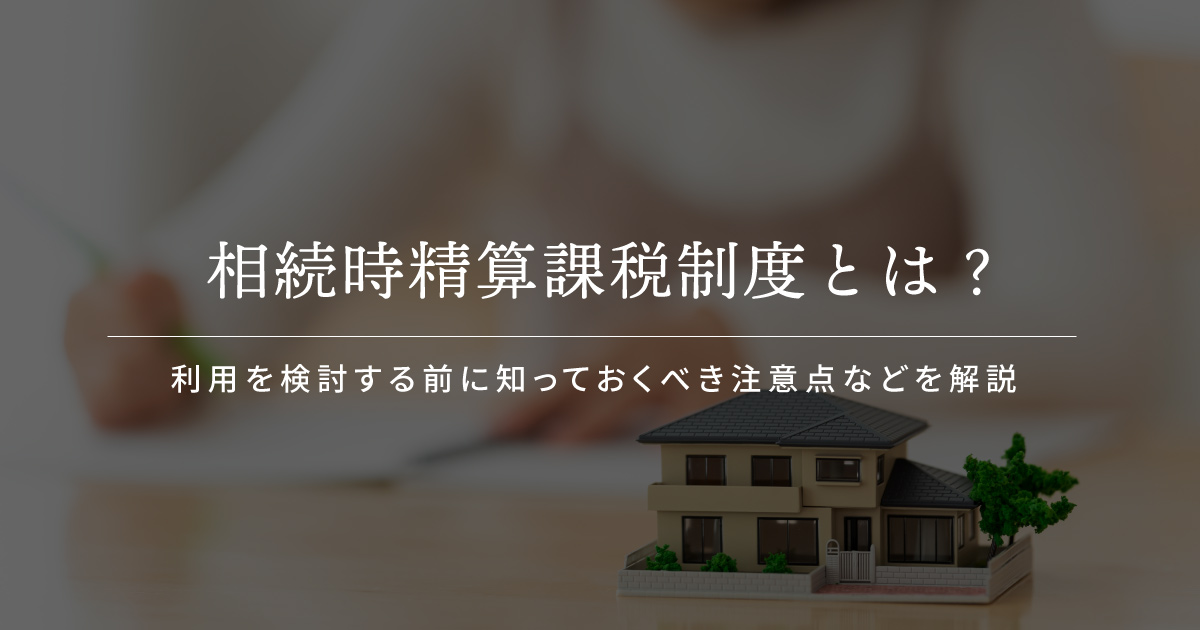
令和6年の税制改正により、相続時精算課税制度は新しく生まれ変わりました。
相続時精算課税制度が使いやすくなったことで、これまで以上に、暦年贈与との使い分けが重要になります。
この記事では、相続時精算課税制度の改正点や、新制度のメリット・デメリットについて解説します。
相続時精算課税制度について気になる方は、ぜひ参考にしてください。

瀧田 潤
(たきた じゅん)
税理士
2005年税理士試験合格。都内3カ所の会計事務所、税理士法人勤務を経て、2017年に独立開業。特に独立前の税理士法人では相続・事業承継の責任者として活躍し、その当時から現在に至るまで毎年100件以上の相続関連の相談を受けている。税金で損をしている方を一人でも多く減らすことをモットーに「日本一相談のしやすい税理士」を目指して日々邁進中。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
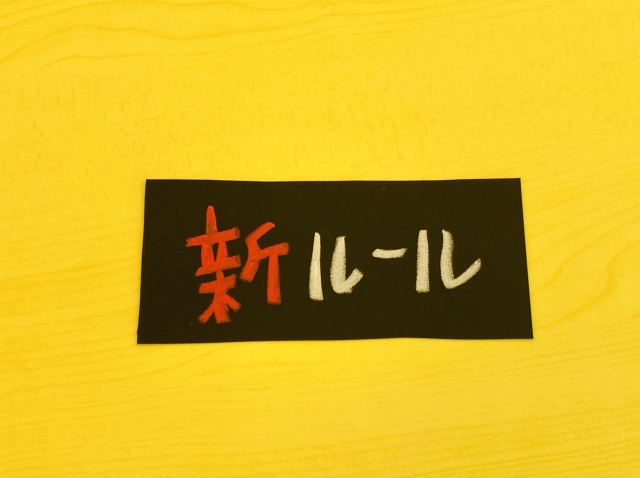
まずはじめに、相続時精算課税制度の概要や仕組みについて解説します。
「相続時精算課税制度」は、2,500万円までであれば贈与税を納めずに贈与を受け取れる制度です。
この制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子ども・孫への生前贈与の際に、納税者となる子ども・孫の選択により利用できます。
贈与が令和4年4月1日以後の場合は、成人年齢の引き下げにより、贈与を受ける子や孫が18歳以上であれば適用できるようになります。
通常の贈与は「暦年課税」と呼ばれ、贈与税がかからない非課税枠は年間110万円までとなっています。そのため、一度に大きな額を非課税で贈与できるのは、相続時精算課税制度の大きな特徴といえるでしょう。
ただし、贈与者が亡くなったときには「贈与者から受け取った贈与財産」と「その他の相続財産」を合計して相続税額を計算しなければならない点に注意が必要です。
相続時精算課税制度が改正され、令和6年1月から新制度へと移行します。
相続時精算課税制度の、改正点を確認しましょう。
改正後、年間110万円以内の贈与である限り、贈与税の申告は不要です。
改正前の相続時精算課税制度は、贈与が1円であっても税務申告が必要であったため、使い勝手が良くありませんでした。
申告の手間を嫌い、相続時精算課税制度よりも暦年贈与を選ぶ方が、相当数いたと思われます。
しかし改正により、贈与額が年間110万円までにおさまる限り、申告は不要となりました。
暦年課税を選んだとしても、年間110万を超える贈与には申告義務が生じます。
申告にかかる手間の観点からは、暦年課税と相続時精算課税制度の差は無くなったといえるでしょう。
改正により、年間110万の贈与にとどまる限り、相続財産への加算は不要になりました。
改正前の相続時精算課税制度は、贈与額を相続財産に加算しなければなりませんでした。贈与税の免除はされても、相続時には相続税として納税義務が生じるため、改正前の制度は減税効果が乏しかったのです。
減税効果の観点からは、相続時精算課税制度よりも暦年課税が優れていたといえます。
しかし改正により、2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円までの基礎控除が与えられました。
贈与額が年間110年以内におさまる限り、相続財産に加算する必要がなくなります。相続時精算課税制度を選んでも、暦年課税と同じく、減税効果が期待できます。
相続時精算課税制度の適用対象となる条件は次のとおりです。
成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、贈与を受ける子や孫が18歳以上であれば適用できるようになりました。
また、養子も一親等の血族である推定相続人であることから、人数に制限なく相続時精算課税制度の対象者となります。
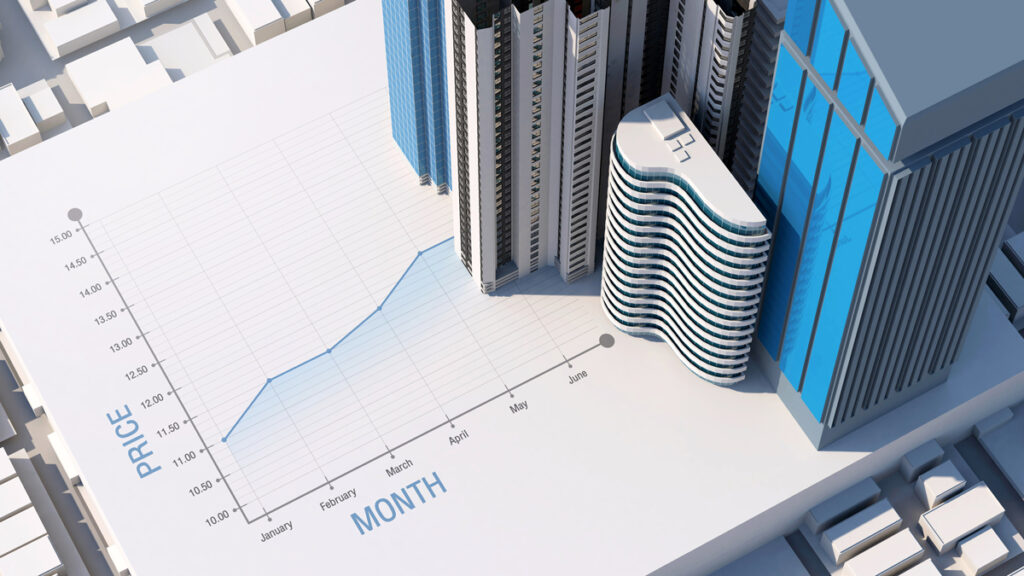
相続時精算課税制度が適用される財産、金額、贈与回数に制限はありません。みなし贈与財産も含まれます。
また、受贈財産は相続開始時に無価値になっていたとしても「贈与した時点での価額」で相続税が計算されます。
そのため、財産を選択する際は価格変動の影響も考慮した上で、相続時までに評価額が上がりそうなものを選ぶと良いでしょう。
評価額が上がりそうなものの具体例としては、土地や株式などが挙げられます。

相続時精算課税制度の利用を希望する方は、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
相続時精算課税選択届出書を提出する際は、既定の添付書類もあわせて提出する必要があります。
届出書の提出期間は、対象となる贈与を受けた年の「翌年」の2月1日〜3月15日までの間です。
提出先は「受贈者(贈与を受けた者)」の住所を管轄する税務署です。贈与者の住所を管轄する税務署ではないため、混同しないようにしましょう。
参考:国税庁
贈与を受けた際に受贈者が相続時精算課税制度を選ばなかった場合、「暦年課税」が適用されます。この2つの課税制度にはどのような違いがあるのでしょうか。
大きな違いは次のとおりです。
| 暦年課税 | 相続時精算課税制度 | |
|---|---|---|
| 贈与者の要件 | 特になし | 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上である父母または祖父 |
| 受贈者の要件 | 特になし | 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人および孫 |
| 非課税枠 | 受贈者あたり毎年110万円 | 贈与者ごとに累計2,500万円まで |
| 控除額以下の場合の届出等 | 不要 | 要 |
| 控除額超の贈与税 | 超過累進税率 | 一律20% |
| 相続税の課税対象 | 相続前3年内限定 (贈与時の価額) | 全て相続税の対象 (贈与時の価額) |
| 回数制限 | なし。 ただし、相続時精算課税制度を選択すると利用不可。 | なし。 一度選択すると暦年課税に戻れない。 |
改正後の相続時精算課税制度では、非課税になる贈与税の上限は、2,500万円+(年間)110万円です。
相続時精算課税制度では、2種類の贈与税非課税枠が与えられます。
相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税と同様に年間110万円までの基礎控除が受けられます。
さらに、相続時精算課税制度では、2,500万円の特別控除が受けられるため、非課税になる贈与税が暦年課税よりも大きいです。
ただし、特別控除(2,500万円)の部分に関しては、相続財産に加算され、相続時に相続税として支払う形になります。
相続時精算課税制度の適用を受けられる主体には、条件があります。
制度の利用にあたっては、当事者(贈与者・受贈者)双方が条件を満たしている点を確認しましょう。
対象者の範囲は、贈与者と受贈者で分けたほうがわかりやすいです。
具体的な制度対象者の範囲は、次のとおりです。
60歳以上の父母 or 祖父母
18歳以上の子 or 孫
*2022年3月31日以前に贈与を受けた場合は20歳以上
相続時精算課税制度も暦年課税も、年間110万円の贈与税非課税枠を持ちます。
ただし、非課税枠の内容に関しては違いがあります。
相続時精算課税制度には、生前贈与加算のルールがありません。
暦年課税では、生前贈与加算のルールが適用されます。
生前贈与加算の有無は、相続時精算課税制度と暦年課税の大きな違いといえるでしょう。
生前贈与加算の縛りを受けない分、相続時精算課税制度のほうが、非課税対象となる贈与が多くなると考えられます。
なお、生前贈与加算とは、相続開始直前の贈与を相続財産に加算する算定方法です。
暦年課税では、相続開始前7年以内の贈与が生前贈与加算の対象となり、相続税の課税対象となります。

改正前と改正後で、贈与税の計算がどのように変わるか、比較してみましょう。
相続時精算課税制度の特別控除額は最大2,500万円です。
そのため、その金額までの贈与は一律非課税となります。
また、この制度は利用の申請をしてから贈与者(財産を贈与する父母や祖父母)がなくなるまでの間、合計の控除額が2,500万円に達するまでは何回でも利用可能です。
まず、基本的な贈与税額の計算式について見ていきましょう。
贈与税額=(贈与財産の価額-特別控除額)× 20%
この算式を踏まえた上で、相続時精算課税制度を選択した贈与者から次のように贈与を受けた場合について解説します。
【前提】1年目に1,200万円、2年目に800万円、3年目に600万円の贈与を受けた
(2,600万円-2,500万円)× 20%=20万円(贈与税額)
また、前述したように、この制度を選択した場合、以後は暦年課税の適用ができません。
そのため、従来は4年目以降にも同じ贈与者からの贈与があった場合、贈与財産額が110万円以下であったとしても贈与税の納税が生じる点に注意が必要でした。
改正前と改正後で、どのように計算が変わるかシミュレーションしてみましょう。
前提となる事例は、改正前と同じとします。
【前提】1年目に1,200万円、2年目に800万円、3年目に600万円の贈与を受けた
改正後では、基礎控除(年間110万円の控除)も適用されるため、3年目でも贈与税は発生しない結果となりました。
改正後の相続時精算課税制度でも、暦年課税の選択ができなくなる点は同じです。
しかし、改正後の相続時精算課税制度では独自の基礎控除の適用があるため、特別控除枠(2,500万円)の消費後も、年間110万円の非課税が受けられます。

相続時精算課税制度の主なメリットを3つご紹介します。
相続時精算課税制度を選ぶ最大のメリットは、2,500万円という大きな控除を受けられることです。
普通の贈与(暦年課税)を選択した場合、控除は年間で110万円までしか適用されません。
また、暦年課税の場合は贈与額が大きくなるにつれ、以下のように税率が上がっていきます。
<一般贈与財産用>(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
<特例贈与財産用>(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
※20歳以上の人が直系の父母や祖父母から贈与を受けた場合、特例税率が適用される。(それ以外の場合は一般税率となる)
出典:国税庁HP
短期間で大きな金額を移動させたい場合や、定期的に収益のある不動産を持っている人などは相続時精算課税制度を利用すると良いでしょう。
相続時精算課税制度ができた背景には、両親や祖父母の財産をなるべくスムーズに子どもや孫へ相続させ、消費を促したいといった考えが含まれています。
そのため、この制度を利用することで、受贈者となった子どもや孫が自分たちのタイミングで相続した財産を有効に活用できるでしょう。
また、暦年課税で毎年まとまった金額で贈与を繰り返していると、定期贈与とみなされて課税される恐れもあります。
相続時精算課税制度は、タイミングを気にせず年間110万円までの贈与ができます。
相続時精算課税制度は、暦年課税と異なり、生前贈与加算のルールが適用されないためです。
暦年課税には、生前贈与加算のルールが適用されるため、贈与の時期が重要になります。
相続開始から7年以内の贈与は相続財産に加算され、相続税として課税されるためです。
暦年課税では、贈与のタイミングが遅れた場合、生前贈与加算により十分な節税効果が得られません。
しかし、相続時精算課税制度には、生前贈与加算のルールが適用されません。
精算課税制度の利用者は、相続のタイミングを気にせず、年間110万円の非課税枠を利用できます。
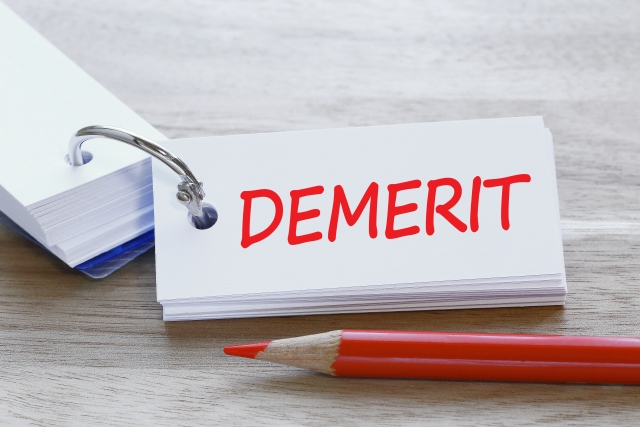
相続時精算課税制度にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
上記についてひとつずつ確認していきましょう。
相続時精算課税制度の最大のデメリットは、一度でも利用を選択すると暦年贈与を選べなくなることです。
相続時精算課税制度を選んだ場合、年間110万円の非課税枠が一生使用できなくなってしまいます。
まだ相続するのが遠い先の話である場合、暦年課税を選択しておくと良いでしょう。
とはいえ、暦年課税の非課税枠(110万円)が使用できなくなるのは「相続時精算課税制度を利用した贈与者からの贈与」であり、他の贈与者からの贈与については適用可能です。
利用する前に「相続時精算課税制度」と「暦年課税」のどちらが得なのか、よく考えた上で選択するようにしましょう。
相続時精算課税制度を選択する方は、申告期限に注意しましょう。
申告期限に遅れると、2,500万円の特別控除枠が利用できないためです。
相続時精算課税制度の利用者は、申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
相続時精算課税制度を利用するつもりで多額の贈与をしたとしても、届出書の提出が遅れると、2,500万円の特別控除枠が適用されません。
相続時精算課税制度が利用できなかった場合、暦年課税となります。
暦年課税で受けられる非課税枠は、年間110万円までです。110万円を超えた部分は、贈与税の課税対象になります。
相続時精算課税制度を選択し、住宅などの宅地等(土地や敷地権)の贈与を受けた場合、「小規模宅地等の特例」を使うことができません。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす状況で宅地等を相続した場合に、その宅地等の相続税評価額が最大80%減額される制度のことです。
この特例で対象となるのは相続や遺贈によって受け取った土地のみであり、贈与で受け取った土地は適用対象外となります。
上限面積や減額割合、要件は土地の用途によって異なりますが、引き継ぐ土地の種類によっては相続時精算課税制度を利用するよりも節税に繋がる可能性があります。
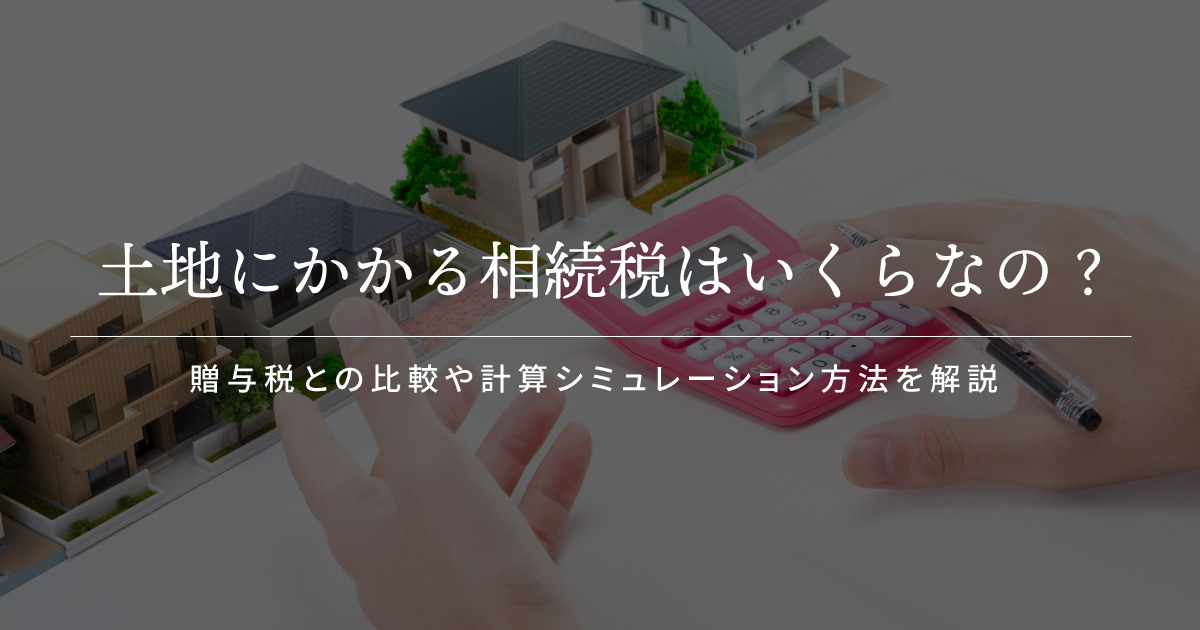
相続時精算課税制度は、2,500万円を上限として贈与税が非課税となる制度でした。
しかし、将来的に贈与者の相続が発生した際、制度を選択した贈与財産(2,500万円まで)を相続財産に足し戻す必要があります。
その際、足し戻した場合の総額が相続税の基礎控除を超えてしまうと、相続税の課税対象となります。
また、受贈者が孫で相続税が課税されるケースでは、孫は相続税の2割加算の対象となることも覚えておきましょう(代襲相続によって孫が法定相続人となる場合を除く)。
通常の相続であれば、税金の手続きは一回のみです。
しかし、相続時精算課税制度を選択すると、手続きに対してそれなりの手間と費用が生じます。
また、相続が発生した際は相続税の申告をしなければならない他、2,500万円を超えても毎回申告する必要があります。
不動産を生前に贈与した場合、贈与税や相続税以外に「登録免許税」や「不動産取得税」といったコストが生じます。
通常の相続であれば登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)のみで、不動産取得税はかかりません。
しかし、生前贈与の場合は登録免許税(固定資産税評価額の2.0%)に加え、不動産取得税(固定資産税評価額の3.0%)がかかるので注意しましょう。
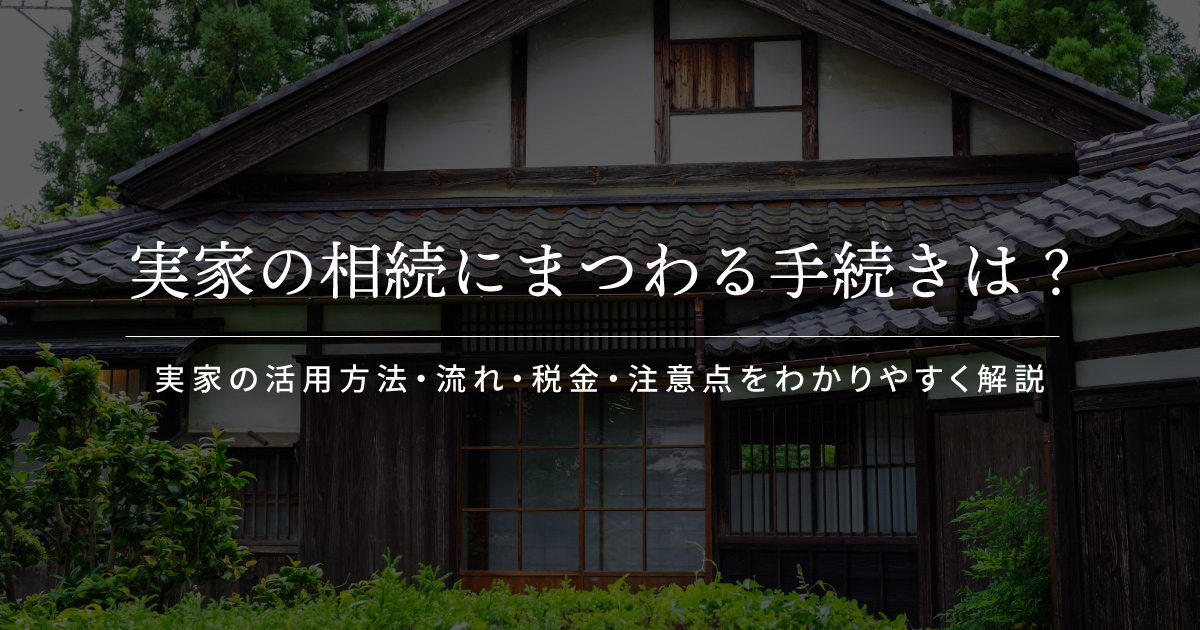
相続時精算課税制度では、贈与額が2,500万円を超えた場合に、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
そのため、仮に1年で4,000万円の贈与がなされた場合、以下の税額が課税されます。
(4,000万円-基礎控除110万円-特別控除2,500万円)× 20%=278万円
ただし、贈与税は相続時に相続税額から差し引かれるため、相続税額が少ない場合は差額が還付されることも覚えておきましょう。

相続時精算課税制度の利用が向いているケースを紹介します。
相続時精算課税制度の特徴を理解し、上手に暦年課税と使い分けましょう。
相続時の相続財産が、相続税の基礎控除を超えないと判断できる場合、相続時精算課税制度の利用を検討する価値があります。
相続時精算課税制度の特別控除枠(2,500万円)が、将来の相続財産に加算されるとしても、基礎控除でおさまる以上、相続税は0円になるためです。
次の事例で考えてみましょう。
(*年間110万円の基礎控除部分は考慮しない)
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
今回の相続税の基礎控除は、3,600万円です。
今回のケースでは、基礎控除(3,600万円)>相続財産の総額(3,000万円)となり、相続税は0円になります。
相続時精算課税制度の利用により、贈与税も相続税も非課税となるため、制度の利用価値が高い場面といえるでしょう。
必要なときにまとまった額を贈与したい人は、相続時精算課税制度の利用に向いています。
相続時精算課税制度では、多額(2,500万円)の非課税枠が与えられるからです。
父から息子へ、事業資金として2,000万円贈与するケースを考えてみましょう。
(*年間110万円の基礎控除部分は考慮しない)
一度に多額の贈与をする場合、暦年課税は不向きです。
暦年課税の非課税枠は、年間110万円が上限であり、金額が小さすぎるからです。
1890万円(2,000-110万円)が贈与税の対象となり、多額の贈与税が発生してしまいます。
贈与税の支払いで、息子の手元に残る事業資金は少なくなってしまうでしょう。事業者にとって、税金の支払いが理由で、使える事業資金が減るのは痛手です。
しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、一度に2,500万円の非課税枠が与えられます。父から受け取ったお金を、贈与税を支払うことなく、事業資金に充てられます。
事例のように、特定のタイミングでまとまったお金を贈与する場合は、相続時精算課税制度が有効です。
株式など、一時的に下がっている資産を保有している方は、相続時精算課税制度の利用を検討してみましょう。節税に繋がる可能性があります。
相続時精算課税制度では、原則として、贈与分が相続財産に加算されます。
資産価値が低いタイミングで株式を贈与しておけば、後で値段が上がっても、値上がり分を相続財産に加算する必要がありません。
相続時精算課税制度の贈与で相続財産に加算される価値は、贈与時の価値が基準となるためです。
立地の優れた不動産など、価値上昇が見込まれる財産を所有している方は、相続時精算課税制度の利用を検討してみましょう。節税に繋がる可能性があります。
相続時精算課税制度では、原則として、贈与分が相続財産に加算されます。
相続財産に加算される金額は、贈与時の価値が基準となります。相続時に贈与した財産の値段が上がっていたとしても、値上がり分が、相続財産に加算されることはありません。
相続時精算課税制度で、価値上昇が見込まれる財産をあらかじめ贈与しておくことで、相続時の相続財産評価額を下げられるのです。
相続財産評価額の低下は、相続税の節税に繋がります。
事業承継の予定がある人は、相続時精算課税制度を検討してみましょう。
事業承継は、株式など不動産など、多額の贈与がされるケースが多いです。一度にまとまった額の贈与がされる場面では、上限が年間110万の暦年課税よりも、非課税枠の大きい相続時精算課税制度が向いています。
兄弟同士の仲が悪いなど、相続時にもめそうな場合は、相続時精算課税制度を用いた贈与が向いています。
まとまった資産をあらかじめ贈与しておくことで、特定の相続人に資産を残せるためです。
相続人同士でもめると、被相続人が望んだとおりの、遺産承継がされない恐れがあります。
贈与の形を取りあらかじめ相続させておけば、確実に希望の相手に資産を承継できます。
「結局のところ、相続時精算課税制度は節税対策になるのか?」といった疑問をお持ちの方も多いかもしれません。
結論からいえば、相続時精算課税制度は節税対策になるというわけではありません。
「相続時精算課税制度の概要」の中でも述べたように、相続時精算課税制度は、贈与税が非課税になるものの相続税は課税され、税金の先送りにしかならないためです。
しかし、アパートなどの収益不動産を所有している場合、また値上がりが予想される財産を所持している場合には、相続時精算課税制度を利用することで節税効果が見込めます。
相続時精算課税制度を選択して収益物件を贈与した場合、贈与者の相続時に相続税の課税対象となるのは収益物件のみです。
つまり、収益物件から生じた家賃収入等の収益を相続税に含める必要がありません。
この制度を使わず、両親や祖父母が収益物件を所持したまま相続が発生してしまうと、「収益物件+家賃収入」が相続財産として課税対象となってしまいます。
そのため、賃貸アパート・マンションなどの収益物件がある場合には、相続時精算課税制度を選択して相続税対策をするのも一手かもしれません。
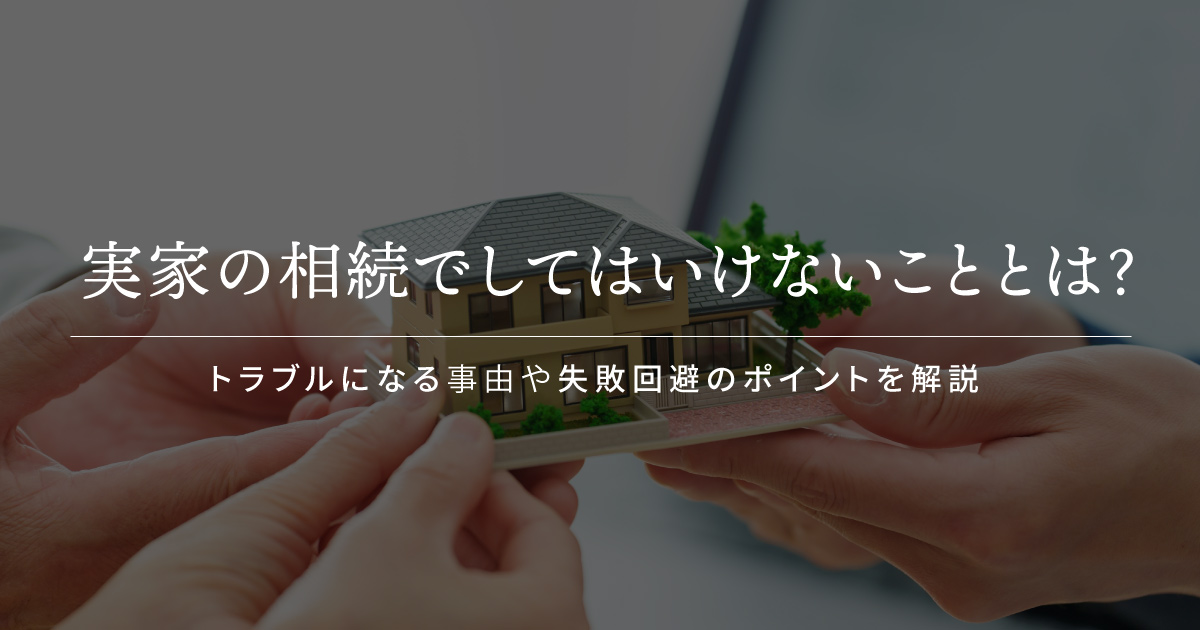

相続時精算課税制度に関して、よくある質問に回答します。
改正における主な変更点は、次のとおりです。
最も大きな改正点は、基礎控除部分が創設された点です。
改正により、既存の特別控除枠(2,500万円)とは別に、年間110万円までの基礎控除が与えられることになりました。
基礎控除部分に限り、贈与税のみならず、相続税の対象からも外れます。
改正前の相続時精算課税制度は、節税対策の制度としては不十分と指摘されてきました。贈与した部分につき、贈与税が非課税になっても、結局は相続税として課税されるためです。
しかし、基礎控除部分が新たに創設されたことで、年間110万円贈与については、完全に非課税の扱いを受けられるようになりました。
贈与額が年間110万円におさまる限り、贈与税の申告も不要です。
従来の相続時精算課税制度は、1円でも贈与があれば申告義務が生じたため、改正でより使いやすい制度になったと評価できるでしょう。
ケースバイケースですが、相続時精算課税制度のほうが、暦年課税よりも節税効果が期待できるとされます。
相続時精算課税制度には、生前贈与加算のルールが適用されないためです。
もっとも10年以上のスパンで考えると、暦年課税が得になる場合もあります。また、贈与額によっても優劣は変わります。
さらに、相続時精算課税制度は小規模宅地等の特例が使えなくなるため、相続財産に不動産が含まれる場合は要注意です。
どちらの制度が望ましいか、詳細を知りたい方は、税理士などの専門家に相談しましょう。

税制改正により、相続時精算課税制度は従来よりも使いやすくなりました。
年間110万円までの基礎控除が新たに創設され、暦年課税と同等、あるいはそれ以上の節税効果が期待できます。
ただし、必ずしも暦年課税よりも優れているとは限りません。
状況によっては、暦年課税を選んだほうが良い場合もあるでしょう。
ファミトラでは、相続税に関する情報提供の他、家族信託を含む相続対策全般の相談に応じています。
効果的な相続対策を希望する方は、ファミトラまでご相談ください。

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。