
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
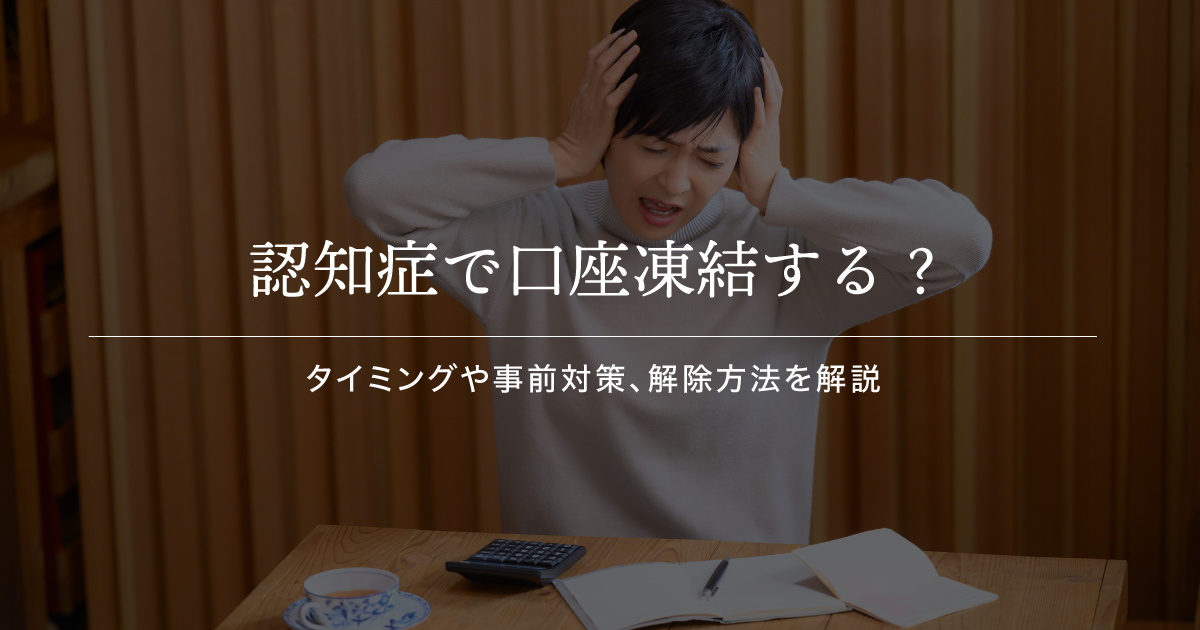
ご家族が認知症と診断された場合、その方の銀行口座が「凍結」される可能性があることをご存じでしょうか。
判断能力の低下を理由にご本人名義の取引が制限されると、生活費はもちろん、高額な介護費用が引き出せなくなる恐れがあります。
しかし、事前に対策を講じておけば、資産が動かせなくなる事態は回避できます。
当記事では、なぜ口座が凍結されるのかという仕組みから、今すぐ始められる具体的な予防策(生前対策)、そして凍結後に困らないための現実的な対処法まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。

田中 総
(たなか そう)
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

田中 総
家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

そもそも、口座凍結とはどのようなものなのでしょうか。
銀行が口座凍結を実行するケースについて解説します。
口座凍結とは、銀行が対象の口座の取引を停止することです。
お金を下ろせなくなるだけでなく、振り込みができない上、自動引き落としも停止されてしまいます。
口座凍結されたら永久に預金を引き出せなくなるわけではありませんが、再び利用できるようにするには手続きが必要になるため、注意が必要です。
銀行が口座凍結を実行するのは、主に口座名義人の死亡時と口座名義人が認知症に罹患した時です。
死亡時には相続対策で不正が働かないようにするために、認知症に罹患した時は判断能力が低下した名義人の財産を守るために口座凍結が実行されます。
とはいえ、銀行は口座名義人が死亡したり認知症に罹患したりしたことを即座に知るわけではありません。
口座名義人の死亡時には、親族が銀行に直接伝えるだけでなく、稀に葬儀の告知を見ることで死亡を知り、口座が凍結される場合もあります。
一方、口座名義人の認知症罹患時には、親族が直接銀行に伝えることもありますが、生活が不便になるため、直接伝える方は多くありません。
しかし、認知症に罹患した本人が銀行に出向いた際に、判断能力が著しく低下している場合や、親族と一緒に銀行を訪れ、施設入所のために定期預金などの解約をした場合には、認知症が疑われます。
そのため、認知症と診断されていなくても、銀行側が取引に著しい不安があると感じると、口座凍結を実行します。
認知症になると証券取引用の口座も凍結されます。
株や証券を持っている人が認知症になると、意思能力がなくなるためこれらの売買はできなくなります。
老後の生活資金のために株や証券を運用していたのに、必要なときに売却できず資産運用がに支障をきたす可能性もあります。
認知症発症後は、法定後見制度以外に預金を引き出す方法がありません。
法定後見制度では、家族が法定後見人に選ばれるとは限らず、家族の思うような資産運用ができなくなるかもしれません。
そのためにも、判断能力があるうちに家族信託を利用することをおすすめします。
認知症罹患時の口座凍結と、死亡時の口座凍結は全てが同じ扱いというわけではありません。
認知症罹患時には一部の取引利用が可能である一方、死亡時の口座凍結では一切の利用ができない点に違いがあります。
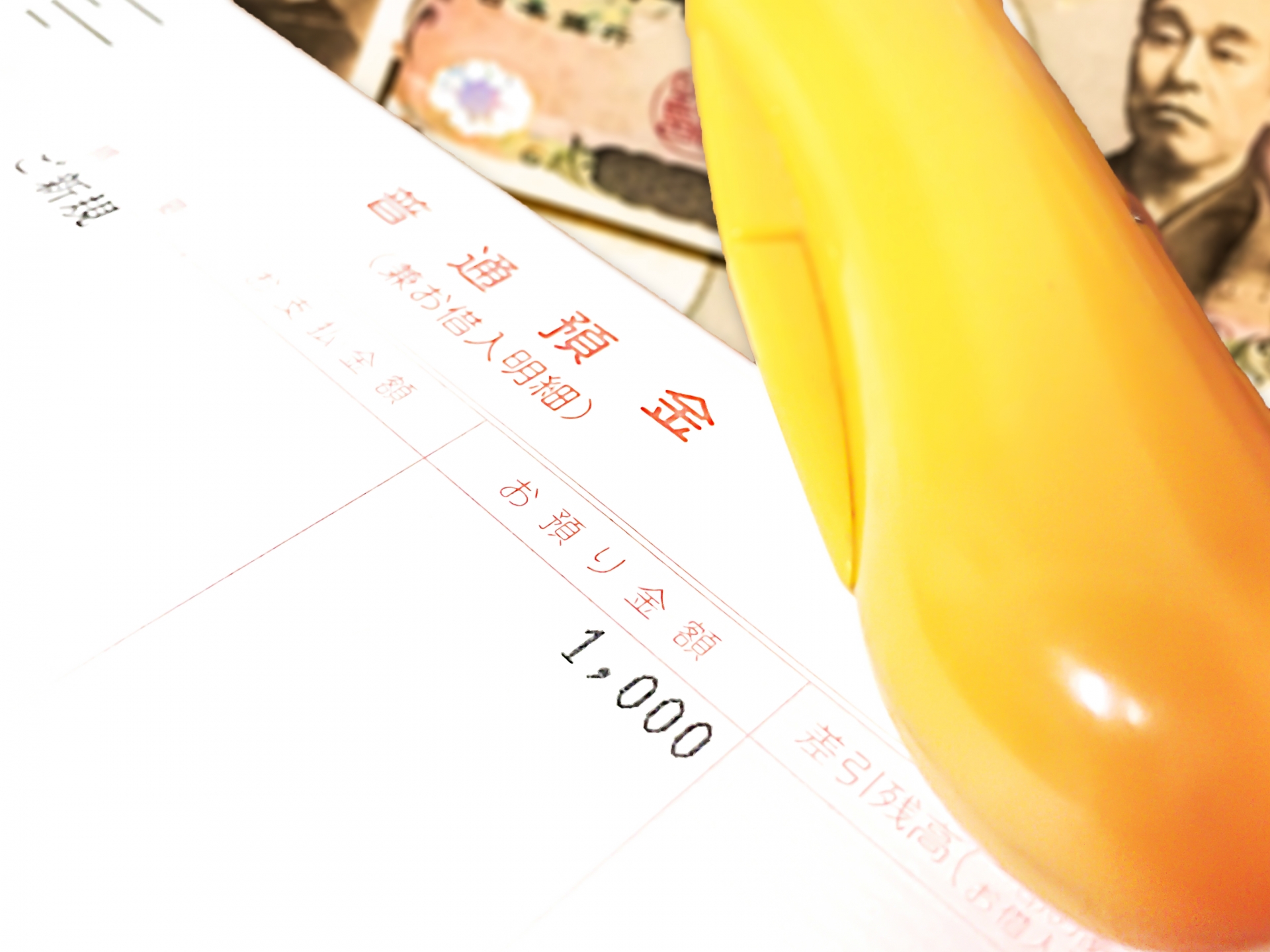
ここでは、認知症の人の銀行口座が凍結される3つの理由について解説します。
認知症に罹患すると口座凍結される理由の1つに、口座や財産の悪用防止があります。
例えば、悪意をもった家族が口座名義人の口座情報を聞き出したり調べたりすることで、お金を引き出してしまうことが考えられます。
判断能力が正常であれば、不自然な利用に気づくことも多くありますが、判断能力が低下していると気づくのが遅れてしまい、場合によっては全く気づかないこともあるでしょう。
そのような状態では口座や財産が悪用されてしまうため、口座を凍結をして取引を停止するのです。
自分で適切に財産管理できないことも理由の1つに挙げられます。
判断能力が低下しているため、暗証番号を忘れたり、お金の使い道を忘れたりしてしまうことがあるでしょう。
このような状態では、自分で適切に財産管理できないため、周囲に頼らざるを得なくなります。
しかし、周囲が口座名義人の意向通りに財産管理をしなければ、先ほど解説したように悪用されてしまうことも考えられます。
そのため、自分で適切に財産管理できない状態であれば、財産を守るために口座凍結するのです。
判断能力が低下していると、詐欺などの事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
例えば、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」のような特殊詐欺の電話がかかってきた際に、判断能力がなければ、それが詐欺であることに気づきません。
詐欺だと気づかなければ、電話で伝えられたとおりにお金を振り込んでしまったり、キャッシュカードを手渡してしまったりしてしまうでしょう。
判断能力が衰えていなくても詐欺に引っかかってしまうことがあるため、判断能力が低下していれば、より一層騙されやすくなります。
そのため、口座を凍結し、お金を引き出したりキャッシュカードの利用を停止したりすることで、詐欺に巻き込まれることを防止できるのです。

ここでは、認知症により口座が凍結してしまうタイミングについて解説します。
どのタイミングで凍結されるのか、凍結されるきっかけは何かを確認しましょう。
口座の凍結は、銀行が認知症の罹患を知ったタイミングで行われます。
認知症を罹患したタイミングで、すぐに銀行が認知症かどうかを知ることは考えにくいでしょう。
しかし、何らかのきっかけから認知症を罹患していることを銀行が知ったときに、口座が凍結されます。
では、銀行はどのタイミングで認知症の罹患を知るのでしょうか?
実は名義人自身やその家族の行動は、銀行に観察されています。ここでは、銀行が認知症を判断しているといわれる、名義人や家族の行動を紹介しましょう。
認知症の罹患が疑われる名義人の行動には、主に以下のようなものが挙げられます。
このように、認知症を罹患した方に典型的な症状や行動が頻発すると、銀行員が認知症の罹患を疑います。
名義人自身の行動のみならず、家族の行動でも認知症の罹患が疑われます。
このように、直接的であろうと間接的であろうと、認知症の罹患が疑われる行動があった場合、口座凍結されてしまうことがあります。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

認知症により口座凍結された時に行えなくなることについて解説します。
認知症によって口座凍結されても、一部の取引は可能です。
例えば、口座からの自動引き落としなどは、認知症により口座凍結されても引き続き利用できます。
認知症による口座凍結は、口座や財産を悪用されたり詐欺などの巻き込まれることを防ぐことが目的であるため、自動引き落としなどは引き続き利用できるのです。
しかし、生活に必要な資金であっても、新たに口座から引き出すなどの手続きが必要な場合は利用できないことが多いので注意してください。
口座凍結で停止される手続きは、振り込みや入出金だけではありません。
窓口での様々な取引も停止されます。
例えば、定期預金の契約や解約、カードや通帳などの再発行手続き、投資信託の購入や解約などが停止の対象です。
多くの取引が停止されてしまうため、かなり不便になることを理解しておきましょう。
窓口での取引のみならず、ATMでの入出金ももちろんできなくなります。
窓口であろうとATMであろうと、基本的に入出金やその他の手続きはできなくなると考えておきましょう。
加えて、まだ口座凍結されていない状態でも、ATMでの入出金には注意が必要です。
例えば、認知症に罹患していることが知られると口座凍結される恐れがあるため、家族がその前に口座から預金を引き出しておこうと考え、毎日限度額いっぱいまで引き出したとします。
このような行為は通常では想定されない行為であり、銀行から確認の連絡が入る場合があるのです。
このように、窓口で担当者と対面していなくても、口座名義人が認知症に罹患していることが知られることもあるため、注意してください。
1つ目の影響は、認知症に罹患した本人の生活費や介護費用を子どもが代わりに支払う必要が生まれることです。
将来の生活費として、多額の預金が銀行口座に入っており、認知症になったら「預金から使っていいよ」と言われていても、口座凍結が実行されれば生活費を引き出すことは難しくなります。
そのため、生活費や介護費用を子どもが代わりに支払わなければならなくなるため、子どもの生活が圧迫される可能性もあるでしょう。
認知症に罹患した本人の定期預金も解約できなくなります。
年金が引き出せない場合と同様、本人の医療費や介護費を定期預金で賄うことができません。
必要があれば子どもの預貯金から出す必要があるため、子どもの生活が困窮してしまう可能性も考えられるでしょう。
家族も本人の口座のキャッシュカードを持てる「代理人カード」がつくれる銀行もあります。
しかし、本人が認知症に罹患すると代理人カードの発行や利用ができなくなります。
代理人カードは利便性を高めるために利用するものであって、判断能力が衰えた人の代わりに口座を管理するものではないことが理由です。
もし本人が認知症に罹患した後も代理人カードを使い続けていると、銀行から重大な問題を指摘される可能性があるため、注意してください。
株や投資信託の売買も当然ながらできなくなります。
株や投資信託を購入している方の多くは、資産運用を目的としているはずです。
しかし、認知症に罹患すると株や投資信託の売却ができなくなり、生活資金に充てることができません。
積極的に株や投資信託を購入していた方も、的確なタイミングでの損切りや利確ができなくなる点に注意が必要です。

銀行に親が認知症に罹患していることがバレないように、親族が勝手に出金すれば良いのではないか、と考える場合もあるでしょう。
その場合、罪に問われる場合があるのか、もしくはトラブルが発生することがあるのかについて解説します。
本人の口座から勝手に出金すると、刑法により窃盗罪や横領罪に問われる可能性があります。
ただし、刑法244条1項や刑法255条では、親族間の犯罪に関する特例として、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗や横領が起きた際には刑を免除すると規定されています。
そのため、刑法上では窃盗罪や横領罪に問われる可能性があるものの、その可能性は低いといえるでしょう。
しかし、引き出した預金を親の生活費に使っている場合ならまだしも、引き出した本人の遊興費などに使っている場合は、被害届が提出される可能性もあります。
その場合は、犯罪が成立してしまう可能性も十分に考えられるので、自らの遊興費には使わないようにしましょう。
相続人が複数いる場合は、相続トラブルに発展する可能性もあります。
出金したお金の使い道が明確になっていれば、トラブルに発展するケースは多くありません。
しかし、使途不明金が多くあれば、何に使ったのかが確認できないため、他の親族から追求を受けることがあるでしょう。
不信感が募るだけでなく、実損が出ていることも考えられます。そのため、他の親族が銀行に凍結依頼をし、口座凍結されてしまうことも考えられます。
親の口座から出金する場合は必ず親のために使い、レシートを保管しておくなど使途が明確になるように努めることをおすすめします。
また、他の親族が勝手に出金している場合、相続人同士での遺産分割協議が成り立たなくなる可能性が高いでしょう。
その場合は、遺産分割調停の申し立てにより、第三者を挟んだ話し合いをしてみてください。相続人同士では解決しなかった問題が第三者を挟むことにより解決できる可能性も考えられます。
しかし、遺産分割調停も「話し合い」の一種であるため、解決に至らない場合も少なくありません。
その際は、民事的な損害賠償請求や不当利得返還請求を提起することも検討してみてください。
これらの手続きは裁判の場で争うことになるため、形式上は解決に至ります。
しかし、時間やお金がかかる上、相続人同士の関係がかなり悪化し、関係を元に戻すのが困難になる可能性もあるため、裁判所への請求は慎重に検討しましょう。
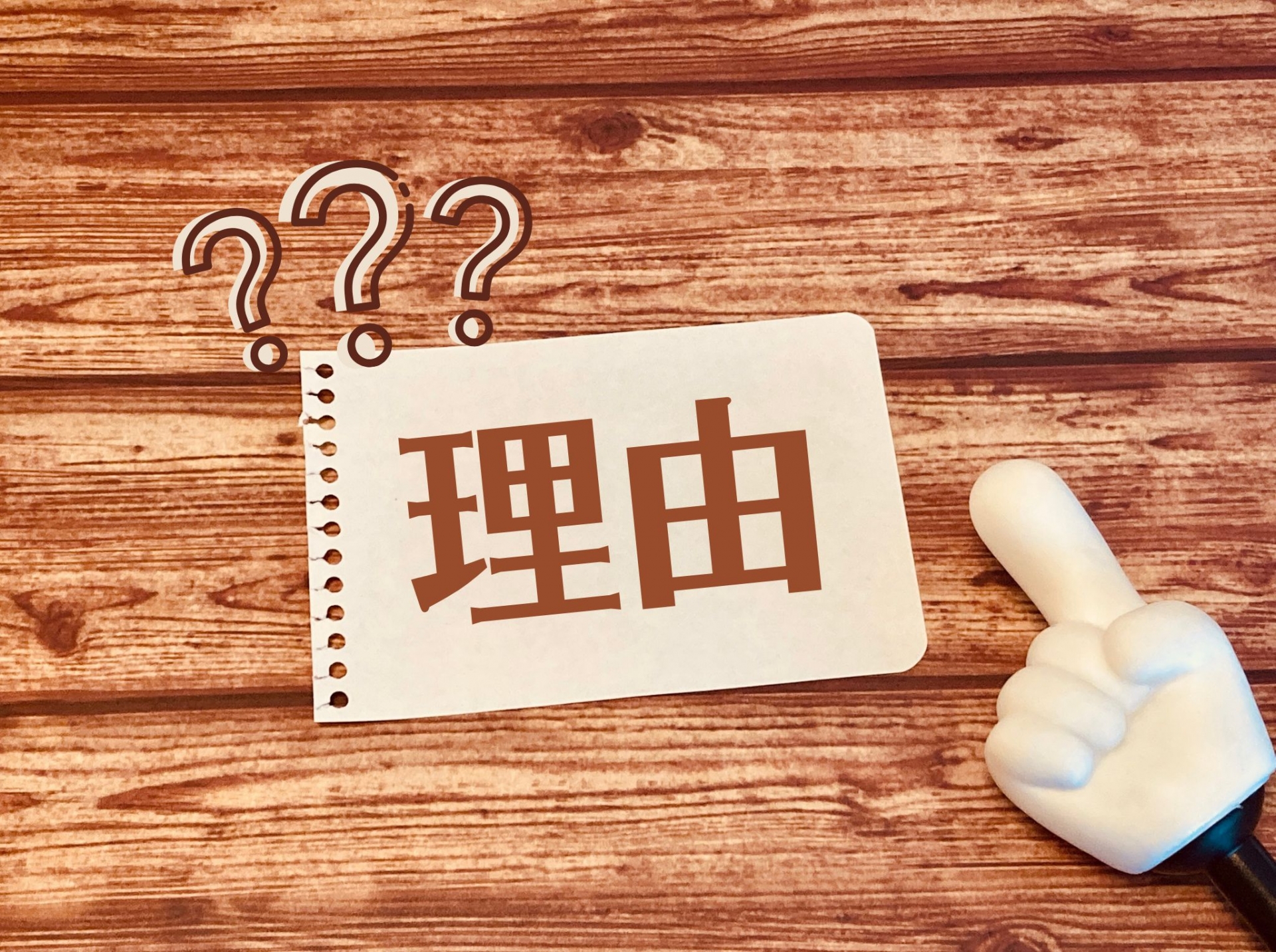
認知症が発症し本人の口座が凍結されると、口座の預金を引き出す手段は、法定後見制度以外なくなります。
判断能力が低下する前であれば、代理人登録、任意後見制度、家族信託と多くの選択肢から家族に最も合った口座凍結対策を選べます。
本人に判断の力があるうちなら、上記のように様々な方法から自分の任意の方法を選択できます。
家族信託でも任意後見制度でも、本人は受託者や任意後見人に自分の意図を直接、詳細に告げることができます。
特に家族信託は、財産管理の仕方を柔軟に決められるので、契約内容によっては二次相続以降の資産承継も本人の望むようにできるのです。
例えば、会社経営者である委託者本人が、代々長男が会社の株式を承継するように、信託を組成することも可能です。
認知症発症後の財産管理は、法定後見制度以外に選択肢はありません。
法定後見制度では、家庭裁判所が選んだ人が法定後見人に就任します。
本人の望んだ人が法定後見人に就任するとは限らないのが現状です。
判断能力があるうちならば家族信託や任意後見制度を使い、本人の家族や親族など信頼できる人を受託者や任意後見人にすることができます。
家族信託と任意後見制度は、お互いが納得した上で契約を結ぶので、双方にとって安心できる方法です。
任意後見制度では、制限も多く積極的に資産運用をすることは難しくなります。
もし、判断能力低下後も積極的に資産運用をしたい場合は、家族信託を利用することになります。
家族信託契約を結ぶときに、積極的に資産運用する財産を信託財産とすれば、受託者により資産運用が可能です。
家族信託自体に直接的な相続税節税効果はありませんが、受託者が預貯金で不動産を購入するなどして相続税を節税することはできます。
いわば間接的な節税効果となります。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

認知症による口座凍結の対策の1つに、成年後見制度が挙げられます。
ここでは、成年後見制度の内容や利用するメリット・デメリット、さらには手続きの流れについても説明します。
成年後見制度とは、認知症の人に代わり財産の管理ができる制度です。
家庭裁判所へ申し立てをし、審判により選ばれた「成年後見人」が、認知症である本人に代わって財産の管理をすることができます。
財産の管理だけでなく、契約行為などについても代理での対応が可能です。
認知症の他にも、精神疾患・知的障がいによる判断能力の低下にも利用できます。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
それぞれ対象が異なるため、1つずつ説明します。
「法定後見制度」は、すでに認知症の人が対象となる制度です。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、それぞれサポートできる内容が変わります。
「後見」「保佐」「補助」のうち、どの段階になるのか、誰がサポートするのかなどは裁判所により判断されます。
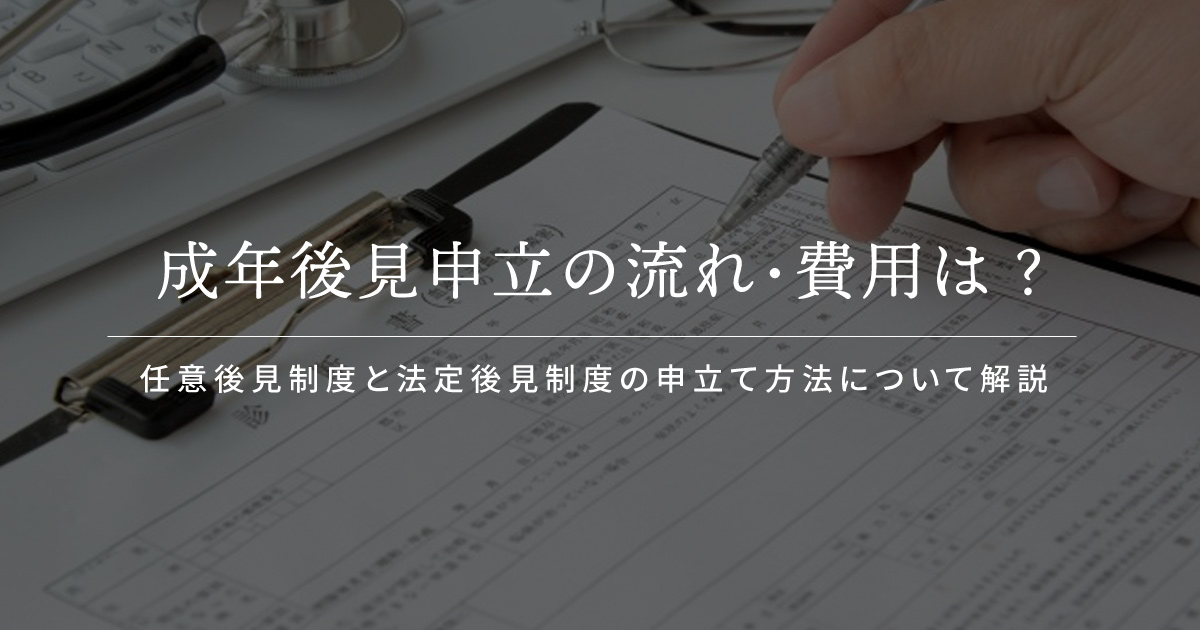
「任意後見制度」は、認知症になる前に備えておくための制度です。
認知症発症後の財産管理に備え、任意後見制度を活用し、自分の意思で信頼できる後見人を選んでおきましょう。

成年後見制度を利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
法定後見制度では、家庭裁判所が法定後見人に適している人を選任し、その人が財産の管理を行うことになります。任意後見制度でも、任意後見人が自由に財産を管理できるわけではなく、裁判所が選任する任意後見監督人の監督を受けます。
裁判所に認められた人が管理することで、安心して管理を任せることができるでしょう。
法定後見制度の法定後見人や任意後見監督人には、弁護士や司法書士などの士業に携わる人が選任されるケースが多いです。
法定後見制度は「認知症になっても」対策ができる唯一の制度です。
法定後見制度があるおかげで、認知症になっても全ての預貯金が引き出せなくなるわけではありません。
一方、任意後見制度は、対策を「事前にできる」ことがメリットです。
他にも事前に対策できる方法はありますが、裁判所のお墨付きがある安心した制度の下で対策できる点が安心です。
法定後見制度を利用するデメリットは、主に以下の5つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
成年後見制度は費用が高額になりがちです。
成年後見制度では、制度の利用を開始するための手続きに関する費用だけでなく、毎月、成年後見人へ報酬を支払う必要があります。
成年後見人の報酬は月額2〜6万円程度が目安とされています。これらの報酬を支払うことも念頭においた上で、利用を検討してください。
成年後見制度は原則、途中でやめることができません。
口座の凍結を解除する目的のためだけに一時的に使うことはできないので、注意してください。
家庭裁判所による審査があるため、申し立てから利用を始めるまでに、3〜4カ月かかります。
すぐに利用できるわけではないので、あらかじめ注意しておきましょう。
後見が開始された口座は、毎年、後見人が裁判所へ報告しなければなりません。
そのため、「管理されている」という印象を受ける方もいるでしょう。
また、まとまったお金を引き出す際や、居住用の不動産を売却する際には、裁判所の許可が必要である点も認識しておいてください。
本人の死後、葬儀の手続きや介護施設への支払いなどの事務行為を誰かにしてもらう必要があります。
しかし、法定後見制度では生きている間の支援しかできないため、死後の事務委任はできません。
生前の支援と死後の支援を同じ人にしてもらいたいと考えるときは、死後事務委任契約を別に結ぶことが必要です。
生前から死後まで、トータルで支援をしてもらいたい場合には、法定後見制度と死後事務委任契約の両方を契約することをおすすめします。
一方、任意後見制度のデメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
任意後見制度を契約するには、本人の判断能力が十分であることが条件です。
そのため、本人の判断能力が低下し認知症に罹患してしまうと、任意後見契約を結べなくなります。
判断能力の低下が軽微であれば契約できる可能性もありますが、原則として認知症に罹患すると任意後見制度は利用できなくなる点に注意してください。
任意後見制度では、裁判所により任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人には裁判所が決めた額の報酬を支払う必要があります。
専門家が選任されることが多く、一定額の費用がかかることを想定しておくと良いでしょう。
なお、任意後見人への報酬は事前の契約で決めることができ、任意後見人との合意ができれば無償で依頼することも可能です。
任意後見人には取消権がないことに注意が必要です。
法定後見制度には、本人に不利益な契約を間違えて結んだ場合、後から取り消す権利があります。
一方、任意後見人には取消権がなく、本人が不利益な契約を結んでも後から対応することが難しいのです。

認知症による口座凍結の対策として、家族信託も考えられます。
ここでは、家族信託の仕組みや利用するメリット・デメリット、流れを解説します。
家族信託とは信頼できる家族に財産の管理を託す仕組みのことです。
成年後見制度ほど複雑な手続きがなく、比較的自由に財産を管理できます。
しかし、成年後見制度とは異なり、あくまで本人の判断能力があるうちに行わなければいけないので、注意が必要です。

家族信託とは、親や祖父母が自分の財産の管理・処分を子や孫に任せる財産管理の制度です。
家族信託には、委託者、受託者、受益者の三者が登場します。
委託者が管理・処分を任せた財産を信託財産といい、実質的な所有者は受益者です。
すなわち、受託者は受益者のために財産を管理・処分します。
家族信託には以下のメリット・デメリットがあります。
家族信託が口座凍結の対策になるのは、以下の理由からです。
家族信託を利用するメリットは、主に以下の4つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
成年後見制度では裁判所による預金口座チェックや、引き出しの許可が必要ですが、家族信託ではより自由に財産を管理できます。
例えば、相続後のことを考え、財産を管理する人が家などの不動産を処分することが可能です。
また、家族信託には認知症対策としても有効です。
何も対策していない場合、認知症に罹患した本人の財産はセキュリティ対策のため凍結され、預金口座からの引き出しや不動産・株などの売買などができなくなります。
一方、家族信託では信託口口座でお金を管理・運用しているため、本人が認知症に罹患しても預金口座が凍結されません。
財産を管理する人は、預金口座からの引き出しや不動産・株などの売買など、本人の財産に関する取引を続けることができるのです。
成年後見制度では、特に法定後見制度を利用する場合において、弁護士や司法書士などが成年後見人に選任されることが多く、成年後見人に対する報酬を支払う必要があります。
しかし、家族信託では弁護士や司法書士などに依頼する必要がないので、低コストで運用できます。
相続の際に、財産が誰の手元に渡るのかを決めておくことができます。
相続にありがちな相続財産の割合をめぐるトラブルを未然に防げるでしょう。
遺言書にも同じ機能がありますが、家族信託のほうが柔軟に財産承継できます。
遺言書で決められる財産の行方は、一代限りです。
一方、家族信託では財産の行方を二代目以降も指定できます。
例えば、自分が亡くなったら自宅を子どもAに相続し、子どもAが亡くなったら孫Bに相続する、という内容を設定したい場合を考えてみましょう。
遺言書では子どもAへの相続までしか効力を持ちませんが、家族信託では孫Bへの相続にも効力を持ちます。
「誰に財産を引き継がせたいか」が明確に決まっている場合、家族信託の利用も検討してみてください。
「財産を管理している人が破産をしたら、信託した財産も差し押さえられてしまうのではないか?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、家族信託で信託した財産が差し押さえられることはありません。
実際には財産を子どもが管理しているものの、形式的な財産権は以前として元の所有者にあります。
そのため、財産を管理している人が破産しても、信託した財産が差し押さえられることはありません。
家族信託を利用するデメリットは、主に以下の4つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
家族信託は、本人の判断能力が十分でないと契約できません。
そのため、認知症になった後は利用できない場合がほとんどです。
ただし、任意後見制度と同様、認知症の程度が軽微であれば家族信託契約を結べる場合もあります。
家族信託を締結できるのか気になる場合は、家族信託の専門家に相談してみることをおすすめします。
成年後見制度では、家庭裁判所が成年後見人を選任する方式をとっています。一方、家族信託では家族が受託者(財産を管理・運用・処分できる人)となります。
そのため、安心して任せられる家族は誰かを決められなかったり、お互い受託者となることを譲らなかったりすると、家族信託を利用するのは難しいといえるでしょう。
家族信託では、基本的に節税効果はありません。
もし、節税対策として家族信託を考えている場合は、後で紹介する生前贈与などとの併用を検討してみてください。
家族信託は比較的新しい仕組みのため、家族信託の専門家が少ない状況です。
弁護士や司法書士、行政書士、税理士などが対応できる専門家ではありますが、家族信託に精通している専門家は多くないため、探すのに苦労するかもしれません。

1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

認知症による口座凍結の対策としては、生前贈与も考えられます。
認知症になる前に自身の財産を贈与しておけば、認知症になっても凍結される心配はいりません。
以下では、生前贈与のメリット・デメリット、流れを解説します。
生前贈与を利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
相続の際には相続財産の配分で揉めることがしばしばありますが、生前贈与で先に財産を配分しておけばその心配は必要ありません。
仮にトラブルが起きたとしても、生前に直接対応できれば大きな問題とならずに済むでしょう。
贈与には「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの制度があります。
このうち、「暦年課税」では年間110万円の基礎控除が受けられるため、節税効果が期待できるでしょう。
なお、「暦年課税」においては、子ども名義の口座に、子どもが知らない状態で勝手に贈与したり、毎年同じようなタイミングで計画的に贈与したりすることは認められていません。
加えて、相続発生から3年以内の贈与においては、贈与ではなく相続財産としてみなされる点にも注意をしてください。
相続が発生すると、相続税がかかることがあります。
あらかじめ財産を贈与しておくことで、相続税を減らすことができます。
ただし、後ほど解説するように、贈与税がかかることがあるため、両者を比較した上で検討するようにしてください。
生前贈与を利用するデメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
1つずつ確認していきましょう。
生前贈与では贈与税がかかる可能性があります。
暦年課税では年間110万円を越える贈与を受けると、贈与を受けた人に贈与税がかかります。
その他にも、不動産を贈与する場合は「登録免許税」「不動産取得税」などがかかります。
先ほども解説したように、相続税の節税はできますが、逆に贈与税が多くかかってしまう可能性があるので、両者を比較してから生前贈与をしましょう。
遺留分とは、民法で保証されている財産の相続を受けられる割合のことです。
生前贈与により、他の親族が遺留分の相続ができなくなる、すなわち遺留分侵害をしてしまう可能性があります。
遺留分侵害をすると、遺留分侵害額の請求を受けることがあるので注意してください。
生前贈与があったことを税務署に認めてもらうためには、少々手間がかかります。
贈与契約書を提出したり、贈与税の申告をする必要があるでしょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

これまで金融機関は、認知症発症以降の取引は法定後見制度の使用を原則としていました。
しかし、法定後見制度は本人や家族にとって決して利用しやすいものではありません。
超高齢社会という背景もあり、金融機関も柔軟に対応する姿勢を見せてきています。
2021年2月18日、一般社団法人全国銀行協会は「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」を発表しました。
判断能力の低下した人の預金の入出金は、例え家族といえども応じず、法定後見制度の利用が原則です。
しかし、成年後見制度の利用がなかなか進まない一方、本人の医療費や介護費用又は生活費のため、家族が預金を引き出したいと窓口に来るケースが多く見られました。
このような状況に鑑み、本人のために預金を引き出すことが明らかな場合に限り、正式な代理権のない家族が預金を引き出すことを認めるという指針です。
代理取引は、法定後見制度を利用できない人や法定後見制度の開始を待っていたのでは間に合わない人たちにとっては、便利な方法です。
しかし、これはあくまで一般社団法人全国銀行協会が各金融機関に向けて出した指針にすぎず、特に拘束力のあるものではありません。
したがって、この指針どおり運用するかどうかは、各金融機関の判断にゆだねられます。
実際に、金融機関の窓口に行って断られるケースも十分あり得るので、注意が必要です。
「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)」においても、基本的な考え方は、従前どおり口座凍結後の取引は法定後見制度の利用が原則です。
理由としては、①口座にある預金は本人に所有権があること、②家族とはいえ代理権のない者に出金を認めるのはリスクが高いことが挙げられます。
やはり、口座が凍結されて慌てないように、判断能力があるうちに任意後見制度や家族信託の利用などの対策を講じる必要があります。

最後に、認知症の口座凍結に関するよくある質問を7つ紹介します。
口座凍結とは、一定の条件に該当した場合に、預金の引き出しなどの取引が停止されることです。
「取引の停止」とは、お金を下ろすだけではなく、振り込みなど、一切の手続きができなくなります。口座が凍結された場合、自動的に解約される事はありませんが、元通り使えるようにするには一定の手続きが必要です。
口座が凍結してしまった場合、法定後見制度の利用によって法定後見人を立てる事で解除できる可能性があります。ただし、先々の事を考えて、事前に「家族信託」や「任意後見制度」によって備えておくのがおすすめです。
代理人カードも、口座名義人の判断能力が低下すると利用できなくなります。
代理人カードとは、本人以外にも発行されるキャッシュカードで、本人以外でも預金を引き出せるため、便利に使えます。
しかし、口座名義人の判断能力が低下すると、利用が停止されるように要件を定めている場合がほとんどです。そのため、名義人が認知症に罹患すると代理人カードも使えなくなるのです。
認知症に罹患したことを隠して利用を続けていると、銀行から目をつけられてしまい、大きなトラブルに発展することもあるため、注意してください。
成年後見制度とは、判断能力が低下した人などの財産管理を成年後見人と呼ばれる人が代理する制度で、成年後見人であれば名義人の口座から預金を引き出せます。
しかし、手続きには多くの手間がかかる他、成年後見人には家族がなれるとは限らず、弁護士などの専門家が選任される可能性もあります。専門家が選任されると、名義人が死亡するまで報酬を支払い続ける必要があるなど、デメリットもある制度です。
口座凍結されてしまった場合、解除するには基本的に成年後見制度しか利用できません。そのため、認知症に罹患する前から対策しなければなりません。
口座凍結の解除は成年後見制度しか認められていませんが、前述したようなデメリットがあるため、利用が促進されていません。
そのため、一般社団法人全国銀行協会は、認知症に罹患した際でも一定の要件を満たすことで、預金の引き出しが可能になる指針を発表しました。
要件は、主に以下の2つが挙げられます。
要件を満たしていないと認められない他、あくまでも指針であるため、必ずしも全ての銀行で認められているわけではない点に注意してください。
参照:一般社団法人全国銀行協会|金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版)
2018年1月より施行された「休眠預金等活用法」により、2009年1月1日以降、10年以上取引がない口座の預金は「休眠預金等」となり、民間公益活動に活用されることになります。
口座が凍結されたまま10年間放置し続けると、その口座は「休眠預金等」として扱われます。
「休眠預金等」となっても、口座のある金融機関で引き出すことが可能です。
口座のある金融機関に、通帳、キャッシュカードと免許証などの本人確認書類を持っていけば、預金を引き出すことができます。
引き出すための手続きや口座の取り扱いは金融機関により異なるのでご注意ください。
民法では、夫婦間、親子間、兄弟間には扶養義務があり、認知症の親の生活費や介護費用は扶養義務の範囲と考えられます。
すなわち介護費用は家族が当然負うべき義務になります。
したがって、立て替えた生活費や介護費用は相続分に加算されません。
立て替えた人は納得できないかもしれませんが、法律的には上記のとおりです。
親孝行をしたと考えて気持ちを切り替えましょう。
相続時にトラブルにならないように、介護をしてくれる人に贈与により予め生活費や介護費用を渡しておくか、家族信託を利用しましょう。

認知症により口座が凍結された後では、原則として法定後見制度を利用するしか口座から預金を引き出すことはできません。
そのような事態を避けるために、判断能力があるうちに対策を講じる必要があります。
任意後見制度もありますが、柔軟に資産管理ができる家族信託がおすすめです。
しかし、家族信託を組成するには高度な法律知識が必要になります。
ファミトラでは、弁護士や司法書士をはじめとする法律の専門家が無料相談を開催しております。
口座凍結への対策や家族信託に興味のある方は、ファミトラに一度ご相談ください。
家族信託に精通した専門家が、お客様の相談を受け付けております。
ファミトラでは、家族信託に限らず相続対策や成年後見制度にまつわるご相談など幅広く対応することが可能です。

さまざなお客様のケースに対応してきた経験豊富な家族信託コーディネーターが、お客様一人ひとりのご状況に合わせて親身にサポートいたしますので、「まずはお話だけ…」という方もお気軽にご相談ください。
\ 24時間いつでもご相談可能 /

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。