
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

加齢により認知機能は徐々に低下します。認知症になり症状が進行すればなおさらです。
将来、今と同じように一人で日常生活が送れるのかなどの懸念を抱えている方も多いのではないでしょうか。
これらの不安は、元気なうちに任意後見制度の利用準備をすれば解消可能です。
ここでは、任意後見制度についてわかりやすく解説していきます。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

任意後見制度を利用する際の手続きの流れや費用、成年後見制度との違いなどについてわかりやすく解説します。
成年後見制度とは、後見人をつけて認知や判断の機能に問題を抱える方の権利利益を守る制度です。後見人は、本人に代わって土地建物や現預貯金、有価証券などの財産を管理します。また介護サービスの利用先を決めるなどの身上監護を行い、本人の権利利益の確保を目的に行動します。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類です。前者では認知症で1人の生活が難しくなった段階で初めて家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、後者では元気なうちに契約によって自ら選びます。
| 成年後見の種類 | 後見人の選任方法 |
|---|---|
| 法定後見 | 認知症で1人の生活が難しくなった段階で家庭裁判所が選任 |
| 任意後見 | 元気なうちに契約で自ら選任 |

2つの制度はそれぞれどう違うのでしょうか?

両者を比較しながら確認していきましょう!
法定後見制度は、認知機能や判断機能に問題が生じ、日常生活が困難となった人の生活をサポートする国家主体の制度です。後見人の選定や権限内容は家庭裁判所が決定します。
種類は、本人の判断能力に応じて3段階に分かれています。

判断能力が低い方から後見、保佐、補助の3段階です。
制度の主な特徴は以下の通りです。
任意後見と法定後見の各項目を比較してみましょう。
以下の通り、各項目によってそれぞれ特徴があることがわかります。将来の準備をする際には、それぞれの共通点、相違点、特徴をよく押さえて検討すべきです。
| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 準備時期 | 判断能力の低下前 | 判断能力喪失後 |
| 開始時期 | 判断能力の低下後 | 判断能力喪失後 |
| 後見人の選任権者 | 本人が自由に選任 | 家庭裁判所が法律に沿って選任 |
| 後見人の権限設計 | 本人が自由に設計 | 家庭裁判所が法律に沿って決定 |
| 同意見、取消権の有無 | なし | あり |
なお、法務省が作成した後見制度全般についてのパンフレットにも、違いがまとめられているので、必要に応じてご覧ください。

任意後見制度の利用方法は、以下の3つの種類に分けられます。
契約の締結後、ただちに任意後見人選任の申し立てを行うケースです。
契約を締結する時にすでに認知症などの症状がある程度進んでいて、急いで後見人を選ぶ必要があるケースに向いています。
このケースでは、手続き後ただちに後見が開始され、後見人が本人の財産を管理します。そのため、後に不動産や現預貯金を勝手に処分されたなどの認識相違が生じないよう注意すべきです。
任意後見人にどの程度の権限を与えておくかなど、事前に本人と認識をすり合わせておくことが重要です。
本人に何も問題ないうちに、認知症などの症状の進行を想定し任意後見契約と財産管理契約を結んでおくケースです。
元気なうちは財産管理の受任者として資産管理をサポートします。その後、症状が進行したら任意後見人に就任し、財産管理を行ってもらうことになります。
健康状態や病気の症状に応じて財産管理をサポートしてもらいたい方に向いているでしょう。
移行型と同じく、元気なうちに任意後見契約を結んでおき、認知症などの症状が進行したら、任意後見を開始して財産管理を行なってもらうケースです。
移行型との違いは、健康状態に問題がない時点では、財産管理契約を結ぶことなく1人で財産管理を行う点です。
認知症などの症状の進行には事前に対応する意思を持っているが、元気なうちは自分1人で財産を好きに使いたいという方に向いています。
任意後見人には法律上の資格はありません。一般的には親族がなることが多いですが、原則として誰でもなることができます。
ただし、法律で例外事由があり、例外事由に該当する人は就任できません。
任意後見監督人の役割は任意後見人の監督です。
任意後見人は、必要に応じて、本人に代わり土地建物、預貯金から株式や投資信託といった有価証券など、さまざまな資産を処分する権限を持つことがあります。
親族が任意後見人だと第三者の目が入らず、本人の資産を横領などで散逸する危険性があるのです。
家庭裁判所は逐一監視できないので、任意後見監督人に業務を委ねます。役割上、第三者的視点を持つ弁護士や司法書士といった法律の専門家が選ばれるケースが多いです。
任意後見制度を利用するには、主に以下の3種類の費用が必要になります。
| 公証人の手数料 | 1契約につき1万1,000円 (4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円を加算) |
|---|---|
| 印紙代 | 2,600円 |
| 登記費用 | 1,400円 |
| 書留郵便料 | 約540円 |
| 正本、謄本の作成費用 | 1枚250円×枚数 |
| 申立手数料 | 800円 |
|---|---|
| 登記費用 | 1,400円 |
| 郵便切手(連絡用) | 数千円程度 |
| 精神鑑定の費用(必要な方のみ) | 5〜10万円 |
【後見人の報酬】
任意後見人の報酬額は任意後見契約によって決まります。弁護士などの専門家に依頼した場合、依頼手数料が高額になる可能性があるため、契約時に確認しておくことが重要です。
【後見監督人の報酬】
家庭裁判所の判断で決定されます。本人の総資産額や後見事務の内容などを踏まえて総合的に判断されます。一般的には月額1〜2万円程度が目安です。

ここでは、法定後見制度と家族信託との違いについて、以下の7点を中心に解説します。

法定後見制度とは、判断能力が低下した人をサポートするため、親族等が申し立てることにより利用が始まる制度です。
裁判所が選任した人が後見人として、判断能力が低下した人の生活をサポートします。
後見人には本人の財産をどのように使ったのかなどを定期的に裁判所に報告する義務があり、不動産の処分などをする際は裁判所の許可を取らなければなりません。
本人の判断能力が低下してから利用する制度であるため、判断能力の低下に備えて事前に準備しておきたい場合は他の制度を利用することになるでしょう。
一方、家族信託とは、家族や親族など委託者が信頼のおける人を受託者とし、財産の管理等を受託者に依頼する制度です。
法定後見制度とは異なり、本人の判断能力があるうちに契約しなければならない制度であるため、認知症等で判断能力を失ったときに備える際に用いられます。
法定後見制度では後見人が法律行為の代理なども可能ですが、家族信託では財産の管理・運用等しか認められていません。
しかし、財産の管理者は裁判所に選任されるのではなく、自分で決められるため、安心して管理を任せられることが大きな特徴です。
概要でも少し触れましたが、法定後見制度と家族信託では対策できる時期が異なります。
法定後見制度では判断能力が低下したとき、もしくは失ったときに申し立てをする一方、家族信託では判断能力がまだある状態で契約を結ぶという違いがあるのです。
なお、家族信託では判断能力が低下していることが見受けられても、低下の度合いが軽微であれば契約が認められるケースもあります。
利用する際の条件についても違いがあります。
対策できる時期でも述べた通り、法定後見制度は判断能力が低下した場合でないと利用できません。
なお、判断能力が低下したとする医師の診断書が必要であることに注意してください。
一方、家族信託は判断能力が低下していないことが利用する際の条件です。
ただし、判断能力の低下が軽微であれば、利用が認められる場合もあります。
法定後見制度も家族信託も、利用するには以下の費用が必要です。
それぞれの制度でどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
法定後見制度の初期費用のうち、契約や登記等で必要なのは後見開始の申し立てにかかる約1万円です。
また、場合によっては精神鑑定が必要となり、5万円〜10万円ほどの費用がかかります。
一方、家族信託の初期費用のうち、契約や登記等で必要なのは公正証書の作成費用です。
費用は5,000円〜25万円ほどであり、財産額によって大きく異なります。
例えば、財産額が100万円以下の場合は5,000円、財産額が10億円の場合は約25万円です。
手続き等を専門家に依頼する場合はその費用も必要です。
法定後見制度では申し立ての代理手数料として、およそ10万円〜30万円かかります。
一方、家族信託では信託契約書の作成費用としておよそ50万円〜150万円、コンサルティング費用として別に5万円〜10万円がかかります。
法定後見制度でも家族信託でも、ランニングコストがかかる場合があります。
法定後見制度では成年後見人や法定後見監督人に対し、3万円〜10万円ほどの月額報酬を支払います。
ただし、法定後見監督人を付けない場合、費用はやや安くなり、家族が成年後見人に選任される場合、月額報酬が必要ない場合もあるでしょう。
一方、家族信託でも信託監督人への報酬として、月額数万円が必要です。
ただし、信託監督人を付けなければこの報酬は必要ありません。
法定後見制度で財産管理者となるのは、家庭裁判所が選任した成年後見人です。
なお、成年後見人は財産を管理しつつ、財産の状況について定期的に裁判所へ報告する義務があります。
一方、家族信託で財産管理者となるのは、委託者と契約を結んだ受託者です。
受託者は自由に決めることが可能であり、信頼のおける人物であれば家族以外でも選任できます。
法定後見制度は、原則として途中でやめることができません。
任務が終了するのは、被後見人の判断能力が回復する場合と被後見人が死亡する場合だけであるため、それ以外の場合は途中でやめることができないのです。
一方、家族信託は委託者と受益者との間で合意がなされれば終了できます。
また、信託契約で終了事由を定めておくことが可能であり、終了事由を満たした場合も終了できます。
成年後見制度の監督機関は、家庭裁判所と成年後見監督人です。
加えて、成年監督人は家庭裁判所に定期的に財産状況について報告する義務があります。
一方、家族信託の監督機関は、信託監督人や受益者代理人です。
ただし、信託監督人や受益者代理人は契約で定めない限り設置されないため、委託者が受託者について監督してほしいと考える場合は、信託契約で決めておく必要があります。
主なメリットとしては以下の2点です。

法定後見制度である成年後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。
選任過程で後見人の希望者を申し出ることは可能ですが、希望通りになるとは限りません。
たとえば、面識のない弁護士などの専門家が選任される場合もあります。つまり、自分の意思で自由に選任できるわけではないということです。
任意後見であれば「任意後見人になれない人」を除いて、親族であれ、弁護士などの専門家であれ、自分が信頼を寄せている人を誰でも自由に選任できます。
本人の判断能力がなくなった場合、後見人による財産管理を本人がチェックするのは難しく、後見人の権限濫用により財産が散逸する危険があります。
そのような事態を防ぐことが後見監督人の役割です。家庭裁判所が選任した後見監督人が客観的立場で後見人の事務をチェックすることで、任意後見制度を安心して利用できます。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
主なデメリットは、以下の2点です。

下記にて、順番に説明します。
任意後見人には、本人の取引を後で取り消す権限(取消権)が認められていません。法定後見制度では、本人に必要のない借入れや、割高な価格での不動産購入など財産を散逸させる行為を後で取り消すことができます。
詐欺や錯誤などの他の取消事由がない限り、取り消すことができないのは、デメリットとしては大きいと言わざるを得ません。大切なのは、このようなデメリットを事前に把握した上で利用することです。
任意後見契約は本人が死亡することで終了します。そのため、死亡後に必要となる財産管理はできないというデメリットがあります。例えば、葬儀や墓石などの費用支出を任せることはできません。
死亡後も継続して財産管理を任せたい場合、任意後見契約に加えて、事前に死後事務委任契約や家族信託により備えておく必要があります。
任意後見制度のデメリットについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。


任意後見人と任意後見監督人の仕事内容を紹介します。
原則として、任意後見業務は任意後見人が担います。ただし、任意後見人を監督する者がいないと任意後見人の怠慢が放置されるかもしれません。
任意後見制度は、任意後見人の他に任意後見監督人を置き、本人の利益が守られるようにしています。
任意後見人の主な仕事内容は、財産管理・身上保護・報告業務の3つです。
任意後見人に就任する方は、業務内容を十分に把握しておきましょう。
財産管理は任意後見人の中心となる仕事といえます。
認知症後の、本人の財産管理を目的として、任意後見契約を結ぶ方が多いからです。
財産管理の主な具体例は、次の通りです。
任意後見人が、預貯金の管理業務を担える点は重要です。認知症により、本人の銀行口座が凍結される可能性があるからです。
任意後見契約を締結し、任意後見人に口座管理の権限を与えておけば、任意後見人は契約を根拠に本人の口座からお金を引き出せます。
また、任意後見人は不動産の管理も担います。
ただし、任意後見人による不動産の運営・管理は、現状の財産を維持するための消極的なものに限定されることに注意が必要です。家族信託における受託者と異なり、利益獲得を見越した積極的な不動産運用はできません。
身上保護も、任意後見人の職務に含まれます。
身上保護に該当する具体例は、次の通りです。
身上保護の権限が与えられるのは、任意後見の大きな特徴といえます。任意後見と似た制度に家族信託がありますが、家族信託では受託者に、身上保護の役割を担わせることができないからです。
認知症対策として、家族に身上保護の権限を与えたい場合は、任意後見が役立ちます。状況によっては、任意後見と家族信託を重ねて利用することも検討しましょう。
なお、任意後見人は任意後見監督人への報告が求められます。業務内容を証拠として残すため、契約書等の保管が必要です。
任意後見人には、報告業務も課されます。
報告先は任意後見監督人です。任意後見監督人は、任意後見人の業務が適切にされているか監督する役割を担います。
任意後見人は、自らが行った業務を任意後見監督人に報告し、任務が適切に全うされている事実を明らかにしなければなりません。報告は口頭のみでは足りず、業務の際に交わした契約書等に関しては、証拠として写しを提出する必要があります。
任意後見人は、報告業務等を通して、任意後見監督人からのチェックを絶えず受ける立場にあります。そのため、任意後見人に就任する方は、責任の重さや業務内容を十分に理解しておく必要があるでしょう。
任意後見監督人の主な業務は、任意後見人の監督です。
もっとも必要に応じ、任意後見監督人が、自ら後見業務にあたる場合もあります。
任意後見監督人の中心業務は、任意後見人の監督です。
任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりをチェックすることで、本人の財産管理や身上保護が適正にされる仕組みになっています。
家族が任意後見人の場合、身内同士という事情もあり、任意後見人の業務が杜撰(ずさん)になるかもしれません。しかし任意後見監督人の存在により、第三者のチェックが入り、任意後見人の業務がより適切に遂行されるようになります。
任意後見監督人は、3カ月に1回程度、任意後見人から業務の報告を受けます。任意後見業務の適法性・妥当性をチェックするためです。
また、任意後見監督人は、裁判所との連携も果たします。年に1回は、任意後見人の業務が適正に行われているかについて、家庭裁判所に報告します。
一定の場合、任意後見監督人は任意後見人と同じ役割も果たします。
任意後見人に後見業務をさせることが、ふさわしくない場合が想定できるからです。
例えば利益相反に該当するケースが考えられます。
任意後見人と本人が、それぞれ相続人となり、遺産相続する状況を考えてみましょう。遺産相続では、遺産という限られた財産を相続人間で分け合うため、相続人間で利害が対立する状況が生まれます。
そのため、任意後見人に本人の代理人を任せてしまうと、本人の利益がないがしろにされる危険があります。任意後見人は代理人の立場を利用して、自己にとって有利な、本人にとって不利な遺産分割協議へと導くかもしれません。
このように利益相反に該当する場合、任意後見人に代わり、任意後見監督人が本人の代理人の役割を果たします。
他に、任意後見人が病気等で身動きできない場合など、緊急時においても任意後見監督人は代理人の役割を果たします。
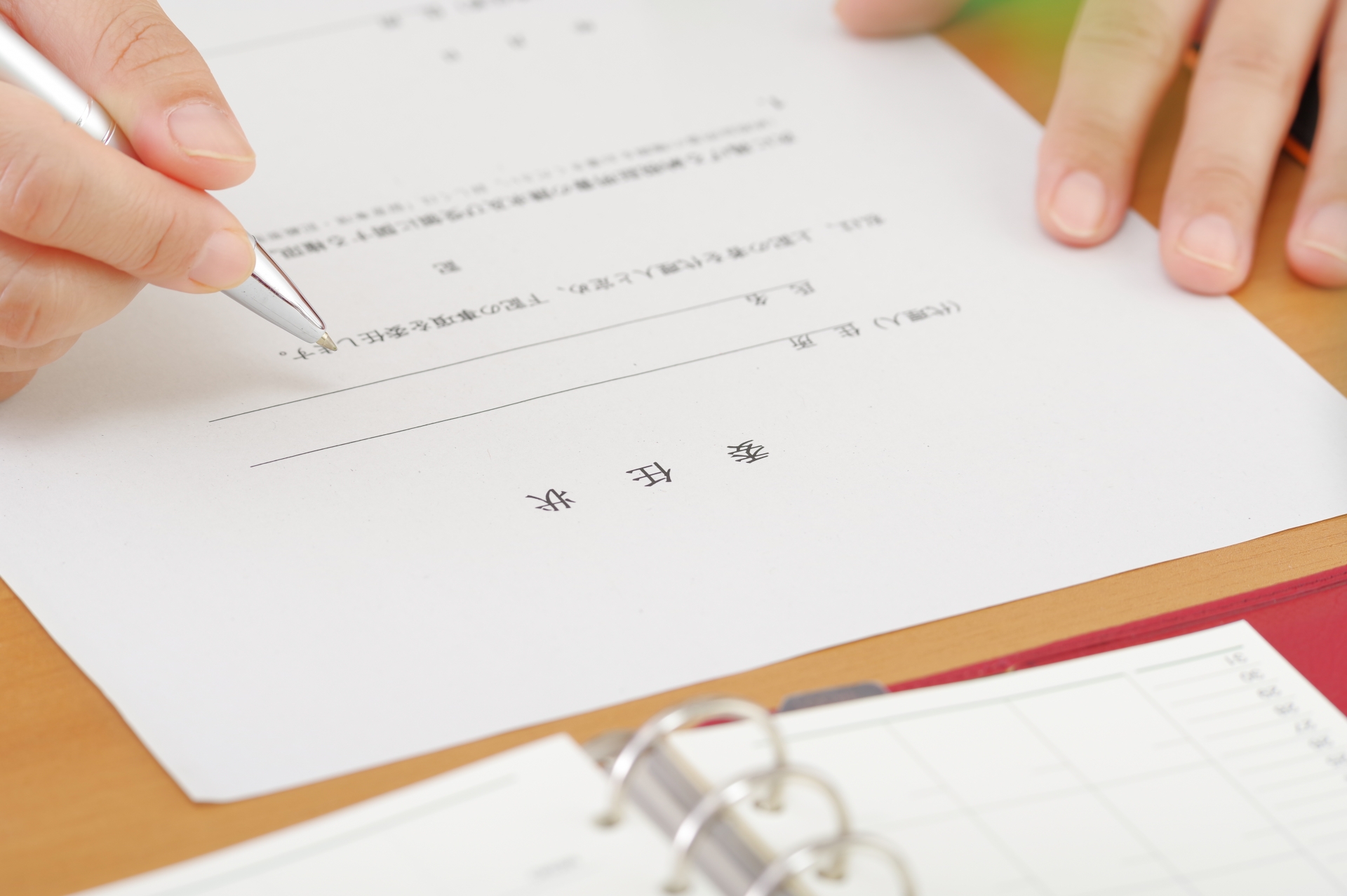
任意後見監督人選任の際にはいくつかの書類の提出が必要です。以下は申し立ての際に必要な書類であるため、準備をする際の参考にしてください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

実際に任意後見制度を利用するためには以下の4つのステップが必要です。1つずつ確認していきましょう。
最初に行うのは、自身の大切な財産の管理を任せる人を決めることです。このような将来の任意後見人を「任意後見受任者」と呼びます。
資産の処分や活用を委ねるので、信頼できる人を選ぶことが重要です。また、本人の意思を尊重して財産管理を行ってもらう必要があるので、遠慮なく相談できる人に任せることも同じように大切です。
一般的には、信頼する親族、あるいは弁護士や司法書士といった専門家を選ぶケースが多い傾向にあります。
次に、支援内容を決めます。
将来、「何を」「どうやって」支援してもらいたいかを具体的に擦り合わせます。契約において主に決定しておくべき事項は以下3点です。
| 支援してもらう内容 | |
|---|---|
| 財産管理 | 土地建物、現預貯金、株式、投資信託などの保有資産の処分や利用方法に関する希望 |
| 身上監護 | 介護サービスの利用、施設や病院への入所または入院などの生活や療養に関する希望 |
| 後見人に関する事項 | ・報酬金額、報酬や経費の支払方法など ・代理権の範囲 |
3つ目のステップは、任意後見契約の締結です。
法律上、公正証書で作成する必要があります。そのため、支援内容をまとめた契約書案をもとに、公正証書を作成してもらいます。
公正証書とは、元裁判官などの実務経験豊かな公証人が作成する証拠力の高い書面のことです。全国の公証役場で作成してもらえます。
最後に、任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見は、申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で開始されます。判断能力が低下したら自動的に開始するわけではありません。申し立てができるのは、以下の4名のいずれかに当てはまる人です。
任意後見受任者に適切なタイミングで申し立てを行ってもらうためには、日頃から密な関係性を築いておくことが重要です。

任意後見人が選ばれた後でも、法律上の理由があると辞任や解任が認められます。
選任された後見人が自ら辞めるには、正当な事由が必要です。例えば、任意後見人自身の健康状態が悪化したりして、後見事務を行うことが困難な場合です。
この場合、申し立てに対して家庭裁判所が許可すれば、辞任が認められます。
不正行為など任務不適合事由があるときは解任を求めることが可能です。解任を求める手続きは、家庭裁判所に対して行います。
手続きができるのは、以下の4名です。
解任されるのは、裁判所が検討した結果、任務不適合事由があると判断したときです。

認知能力低下による想定外のトラブルを回避するためには、任意後見制度と家族信託を併用することがオススメです。
任意後見制度では、本人が元気なうち、あるいは亡くなった後は、任意後見人が財産管理をすることはできません。
また、判断能力が低下した後であっても、任意後見を開始するために家庭裁判所の審判を受ける必要があります。そのため、任意後見人が本人の判断能力を十分に把握できていないと、円滑な財産管理の開始に支障をきたす場合があります。
この点、家族信託を併用しておけば、判断能力が低下する前から財産管理の支援を受けることが可能です。また、葬儀費用の支出などの死亡後における事務処理も可能になります。
このように、家族信託であれば本人の判断能力の程度や生死にとらわれず、一貫して円滑な財産管理の支援を受けることができます。なお、家族信託の詳細についてはこちらをご覧ください。

任意後見制度では財産管理のみならず、本人の日常生活で必要となる各種手続きや、介護サービスの利用、入院などの手続きの支援を受けられます。これらの支援を身上監護といい、具体的には以下の支援があります。
家族信託では、身上監護による支援を受けることができません。判断能力が低下すれば財産管理のみならず、身上監護も必要となることが多いです。任意後見制度を併用することで備えましょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

任意後見制度に関し、不明点があるときは各種の窓口で相談できます。以下のリンク先に窓口一覧が掲載されていますので、任意後見制度を利用される際はご活用ください。
本人に「判断能力がある」と判断された場合に限り利用できます。
認知症の症状が進み自身の行為の意味が理解できない状態であれば、利用は難しいです。他方で、症状が出始めたくらいであれば利用できることが多いです。
判断能力があるかどうかは程度問題ですので、公証人が以下の事情などを総合的に考慮して判断します。
任意後見人は複数人いても大丈夫です。任意後見人が複数人いる場合、代理権の種類は以下の3つに分けられます。
| 代理権の種類 | |
|---|---|
| 単独代理(全行為型) | 各後見人がすべての権限を行使可能 |
| 単独代理(分担型) | 種類に応じてそれぞれの後見人が権限を持つ |
| 共同代理 | 権限行使には全員の賛成が必要 |
単独代理には、円滑なサポートの実施が期待できるというメリットがある一方、他の後見人による牽制が図れないというデメリットがあります。
共同代理には、全員一致による慎重な行動が期待できるというメリットがある一方で、意見対立により円滑なサポートが受けられない可能性がある点がデメリットです。
家族や親族に適任者がいない場合は、専門家を任意後見人に選ぶのが一般的です。
任意後見人として選ばれるケースが多い専門家は次の通りです。
どの専門家がベストかは、契約内容や個々の状況・希望により異なります。
弁護士は扱える業務の幅が広く、訴訟にも対応できます。しかし不動産を扱う案件であれば、不動産登記の専門家である司法書士がより適しているかもしれません。
また、弁護士や司法書士以外に、行政書士という選択肢もあります。行政書士の中にも後見業務に注力している方は多いからです。さらに、介護に詳しい方を任意後見人にしたい場合は、社会福祉士を任意後見人に選ぶのも良いでしょう。
なお専門家以外の選択肢として、NPO法人や公益団体、市民後見人制度のもと活動する市民後見人等にも任意後見人を依頼することができます。
任意後見人が仕事を始めるタイミングは、本人の判断能力の低下後です。
任意後見契約を交わした直後から任意後見人の仕事がスタートするわけではありません。本人が元気なうちは、本人自らが、自己の財産を管理すれば足りるからです。
認知症が進行し本人の判断能力が低下して初めて、任意後見人の後見業務は開始されます。さらに、任意後見業務の開始にあたっては、任意後見監督人の選任も必要です。
本人の判断能力が低下し任意後見監督人が選任されるまで、任意後見人の仕事は始まらない点を押さえておきましょう。
任意後見契約が終了するタイミングは、次の通りです。
任意後見人は解任される可能性があります。ただし解任請求できる主体も限定されており、解任請求できる者は、任意後見監督人・本人・本人の親族・検察官です。
任意後見人が解任される事由は、次の通りです。
任意後見人に依頼できる内容の範囲は、財産管理や法律行為の代理、身上保護に限られています。
具体的には以下のような内容が挙げられるでしょう。
後見人がつくことは戸籍には載りません。
しかし、任意後見契約公正証書を作成する際、公証人が法務局に嘱託することで登記がなされます。
登記がなされることで、自分が後見人であることの証明になるでしょう。
契約の取りやめは可能です。
任意後見監督人選任前は公証人の認証のある書面で行い、選任後は家庭裁判所の許可が必要です。
契約の変更は代理権に関わる内容であれば変更できません。
その他の場合は、公証人の認証のある書面で行います。
なお、代理権に関わる内容を変更したい場合は新たに契約を結び直すことで変更が可能です。
判断能力が低下する前から任意後見契約の効力を発生させることはできません。
そのため、判断能力が低下する前から財産管理をお願いする場合は、通常の委任契約を締結することになるでしょう。
委任契約と任意後見契約の2つを結んでおくことで、判断能力が低下する前も低下した後も財産管理をお願いできます。
任意後見人契約は、判断能力の低下に備えるための契約であり、体の不自由まではカバーしていません。
体の不自由にも備えたい場合は、任意後見契約とあわせて、(財産管理等を目的とする)委任契約も締結しましょう。
任意後見契約とは別個の委任契約を交わすことで、判断能力の低下前であっても財産管理を将来の任意後見人に任せることができます。
判断能力低下後は、任意後見契約に切り替わり、任意後見業務がスタートする流れになります。
判断能力低下のみならず身体的な不自由にも対応したい方は、任意後見契約とは別に委任契約を締結することで、目的を実現できるでしょう。
任意後見契約の内容は、法律の趣旨に反しない限り、自由に決められるのが原則です。
当事者で自由に契約内容を決定できるのが、法律の基本的な考え方だからです。
任意後見人にどのような代理権を与えるか、どのような仕事を任せるか等について、契約当事者で自由に決められます。
ただし、任意後見契約で任意後見人に与えられる財産管理権限は、消極的な内容に限られる点に注意です。積極的な資産の増加を目的とした財産の処分は、任意後見契約では困難です。
より自由な財産管理を希望する方は、家族信託もあわせて検討しましょう。

本記事では、任意後見制度について説明しました。任意後見制度を利用する際は、その特徴をよく理解し、足りない部分は家族信託と併用することで補うことがおすすめです。
家族信託には専門知識が必要になるため、1人で手続きを行うのは困難です。
大事な手続きですので、ファミトラなどの家族信託の専門業者を利用するのがよいでしょう。将来の財産管理を安心して任せるためにも、早めに準備を始めてはいかがでしょうか。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!



家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!



PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。