
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
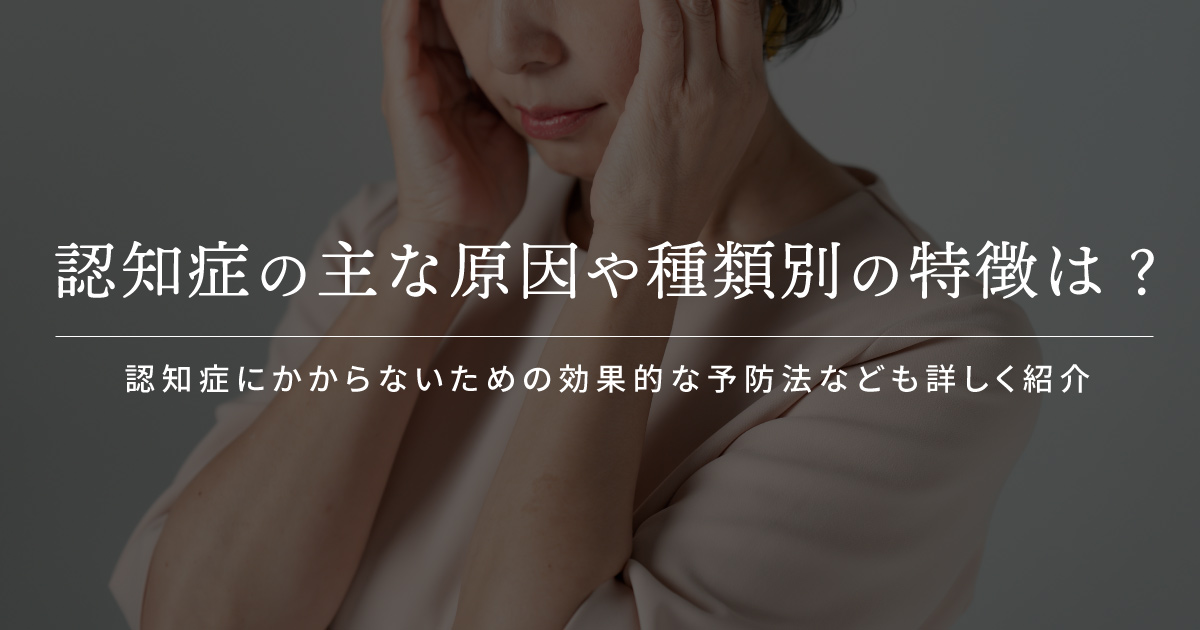
「認知症にかかってしまう原因を知りたい」
「認知症にならないように、早めの予防をしたい」
このような思いを抱えている方は多くいるのではないでしょうか。
高齢者の約5人に1人が認知症にかかることを考えると、「親や自分が認知症にかかったらどうしよう」と不安になるのは当然といえます。
そこで、本記事では認知症の原因について解説します。
認知症の種類や予防のためにできる対策などを知って、認知症に備えましょう。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

認知症とは、脳が病気や障害を抱えてしまい、認知機能が低下し、日常生活が正常に送れなくなってしまう症状のことです。
認知症の症状には大きく分けて、中核症状と周辺症状(行動・心理症状)の2つがあります。
中核症状は認知機能が低下することにより現れる症状で、物忘れを含む記憶障害がよく知られています。
一方、周辺症状(行動・心理症状)は、行動や心理状態に影響が出てしまう症状で、徘徊や幻覚・妄想などが主な症状に挙げられます。
中核症状や周辺症状(行動・心理症状)は、具体的に以下のような初期症状となって現れます。
これらの症状が見られたら、認知症の初期症状だと疑って、医療機関を受診すると良いでしょう。
認知症の初期症状について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
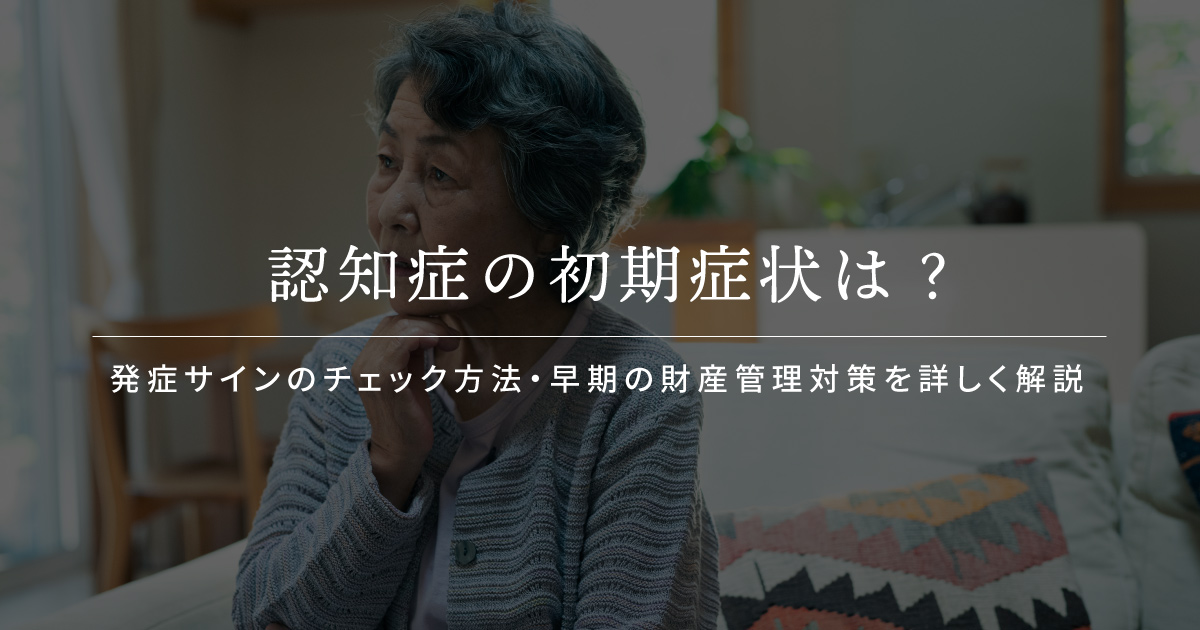

認知症の主要な種類として、以下の4つが挙げられます。
それぞれの種類について、その特徴を詳しく見ていきましょう。
認知症の種類について、より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
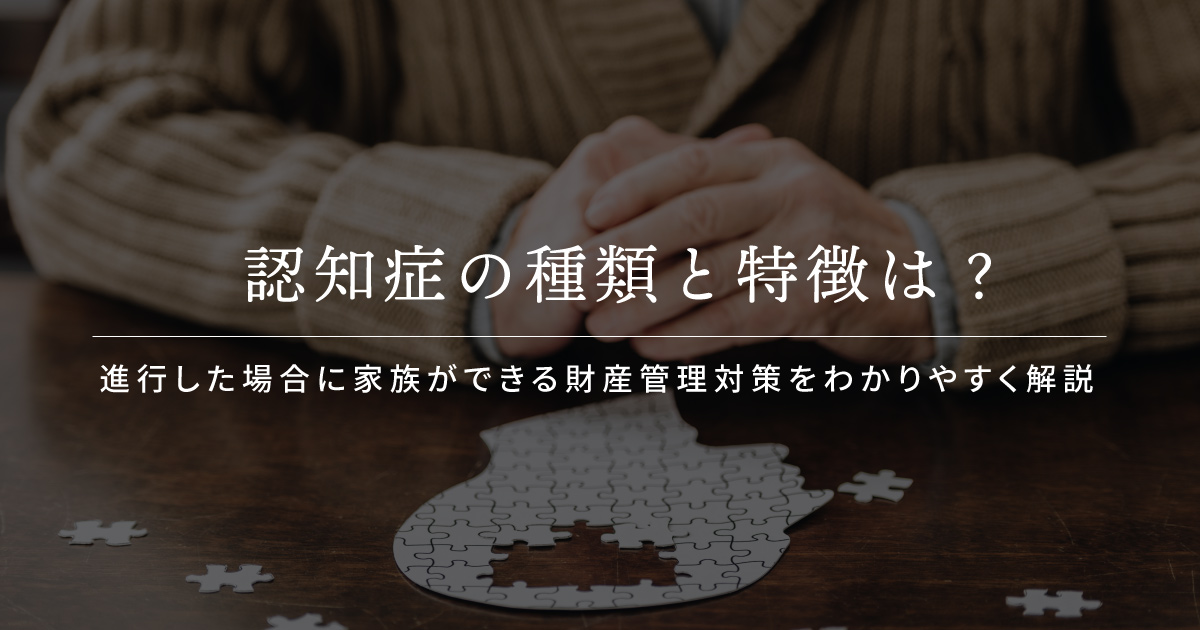
1つ目はアルツハイマー型認知症です。
脳の神経細胞に異質なタンパク質「アミロイドβ」が溜まることで、神経細胞が破壊され、脳が萎縮してしまうことで発症します。
認知症全体の70%を占めており、多くの認知症患者がアルツハイマー型認知症にかかっていることがわかります。
「アミロイドβ」が溜まる原因は、加齢によるものが大きいとされています。しかし、詳しいメカニズムまではわかっていません。
なお、生活習慣の改善がアルツハイマー型認知症の予防に効果があることがわかっています。栄養バランスの取れた食事や適度な運動など、正しい生活習慣を身に付けると良いでしょう。
2つ目は、脳血管性型認知症です。
脳血管性型認知症は、認知症全体の約20%にあたるとされており、アルツハイマー型認知症に次いで、2番目に多い種類の認知症です。
脳出血や脳梗塞などにより脳血管に障害が起きてしまうことで、脳の血液の流れが止まり、脳が壊死してしまうことで発症します。
症状は、脳のどの部分に障害が起こるかによって異なります。
例えば、手足のしびれや麻痺、歩行障害、言葉が出にくくなる、意欲低下、不眠などが挙げられます。
血管障害により発作が起きるたびに症状が重くなるため、生活習慣を改善したりリハビリテーションを活用したりして、発作を起きにくくすることが大切です。
なお、生活習慣に気を付けて生活することが発症や発作の予防に繋がるため、規則正しい生活を送るようにしましょう。
3つ目は、レビー小体型認知症です。
特殊なタンパク質「レビー小体」が脳に溜まってしまい、神経細胞が破壊されることで発症します。
「レビー小体型認知症」の症状の最大の特徴は「幻視」です。
「幻視」の症状を抱えると、物理的に存在していない人影や動物などが見えてしまいます。
意識がはっきりするときとしないときを繰り返しながら、徐々に認知機能が低下していくことも特徴的です。
他にも、睡眠障害や手足の震え、歩行障害、さらには身体のこわばり、うつ症状なども症状として現れます。
「レビー小体」が脳に溜まってしまう原因については解明できていないため、予防方法や治療方法が確立されていません。
そのため、症状の進行を和らげるような治療方法が用いられることがほとんどです。
4つ目は、前頭側頭型認知症です。
脳の前頭葉や側頭葉が萎縮してしまうことで発症します。
前頭側頭型認知症には様々な種類があります。脳の神経細胞に球状物の「Pick球」が溜まり発症する種類や、タンパク質「TDP-43」が溜まり発症する種類などです。
前頭葉の機能が低下すると、行動や感情のコントロールが効かなくなり、性格の変化や反社会的な行動の増加などの症状が現れます。
側頭葉の機能が低下すると、言語や記憶の機能に障害が発生し、物の名前がわからなくなったり言葉が出なくなったりします。
他の認知症に比べ、母数が少ないことから原因は特定できておらず、有効な薬物治療ができないのが現状です。

認知症を引き起こす主な原因として、以下の6つが挙げられます。
その他にも考えられる原因があるため、認知症を引き起こす原因について詳しく見ていきます。
1つ目の主な原因は、加齢による脳内の異常タンパク質の増加です。
年齢を重ねると、異常なタンパク質である「アミロイドβ」が脳内に溜まりやすくなります。
「アミロイドβ」が溜まると、脳細胞が破壊されてしまい、それが原因で認知症になってしまうのです。
「アミロイドβ」が溜まる原因は加齢によるものであるため、予防するのは難しいでしょう。
2つ目の主な原因は、生活習慣病による脳血管のダメージです。
高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、一見すると認知症とは関係ないように見えるかもしれません。
しかし、生活習慣病にかかると、動脈硬化などにより脳出血や脳梗塞などの病気を引き起こすことに繋がります。
後ほど詳しく紹介しますが、脳出血や脳梗塞などの病気になると、認知症の1つである「脳血管性型認知症」にかかりやすくなるのです。
生活習慣病になった上に認知症にもかかってしまうのは、生活に大きな影響を与えてしまうため、生活習慣には気を付けて生活することが大切でしょう。
3つ目の主な原因は、けがや疾患による脳神経細胞の損傷です。
脳出血や脳梗塞、くも膜下出血など脳に疾患を抱える病気などにかかると、脳血管にダメージが加えられてしまいます。
すると、先ほど紹介した「脳血管性型認知症」にかかるリスクが高まってしまうのです。
他にも、脳に直接障害を加えるような病気でなくても、認知症にかかるケースもあります。
例えば、入院が長期間にわたることで脳に刺激が加えられなくなり、認知機能が低下することにより、認知症にかかるケースが挙げられます。
なるべくけがをせず、また疾患にかからないように、周囲もサポートをする必要があるでしょう。
4つ目の主な原因は、ストレスによる脳神経細胞の萎縮です。
ストレスは認知症のみならず、様々な病気の原因となることがありますが、認知症の原因にもなり得ます。
しかし、ストレスが直接的に認知症を引き起こすわけではありません。
例えば、ストレスを受けるとうつ傾向になることが多くあります。
そのような場合に外出を控えるようになり、他者との交流が減ることで周りから受ける刺激が減少し、認知機能が低下、そして認知症へと繋がるケースが考えられます。
ストレスは、認知症を含む様々な疾患や病気の原因になりうるため、可能な限りストレスのかからない生活を送るように心がけましょう。
認知症のほとんどは遺伝とは無関係に発症しますが、中には、遺伝の影響により引き起こされるものがあります。
例外的に、アルツハイマー型認知症の中で、遺伝的要素が関係するものが家族性アルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症は通常70歳以上で発症することが多いのですが、家族性アルツハイマー型認知症は40~50歳代で発症することもあります。
家族性アルツハイマー型認知症は原因遺伝子が判明しているものもあります。
若年性アルツハイマー型認知症の約1割が、家族性アルツハイマー型認知症だといわれています。
認知症の中には、感染症や炎症の影響により発症するものがあります。
発症の原因となる感染症には、梅毒、ヘルペス、ウイルス性脳炎、クロイツフェルトヤコブ病やHIVなどがあり、これらの感染症で脳の組織が破壊されることが認知症発症の原因となり得るのです。
感染症の一部は、早期に治療を行えば治る可能性もあるため、症状が現れたら、なるべく早く医師の診察を受けることが大切です。
また、脳への血流が低下すると、中枢神経系が過剰に炎症して、認知障害を起こす可能性もあります。
他にも、認知症を引き起こす原因は様々なものがあります。
例えば、アルコールが原因となる「アルコール性認知症」などがあります。
お酒などを飲みすぎると、アルコールの吸収がうまくいかなくなり、脳が委縮したり認知機能が低下したりすることで、認知症になるケースがあるのです。
その他にも、脳の前頭葉や側頭葉などが委縮することによって引き起こされる認知症や、甲状腺ホルモンの低下により脳の代謝が低下してしまい引き起こされる認知症などもあります。
このように、認知症は様々な原因により発症してしまう病気です。全ての原因を対策することは難しくても、主な原因を理解し、予防に努めることが重要です。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

認知症の様々な原因を解説してきましたが、実は、いまだに発症の原因を特定できない認知症があります。
それは、アルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症は、認知症の過半数を占めていますが、いまだにその明確な原因は分かっていません。
アルツハイマー型認知症は、脳内でアミロイドβが蓄積することにより、神経細胞が破壊され、脳が委縮して認知症を発症します。
アルツハイマー型認知症患者の脳にはアミロイドβが蓄積することで老人斑ができるのが特徴です。
アミロイドβは、アルツハイマー型認知症発症の10〜25年ほど前から蓄積されるといわれ、原因は加齢、遺伝、生活習慣等と関係があるといわれていますが、特定はされていません。

認知症はゆっくりと進行するのが特徴ですが、一気に進むこともあります。
その原因は主に以下の4つです。
それぞれ以下で詳しく解説します。
脳への刺激が不足すると、脳が活性化しなくなり脳の老化に繋がります。
認知症を発症すると、自分で行動に制限をかけることがあります。
例えば、外出をしなくなる、他人とのコミュニケーションを取りたがらないなど外部からの刺激を受けなくなり、脳の機能を使わなくなります。
また家族から行動を制限されることがあります。
家族内の役割を取り上げたり、過度に外出を制限したりすると、やはり脳への刺激が不足し、認知症が進行する原因となります。
家族は、脳への刺激が不足しないよう、家庭内の役割を与えたり、外出を勧めたりすることで、認知症の進行を防ぐことができます。
ストレスが日常生活を送ることも認知症が進行する原因の1つです。
記憶をつかさどっているのは海馬ですが、海馬はストレスを受けやすい特徴があります。
ストレスが長く続くとストレスホルモンが分泌され、脳の血流が悪化します。
脳に血液が十分に流れないと脳に必要な酸素や栄養素が届かずに、海馬が委縮し認知症が進行するといわれています。
また、ストレスが溜まると、行動や考える意欲が減退し、家に閉じこもったり、ボーっと過ごしたりして、脳への刺激が不足します。
その結果、認知症が進行してしまうのです。
認知症を発症すると、排せつ障害や記憶力の低下による失敗などが起こります。
そのときに、家族から過度に失敗を責められると、認知症が進行する原因となります。
失敗を責められることで、自分で行動に制限をかけてしまい、外出や他人と接することを拒むようになります。
外部からの刺激が少なくなると、脳を使わなくなり認知症が進みます。
また、失敗を責められること自体がストレスになり、海馬が委縮し認知症が進行する原因となります。
認知症であることを十分理解し、失敗を責めすぎないようにしましょう。
認知症が進行する外部的要因に、急激に環境が変わることがあります。
誰しも、新しい環境に慣れるまでは多少なりともストレスを感じるものですが、時間が経つにつれ新たな環境に慣れていきます。
しかし、認知症の方は新しい環境に慣れることが苦手です。
そのため新しい環境の変化を理解することは困難です。
具体的には、家族の仕事の都合などで転居した、あるいは家の建て替えやリフォームなどが挙げられます。
また、住居は変わらなくても配偶者などの家族が亡くなった場合なども、認知症が進行する原因の1つです。
家族は認知症の方に対して、急激な環境の変化を理解できないことを受け入れた上で、認知症の方の負担を軽減するように努めましょう。

認知症予防のためにできる対策として、主に以下の4つが挙げられます。
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
1つ目は、食べ物や食習慣に気を使うことです。
バランスの良い食事を取ることで、身体を健康に保つことができます。
例えば、老化防止の役割を果たす緑黄色野菜やビタミンC、脳梗塞を予防する効果があるとされている魚などを取ることが大切です。
自分でバランスの取れた食事を作れないときは、配食サービスなどを利用することも検討してみると良いでしょう。
2つ目は、適度に身体を動かすことです。
無理のない範囲で運動を繰り返すことで、脳の認知機能が低下することを防げます。
可能であれば、少しの時間でもよいので毎日運動をすることで、運動を習慣化しましょう。
外で行う運動だけでなく、家の中でできる運動も取り入れられると、より習慣化しやすくなるでしょう。
3つ目は、社会活動に積極的に参加することです。
他人とのコミュニケーションの機会を作ることで、脳に刺激を与えられるため、認知機能の低下を防げます。
社会活動に参加することで、必然的に他人とコミュニケーションを取るようになるため、地域の行事やボランティア活動があれば積極的に参加するようにしましょう。
また、社会活動に参加すれば、身体を動かすことにも繋がるため、より認知症の予防になることが期待できます。
4つ目は、ストレスを発散することです。
ストレスは多くの病気の原因になりますが、認知症の原因でもあります。
そのため、ストレスを溜めずに発散することが、認知症を含めて様々な病気の予防に繋がります。
ストレスの発散方法は人によって異なるため、趣味や散歩、人との会話など、自分に合ったストレス発散方法を見つけてみてください。
認知症の進行を防ぐために、認知機能の向上ができるトレーニングをしましょう。
トレーニングには、運動と知的活動があります。
前者は、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動と、筋力トレーニングなどの無酸素運動がありますが、どちらも認知症の進行を妨げる機能があります。
後者は、認知機能を使う活動で、トランプや塗り絵、間違い探しなどは考えたり指を使ったりすることから認知症の進行を妨げる働きがあるといわれています。
近年の研究で、聴力低下と認知症との関係がわかってきました。
聴力が低下すると、認知症のリスクを高めます。
脳は音の情報を処理するため様々な部位を使います。
聴力が低下すると音が入ってこなくなり、脳を使わなくなるので脳の機能が低下します。
また、聴力が低下すると他者とのコミュニケーションを取らなくなり、脳を使用する機会も少なくなります。
その結果、認知症発症のリスクが高まるのです。
話がかみ合っているか、聞き返すことが増えていないかなど、家族は普段から気をつけましょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

最後に、認知症の原因に関するよくある質問とその回答を4つ紹介します。
認知症の原因について理解を深めるために、参考にしてみてください。
認知症になりやすい人の特徴は、主に以下の3つです。
生活習慣の乱れは認知症の原因の1つであるため、生活習慣が乱れている人は認知症になりやすいといえます。
また、小さなことを気にしすぎる人などストレスを抱えやすい傾向にある人も、認知症になりやすいといえるでしょう。
ストレスも認知症の原因の1つであるため、なるべくストレスを抱えない生活を送ることが大切です。
さらに、怒りやすい人は孤立しやすく、他者との交流が希薄になりがちです。
他者との交流が減り、脳に刺激が与えられなくなると、認知機能が低下しやすいため、怒りやすい人も認知症になりやすいといえます。
脳の神経細胞が壊れて発症してしまう認知症を根本から治せる治療方法は、現時点では確立されていません。
そのため、脳の神経細胞が壊れてしまった場合、認知症の治療方法は症状の進行を遅らせることが主な目的となります。
一方、睡眠障害や徘徊などの行動症状や不安、妄想などの心理症状は、治療できるものもあります。
認知症が治るかどうかは、認知症の種類や症状によるといえるでしょう。
認知症の発症にかかわる遺伝子があることは確認されていますが、認知症が遺伝により発症する可能性は高くありません。
「遺伝の影響が強いのではないか」といわれることのある若年性アルツハイマー病でも、遺伝の影響があると考えられるのは約1割にとどまっています。
そもそも認知症の原因は複雑であり、解明できていない部分も多いです。遺伝による影響を心配するのではなく、生活習慣の改善や社会活動への参加など、自分ができることから認知症対策を始めましょう。
認知症の原因として最も多い疾患は、アルツハイマー型認知症です。
認知症全体の67.6%を占めています。
その後に、血管性認知症が19.5%、レビー小体型認知症が4.3%と続きます。
上位3つで全体の約9割を占めています。
アルツハイマー型認知症が突出して多く、また、アルツハイマー型認知症は他の症状と合併していることも少なくありません。

認知症は様々な原因が重なり合って発症することも多いため、全ての原因を特定するのは難しいです。
しかし、生活習慣の乱れや他者とのコミュニケーション不足など、自分で改善できるような原因も含まれています。
そのため、認知症にならないために、自分でできることを1つずつ行うことが大切です。
とはいえ、認知症の予防を100%行うのは簡単ではありません。
もし認知症にかかってしまうと、銀行口座が凍結してしまい、預金の引き出しができなくなってしまいます。
預金の引き出しができないと日常生活に支障を来してしまうでしょう。
そこで、おすすめなのが事前に「家族信託」の準備をしておくことです。
認知症にかかってしまっても、銀行口座が凍結することなく、信頼する家族に自身の口座の管理を任せられます。
ファミトラでは相談者とその家族の想いや状況・要望を整理し、弁護士や司法書士等の専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう、調整を行う役割を担う専門家(家族信託コーディネーター)が、無料相談を受け付けています。


活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!



家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!



PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。