
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

自身や家族のために成年後見制度を利用したいと考えているものの、成年後見人に親族がなることはできるのかと疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、親族が成年後見人になることは可能です。
しかし、利用を検討する上で知っておくべきデメリットや注意点があるということを理解しておくことが大切です。
そこでこの記事では、親族が成年後見人になった場合のメリットやデメリット、注意点について解説します。親族が成年後見人になるための条件や手続きについてもご紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!


成年後見制度とは、高齢者や障がい者などの、精神上の障害により物事を理解することが難しい人の権利や財産を保護する制度です。
成年後見制度では、後見する人を「後見人」、後見を受ける人を「被後見人」または「本人」といい、法定後見制度と任意後見制度の 2 種類に分けられます。
意思能力が不十分な人に対して適用される保護制度。
家庭裁判所への申立てによって選ばれた成年後見人が、本人の代わりに財産や権利を守る役目を担う。
本人の意思能力が衰える前に、予め自分が成年後見人になって欲しい人との間で後見契約を結びます。
その後、意思能力が衰えた後に契約の効力を発動させることで、任意後見を開始する制度。
このうち「法定後見制度」では家庭裁判所が法定後見人を選任するため、必ずしも親族が成年後見人になれるわけではありません。
親族が成年後見人として選任されなかった場合は第三者が選任され、多くの場合は弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます。
最高裁判所事務総局家庭局が作成した「令和4年成年後見関係事件の概況」によると、2022年の全国家庭裁判所の成年後見関係事件のうち、家族・親族が成年後見人等に選任されたケースは全体の約19.1%です。
一方で、親族以外が成年後見人等に選任されたケースは全体の約80.9%です。
現状では、家族・親族が成年後見人等になるケースが少ないことがわかります。
しかし近年、厚生労働省による成年後見制度利用促進専門家会議において「身近な親族を選任することが望ましい」という判決が出されました。
今後は、親族が成年後見人になるケースも増えるのではないかと考えられています。
既出の「令和4年成年後見関係事件の概況」では、家族・親族が成年後見人等の候補者になった事件の割合は、全体の約23.1%にとどまっています。
成年後見人等の候補者になろうと希望しているのは、家族・親族のわずか4分の1以下であることがわかります。
家族・親族が成年後見人等に選任されたケースが全体の約19.1%という数字と合わせて見ると、家族・親族が希望すれば成年後見人等に選ばれる可能性は十分にあるといえるでしょう。


ここでは「任意後見制度」と「法定後見制度」のそれぞれにおいて、親族が成年後見人となるための手続きを見ていきましょう。
任意後見制度における手続きの流れは次のとおりです。
任意後見契約は法律により公正証書で作成することが定められています。
契約内容がまとまったら原案を公証役場へ持ち込んだ後、公正証書で作成してもらう必要があります。
最寄りの公証人役場は以下より調べられるので、前もって確認しておきましょう。
法定後見制度には、本人の意思能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の 3 種類があり、それぞれ次のように区別されています。
法定後見制度を利用する場合は、以下の手続きを経なければなりません。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などとなっています。
場合によっては、市区町村長が申し立てをすることもあります。

成年後見制度では、成年後見人を家族・親族のうち誰にするかを十分に話し合いしておくことが、後々のトラブル防止策の1つです。
原則として成年後見人の職務は、途中で投げ出すことができないためです。
以下では家族・親族を成年後見人にする方法を見ていきます。
任意後見制度を利用して、本人に判断能力があるうちに、任意後見契約で家族・親族を任意後見受任者に指定します。
任意後見契約では、本人が自分の財産管理などを任せたいと信頼している家族・親族などを任意後見受任者とし、自身の介護の希望などについても意思を反映することが可能です。
任意後見契約では、契約内容の決定権はあくまで本人にあります。
本人の判断能力が低下すれば、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任され初めて任意後見契約の効力が発生します。
任意後見受任者である任意後見人が本人に代わって、財産管理や契約内容に沿って本人をサポートすることが可能です。
なお、任意後見契約に関する法律第3条により、任意後見契約は公正証書で行うことが規定されています。
法定後見制度の場合には、必ずしも親族が成年後見人に選任されるとは限りません。家庭裁判所から成年後見人に選任されることが条件となります。
家庭裁判所から親族が成年後見人に選ばれるためのポイントや準備として、以下の4つが挙げられます。
推定相続人とは、今の状況で相続が発生した際に、遺産を相続すると推定される人のことです。
配偶者や子ども、親、兄弟などが推定相続人に該当する場合が多いものの、本人の家族関係によっても左右されます。
ここでは、本人(成年被後見人)に配偶者と子どもがいると仮定しましょう。
このケースにおいて、成年被後見人が「自分の妹を成年後見人候補者に指定したい」と考えている場合、配偶者と子どもに対してあらかじめ同意をとっておくことが極めて重要です。
また、話し合った上で同意に至った場合には、同意したことが第三者にもわかるように「同意書」といった書面で残しておき、申し立てと共に家庭裁判所に提出しましょう。
同意書は手続き上絶対に必要なものというわけではありませんが、同意書があることで家庭裁判所の審理がスムーズに進みやすくなります。
成年後見人の選任申立書を家庭裁判所に提出することが、法定後見制度で家族・親族が成年後見人になるためのスタートです。
家族・親族が成年後見人になりたければ、申立書の「後見人等候補者」欄に家族・親族の氏名を記載して提出しなければなりません。
申立人が自薦の形で自身を後見人等候補者としても、問題はありません。
家族・親族を後見人等候補者と記載して選任申し立てをしても、希望通りにいかないこともあります。
家庭裁判所の判断で、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることがあるためです。
成年後見人の候補者や申立人は家庭裁判所で面接を受ける必要があります。
候補者に対して、欠格事由の有無や成年後見人としての適格性が判断されます。
その他、被後見人の財産管理や身上保護を行う後見事務に関して、どのような方針を抱いているのかについて聞かれることになるでしょう。
難しい質問がされるわけではないものの、きちんと受け答えができないと成年後見人として適性がないと判断されてしまう可能性があります。前もってしっかり備えておくことが大切です。
成年後見支援信託は下記のような信託の仕組みです。
信託財産は、元本が保証されて預金保険制度の保護対象であることが特徴です。
財産が多い方の場合には成年後見支援信託の利用の検討も視野に入ります。
注意点としては、成年後見と未成年後見において使用可能ですが、保佐・補助や任意後見制度では利用できません。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

本人が親族を候補者に指定した場合であっても、その意向が認められないこともあります。
ここでは、親族が成年後見人になれないケースについて見ていきましょう。
成年後見人は意思能力が低下した人に代わって、その人の財産を管理する必要があります。
そのため、成年後見制度において後見事務を適切に行えるかどうかといった観点は非常に重要であり、民法 847 条において成年後見人の欠格事由が定められています。
欠格事由に該当する場合は成年後見人となることができません。
具体的には以下のとおりです。
なお、上記の欠格事由は任意後見制度、法定後見制度のいずれにも適用されるので注意しましょう。
被後見人となる人に多額の財産がある場合や賃料収入などの事業系収入がある場合、家庭裁判所は成年後見人に親族を任命することを避ける傾向にあります。
本人に多額の財産がある場合、財産管理が複雑になるだけでなく一定の専門知識が必要になることがほとんどです。
成年後見人は年に1度、家庭裁判所に対して本人の収支状況を報告する義務を負っています。
管理財産が多いと、収支状況の報告時に必要となる書類について、作成難易度が上がることは言うまでもありません。
そのため、こうした場合には弁護士や司法書士、税理士などの専門職が選任されるケースが多く見受けられます。
親族の中に候補者が成年後見人になることに反対している人がいる場合、親族以外の専門職が成年後見人に選任される可能性があります。
そのため、あらかじめ親族の同意を得ておくことが大切です。
親族が成年後見人になれない理由の1つに候補者が後見事務に自信が持てない場合もあります。
例えば、以下の方のようなケースです。
領収書などを管理し収支報告ができるように準備しておくことが苦手な方
報告義務は成年後見人に家族・親族がなる場合と専門家がなる場合も変わりないため文書の作成が苦手な方
日々の詳細な記録を取ることが苦手な方
後見事務は財務や税務経験がないと難しい面もあり、そもそも候補者に時間的な余裕がない方にとっては困難な事務でしょう。
被後見人の年間収支の変動幅が大きい場合には、専門知識のない家族や親族では困難と家庭裁判所から判断されることもあります。
一例としては、流動資産の額や種類が多い場合です。
成年後見人の職務の中でも、本人の収支を正確に把握することで財産管理と財産保護を行うことは重要な仕事の1つです。
年間収支の変動が大きいと、専門職の成年後見人が選任されることになります。
財務や税務などの専門的な知識が必要なためです。
親族である成年後見人と本人との間に当初から相続に関して意見の食い違いがある場合などは、家族や親族は成年後見人になるのは困難です。
遺産分割を事前に相談する上でも、お互いの利益相反が見込まれるためです。
成年後見人にとって被後見人の財産保護は最優先すべき職務であるため、成年後見人と本人の利益相反があれば親族であっても成年後見人にはふさわしくありません。

親族が成年後見人となるにあたっては、メリットとデメリットがそれぞれ存在します。
メリットとデメリットについて解説します。
親族以外の専門職を成年後見人とした場合、本人の財産から毎月2~4万円程度の報酬を支払う必要があります。
親族が成年後見人となった場合も報酬を受け取れますが、無報酬で引き受けるケースがほとんどです。
そのため、本人の財産が少なく報酬の支払いが負担になる場合でも、成年後見制度を利用できることがメリットといえるでしょう。
被後見人の中には、第三者に財産の管理を任せることに対して抵抗を感じる人も少なくありません。
親族であれば自身の性格や状況をよく知っているため、安心して財産を任せられるでしょう。
もちろん、全てのケースにおいて親族が成年後見人に適しているとはいえませんが、本人との信頼関係が強い場合には親族を成年後見人とした方が安心感があります。
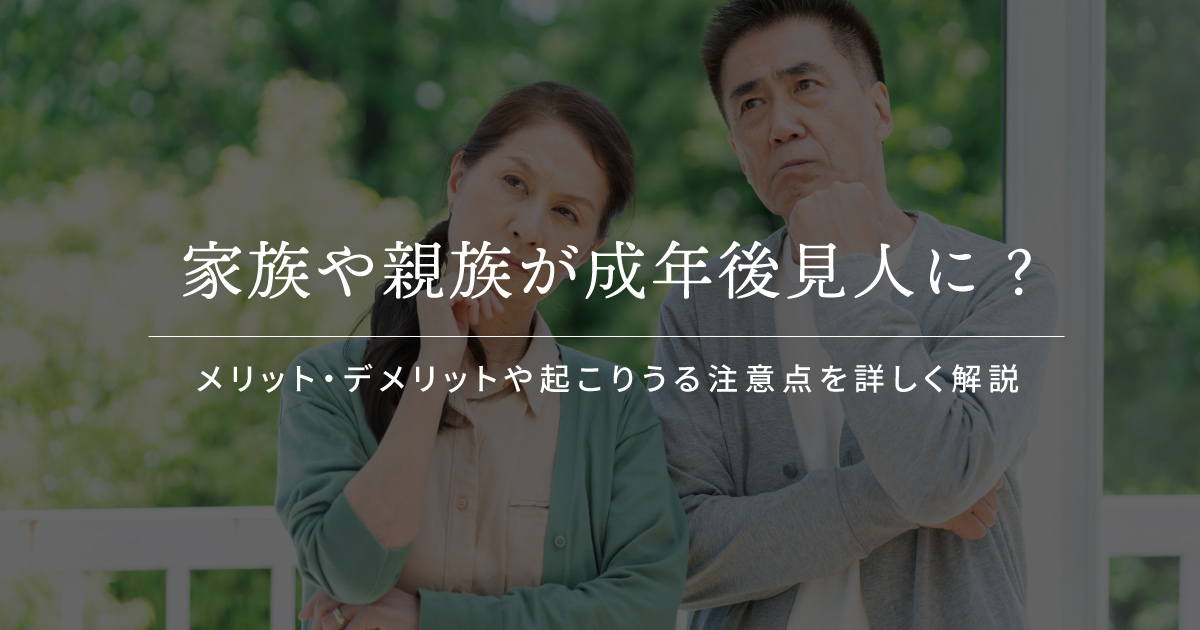
成年後見人は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を適切に管理し毎月の収支や財産管理の状況を年に1回、家庭裁判所に対して報告する義務があります。
この義務は親族が成年後見人になった場合でも必須であり、上記の収支状況とあわせて本人の状態についても伝えなければなりません。
その際、報告書や財産目録、収支状況報告書なども提出する必要があります。
そのため、日ごろからきちんと金銭の出入りを把握しておかなければならず、成年後見人にかかる負担は大きいといえるでしょう。
なお、財産管理が複雑な場合は成年後見人の善管注意義務を適切に果たす必要があるため、前もって専門職に相談することをおすすめします。
親族同士の関係性があまり良くない場合、親族間のトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。
よくあるケースとして、成年後見人が本人の財産を横領しているのではないかと虚偽の疑いをかけられ、嫌がらせが続いているといったことが挙げられます。
成年後見人が第三者の弁護士や司法書士であれば、そうしたトラブルに発展するようなことは滅多にありません。
しかし、親族間においては些細なことをきっかけにトラブルが起きてしまうことも少なくないでしょう。
そのため、親族間の関係性に不安が残る場合には、弁護士をはじめとする第三者の専門職を成年後見人に選任することをおすすめします。
親族を成年後見人に選任した場合、主に4つの点に注意しなければなりません。
いずれもあらかじめ押さえておきたい注意点となりますので、しっかりと理解しておくようにしましょう。
成年後見人を辞任することは可能ですが、基本的には本人が亡くなるまで成年後見人を続ける覚悟が求められます。
「忙しくなったから」「大変だから」といった自分の都合で成年後見人を辞任することはできず、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
また、その場合には新たな成年後見人が選任される必要があります。
後任の成年後見人が選任されない限りは、家庭裁判所が成年後見人の辞任を許可することはないので注意が必要です。
なお、家庭裁判所に選任された成年後見人を解任したいと思った場合でも、解任事由として「不正な行為」や「著しい不行跡」などが家庭裁判所に認められない限り、解任は難しくなります。
成年後見人の解任を求める場合には、不正の証拠を集める必要がある他、弁護士や司法書士といった専門家職を頼らなければならないようなケースもあるということを覚えておきましょう。
成年後見人はあくまでも「人の財産を預かる立場」にいるだけであるため、本人の所有する財産を勝手に使うことは許されません。
同居する家族を後見する場合でも同様、本人の財産と家計の管理は別々にする必要があります。
また、本人のための支出であっても家庭裁判所の許可が必要となるケースもあり、場合によっては家庭裁判所から指摘・注意されることもあるでしょう。
成年後見監督人とは、成年後見人の後見事務を監督する人のことです。
弁護士や司法書士などが成年後見監督人として家庭裁判所によって選ばれることがあります。
家族が成年後見人のときには、成年後見監督人が選任されやすいといわれています。
一般的な家族では、専門的な知識を有していないことが多いためです。
特に管理する財産が高額で複雑なために専門家の知識を必要とする場合には、家庭裁判所は被後見人の財産を保護するために成年後見監督人を選ぶ傾向があります。
成年後見監督人を選任することにより、本人の財産管理・保護の安全性や正当性を高めることに繋がります。
ただし、専門家が成年後見監督人が就任するとランニングコストの発生が大きい点はデメリットです。
後見事務の中でも成年後見人が居住用不動産の売却や賃貸借契約などを行う際には、家庭裁判所の許可が必要です。
不動産の処分によって本人の財産に不利益が生じないようにするためです。
居住用でない不動産の処分はこの限りでないものの、成年後見監督人が選任されていれば同意が必要になります。
成年後見人の職責を考えれば、本人の財産を保護するために自由に扱えないのが原則です。
相続対策や自由度の高い財産の管理・運用・処分を重視するのであれば、成年後見人制度は不向きといえます。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。


成年後見制度は本人の意思能力が不十分な場合に利用できる便利な制度である一方、制約が多い制度であることもまた事実です。
そういった縛りを受けることなく、柔軟な財産管理・運用ができる方法として「家族信託」があります。
家族信託は任意後見制度と同様に、本人の意思能力が低下する前であれば利用することができ、任意後見制度との併用も可能です。
2つを併用することで、家族信託としての利点は残しつつ、家族信託では認められない身上保護が利用できます。
本人の意思能力がまだ十分にあるという場合、家族信託も選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。
本人の状態によってどの制度を利用するのがベストかは異なるものの、それぞれの特徴を押さえた上で後悔のない選択をするようにしましょう。

成年後見人を途中で辞任できるのは、正当な理由がある場合で家庭裁判所の許可が得られたときに限られます。
単に「仕事が多忙である」ことや「子どもの世話で忙しくなった」などの自身の都合では、成年後見人を辞任できません。
成年後見人は被後見人の財産保護や権利などを守るために選任されており、自己都合により辞任すると被後見人の利益を守れないためです。
正当な理由とは、成年後見人自身が病気や高齢のために職務の遂行が困難になったり、遠方に引っ越すことで職責を十分に果たせなくなるような場合です。
正当な理由に該当するかどうかは家庭裁判所が判断し、辞任の許可を行います。
家庭裁判所が最終的に辞任の許可を行うまでは、成年後見人は職務を遂行しなければなりません。
家族が成年後見人になると、報酬の負担を抑えられる場合が多いです。
専門家が成年後見人になれば、管理する財産額にもよりますが月額2万円から6万円程度の報酬がかかります。
家族が成年後見人になると、専門家がなるよりも報酬が低く設定される傾向にあります。
家族が納得していれば、無報酬で職務にあたることもあるでしょう。
成年後見制度の手続きは、原則として家族だけで行うことが可能です。
任意後見制度の手続きは下記の流れで行います。
法定後見制度の手続きは下記の流れで行います。
任意後見制度と法定後見制度のいずれにおいても、家庭裁判所での申し立てなどが必要です。
なるべく時間と手間をかけずにスムーズに行いたい方であれば、専門家に依頼すると良いでしょう。

本記事では、家族・親族が成年後見人になる方法とメリット・デメリットについて解説しました。
家族が成年後見人になる場合の注意点や家族が成年後見人になれないケースについても、具体的に紹介しました。
相続対策や自由度の高い財産の管理・運営・処分を重視される方には、家族信託制度が向いています。
成年後見制度や家族信託に疑問をお持ちの方は、ぜひファミトラまでご相談ください。ファミトラでは、専門家と連携してお客様に寄り添ったサポートを行っています。
メールフォームから24時間無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。


活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!



家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!



PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。