
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中


活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった方に代わり、成年後見人などが財産管理や身上保護を行う制度です。
本記事では、成年後見制度の3つのメリットと9つの注意点や、成年後見人の選び方を解説します。また、成年後見制度と併用可能な家族信託についても紹介します。
本記事を読むと、成年後見制度の仕組みと財産管理の自由度が高い家族信託の概要がわかるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

この項目では、成年後見制度(成年後見人制度)の概要や家族信託との違いについて解説します。
成年後見制度とは、認知症などにより意思能力が低下・喪失してしまった人に代わり、財産管理・契約手続きなどの法律行為や、生活を支えるためのサポートを行う制度です。
意思能力が十分でなくなってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理を行うことが難しくなります。
また、介護施設への入退去手続き、医療機関への入院手続きや、それに伴う費用の支払い、契約行為なども、自分自身で行うことも難しくなります。
「自分の行為によって、どのような不利益(または利益)が生じるか」の判断を下すことができなくなってしまうのです。
そのため、本人が知らず知らずのうちに不当な契約を結んでしまったり、詐欺や悪徳商法に引っかかったりしてしまい、財産を失ってしまうことがあるかもしれません。
成年後見制度は、こうした事態に陥って本人が不利益を被ることがないよう、本人に代わって財産の管理・保護、生活の支援をすることを目的として作られた制度です。
成年後見制度ができる前にも、意思能力が低下した人や浪費癖のある人の財産管理を行う制度として、禁治産制度・準禁治産制度の2つの制度がありました。
禁治産制度・準禁治産制度の適用を受けると、戸籍に禁治産者・準禁治産者と記載されていました。
しかし、戸籍に禁治産者・準禁治産者と記載されることで、差別や偏見を生んでしまうのではないかという懸念や、より個人を尊重した制度に変えるべきとの意見が出たことから制度が見直されます。
そして、2000年の民法改正で、成年後見制度ができるに至りました。
成年後見制度と似たような仕組みに家族信託があります。
成年後見制度と家族信託の最大の違いは、利用可能なタイミングです。
成年後見制度は本人の意思能力が喪失した後になってはじめて利用可能ですが、家族信託は本人の意思能力喪失前から利用できます。
成年後見制度は、本人の意思能力の喪失後に利用する制度です。
一方、家族信託は本人の意思能力の喪失前しか利用できません。本人の意思能力の喪失を見込んで、前もって申し立てしなければいけないことを理解しておくと良いでしょう。

成年後見制度の対象者は、「精神上の障害」があり、「事理を弁識する能力が低下している」人です。
精神上の障害とは、例えば認知症や知的障害、精神障害、高次脳機能障害などが当てはまります。
また、事理を弁識する能力とは、簡単にいえば「判断能力」のことです。
実際に成年後見制度を利用しているのは、65歳以上の人が男性では約72%、女性では約86%を占めており、中でも80歳以上が最も多くなっています。
超高齢社会が急速に進行する中で、成年後見制度を開始する1番の原因は認知症です。開始原因全体の63.2%と全ての開始原因の約3分の2近くを占めています。
2023年に発表されたデータにおける成年後見制度の開始原因別割合は下表のとおりです。
【開始原因別割合】
| 開始原因 | 割合 |
|---|---|
| 認知症 | 63.2% |
| 知的障害 | 9.4% |
| 統合失調症 | 8.7% |
| 高次脳機能障害 | 4.1% |
| 遷延性意識障害 | 0.6% |
| その他 | 14.0% |
認知症が他の開始原因を大きく引き離していることがわかります。
参考:裁判所「成年後見関係事件の概況」
成年後見制度の申し立ての動機からみると、預貯金などの管理・解約が31.6%、身上保護が24.2%で2つ合わせて約55%を占めています。
2021年における成年後見制度の申し立ての動機別割合は下表のとおりです。
【申し立ての動機別割合】
| 申し立ての動機 | 割合 |
|---|---|
| 預貯金などの管理・解約 | 31.6% |
| 身上保護 | 24.2% |
| 介護保険契約 | 14.0% |
| 不動産の処分 | 11.9% |
| 相続手続 | 8.5% |
| 保険金受取 | 5.5% |
| 訴訟等手続など | 1.9% |
| その他 | 2.5% |
認知症などにより親の判断能力が不十分なために、成年後見制度の検討が必要になる可能性は大きいです。
以下では、具体的な4つの場面について見ていきましょう。
金融機関や生命保険会社で口座や生命保険などを解約する際には、本人の意思によることが原則です。本人以外が窓口に行った場合には、原則として本人の有効な委任状が必要です。
親が認知症などで判断能力が低下していると解約手続きができません。しかし、成年後見人であれば、本人に代わって解約手続きが可能です。
口座や生命保険などを解約するケースは、成年後見制度の検討が必要な場面の1つです。
親が持ち家で1人暮らしをしているような場合には、土地・家屋を売却し介護施設などへの入居が安心と思われるかもしれません。
しかし、本人に法律行為を行う判断能力がなければ、不動産を売却するためには、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
なお、成年後見制度では本人の財産保護の観点から、成年後見人であっても本人の住居の売却には家庭裁判所の許可が必要です。
家族による親の介護が困難になれば、介護サービスや施設への入所手続きなどの契約が必要になります。しかし、本人以外では契約手続きを行えません。
成年後見人などの法定代理人であれば、本人に代わって契約することができます。
遺産分割協議では、相続人全員が参加しての合意が必要です。
父が亡くなった場合に、母が認知症で判断能力が不十分であれば遺産分割協議へ参加することはできません。
成年後見人などの法定代理人であれば、母に代わって遺産分割協議への参加が可能です。

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。

「本人に代わって財産を保護・管理し、生活面のサポートをする」という根本的な趣旨はどちらも同じですが、この2つには大きな違いがあります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
「法定後見制度」は、本人の意思能力が既に低下・喪失してしまった場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てをすることにより、法定後見人を選任してもらう制度です。
法定後見制度は、本人の意思能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。
基本的に身の回りのことが何もできない状態を指します。
財産管理や契約行為はもちろん、日常的な買い物に至るまで、誰かのサポートを必要とするケースです。
「後見人」に選ばれた人は、財産管理など全ての法律行為に対して、「代理権(本人に代わって、契約などの法律行為を行う権限)」や、「取消権(本人が行った法律行為を取り消すことができる権限)」が与えられます。
日常的な買い物などは問題なくできるけれど、財産に関する重要な行為(預貯金の引き出し、不動産の売却など)については、誰かのサポートを必要とするケースです。
「保佐人」に選ばれた人は、「同意権(本人が行った行為に対して同意する権限)と「取消権」が与えられます。
本人が保佐人の同意を得ずに行った行為で本人にとって不利益になる場合は、この行為を取り消すことができます。
保佐人に「代理権」は与えられませんが、必要に応じて家庭裁判所から認められた特定の行為についての「代理権」が与えられることもあります。
基本的に問題なく日常生活を送ることができるけれど、財産に関する重要な行為を1人で行うには少し不安があるため、誰かにサポートしてもらった方が良いというケースです。
「補助人」に選ばれた人は、保佐人と同様「同意権」「取消権」と、必要に応じて、家庭裁判所から認められた特定の行為についての「代理権」を与えられることがあります。
ただし、補助人が持つことのできる同意権(取消権)は保佐人に与えられるものよりも限定されています。
法定後見制度を申し立てる際には、以下のような流れで手続きを進めます。
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に「後見開始の審判」の申し立てを行います。
申し立て先は、被後見人となる人の住所を管轄する家庭裁判所です。
申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官又は市町村長などに限られています。
申し立ての際には、「医師の診断書」が必要です。「後見」「保佐」「補助」の3つのうち、どの類型になるかを最終的に判断するのは家庭裁判所になります。
そのため、医師の診断書は、本人の意思能力の程度を家庭裁判所に示す上で重要な書類です。
診断書の他、必要書類(住民票や財産目録など、家庭裁判所のHPで公開されています)を揃えたら、郵送又は窓口にて申し立ての手続きを行います。
申し立て後は、家庭裁判所が書類の内容をもとに、申立人や本人、親族などの関係者と面談を行い、意思能力を含め本人の生活・財産状況を確認します。
その調査内容を踏まえて、法定後見人が選任されるのです。
申し立てから法定後見人が選任されるまで、少なくとも 2〜4カ月の期間を要します。
事案によってはもっと時間を要する場合もあるでしょう。
法定後見制度の利用には費用が必要です。
法定後見人の選任には、主に以下のような費用がかかります。
鑑定料とは、専門家により被後見人の判断能力を確認してもらう時にかかる費用です。
また、必要に応じて司法書士に手続きなどを依頼する場合、10〜20万円ほどの費用が必要になります。
利用開始後は、法定後見人に毎月2〜6万円ほどの報酬を支払う必要があります。
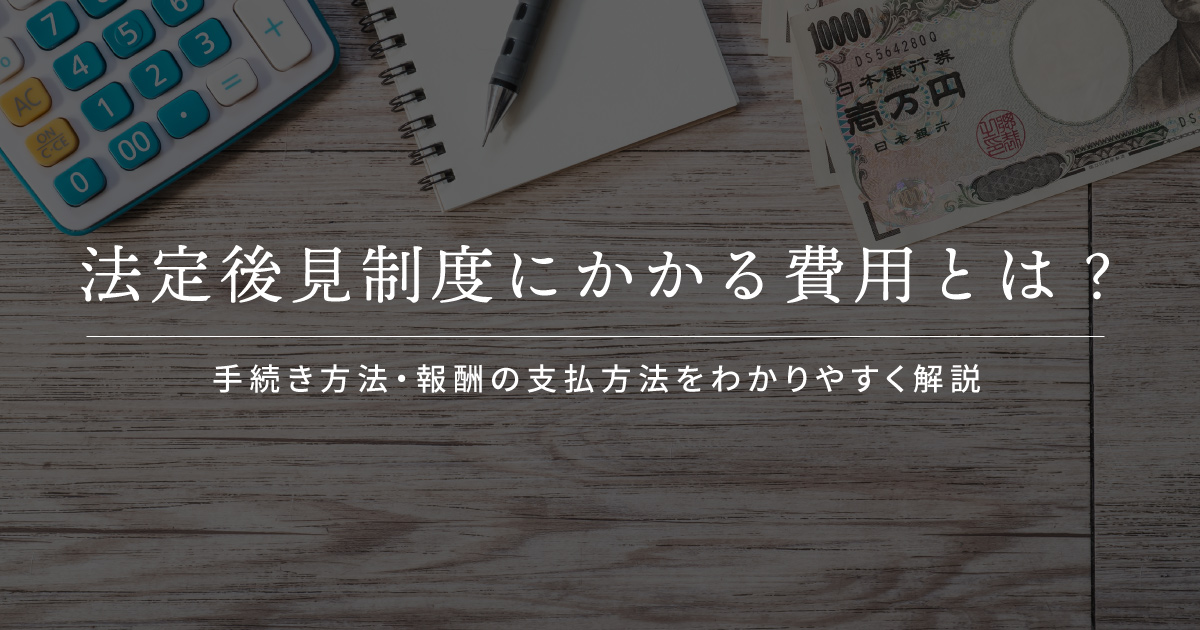
以下では法定後見制度の注意点を3つ解説します。
法定後見制度を利用した後に本人の判断能力の低下が進んでいく場合があります。
しかし、判断能力が低下したからといって、補助から保佐、後見へと法定後見の種類が自動で切り替わるわけではありません。
法定後見制度の種類を切り替えるためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
認知症などの進行度合いによっては、補助や保佐では本人を十分に保護できないことも考えられます。
本人の判断能力の低下に合わせて、法定後見制度の種類の切り替えが必要です。
法定後見制度では、本人や家族が請求することで後見監督人、保佐監督人、補助監督人が選任される場合があります。
後見人や保佐人、補助人の職務を監督するためです。
職務を公正に遂行しているか確認してほしい場合には、それぞれの監督人の選任を申し立てることがあります。
家庭裁判所が後見監督人、保佐監督人、補助監督人を選任します。一般的には弁護士などの専門家が選任される場合が多いです。
成年後見では、本人単独の法律行為は基本的にできなくなります。
また、保佐では重要な法律行為に保佐人の同意が必要になるため、保佐人の同意が必要な法律行為については、本人単独で契約締結を行うことはできません。
本人は成年後見開始後も、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は可能です。
成年後見制度は、本人の保護を目的とする趣旨と、本人の自己決定権の尊重とのバランスを図る趣旨から、本人による「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は後見人の同意なしに行えるのです。
例えば、以下の行為が「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に該当します。
本人と後見人との間に利益相反行為があったときは、特別代理人を選任する必要があります。
利益相反行為とは、当事者間の行為が、ある人には有利になりその他の人には不利になる行為をいいます。
例えば、相続において、本人と後見人が両方とも相続人になった場合、後見人が本人が受け取る遺産を少なくし、後見人が多く受け取るようにするなど、公平な遺産分割ができなくなります。
そのような場合、本人に代わって遺産分割協議に参加するために特別代理人を選任します。
申し立ては、本人の親権者か利害関係人が本人所在地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
特別代理人になるのに特に資格は必要ありません。
しかし、本人の利益を保護するために適切な行為を行えることが必要です。
本人の父が亡くなり、母と本人が相続人である場合、相続とは無関係な方が選ばれます。
この場合、祖父母、叔父叔母、従兄弟などが選任されるケースが多い傾向にあります。
特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為についてのみ代理権を行使することができ、当該行為が終了すれば、特別代理人としての任務も終了します。
「任意後見制度」は、本人の意思能力があるうちに、自分の意思で任意後見人を選定しておくことができる制度です。
依頼をする本人(委任者)と任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)は、「任意後見契約」を、「公正証書」により締結します。
契約締結にあたって、本人は、将来意思能力が低下・喪失した後の財産管理方法や、介護・医療に係る事務的な手続き内容を自由に決めることが可能です。
前述した法定後見制度は、「本人の意思能力が低下・喪失した後」から手続きが開始されます。それに対し任意後見制度は、「本人の意思能力が低下・喪失する前」に、あらかじめ手続きをするという点で大きな違いがあります。
「誰を任意後見人として選ぶのか、何を依頼するのか」を、事前に決めておくことができるという点も、任意後見制度の大きな特徴といえるでしょう。
任意後見監督人とは、任意後見人が被後見人本人にとって不利益となるような財産管理・処分などを行うことを防ぐために、チェック・監督する人物です。
任意後見制度は、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから効力が生じることになります。そのため、利用する際には法定後見制度と同様に、申し立ての手続きを行う必要があります。

任意後見制度を申し立てる際には、以下のような流れで手続きを進めます。
任意後見契約締結後に本人の判断能力が低下し、任意後見制度を利用する場合、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の審判」の申し立てを行います。
申し立て先は、法定後見制度と同様、被後見人となる人の住所を管轄する家庭裁判所です。
申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者に限られています。また、本人以外が申し立てを行う場合には、原則として本人の同意が必要です。
申し立ての際は、「申立事情説明書」や「医師の診断書」「住民票」など、家庭裁判所のHPで公開されている必要書類を揃えて、郵送又は窓口にて申し立て手続きを行います。
その後、家庭裁判所が書類の内容をもとに、申立人や本人、親族などの関係者と面談を行い、意思能力を含め本人の生活・財産状況を確認します。
その調査内容を踏まえて、任意後見監督人が選任されるのです。
任意後見制度を利用するには、以下の費用がかかります。
手続きを司法書士に依頼する場合、10〜15万円ほどの費用が必要です。くわえて、任意後見人・任意後見監督人への報酬もそれぞれ月額1〜6万円を支払う必要があります。
任意後見人との合意があれば報酬をゼロにできます。しかし、任意後見監督人への報酬は裁判所により決められるため、ゼロになることはないでしょう。
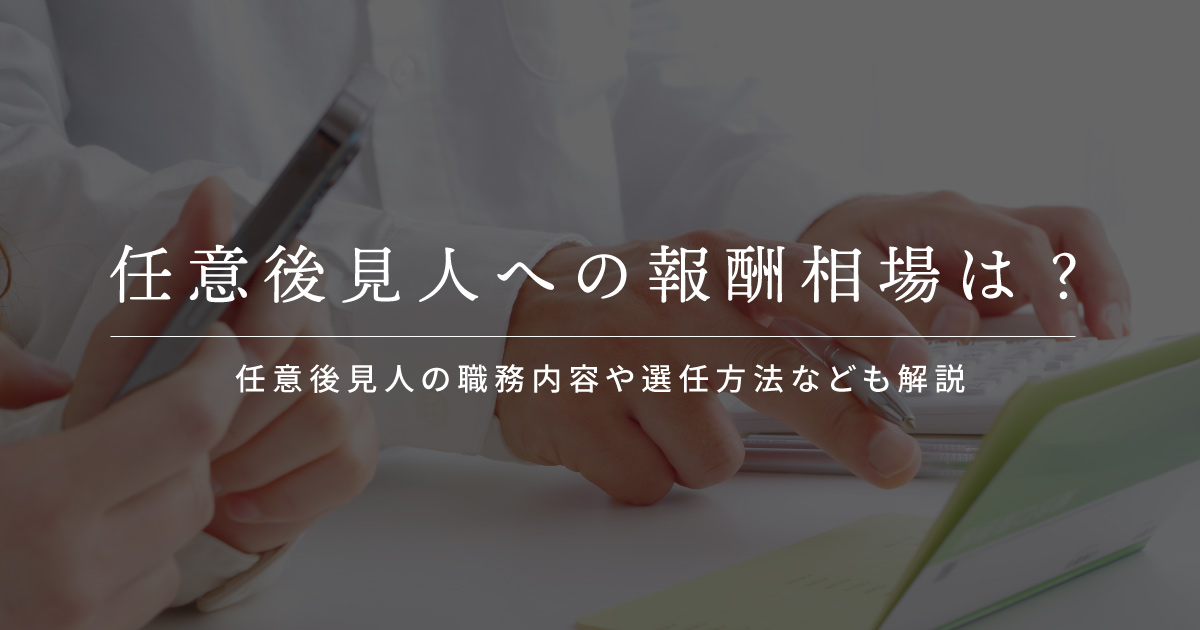
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

成年後見人とは、どのような役割を果たす人なのでしょうか。成年後見人の選ばれ方や成年後見人になれない人、誰がなるのかについても解説します。
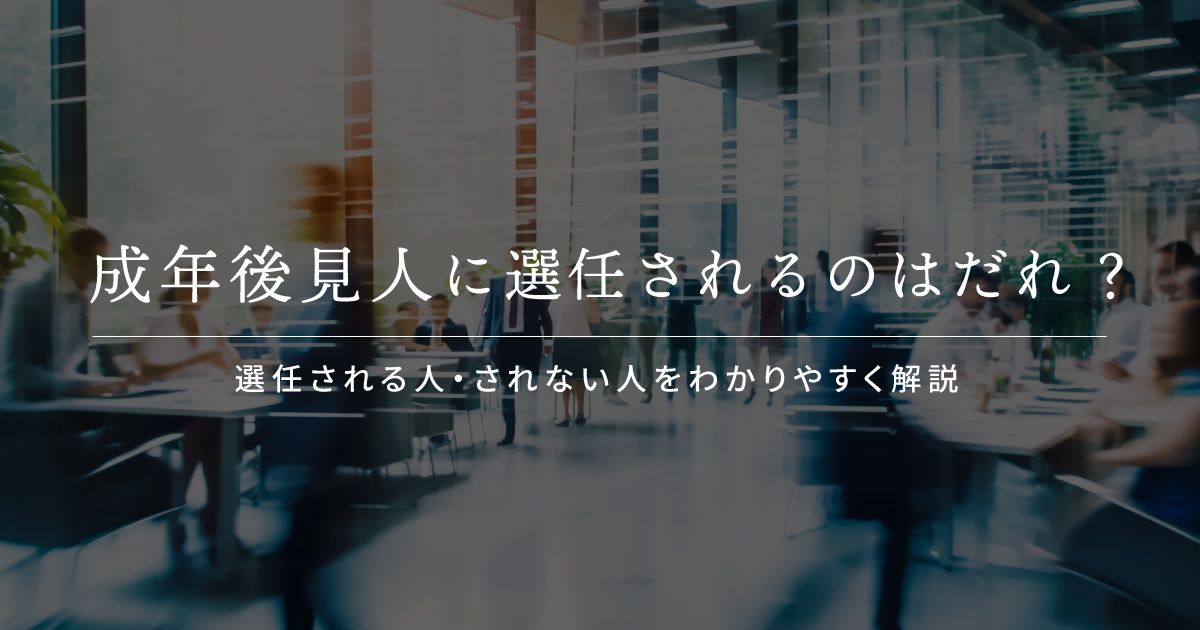
成年後見人には、主に3つの役割があります。
それぞれの役割について解説します。
成年後見人にとって、被後見人の財産管理が一番大きな役割です。管理すべき財産の総額が多ければ多いほど、成年後見人の負担は増えます。
成年後見人が財産管理で果たすべき役割は、財産の現状維持であるため積極的な運用はできません。
不動産などを売却する場合も、家庭裁判所に確認する必要があることも理解しておきましょう。
身上保護も成年後見人の大きな役割の1つです。身上保護とは、被後見人の療養看護に関する契約などの法律行為を成年後見人が代わりにすることを指します。
身上保護は、判断能力を失った人が医療機関への入院や介護施設への入所をする際の契約などで必要になるため、大切な役割です。
なお、成年後見人が自ら介護をするわけではありません。行うのはあくまでも療養看護に関する「法律行為」です。
成年後見人は年1回、成年後見人の事務について家庭裁判所に報告する義務があります。この報告義務があるため、成年後見人が不正をせず安全に利用できる環境が整えられているのです。
成年後見人は、後見等事務の報告が面倒に感じられるかもしれません。しかし、義務であるだけでなく、制度の安全性を担保するものでもあるため、必ず報告するようにしてください。
成年後見人の選び方は法定後見制度と任意後見制度で異なります。それぞれの選任方法について、以下で解説します。
法定後見制度の場合、法定後見人は家庭裁判所によって選ばれます。申し立ての際に候補者を立てることはできますが、候補者を立てたからといって必ず選ばれるわけではありません。
家庭裁判所は、被後見人の状況や法定後見人となる人の職業、被後見人との利害関係、被後見人の意見などを総合して判断します。
家族以外では、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多いです。
特に対象となる財産が多ければ多いほど管理が複雑になるため、専門家が選ばれやすくなるでしょう。
任意後見制度の場合、任意後見人は本人が自由に選べます。
家族や友人など日頃から信頼関係を築いてきた人や、弁護士や司法書士などの専門家を選ぶケースが多いです。「この人なら任せても大丈夫」という家族や友人がいれば、その人に依頼するのがおすすめです。
しかし、浪費癖があったり信頼できない部分があったりする場合は、信頼できる肩書きのある弁護士や司法書士に依頼することも1つの選択肢になります。
後見開始の審判により、成年後見人が選任されます。
審判書が後見人などに送付されてから2週間以内に不服申し立てがない場合、審判が確定し後見が開始します。
審判内容に納得がいかない場合、後見開始前に申立人や利害関係人は不服申し立てができますが、不服申し立てができるのは「後見開始」についてであり、「選任された成年後見人が、希望に沿った人でなかった」など、その選任に対して不服申し立てはできません。
なぜなら後見人の選任は、後見開始の手続きに付随するものであって、後見人の選任についてだけ切り離して審判の対象にはできないからです。
成年後見人には個人と同様に、法人や複数の人でもなることができます。
社会福祉法人や社団法人、NPO法人などが、成年後見人になることを法人後見といいます。
法人の職員が後見事務を行いますが、後見人となるのは法人そのものです。
担当の職員が後見事務を行えなくなっても、担当を変えて後見事務を継続できるのがメリットです。
複数人が後見人になることを複数後見といい、後見人が共同で権限を行使するケースと、家族の後見人と専門家の後見人とが、それぞれ行使する権限を分け合う権限分掌のケースがあります。
後者のケースが多く利用され、身上保護に関しては家族の後見人が受け持ち、契約など専門分野は弁護士や司法書士などの専門家が受け持ちます。
民法第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
これらの事由に当てはまらなければ、基本的に誰でも成年後見人になる資格があります。
成年後見人等と本人との関係別件数・割合
※成年後見関係事件の概況(令和4年1月から12月まで)より
成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)と本人との関係をみると、配偶者、親、子ども、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが、全体の約19.1%となっています。
親族以外が成年後見人等に選任されたものは、全体の約80.9%(前年は約80.2%)であり、親族が成年後見人等に選任されたものを4倍以上上回っています。
成年後見関係事件の概況
※成年後見関係事件の概況(令和4年1月から12月まで)より
弁護士、司法書士、税理士及び行政書士の数値は、各法人をそれぞれ含んでいます。
なお、任意後見監督人の場合も同様に、親族などではなく、第三者(弁護士、司法書士などの専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。
第三者が成年後見人に選任されることが増えた背景として、成年後見人となった親族が、被後見人の財産を使い込むようなトラブルが多発したことが挙げられます。
そのため「不正防止」という観点で、親族が任命されることは少ないです。
特に、被後見人の財産が多額の場合や、成年後見人の就任に反対する親族がいる場合などは、親族が成年後見人になることは難しいのが実情です。
成年後見制度の利用を検討している方は、この点をよく理解しておく必要があります。

成年後見人を辞任したい場合や解任したい場合はどうすれば良いのでしょうか。それぞれの場合について、解説します。
成年後見人を辞任するには、家庭裁判所に正当な事由があると認められなければなりません。自由に成年後見人を辞めることができてしまうと、被後見人の利益を侵害してしまう可能性があるためです。
成年後見人の辞任許可を受けるためには、後見開始の審判を受けた家庭裁判所に申し立てます。申し立てには手数料800円や1,400円の収入印紙、および郵便切手代などが必要です。手続きに関する詳細は裁判所ごとに異なるため、直接裁判所に問い合わせてください。
成年後見人を解任したい場合には、成年後見人に以下の3つのいずれかに該当する事情が認められる必要があります。
これらの事由に該当する場合は、解任の申し立てを行うことが可能です。
申し立てが認められるためには、成年後見人が解任事由に該当することを示す証拠が必要です。まずは証拠を集め、その証拠をもとに解任事由をまとめてください。
なお、申し立て先は成年被後見人の住所地の家庭裁判所であるため、間違えないように事前に確認しておくことをおすすめします。
成年後見人が死亡した場合、後見は終わるのでしょうか?
結論から言うと、成年後見人が死亡しても後見は継続します。
最初から申し立てをする必要はありませんが、新たな後見人選任の手続きをしなければなりません。
後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が遅滞なく管轄裁判所に新たな後見人の選任を請求します。
それ以外の場合は、本人または親権者等の利害関係人が新たな後見人の選任を請求するか、家庭裁判所が職権で新たな後見人を選任します。
利害関係人は範囲が広く、老人ホームなどに入っている場合、施設長なども利害関係人として新たな後見人の選任の請求が可能です。
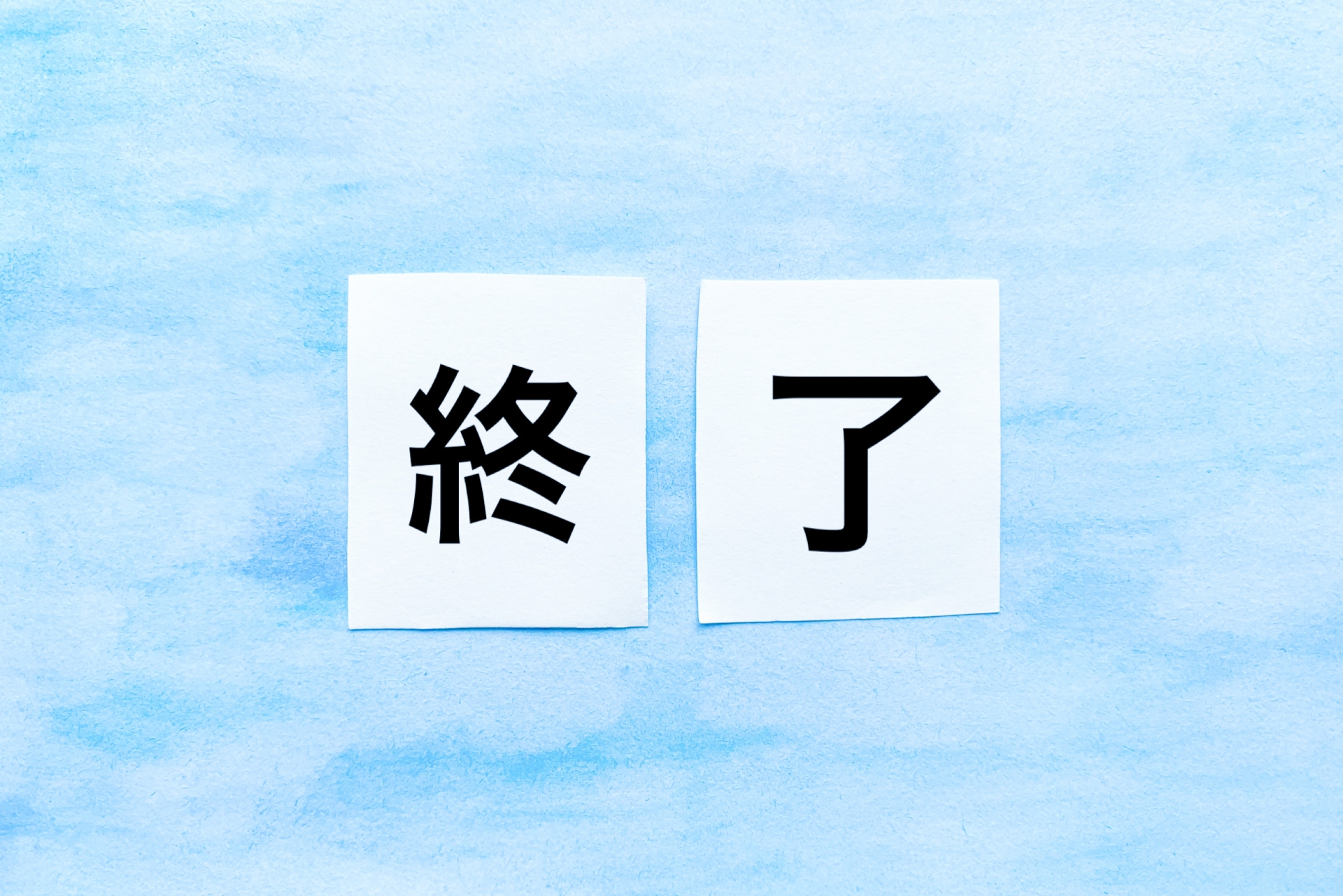
成年後見が終了するのは、以下の4つの場合です。
後見自体が終了する絶対的事由と後見人との関係で終了する相対的事由とがあります。
本人の死亡、審判の取り消しが絶対的事由で、その他が相対的事由です。
以下で詳しく解説します。
成年後見人が辞任したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、本人の利益を保護するために、後見人の辞任には正当な事由が必要になり、容易に辞任できるわけではありません。
辞任する後見人は、後任の後見人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
後見人が不正な行為をした場合、あるいは後見人としてふさわしくない行為をした場合、本人、本人の家族、検察官、後見監督人は家庭裁判所に後見人の解任を請求できます。
また、家庭裁判所は職権で解任することもできます。
他の後見人がいない場合は、新たな後見人を選任することが必要です。
本人または成年後見人の死亡は絶対的な終了事由に該当します。
被後見人の死亡後、後見人の代理権等は消滅し、管理計算業務と相続人への相続財産の引き渡しだけが、業務として残ります。
後見人の死亡は相対的な終了事由であるため、被後見人と後見人との間においては後見は終了しますが、後見自体は終了しません。
被後見人、被後見人の親族、後見監督人、その他利害関係者は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
審判の取り消しとは、被後見人が後見の必要のない状態になった場合に後見開始の審判を取り消すことです。
後見の必要のない状態とは、被後見人の判断能力が後見の必要のない状態まで回復したことをいいます。
被後見人の判断能力が回復した場合、被後見人、後見人、被後見人の配偶者、四親等以内の親族等は家庭裁判所に審判取消の請求をしなければなりません。
審判の取り消しには、被後見人の判断能力が回復したことを認定する必要があり、そのため鑑定書等で確認を行います。
後見人は、被後見人の身上を保護し財産を管理する義務を負うものです。
そのため、その義務を果たすのに問題がある者をあらかじめ欠格事由として定め排除しています。
破産した者は後見人の欠格事由にあたり、選任された後に破産した者も当然にその後見人としての地位を失います。
したがって、家庭裁判所は後見人が破産した場合、裁判所は新たな後見人を選任する必要があります。
後見が終了すると、成年後見人は以下の手続きを行います。
後見終了から2カ月以内に、後見の計算を行い財産目録を作成します。
後見の計算とは、後見人に就任していた期間の収支について計算し、財産の変動と現在の残高を明確にすることで、それをまとめて財産目録を作成し、被後見人等に報告します。
被後見人の死亡により後見が終了した場合は、後見人は後見終了登記の申請をする必要があります。
その他の事由で終了した場合は、裁判所が嘱託で行います。
本人死亡以外の事由で後見が終了した場合、後見人は預かっていた財産を被後見人に引き渡します。
本人の死亡により後見が終了した場合、相続の内容により後見人は預かっていた財産を誰に引き渡すのかが異なります。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

ここまで成年後見制度の概要や申し立ての流れについて説明してきました。ここでは、成年後見制度のメリットを解説していきます。
認知症の親を抱える子どもにとって、「親と同居している親族が、財産を使い込んでいる」といった悩みが起きることがあります。これは決して珍しいケースではありません。
意思能力の低下により、自身で財産を管理することができない場合には、同居の親族や身近にいる人が、本人に代わって財産を管理していることが多いです。
それらの人によって、勝手に預貯金が引き出されてしまうことが実際にあるのです。
成年後見制度であれば、こうした「親族による財産の使い込み」を防ぐことができます。成年後見人は、裁判所監督の下で財産管理を行ない、管理状況を定期的に報告することが求められるためです。
預貯金の管理も、銀行に対して成年後見人になった旨の届出を行うことになり、成年後見人以外の人は引き出すことができなくなります。
家族内での財産管理を望んでいる人にとっては、公的機関が財産管理に関与することはデメリットとも取れます。
しかし、横領のような事態を防ぎ、厳格に財産を管理をしたい方にとっては、メリットといえるでしょう。
認知症などで意思能力が衰えてしまうと、内容がよくわからないまま不当な契約を締結してしまったり、高額な健康食品などを大量に買ってしまったりすることがあります。
成年後見人には「取消権」と呼ばれる、本人が行った法律行為を取り消すことができる権限が与えられています。
そのため、本人に代わって契約を取り消したり、代金の返還を請求したりすることができるのです。
高齢者を標的にした悪質商法による被害が問題視されている昨今、家族がこうした被害に遭う可能性もあります。心配な場合には、成年後見制度を利用しておくと安心かもしれません。
なお、任意後見制度には、「取消権」がないため、注意が必要です。
成年後見人の3つの役割でも解説したとおり、成年後見人の仕事の大きな特徴として、「身上保護」があります。
「身上保護」とは、意思能力を喪失した本人に代わって、医療機関への入院や介護施設の入所手続き、費用の支払いなどを行うことです。
また、契約・手続き後も、本人を定期的に訪問し、「適切な介護や治療を受けているか」といった生活状況を確認することが求められます。
身上保護はあくまでも、「本人の健康に配慮し、安心した生活が送れるように生活環境の手配・整備を行うこと」が仕事です。本人に対し、直接介護や看護などをすることなどは含まれていません。
離れて暮らしていてなかなか様子を見に行けない方や、本人の近くに身寄りがおらず不安な方もいるでしょう。財産管理だけでなく生活面のサポートまで受けられる成年後見制度は有効な手段といえます。

成年後見制度にはデメリットや問題点も存在します。ここでは、成年後見制度のデメリットや問題点を9つ解説します。
前述したとおり、成年後見人は第三者(弁護士や司法書士など)が任命されるケースがほとんどです。その場合、親族であっても財産を利用できなくなってしまいます。
成年後見人が任命される前は、本人に代わって親族がお金を下ろしていた場合でも、通帳とカードは成年後見人に渡さなければなりません。

任意後見人には、必ず任意後見人が正しく後見行為を行っているかを監督する役割を持つ、任意後見監督人がつくことになります。
任意後見監督人は家庭裁判所によって選任され、任意後見人に対して後見事務に関する書類や財産目録、通帳のコピーなどの提出を求めます。本人の生活や財産状況は、全て家庭裁判所に知られることになるのです。
そのため、親族が任意後見人になったとしても、実質的に家庭裁判所の管理下に置かれることになります。
成年後見制度の利用を開始すると、本人の財産から、成年後見人に対して報酬を支払う必要があります。
報酬の金額は本人の財産額によって異なり、家庭裁判所によって決められます。
なお、任意後見制度の場合は、被後見人との事前の取り決めで指定します。
| 管理財産額 | 月額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円 ~ 5,000万円 | 3~4万円 |
| 5,000万円超 | 5~6万円 |
後見監督人、任意後見監督人の場合も同様です。費用は以下のようになります。
| 管理財産額 | 月額 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 1~2万円 |
| 5,000万円超 | 2万5千円~3万円 |
これらの金額以外にも、申し立ての際に費用がかかってくるため、経済的な負担が非常に大きくなります。
成年後見制度は、一度利用を開始すると本人の意思能力が回復したと認められるような場合でない限り、途中でやめることはできません。
しかし、現在の医療では認知症の進行は不可逆的であり、意思能力の回復は見込めません。
そのため、本人が亡くなるまで上記の報酬・費用を継続的に支払い続けることになります。
成年後見制度は、本人の財産の維持・保護を図ることが最大の目的となります。そのため、積極的に財産を運用するような行為は想定されていません。
財産を運用するような行為とは、財産を子どもや孫の教育資金のような本人以外のために使う場合や、株式への投資なども含まれます。
基本的に「本人の財産を減らす」ことに繋がる行為は認められません。
前述したとおり、成年後見制度は財産の現状維持が主な目的です。そのため、被後見人の財産が減ってしまうような相続対策はできなくなってしまいます。
相続対策の一例として、生前贈与や生命保険への加入、マンションの購入などが挙げられますが基本的にどれも認められないでしょう。特に、財産が多い人は注意してください。
成年後見制度は申し立てたらすぐに利用できる制度ではありません。
一般的に、申し立てから利用開始までは2〜4カ月かかることが多いです。その期間は親の財産を引き出したり身上保護をしたりすることができないのです。
早く利用したいと考える方もいるかもしれませんが、利用開始までの期間を短くすることはできません。利用を検討している方は早めに相談すると良いでしょう。
成年後見制度は判断能力を喪失してからしか効力を持たないため、本人が財産管理の様子を見ることができません。
似た仕組みである家族信託は、契約したタイミングから効力が発生するため、本人が元気なうちに財産管理が行われている様子を見届けられます。
事前に財産管理の対策をしておきたい方は、家族信託の利用も視野に入れておくと良いでしょう。
これまで述べてきたように、後見人等は強い権限を保有して職務を行います。逆に強力な権限を悪用して、本人の財産を横領する事例も一定数は存在します。
お金にだらしのない親族が後見人等になれば、使い込みリスクが高くなります。信頼のおける弁護士や司法書士などの専門家に後見人等になってもらう方が良い場合もあるでしょう。
ただし、全ての専門家が良識を持って職責を果たすわけではないため、親族として後見人等への最低限のチェックは必要です。
死後の事務委任契約とは、被後見人の死後に葬儀や埋葬に関する事務を生前に契約することです。
成年後見は被後見人が生きている間のみで、被後見人が死亡した時点で成年後見は終了します。
したがって、成年後見人には、死後事務を行う権限や義務はありません。
しかし、身寄りのない被後見人が病院や施設で亡くなった場合、後見人の死後に事務を行うケースが多々ありました。
そこで、平成28年の民法改正により、成年後見人は後見人の死亡後も個々の財産の保存に必要な行為を行えるようになりました。
死後事務の要件は以下の3つです。
また、遺体の火葬や埋葬に関する契約等を行うには家庭裁判所の許可を得る必要があります。

成年後見人には、4つのできないことがあります。あらかじめできないことを把握しておくことで、利用後にトラブルが発生しないように準備しておく必要があります。
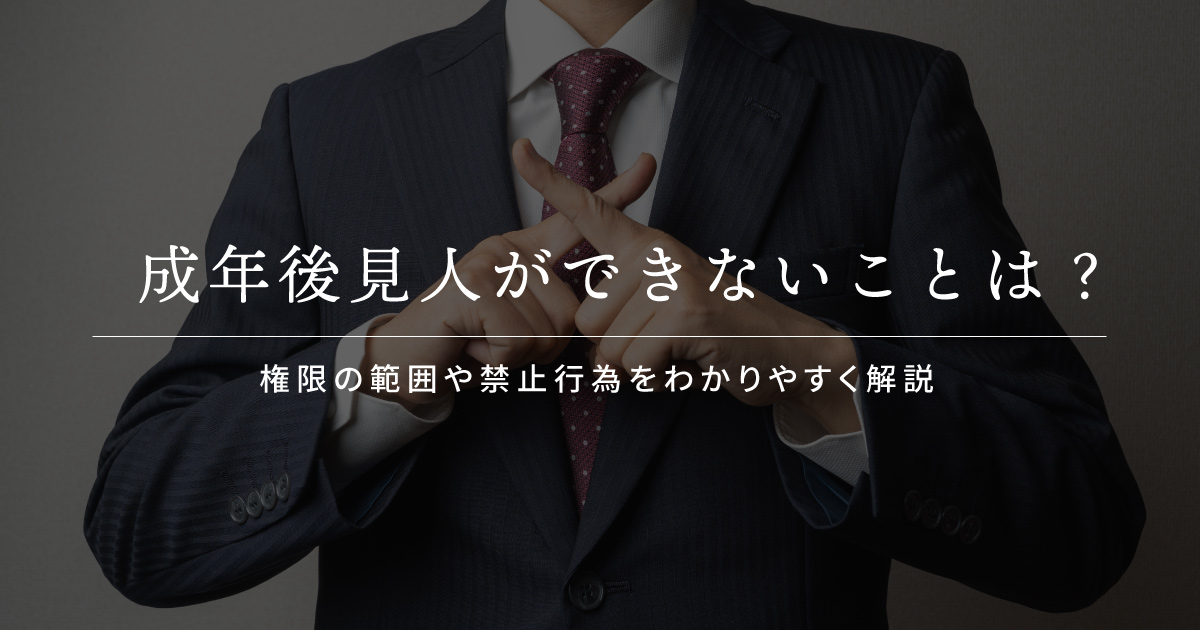
成年後見人は「事実行為」ができません。例えば、本人のための買い物や病院までの送迎、本人の介護などが挙げられます。こうした労務を直接提供する行為は、事実行為として成年後見人にはできません。
そのため、事実行為を支援する必要がある場合は、成年後見人以外の人にしてもらう必要があるため、注意してください。
成年後見人は「身分行為」もできません。
例えば、婚姻届や離婚届の提出、養子縁組をする、遺言書を書くことなどが挙げられます。こうした被後見人の身分に関する法的効果に影響を与える行為はできないのです。
もっとも、成年後見人でなくても、性質上、身分行為を他人が代理することはできません。
事実行為に加え、身分行為ができない点にも注意しておきましょう。
成年後見人は、医療行為への同意もできません。医療行為を受けるために治療や入院の手続きをサポートすることは可能ですが、医療行為そのものへの同意はできないのです。
医療行為への同意も、身分行為と同様に代理権が適用される範囲から外れているため、成年後見人でなくてもできません。
ただし、家族が成年後見人になっている場合や、健康診断や検査などの軽微な医療行為は、同意が有効になる場合があります。状況に応じて確認してみることをおすすめします。
成年後見人は、身元保証人や身元引受人などになることもできません。被後見人の財産管理や身上保護を行う場合は、成年被後見人と同じ立場になるため、本人が本人の身元保証人や身元引受人になれないのです。
ただし、家族が成年後見人になっている場合、医療機関や社会福祉施設を利用する際などの一部のケースでは、施設から身元保証人への就任を依頼されるケースもあります。
この場合は成年後見人が身元保証人になることが例外的に認められている可能性が高いため、依頼された場合は確認してみてください。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

この項では、実際に成年後見制度を利用することで起こり得るトラブル事例を紹介します。
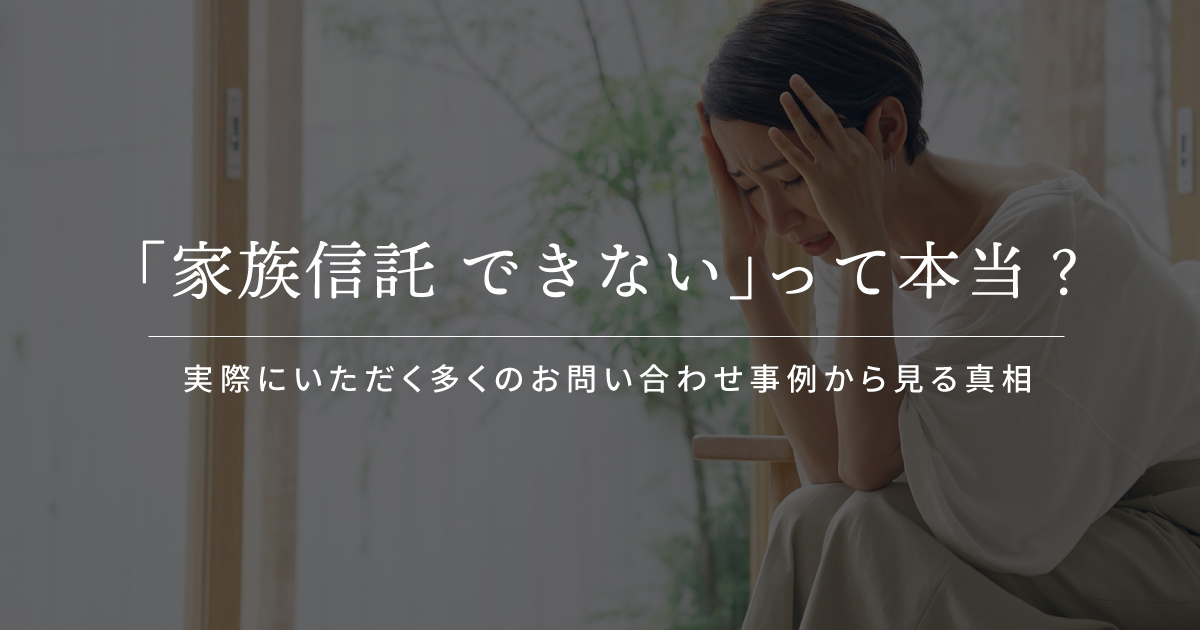

「母の預金を解約したいだけだったのに、いったん利用を開始すると途中でやめることができず、ずっと月4万円程の費用を支払わなくてはならなくなった。」



「任意後見制度を利用すれば家族で管理できると思っていたが、結局家庭裁判所から任命された後見監督人によってお金の利用を大きく制限されることになった。」



「本人のためと思ってお金を使おうとしても、家庭裁判所に確認して認めてもらう必要がある。不動産の売却を申し出た時は、家庭裁判所から『なぜ売却が必要なのかの合理的な理由』を求められ、結局許可が下りなかった。」
など
成年後見制度は負担や制約が多く、本人や親族の意向に沿った柔軟な財産管理を行うことが難しい制度であることが実情です。利用すべきか否かについては慎重に判断する必要があります。
意思能力がまだ十分にある場合には、「家族信託」など、他の方法を検討しても良いかもしれません。




成年後見制度以外に、意思能力が低下した人の財産を代わりに管理する方法として、家族信託が挙げられます。
家族信託とは、家族が代わりに財産を管理する方法であり、成年後見制度よりも財産管理の自由度が高いことが特徴です。
本人の意思能力が低下する前に、家族との間でどの財産を管理するのか、どんな目的で利用するのかなどを決めます。そして、その内容に沿った信託契約を結ぶことで利用することができます。
以下の記事で、家族信託に関する詳しい内容を解説していますので、興味のある方は併せてご覧ください。
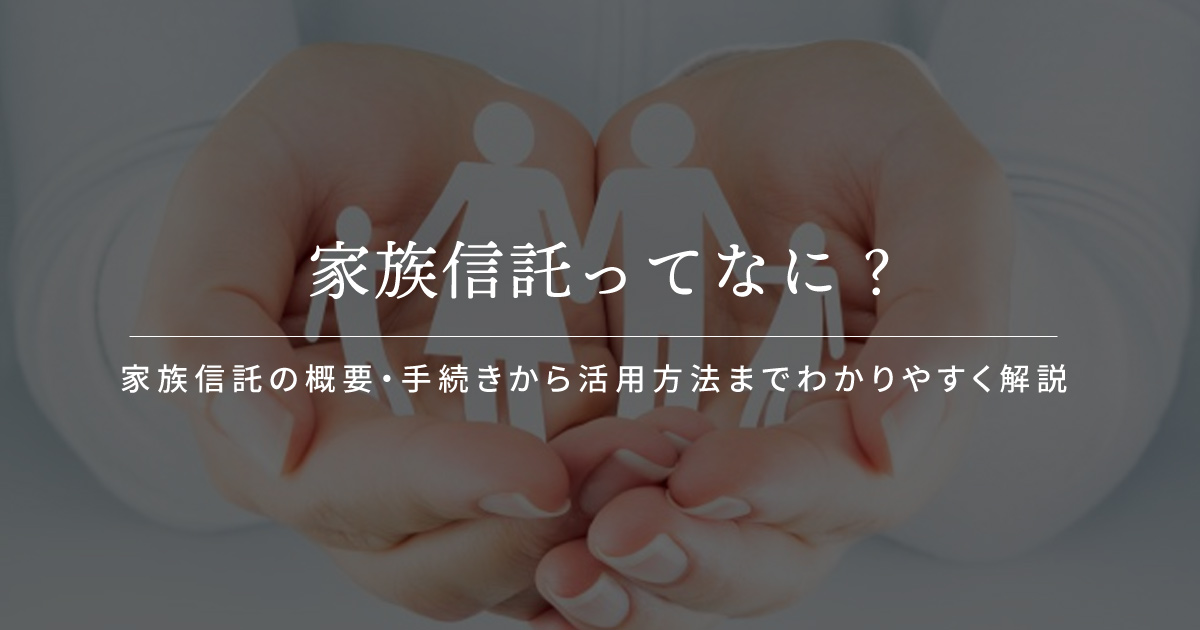
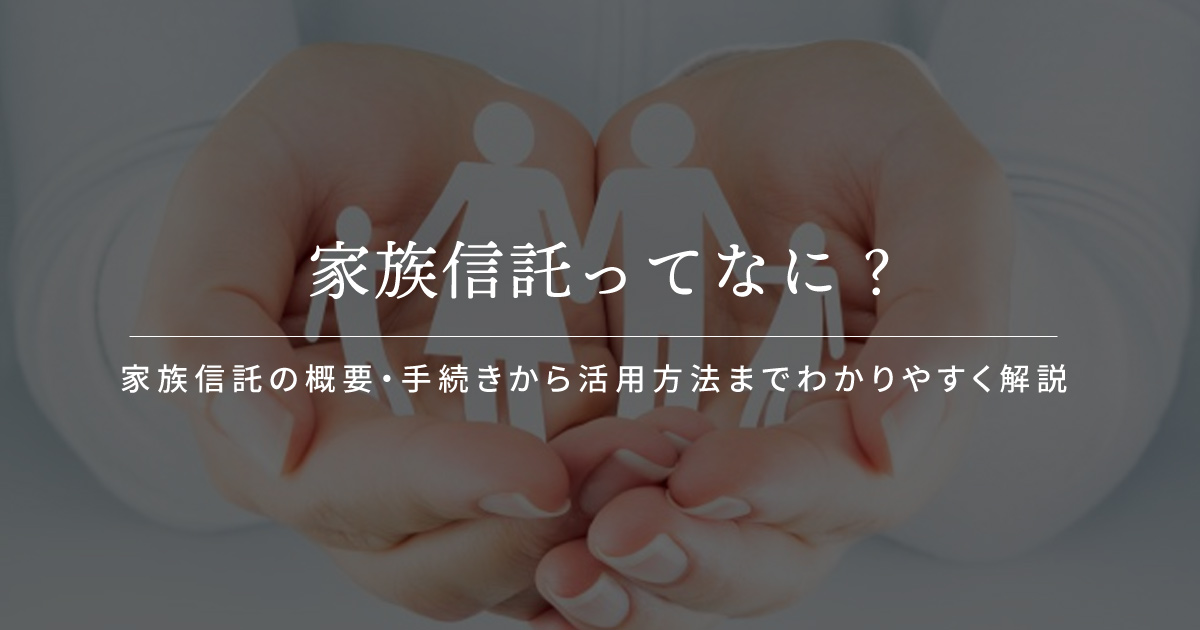


では、成年後見制度と家族信託はどちらを選べば良いのでしょうか。ここでは、成年後見制度がおすすめのケースと、家族信託がおすすめのケースを紹介します。
まずは、成年後見制度の検討をおすすめするケースを3つ解説します。
判断能力が低下している場合、財産トラブルに巻き込まれる事態が想定されます。必要な数よりも何倍も多く注文してしまったり、悪徳商法に引っかかってしまったりすることが考えられます。
このような事態に陥っても、成年後見制度では、本人に代わって契約の取り消しが可能です。他の親族による使い込みも、成年後見制度によって阻止できます。このような財産トラブルが心配な場合は、成年後見制度の利用がおすすめです。
家族信託は本人の判断能力がある状態で、将来、判断能力が失われた場合に備えておくための仕組みです。
そのため、本人の判断能力がすでに失われている場合は、家族信託を利用することができません。
したがって、本人の判断能力がすでに失われている場合には、成年後見制度を利用することになります。
専門家に財産管理や身上保護を任せたい場合にも、成年後見制度の利用がおすすめです。
例えば、家族で財産管理をするのが不安な場合や、忙しくて財産管理や身上保護にまで手が回らない場合が想定されます。
家族信託では家族が財産管理をすることになるため、これらの不安や負担は軽減されません。
しかし、成年後見制度で専門家に依頼すれば、責任を持って財産管理をしてくれます。家族の日常生活の時間が取られてしまうことは少なくなるでしょう。
続いて、家族信託の検討をおすすめするケースを4つ紹介します。
家族だけで財産管理をしたいと考える方も多くいるでしょう。
成年後見制度では、弁護士や司法書士などの専門家が財産管理に関与するケースがほとんどです。しかし、家族信託では、家族のみでの財産管理ができます。
家族だけで財産管理をしたい場合には、家族信託の検討がおすすめです。
成年後見制度では財産管理の方法が限定されています。
資産運用や相続対策などの直接的に本人のためにならない用途には、財産を使用できません。
一方で家族信託は、信託を依頼する本人と家族との間で合意していれば、その範囲内において財産を自由に使えます。
このように、柔軟に財産を管理、運用、処分したい場合は家族信託がおすすめです。
相続では、遺言を遺した場合でも、自分の次の世代までしか相続先を指定できません。
しかし、家族信託は孫の代まで財産の承継先を指定できます。例えば、自分が亡くなったら長男に全財産を承継させ、長男が亡くなったら長男の子どもが残っている財産を全て承継する、などの指定が可能です。
このように、孫の代まで承継先を指定しておきたい場合も、家族信託がおすすめです。
家族信託は、契約したタイミングから効力が発生するため、まだ元気な状態でも財産管理を任せられます。
成年後見制度では、判断能力を喪失してからしか効力が発生しないため、財産の使い道を見届けることが基本的にはできないのです。
自身の財産がどうなるのかを見届けたいと考える人も多く、そのような人には家族信託がおすすめです。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください


法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
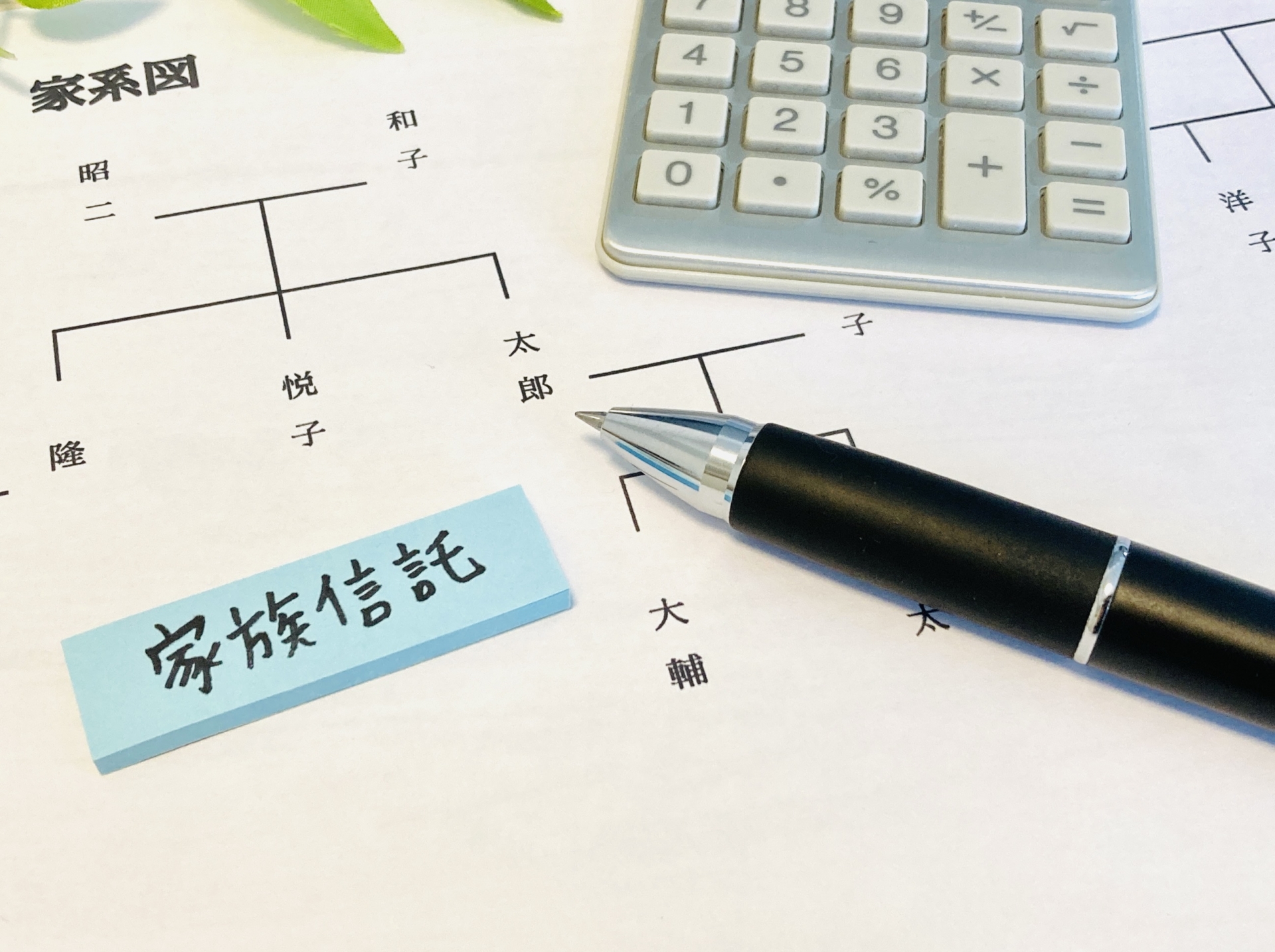
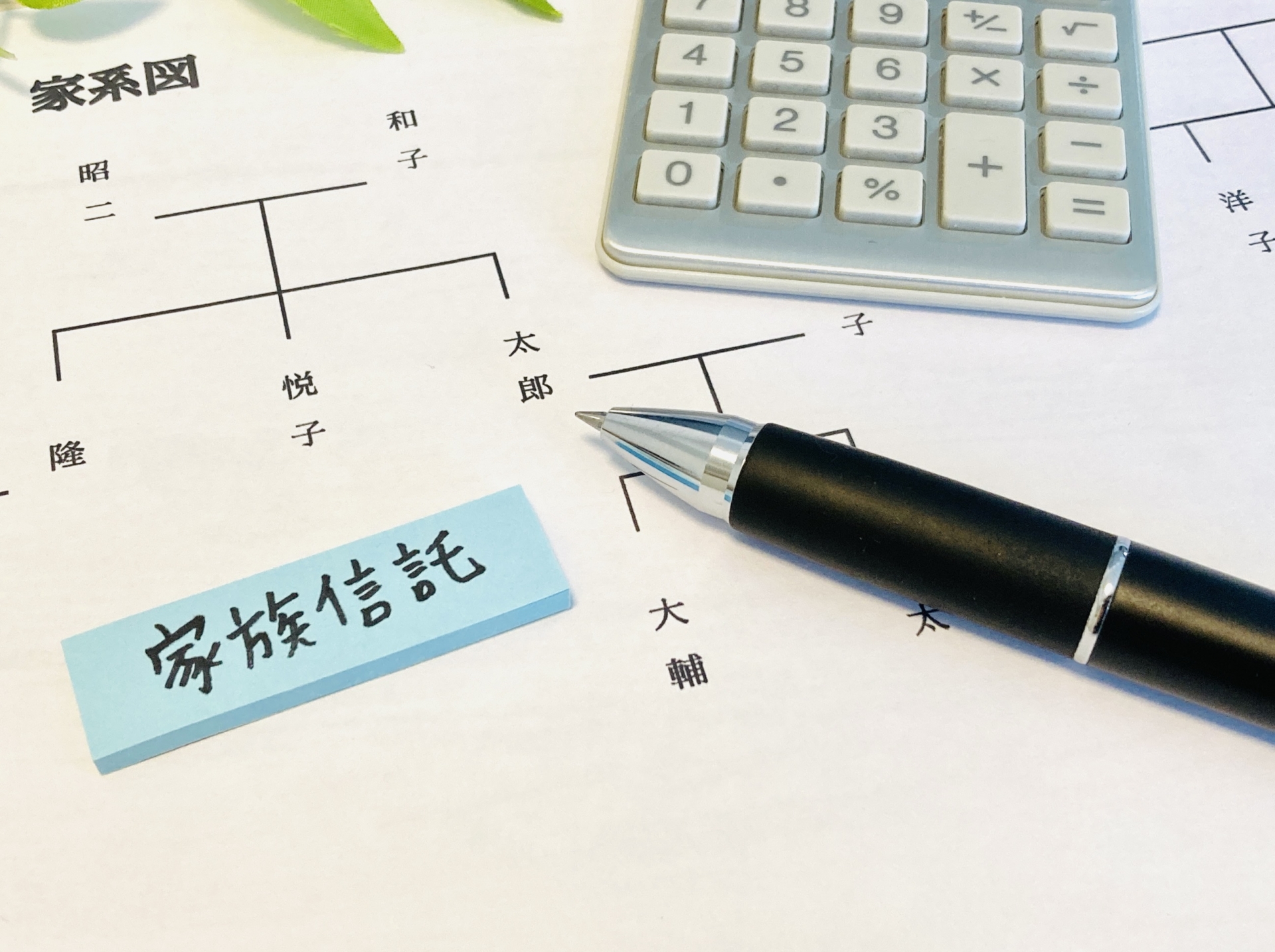
成年後見制度と家族信託は併用が可能です。どのような場合に併用することが望ましいか、また併用する際に気を付けることについても解説します。
成年後見制度と家族信託の併用をおすすめするケースは、財産所有者に身上保護が必要なケースです。
家族信託でも財産管理はできますが、本人の判断能力低下により必要のない契約を締結してしまった場合、家族信託では契約を取り消せません。
成年後見制度を利用している場合、身上保護が認められているため、契約を取り消すことができるのです。
そのため身上保護が必要な場合は、成年後見制度と家族信託を併用することをおすすめします。
家族信託で信託できる財産には制限があるため、中には信託財産化できない財産が出てきてしまうこともあります。
例えば、農地や賃貸人が譲渡を承諾しない借地権、株式などが当てはまります。
信託財産化できていない財産が多くある場合、本人の判断能力が低下したとき、家族信託では財産を管理したり処分したりすることができません。
そのため、信託財産化できない財産がある場合も、成年後見制度と家族信託との併用をおすすめします。




成年後見制度と家族信託の併用は、足りない点を補える点で非常に便利です。ここでは、成年後見制度と家族信託を併用する際に、何に注意すれば良いのかを解説します。
家族信託と任意後見制度を併用する場合において、受託者と任意後見人が同一人物になるのは望ましくありません。
家族信託では家族が本人の代わりに財産を管理・運用し、本人がそれを監視する役割を果たします。
将来、本人の判断能力が低下すると、成年後見人が本人に代わって財産を管理する立場になります。
こうなると、財産を管理する人もそれを監視する人も同一人物になってしまい、利益相反の状態になります。そのため、監視の役割を果たせなくなってしまう可能性があるのです。
しかし、財産管理をしたい本人は、1人に全て依頼したいと考えるのも無理はありません。
では、どうするのが適当なのでしょうか。管理を任せられる人が複数いる場合と、1人しかいない場合に分けて解説します。
実質的に財産を管理するのは、家族信託で財産を託された人です。そのため、管理を任せられる人が複数いる場合は、信頼のおける人に託すのがおすすめです。
他の家族には任意後見人になってもらい、家族信託での財産管理に問題がないかを監視してもらう役割をお願いしましょう。
管理を任せられる人が1人しかいない場合は、1人にお願いするしかありません。ただし、この際には、1人にお願いしても全く問題がないといえるほどに信頼関係が築けていることが前提です。
そうでない場合は、他の方法も検討してみてください。
1人に任せる場合は、利益相反になってしまいます。
そのため、利益相反が想定される条項を代理権目録に盛り込んだり、信託契約書に利益相反許容条項を盛り込んだりする対策が必要です。
家族信託も成年後見制度も、利用を開始する際に専門家のサポートを受ければ、その分の費用がどちらにも発生します。
さらに、成年後見人に専門家を選定する場合には月額報酬を支払う必要もあります。このように、2つを利用する分、多くの費用がかかる点にも注意しておきましょう。
家族信託は、判断能力のあるうちに契約をすることで効力が発生します。
一方、任意後見制度は、契約自体は判断能力があるうちにできます。しかし、利用は判断能力を失った後に開始の審判を請求し、認められることで開始されます。
そのため、家族信託と任意後見制度を同時に開始することができない点にも注意が必要です。


実際に利用するまでは1万2千円〜2万円程かかるといわれています。
但し、医師の診断書が必要な場合には上記金額に加え、5万円〜10万円程度必要です。診断書の内容は医師によっては20万円程かかることもあります。
また、利用が始まった後の報酬は、明確に報酬額が決まっているわけではなく、2万円〜6万円程度となっています。後見人等の報酬額は、家庭裁判所の裁判官が決めます。
平成25年1月1日付で、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が「成年後見人等の報酬額のめやす」をだしています。
かかりつけの医師に相談してください。
上記にも記載のとおり、診断書は医師によっては20万円程掛かる可能性もあります。事前にいくらかかるのか聞いておきましょう。
実子が成年後見人になることを希望することは可能です。
しかし、誰が成年後見人になるのかを判断するのは家庭裁判所であるため、必ず成年後見人になれる保証はありません。
もし、実子が成年後見人を希望する場合は、申し立て時に「後見人等候補者」として実子を含め、家庭裁判所で面接を受けます。
面接などの過程を通して、裁判所から実子が成年後見人に適切だと判断されれば、成年後見人になることができます。
家族が成年後見人になるメリットは、家族ゆえの安心感がある点です。見ず知らずの弁護士や司法書士に管理されるよりは安心できるでしょう。
また、弁護士や司法書士などの専門家に報酬を支払う必要がなく、金銭的負担が軽くなることもメリットの1つです。
一方、家族が成年後見人になるデメリットは、トラブルが起きやすい点です。専門家ではなく報酬を受け取るわけでもない場合、成年後見人になった家族が横領や着服などをしてしまう可能性が考えられます。
さらに、裁判所に提出する書類などの準備が面倒で手が回らなくなる可能性があることもデメリットとして挙げられます。
通帳の紛失などにより本人の財産がわからない場合があるでしょう。その際は、申し立て時に記載する本人の財産目録にある「不明」にチェックを付けてください。
これにより、本人の財産がわからないことを家庭裁判所に伝えることができます。
成年後見制度に関する窓口は、公証役場や権利擁護相談窓口、裁判所、法テラス、日本公証人連合会など、多様な選択肢が用意されています。
相談要件によって窓口が変わることがあります。
厚生労働省が運営する「相談窓口のご案内|成年後見早わかり」や「成年後見制度についての相談窓口|裁判所」などのサイトを参考にしてみてください。
厚生労働省によって設置された成年後見制度利用促進専門家会議は、2021年12月に成年後見制度の運用改善などについて下記のように提言をしています。
成年後見人は、家庭裁判所が正当な事由があると認めた場合に限り辞任することができます。
正当な事由としては、成年後見人が病気や高齢のために十分に職責を果たせないことや、遠方へ引っ越すことで被後見人の財産管理が困難になることなどが挙げられるでしょう。
成年後見人の職務は被後見人の財産保護を目的としているため、成年後見人の都合で安易に辞任することは被後見人の利益に繋がりません。
お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください


法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。


本記事では、成年後見制度全般にわたり様々な視点から詳細に解説しました。銀行口座や保険の解約をするときなどでは、成年後見制度の検討が必要になります。
成年後見制度の問題点として親族が成年後見人に任命される可能性が低く、家族中心の財産管理が難しいことなどが挙げられます。
家族だけで柔軟な財産管理をしたい場合には、家族信託を検討することが良い選択に繋がるでしょう。
ファミトラでは、専門家と連携して家族信託のトータルサポートを行っています。無料で詳しい資料をすぐにお取り寄せ可能です。ぜひ1度資料をご請求ください。
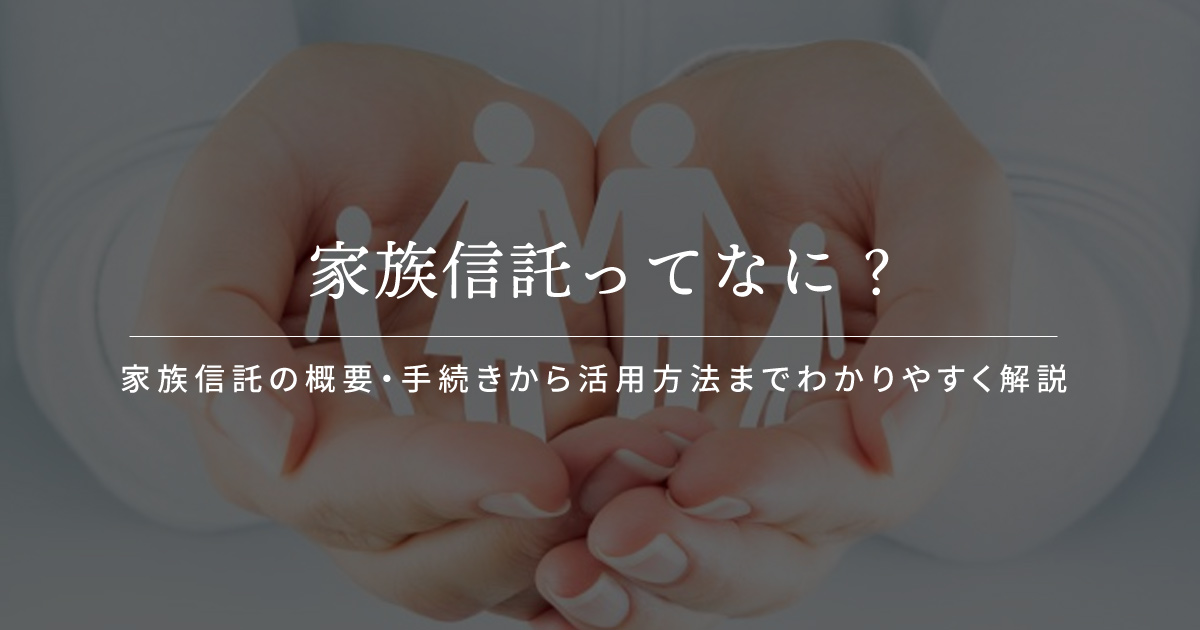
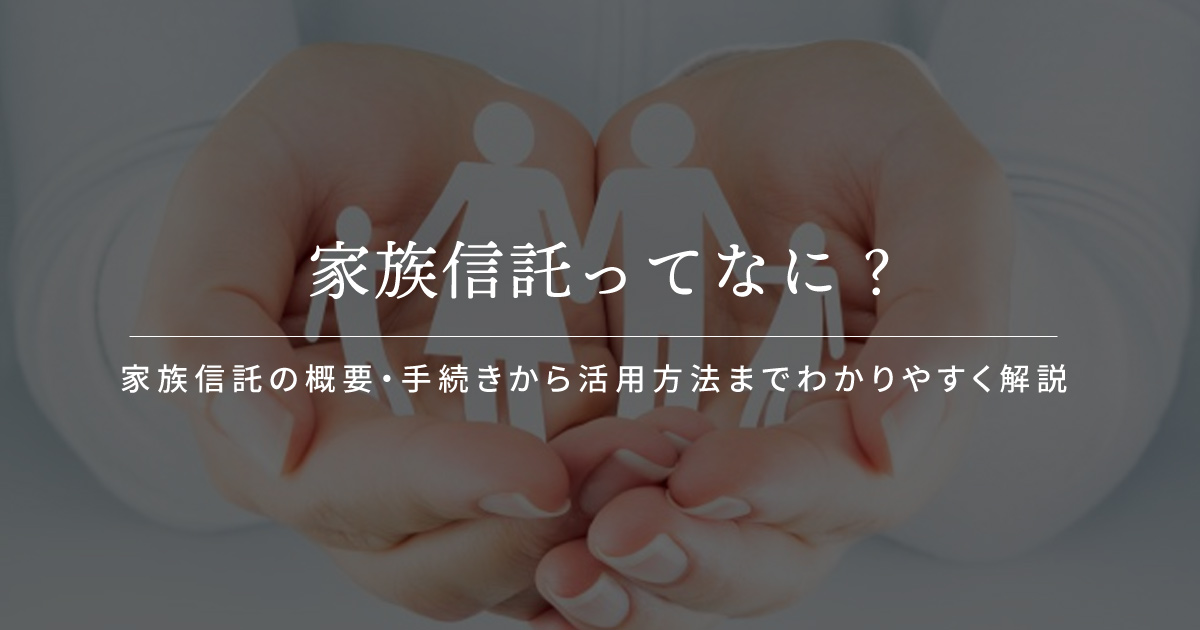
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!






家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!






PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。