
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

相続が発生すると、相続放棄・限定承認・単純承認のどれかを選択しなければなりません。
相続放棄することで不利益は生じないのでしょうか。
相続放棄にはメリットのみならず、デメリットも存在します。
相続放棄は予想外のトラブルを招く可能性もあるため、判断にあたっては慎重になる必要があります。
本記事では、相続放棄の概要とメリット・デメリットを様々な視点から解説します。相続放棄する際の注意点もわかりやすく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
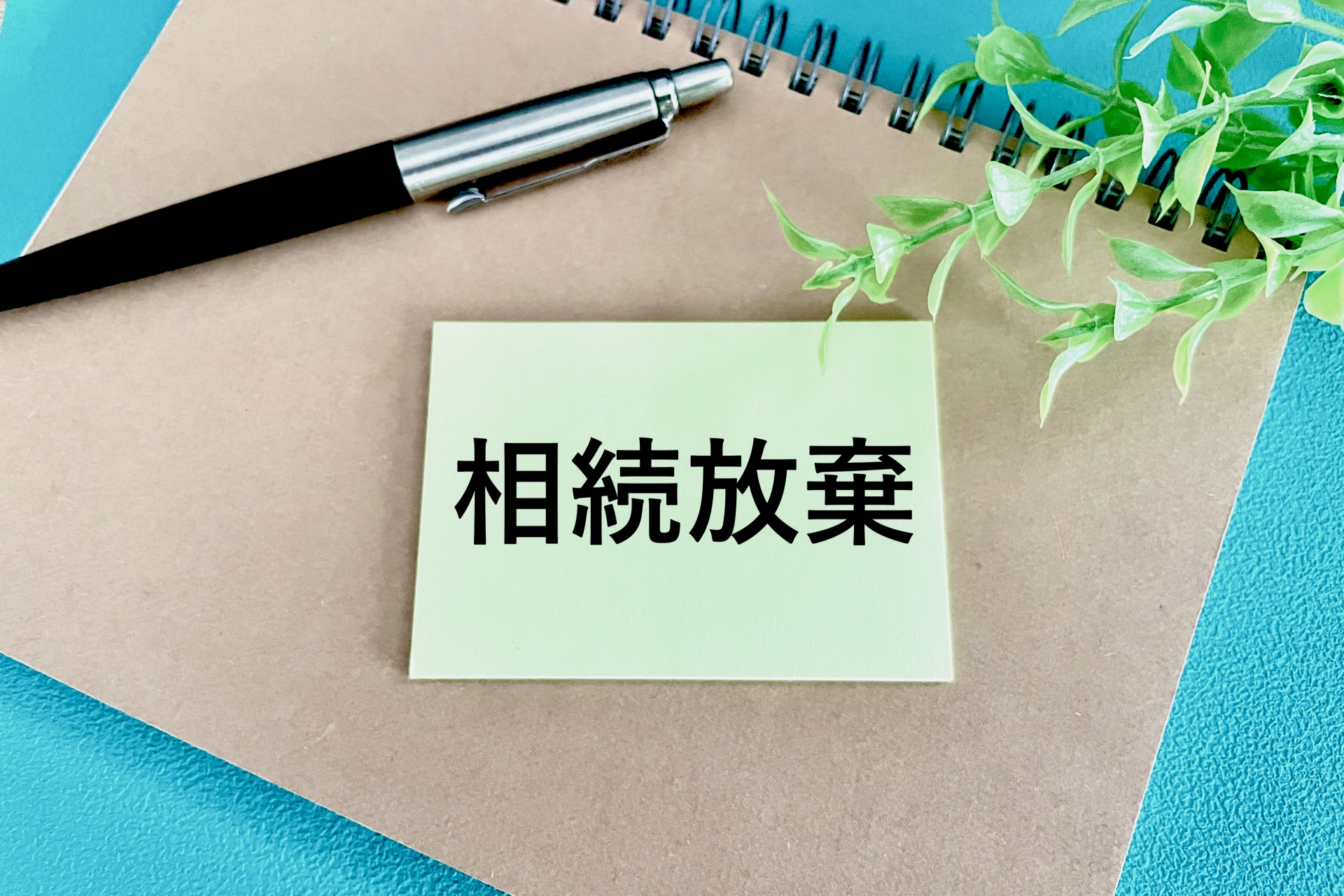
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
民法939条では、相続放棄について以下のように定められています。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
民法 第939条
つまり、相続放棄をした人は「その相続において最初から存在しなかった」という扱いになります。そのため、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、全て相続しないことになるのです。
財産の分け方を決めるために相続人同士で行われる遺産分割協議にも参加する必要はありません。

遺産放棄とは、遺産分割協議で自分に分配される財産を放棄することです。
遺産放棄と相続放棄は似ている言葉ですが、意味は異なります。
遺産放棄は相続人としての地位は失いません。そのため、他の相続人に対して遺留分減殺請求の権利を行使できます。遺産放棄は裁判所に対する手続きが不要で、期限もありません。
相続放棄では、相続人としての自分の権利を放棄し、はじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産だけではなくマイナスの財産である債務も引き継ぎません。
相続放棄には法的な手続きが必要で期限があります。
手続きは、必要書類を家庭裁判所に提出し実施します。期限は「被相続人が亡くなったこと」及び「自己が法律上の相続人となった事実」を知った時から3カ月以内です。

相続放棄を選択することで、様々なメリットが得られます。具体的には以下の3つがあります。
以上のメリットについて詳しく見ていきましょう。
相続は「争族」と表現されることがあるように、相続人間のトラブルや紛争をも引き起こす場合があります。
相続放棄をすると遺産分割協議や遺留分減殺請求などの相続手続きに関与しなくてもよくなります。他の相続人とのトラブルや紛争も、未然に回避できるのです。
これは相続放棄の大きなメリットといえるでしょう。
相続放棄をすると、自分に分配される財産だけではなく、債務も受け取りません。これは、マイナスの財産が多い場合や債務が不明確な場合に有効です。
例えば、被相続人が住宅ローンやカードローンなどの借金を抱えていたり、被相続人が経営していた会社が倒産したりする場合です。相続放棄をしなければ、ローンなどの債務もマイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。
相続放棄をすることで、被相続人の債務を引き継ぐ必要はなく自分の財産を守れます。
相続放棄をすると、自分に分配される財産は、他の相続人に移ります。これは、遺産を分割せずに特定の人に継承したい場合に有効です。
例えば、被相続人が家族経営の会社や農地などの事業資産を持っていた場合や、愛着のある不動産や美術品などの特別な財産を持っていた場合です。
承継させたい相続人以外の相続人が相続放棄をすることで、上記のような特別な財産を特定の相続人に承継させることができます。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

相続放棄には、メリットだけでなく、デメリットもあります。主に次の2つが挙げられます。
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
相続放棄をすると債務の引き継ぎがなくなりますが、同時に自分に分配されるはずの財産も受け取れなくなります。これは、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産もある場合にはデメリットです。
例えば、被相続人が現金や預金、株式や投資信託を持っていた場合や、生命保険などの受取権を持っていた場合です。
相続放棄はプラスの財産だけを受け取ることはできません。相続放棄をすることで、自分に入るはずだった財産を失うことになります。
相続放棄をすると放棄した人は相続人ではなくなるため、死亡保険金の非課税枠が使えません。
死亡保険金の非課税枠とは、被相続人が加入していた生命保険や団体信用生命保険から支払われる保険金に対して、一定額まで相続財産から控除できる枠のことです。
これは、相続人ごとに適用されるため、相続放棄をした人は保険金を受け取っても非課税枠を利用できません。
死亡保険金が多額の場合や相続税率が高い場合には特にデメリットです。相続放棄をすることで、死亡保険金に対して多くの税金を支払うことになります。

では、相続放棄を選択した方が良いケースとは具体的にどのような場合でしょう。
主なケースとして、以下の4つが考えられます。
1つずつ順に見ていきましょう。
被相続人が多額の借金をしていたなど、明らかに負債が多い場合は相続放棄を検討すべきでしょう。
前述したとおり、相続が発生すると相続人は被相続人が所有していたプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債・債務)も引き継ぐことになります。
マイナスの財産が少額であればプラスの財産から返済することができます。しかし、マイナスの財産がプラスの財産から返済することができない程に多い場合は、相続人が代わりに返済義務を負うことになるのです。
マイナスの財産の金額によっては、相続人の生活を維持することが難しくなる恐れもあるでしょう。被相続人の財産を調べた結果、明らかに債務超過である場合には、相続放棄を選択することをおすすめします。
相続争いに巻き込まれたくないような場合も、相続放棄は有効な手段となり得ます。
相続において、財産の分け方を巡って親族同士で争いが起こることは決して珍しいことではありません。
特に、相続人同士で仲が悪かったり疎遠であったりすると、遺産分割協議で揉め、相続トラブルに発展する可能性が高くなります。
遺産がそれほど多くない場合、「自分は何もいらないから話し合いに参加しなくてもいいや」などと考える方がいるかもしれません。しかし、遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければならないため、何もしなければ自動的に争いに巻き込まれることになるのです。
そのため、相続争いが発生する可能性があり「親族同士の揉め事に関与したくない」と強く望んでいる方は、相続放棄を検討すると良いでしょう。
被相続人が第三者の債務の連帯保証人になっているような場合も、相続放棄が有効な対処法となります。
連帯保証人とは、ある人が借金の滞納といった債務不履行を起こした場合に、代わりに債務を弁済する義務(連帯保証債務)を負う人のことです。
連帯保証債務は、主たる債務者がきちんと債務を支払いさえすれば、連帯保証人に対して請求が行われることはありません。しかし、もし債務者が返済しない場合、相続人が請求を受けるリスクを負うことになります。
相続放棄をすれば、連帯保証人としての責任を免れることができます。主債務者の支払い能力が低そうな場合や残債務の額が大きい場合には、相続放棄の選択を視野に入れると良いでしょう。

被相続人が事業を営んでいた場合において、特定の相続人に集中させて財産を承継したいといったケースでも、相続放棄が有用な手段となるかもしれません。
複数の相続人が事業に関わる財産を相続したとすると、意思決定をスムーズに行うことが困難になるなど、事業に支障をきたす恐れがあります。
そこで、被相続人の事業を承継する1人に財産を承継するために、他の相続人が相続を放棄することで、上記のような事態に備えることができます。
別の方法として、遺産分割協議の中で全財産を当該相続人に相続させる旨の遺産分割協議を行うということも考えられます。しかし、相続人の債権者が相続持分を差し押さえてくるといった事態に陥るリスクも拭えません。

相続放棄を選択した方が良いケースがあるのと同様に、相続放棄を選択すべきでないケースもあります。
それは、相続人のプラスの財産とマイナスの財産のバランスが不透明で、どちらが多いのかを比較しにくいようなケースです。
明らかに負債が多いと判断しにくい場面で相続放棄を選択した結果、資産の方が多いことが発覚し、相続人が損をしてしまうことも考えられるためです。
このような場合は「限定承認」という方法を選択した方が良いでしょう。
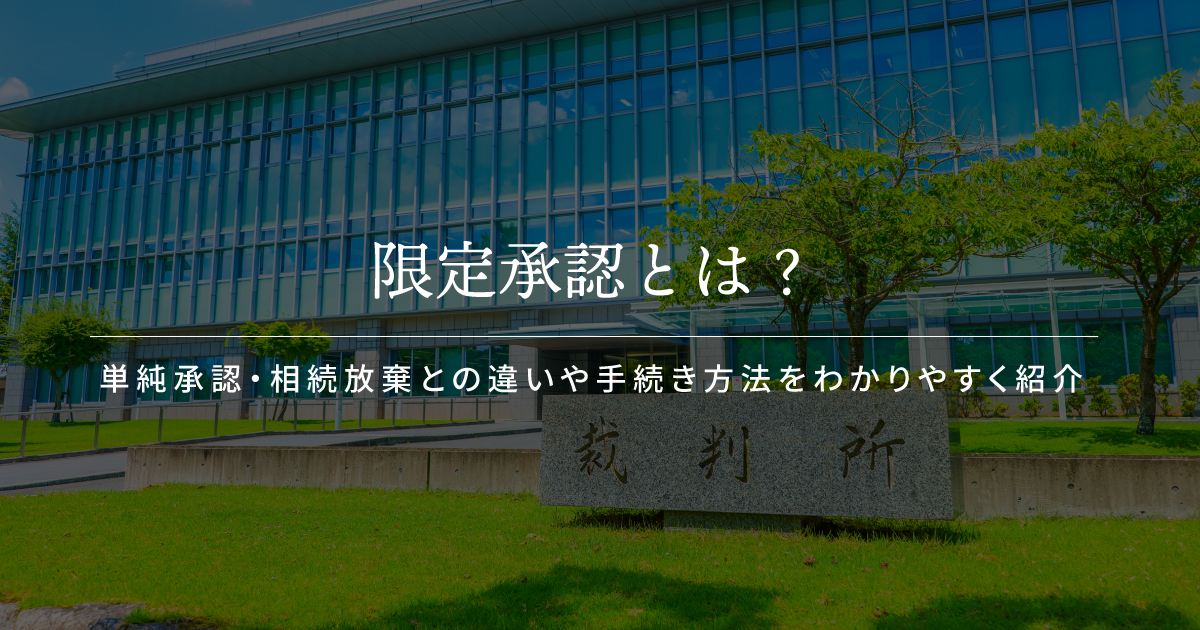
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度額として、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することです。
仮に被相続人のプラスの財産が500万円でマイナスの財産(借金)が1,000万円であった場合、限定承認を選択すると、プラスの財産と同額の500万円のみの返済で済むことになります。
つまり、限定承認を行うことによって、相続した財産以上の借金を弁済する必要がなくなるのです。
ある程度の返済が発生したとしても、自宅などの不動産を相続したいといったケースの他、被相続人の財産がプラスになるかマイナスになるか不透明なケースでは、限定承認の選択も検討しましょう。
法定相続人が複数いれば、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。
相続人のうち1人でも反対すれば、限定承認の手続きはできません。
相続人全員で家庭裁判所への申し立てが必要です。
相続人全員の意見が一致しなければ申し立てできない点は、限定承認を望む方には大きなデメリットです。
相続人間での意思の疎通が悪ければ、限定承認は難しい手続きといえます。
限定承認の手続き終了までに被相続人の不動産の売却処分などを行うと、相続財産を単純承認したものとみなされるので注意が必要です。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

単純承認とは、あらゆる相続財産の承継を承認する行為です。
単純承認の相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産もマイナスの財産も含めて、無条件で被相続人の財産を相続する行為を単純承認といいます。
父親が死亡して、唯一の相続人である長男が相続する例で考えてみましょう。
父親には預貯金や不動産などを含め、総額で3,000万円のプラスの相続財産があり、一方で500万円の借金もあります。
この事例において、長男が単純承認をした場合、3,000万円の財産と500万円の借金の両方を相続する形になります。プラス財産の3,000万円のみを引き継ぐわけではありません。
このように、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続する行為が単純承認です。
単純承認はマイナスの財産も引き継ぐため、被相続人に借金があった場合の単純承認は判断が難しくなります。
マイナスの財産を引き継ぎたくない相続人は、限定承認か相続放棄のいずれかの対応を求められます。

相続放棄には、相続放棄を選択できる期限(熟慮期限)が「相続の開始を知ったときから3カ月」と定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない
民法 第915条
相続放棄を行う場合、この期限内に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません(後述)。
もし3カ月を過ぎてしまうと、「単純承認」といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを受け入れたと見なされてしまいます。
相続放棄を検討している方は、早めに手続きに取り掛かりましょう。
なお、相続財産の調査が十分にできていないなどの理由で、3カ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない場合には、「期間伸長」の申し立てを行うことが可能です。
個別のケースによって異なりますが、期間伸長の申し立てによって延長できる期間は、一般的に1カ月〜3カ月程度だといわれています。
ただし、この申し立て手続きも、熟慮期間である3カ月以内に行わなければ認められないため、注意が必要です。
熟慮期間を超過しても相続放棄が認められるのは、以下のように特別な事情があるケースに限定されます。
普段から全く行き来がなく遠方に住んでいる相続人が、死亡時には知らされずに一周忌などの連絡を受けて、初めて被相続人の死亡の事実を知るようなケースです。

相続財産と固有財産のうち、相続放棄しても受け取ることが可能なのは固有財産です。
相続放棄しても受け取れる固有財産の代表的なものとして、生命保険の保険金・葬儀費用・祭祀財産・遺族年金の4つがあります。
以下で詳しく説明します。
生命保険の死亡保険金は保険金受取人の固有財産であるため、相続人の立場で相続放棄しても受け取ることが可能です。
ただし、みなし相続財産として相続税の課税対象になり相続税を払う必要があります。
相続放棄をした場合、相続人に認められている死亡保険金の非課税措置が受けられない点には、注意しなければなりません。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったという扱いになるためです。
被相続人の葬儀費用を遺産から支払うことは可能です。
一般的に社会から許容される金額であれば、被相続人の財産から支出しても相続を承認したことにはならないからです。
ただし、あまりに華美な葬儀の費用を遺産から支出したときには相続を承認したとみなされ、相続放棄できない可能性があるので注意が必要です。
系譜、祭具、墳墓の所有権については慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する旨が民法第897条に規定されています。
神棚や仏壇に見られるような先祖などを祀るものは、相続放棄しても祭祀財産として受け取ることが可能です。
これらの神棚や仏壇などを祭祀財産といいます。
遺族年金は相続財産でなく、遺族の固有財産であるため相続放棄しても受け取ることが可能です。
また、被相続人の死亡後に支給されていない「未支給年金」も遺族の固有財産であるため、遺族年金と同様に受け取れる財産の1つです。
それぞれの受給要件や受給対象者については、年金事務所で詳細を確認してください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

相続放棄を行う場合の手続きの流れについて紹介します。
相続放棄の手続きの主な流れは以下のとおりです。
1つずつ確認していきましょう。
相続放棄をすべきか否か判断するために、まず行うべきことが相続財産の調査です。
不動産や預貯金,有価証券などわかりやすい財産だけでなく、誰かにお金を貸しているといった借金や未払い金などの負債まで調べなくてはなりません。
十分な調査をしないまま相続をした結果、後になって莫大な負債が見つかるというケースも考えられるためです。
相続財産の調査自体は、相続放棄の手続きにおいて必須というわけではありません。しかし、上述のような事態を未然に防ぐためにも、慎重に行うことをおすすめします。
プラスの財産、マイナスの財産、それぞれの調べ方の一例は以下のとおりです。
| プラスの財産 | マイナスの財産 |
|---|---|
| 預貯金:残高証明書で確認 不動産:固定資産評価証明書で確認 株式:取引残高証明書 | 消費者金融からの借り入れ:JICC(日本信用情報機構) クレジット会社からの借り入れ:CIC(株式会社シー・アイ・シー) 銀行に対する借り入れ:KSC(全国銀行個人情報センター) |
なお、被相続人がどのような財産を所有していたか把握することが困難な場合には、弁護士をはじめとした専門家へ調査を依頼することも1つの手です。
相続財産を調査したら、次に申述先となる家庭裁判所を確認しましょう。
相続放棄を申述する管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地(死亡したときの住所)を管轄する家庭裁判所です。
以下のホームページより確認できます。
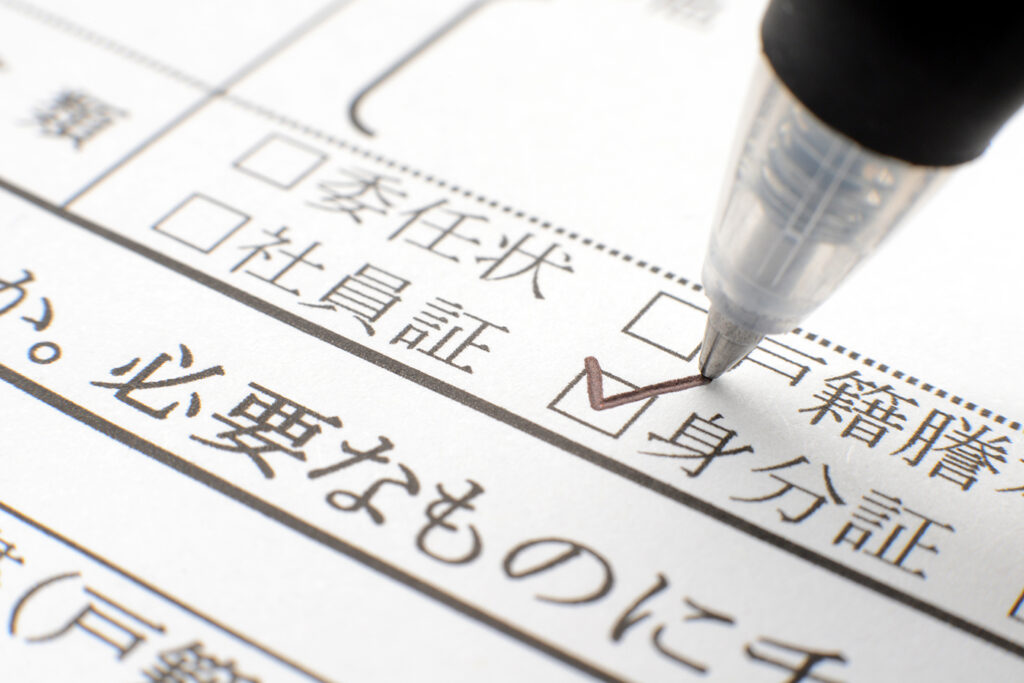
申述先を確認したら、必要書類を準備します。
相続放棄に必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)が被相続人とどのような関係であったかによって異なるため注意が必要です。
まず、全ての場合に共通して必要となる書類は以下のとおりです。
上記にプラスして必要な、申述人によって異なる書類は以下のとおりです。
相続放棄に必要な書類が集まったら、相続放棄申述書を作成しましょう。
相続放棄申述書の用紙は裁判所のサイトでダウンロードすることも、直接裁判所へ出向いて用紙を受け取ることも可能です。
相続放棄申述書は成人の場合と未成年者の場合とで様式が異なるので気を付けましょう。
また、相続放棄申述書の書き方(記載例)についても、裁判所のホームページで確認できます。書き方がわからなくて困っている方は、家庭裁判所のホームページ内で確認できる記載例を参考にすることをおすすめします。
相続放棄申述書を作成したら、家庭裁判所に対して必要書類と一緒に申述書を提出します。
このとき、書類の他に収入印紙や郵便切手なども必要となります。
家庭裁判所のホームページで確認できるため、事前に調べておくと良いでしょう。
なお、提出方法は以下の2つから選択することが可能です。
申述書と必要書類を提出すると、数日〜約2週間の間に、家庭裁判所から「照会書」が送付されることがあります。
これは、申述した相続放棄の内容について、家庭裁判所が申述人の意思を確認するためのものです。
一般的には以下のような事項を質問されます。
照会書と一緒に回答書が同封されているため、申述書の内容と矛盾のないよう回答し、署名捺印した上で返送しましょう。
ここできちんと回答しないと、相続放棄自体却下されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
回答書を返送し、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この書類の到着をもって、相続放棄の手続きは終了です。
この通知書は、相続放棄の申述が受理されたことを公的に証明する重要な書類となります。大切に保管しておきましょう。

相続放棄の手続きには、一般的に相続人1人あたり約3,000円〜約5,000円程度の費用がかかります。
費用の内訳は主に以下のとおりです。
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書に添付する収入印紙代 | 800円(申述人1人) |
| 連絡用の郵便切手代 | 500円程度(家庭裁判所によって変動) |
| 被相続人の戸籍謄本 | 750円 |
| 申述人の戸籍謄本 | 450円 |
| 被相続人の住民票 | 300円(市区町村によって変動) |
なお、上記は自身で手続きを行った場合の目安費用です。弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は、約3万円〜5万円程度かかります。
相続放棄の内容が複雑であるケースや、相続人・債権者とのトラブルを抱えているようなケースでは、確実に手続きをしてもらえる専門家に相談することがおすすめです。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄が受理されたことを第三者に証明できる書類です。
家庭裁判所の窓口で申請する場合は、備え付けの申請用紙で交付申請します。1件150円の収入印紙が必要です。
申請時には、印鑑と受理通知書や運転免許証などの本人確認書類を持参しましょう。
郵送で申請する場合は、受理した家庭裁判所に収入印紙の他に返信用切手を同封して申請します。必要な場合には再発行も可能です。
一方で「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄を受理したことを家庭裁判所が相続放棄する人に知らせる通知書です。相続放棄手続き完了後に裁判所から送付され、再発行はできません。
相続放棄申述受理証明書は、金融機関に相続放棄したことを証明したり不動産の名義変更する場合に必要となることがあります。
言葉が似ている「相続放棄申述受理証明書」と「相続放棄申述受理通知書」の違いを押さえておきましょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
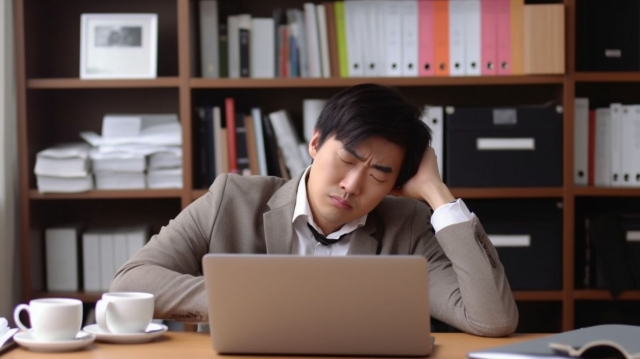
相続放棄には一定の条件や手続きが必要です。条件を満たさない場合には相続放棄ができないケースがあります。
相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなったこと及び自己が法律上の相続人となった事実を知った時を起点とし、3カ月以内の手続きが必要です。期限を過ぎてしまうと、単純承認が成立してしまい、相続放棄ができません。
相続財産を処分した場合も単純承認が成立します。処分とは、財産の現状や性質を変える行為で、遺産を売却したり消費したりする行為です。遺産の一部でも処分してしまうと、相続放棄ができません。
被相続人の死亡に伴って、家族などの間で形見分けをするケースがあります。
資産価値のある着物や高級時計などの形見分けをしたり、自動車を形見分けと称して譲り受けるときなどは十分に注意しましょう。
経済的価値の高い品物の形見分けを受けることで、相続を承認したとみなされる可能性があるためです。
換価価値のあるものの形見分けをするときには、専門業者に査定してもらうなど資産価値がないという客観的資料を残すことが賢明といえます。
必要であれば専門家に相談するようにしましょう。
相続放棄には、申述書や必要書類を家庭裁判所に提出することが必要です。書類に不備や不足がある場合は受理されません。書類の準備や記載は慎重に行いましょう。

相続放棄を行う際の心構えについて確認しましょう。
相続放棄のポイントは次の通りです。
期限を過ぎてしまったり、遺産の管理の仕方を間違えたりすると、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
相続放棄で失敗しないためには、期限を意識することが大切です。
相続放棄には期限が設定されているからです。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。
期限経過後の相続放棄は、原則として認められず、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認が確定すると、被相続人のマイナスの財産も引き継ぐことになります。
例えば、死亡した父親に借金があった場合は、父親の借金を背負う形になります。
借金を上回る額のプラスの財産が父親にあれば、トータルでは損をしないため、単純承認とみなされても問題ないかもしれません。
しかし、プラスの財産が父親にない場合は、借金だけを引き継ぐことになります。
相続にはマイナスの財産を引き継ぐリスクもあるので、相続放棄の期限を意識した早めの行動が大切です。
相続放棄で失敗しないためには、適切な遺産の管理も重要なポイントです。
遺産の管理の仕方を間違えると、単純承認をしたとみなされる恐れがあるからです。
相続財産について行った行為が「相続財産の全部又は一部を処分をしたとき(民法第921条)」に該当すると、相続をする意図がなかったとしても、単純承認をしたとみなされる可能性があります。
例えば、相続財産に関する以下の行為は「相続財産の全部又は一部を処分した」と認定される恐れがあります。
単純承認とみなされないためにも、相続発生後の遺産の管理には慎重な態度で望まなければなりません。
相続放棄で失敗したくない方は、専門家への依頼を検討しましょう。
相続放棄の判断は、適切な財産調査がポイントとなります。
財産調査が正確に行われないと、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できず、相続放棄の判断を誤ってしまう可能性が高くなるからです。
財産調査には、思いのほか時間がかかります。財産調査に時間がかかってしまうと、相続放棄の期限が過ぎてしまい、単純承認したものとみなされるかもしれません。
財産調査以外にも、単純承認とみなされる行為に該当するのか判断が難しい場面に遭遇することもあります。
相続放棄で失敗したくない方は、専門家への依頼を検討しましょう。

相続放棄の前後にしてはいけないことの具体例を紹介します。
ここで紹介する行為は、財産の処分(民法第921条第1号)に該当する行為です。
処分行為に該当すると、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
処分行為に該当するかの判断は、一般の方には難しい場合もあるため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
相続があった場合、被相続人の預金の取り扱いには注意しましょう。
預貯金の引き出し、口座の解約・名義変更などの行為は、相続財産の処分に該当する可能性があるからです。
相続財産の処分は、法定単純承認として、相続を承認したとみなされる可能性のある行為です。単純承認が確定してしまえば相続放棄はできなくなります。
相続放棄を検討する場合は、法定単純承認への該当を避けるため、被相続人の預金はそのままにしておいた方が良いでしょう。
なお、もし預金を引き出してしまった場合は、預金の消費を避けた上で、元の口座に戻すか、個人の口座とは別で管理するようにしましょう。
相続放棄を検討する場合、実家の解体・売却には慎重になる必要があります。
相続財産である不動産の解体・売却は、財産の処分行為に該当する可能性があるからです。
財産の処分行為に該当すると、相続放棄は難しくなります。
従って、相続放棄予定の方は、実家の解体・売却を避けるようにしましょう。
なお、相続した実家の老朽化が進んでおり、取り壊しの必要性が高いと感じる場合もあるかもしれません。
その場合でも、取り壊しは控える方が無難といえます。
取り壊しまでしなくとも、ブロック塀で補修するなどの代替措置もあります。補修であれば保存行為に該当する可能性が高く、保存行為にとどまるのであれば問題ありません。
ただし、処分行為か保存行為かの判断は難しい場合もあります。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄を検討する場合は、賃貸借契約の解約も控えましょう。
被相続人が契約者となっている賃貸借契約を解約してしまうと、財産の処分に該当する可能性があるからです。
賃借権は資産価値のある債権であり、相続財産として扱われます。つまり、賃貸借契約の解約は、財産の処分に該当する可能性が高いということです。
状況によっては、あくまで保存行為に過ぎず、解約をしても処分行為があったと扱われない可能性もあります。しかし、処分行為か保存行為かの判断は難しいので、解約にあたっては慎重になった方が良いでしょう。
判断に迷った際は、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。
遺品の整理も財産の処分に該当する可能性があります。
遺品の整理とは、被相続人が所有していた物を整理する行為です。
不要な物だからという理由で安易に売却したり、贈与したり、または破棄したりすると、財産の処分行為に該当し相続放棄ができなくなるかもしれません。
遺品整理の全ての行為が、財産の処分に該当するわけではありません。経済的価値の低い日用品の整理は、財産の処分にあたらない可能性が高いといえます。
また、単なる片付けや保管目的の整理も財産の処分に該当しません。ただし、売却を目的とした整理は「処分」とみなされる可能性があります。
遺品の価値の判断は一般の方には難しいかもしれません。遺品処分の判断に迷う際は、専門家に相談しましょう。
遺産を用いた借金の支払いについても慎重になる必要があります。
被相続人名義の借金の支払いであっても、処分行為に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
期限到来済みの借金に関しては、被相続人の財産で支払ったとしても、保存行為として処分に該当しない余地があります。
一方、支払期限まで十分な日数が残されていたり、支払いを急ぐ必要がなかったりするにもかかわらず借金を支払う行為は、処分とみなされる恐れがあります。
仮に、借金を支払わなければいけない事情がある場合でも、遺産からではなく、相続人個人の財産から支出した方が安全です。
被相続人の借金の支払いに関して判断に迷った際は、専門家に相談しましょう。
入院費の支払いについても、借金の支払いと同様の問題が生じます。
被相続人の遺産を使って入院費を支払う行為は、処分行為に該当し、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
入院費支払いの必要がある場合は、遺産を使わず、相続人の財産から支出した方がリスクは低いといえます。
相続人の財産から支出する場合は、領収書の宛名に注意しましょう。
領収書の宛名を被相続人宛てにしてしまうと、個人の財産から支出したにもかかわらず、被相続人の財産で支払ったと取られてしまう可能性があります。
例えば、相続人Aが自分の財布から被相続人の入院費を支払った場合は、領収書の宛名を「A」と記載してもらうようにしましょう。
携帯電話の解約についても注意する必要があります。
携帯電話の解約も、賃貸借契約と同様の趣旨で、解約行為が財産の処分に該当する可能性があるからです。
解約に際して違約金が発生するなど、解約行為が相続財産に影響を与える場合は特に注意しましょう。
契約を継続をすると、携帯電話料金が発生し続けるため、無駄な支出が発生する結果になります。それゆえ、早急な契約解約を希望する相続人もいるでしょう。
しかし、処分行為に該当し相続放棄ができなくなるリスクを考えた場合、解約は避けた方が安全です。
解約の目的や状況次第では保存行為に該当する余地もありますが、その判断は一般の方には難しいかもしれません。携帯電話の解約を検討する際は、事前に専門家に相談することをおすすめします。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

相続放棄や限定承認の有無について、家庭裁判所に照会する方法があります。
自分より相続が先の順位の相続人の相続放棄や限定承認の申述の有無を照会可能です。
債務の多い親族の死亡によって、自身が相続人になる可能性がある場合には照会制度を利用すると良いでしょう。
以下では、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会制度を利用可能な方と申請方法を紹介します。
相続放棄・限定承認の申述の有無について、照会制度を利用できるのは以下の方です。
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会制度を利用する方は、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所に照会の申し立てが必要です。
被相続人の死亡時の住所地は、市区町村が発行する住民票の除票や戸籍の附票で知ることができます。
照会の申請にあたっては、相続人及び利害関係者のいずれも「照会申請書」と「被相続人等目録」の提出が必要です。
照会申請書は、照会先の家庭裁判所のホームページからダウンロードするようにしましょう。
家庭裁判所により、書式が異なることがあるためです。
調査にあたっては、被相続人等目録に記載した氏名にもとづいて行われますので正確に記載しましょう。
必要な添付書類は以下のとおりです。
申請者が相続人か利害関係者であるかにより、若干異なります。

最後に、相続放棄を検討する上で事前に知っておくべき注意点を紹介します。
主な注意点は以下のとおりです。
1つずつ順に見ていきましょう。
相続放棄の申し立てが受理された後は、原則として撤回することができません。
たとえ熟慮期間である3カ月以内であっても、一度行った相続放棄を取り消しすることは不可能です。
これは、相続放棄の申述が受理された後の撤回を認めてしまうと、他の相続人や利害関係者に不測の損害を与えてしまう可能性があるためです。
ただし、以下のように例外的な事由がある場合には、申述が受理された後であっても撤回や取消しが認められる場合があります。
相続放棄の撤回、取り立ての申し立ては裁判所に対して行う必要があります。申立期間も「追認できるときから6カ月以内」「相続放棄から10年以内」と定められているので注意しましょう。
いずれにしても、相続放棄は「後から高額な財産があることがわかったから取り消したい」といった理由で取り消すことはできません。慎重に財産を調査した上で利用を検討することが大切です。
被相続人の生前に、前もって相続放棄をすることはできません。
相続放棄は家庭裁判所に申述することで初めて成立します。家庭裁判所が生前の相続放棄を受け付けていないためです。
そのため、相続人の中でも、特定の人には相続をさせたくないという場合は、遺言書を作成するなどの対策を講じると良いでしょう。
ただし、相続では相続人に最低限保証された相続割合である遺留分があります。全ての財産を相続させたくない場合には、遺言書の作成と併せて遺留分の放棄をしてもらう必要があります。
相続放棄の申し立てが受理されると、相続権は次順位相続人に移ります。
しかし、家庭裁判所から次順位の相続人に対して相続放棄をした旨の通知は届きません。
仮に被相続人に借金がある場合、債権者からの督促状などをきっかけに、突如自身が相続人になったことを知るといったトラブルに発展するケースもあるのです。
このようなトラブルを未然に防ぐために、次順位に相続人がいる場合、自身の相続権が移ることや、被相続人の資産・負債の状況などを事前に通知するようにしましょう。
相続財産に共有財産があると、相続人や相続放棄の有無によって、手続きが複雑になることがあります。時間と費用もかかります。
相続人全員が相続放棄し、相続人がいることが明らかではない場合、相続財産は相続財産法人として管理されます。この場合、相続財産の移転登記をするには相続財産清算人を選任することが必要です。
相続人の一部が相続放棄しなかった場合には、放棄しなかった相続人同士で遺産分割協議を行って共有持分の取得者を決めます。遺産分割協議が成立しない場合、法定相続分で共有持分を取得します。
共有財産の相続は、様々な問題を引き起こす可能性があります。遺言書や生前贈与などで事前に対策をすることが望ましいです。
事例:父A・子B・孫CがいてAが死亡し、Bが相続放棄した場合
Aに多額の負債があるためにBが相続放棄をした場合であれば、CがBに代わりAの財産を代襲相続することはありません。
代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡したときなどに相続人の子が代わって相続することです。
相続放棄によりBは最初から相続人ではなかったことになり、BからCへの代襲相続原因そのものがなくなります。
上記の事例でBが先に死亡してCがBの相続を放棄し、その後Aが死亡した場合
Bの相続について相続放棄をしたCは、Aの相続について代襲相続をする権利は失われません。
結論として、CはAの財産を代襲相続することが可能です。
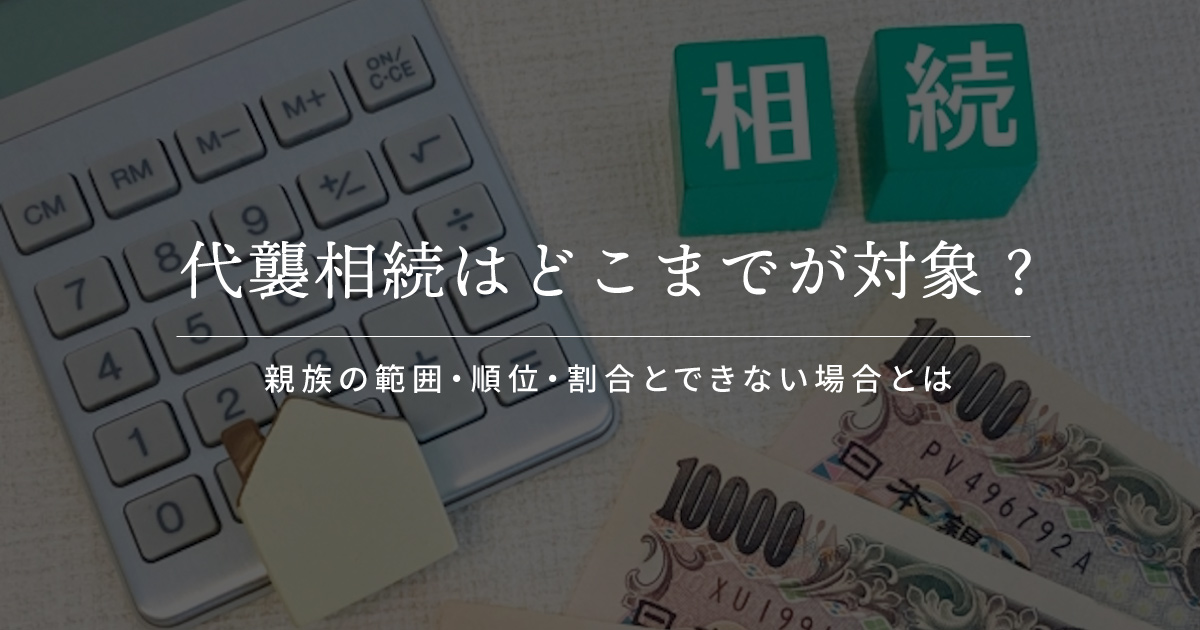
2023年4月から民法第940条が改正され、相続の放棄をした者の義務として財産管理制度の見直しが行われました。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 | 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 |
改正前には空き家や山林などを相続放棄しても、以下の場合などは不動産の管理義務が残っていました。
相続放棄制度の「相続による不利益の回避」の趣旨にそぐわない可能性があったといえます。
今回の改正によって、相続放棄した財産を現に占有している場合に限り、相続放棄後も保存義務を負うことになりました。
引用:民法940条第1項
相続放棄の手続きは、死亡した被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
申述の方法は、家庭裁判所に出向いて行う方法と、郵送で行う方法があります。
家庭裁判所が近い方はどちらの方法でも可能ですが、家庭裁判所が遠方にある方や裁判所が開いている平日の昼間に時間が取れない方は郵送で申述するのが便利です。
相続放棄の申述書を家庭裁判所に送付すると、3~4週間後に「照会書」が届きます。
「照会書」は、相続人の相続放棄の意思が本人の意思によるものなのか、また、意思の変更はないのか確認するものです。
照会書を家庭裁判所に送り返してから、3~4週間後に受理されます。
相続放棄の手続きを郵送で行う手順は以下の通りです。
なお、複数の相続人の書類も一括して送付できます。
その際、共通の書類は1通で済むので、必要書類とともに、800円分の収入印紙、家庭裁判所からの返信用封筒と切手(500円前後)を同封します。
郵送の形式は普通郵便でも構いませんが、配達記録の残る書留や簡易書留、レターパックなどを使うと良いでしょう。
不動産の相続放棄は査定結果を見てから決めるべきです。
相続放棄は一度受理されると撤回できません。
不動産の場合、一般の方では価値がわかりにくいため、相続放棄をしてしまった後に、相続するはずだった不動産に想定以上の価値があったことが判明しても取り返しがつきません。
そこで、不動産の評価額をきちんと査定してから、相続財産の総額がプラスなら放棄をせずに相続し、相続財産がマイナスになる場合は放棄をすれば良いのです。
不動産の査定には時間がかかることも多いので、相続が開始したらまず、不動産の査定を依頼しましょう。
全員が相続を放棄した場合、相続財産は最終的に国に帰属します。
そのまま放置したのでは、所有者のいない土地が増えてしまうからです。
ただし、相続人は放棄した土地を手放してそれで終わりではなく、相続人は放棄した土地を管理する義務があります。
相続人がこの義務から逃れるためには、相続財産管理人(相続財産清算人)選任の申し立てを行うことが必要です。
相続財産管理人(相続財産清算人)の選任は、家庭裁判所が職権で選任するわけではないので、利害関係人が行う必要があります。

相続するか否かは相続財産がプラスかマイナスか確定していれば、判断するのも容易ですが、実際には相続財産の総額がわからないケースが多くあります。
相続放棄をするべきか否か判断できないときは、限定承認制度を利用する方法と専門家に相談する方法があります。
以下で詳しく解説します。
限定承認とは、プラス財産の限度で遺産を相続することです。
後から借金などが出てきた場合、プラス財産で弁済しきれなくてもそれ以上の責任を負う必要がない、また、居住用の家など特定の財産を先買権を使って残すことができるなどのメリットがあります。
一方、相続放棄と違い、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをしなければならないため、相続人の中に1人でも反対する方がいると、限定承認はできません。
また、手続きが煩雑で専門的な知識がいるため、一般の方には難しいこともデメリットです。
なお、限定承認の申し立ては、相続があったことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。
相続は高額な財産と人間関係が複雑に絡み合います。
また、相続開始を知った時から3カ月と、相続放棄までの期間は短い傾向にあります。
そのような状況の中、相続すべきか否かを1人で決めるのは難しいかもしれません。
そのようなときは、相続の専門家に相談してみましょう。
以下に、相続の相談をできる7つの専門家を解説していきます。
法律の相談で真っ先に頭に浮かぶのは弁護士ではないでしょうか。
弁護士は取り扱う業務の幅が広く、刑事事件専門の弁護士や、企業法務専門の弁護士もいます。
相談する際にはホームページ等で、相続専門の弁護士を選びましょう。
弁護士であれば、相続全般の相談に応じ、適切なアドバイスももらえるでしょう。
また、相続人間で争いがある場合には交渉をしてもらえます。
無料相談を開催している事務所も多いので、まず無料相談をしてみて自分に合うようであれば正式に依頼しましょう。
有料相談では、30分で5,000円程度と、他の士業に比べて割高な傾向にあります。
司法書士は登記の専門家ですが、相続を専門に扱っている司法書士も多くいます。
司法書士も相続に関して全般的に相談に乗ってもらえます。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合、最終的に名義変更になれば司法書士に依頼することになるので、そのまま名義変更の登記まで完了します。
司法書士に相談する場合は、ホームページ等で相続専門の司法書士を選びましょう。
初回無料の事務所も多く、有料相談に移行しても1時間で5,000円程度です。
税理士は税の専門家ですが、相続を専門に扱っている税理士も多くいます。
相続財産が高額になれば、相続税の手続きをする必要がありますが、最初から税理士に相談していれば、相続税額の計算や相続税の手続きまで行ってもらえます。
ただし、気をつけたいのが、税理士の全てが相続に詳しいわけではないということです。
相談の際には、ホームページで相続を扱っているのか確認してからにしましょう。
有料相談に移行すると、30分で5,000円程度のところが多い傾向にあります。
法テラスは、全国のどの地域でも均一な法的サービスを受けられることを目的とした公的機関です。
法的なトラブル解決のための情報提供や、経済的余裕のない方のトラブル解決のために、無料相談の開催や弁護士・司法書士の費用の立替えなどを行っています。
相談は弁護士や司法書士が担当し、30分の無料相談を3回まで受け付けてくれます。
弁護士に依頼したいけど、どの弁護士にするか迷っている方や弁護士費用の捻出が難しい方は利用してみると良いでしょう。
ただし、担当した弁護士が相続を扱っているかはわからないので、その点は気をつけてください。
市役所や区役所では、定期的に法律相談を開催しているところがあります。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士等が相談を受けています。
無料であることはメリットですが、1件あたりの時間は30分ほどで途中で打ち切られることがあることと、予約が数カ月待ち等、使い勝手が良いとはいえません。
現在では、多くの士業事務所が初回無料の相談を受け付けています。
ホームページやネットでの評判を参考にして、各士業の無料相談を受けることをおすすめします。
相続放棄は家庭裁判所に申述します。
相続手続きについてわからないことがあれば、家庭裁判所に相談すれば大抵のことは答えてもらえます。
ただし、答えてもらえるのはあくまで手続き上のことであって、どのように遺産を分けるとか相続人間で揉めているのでどうしたらいいかなど、相続の内容に関しては答えてもらえません。
家庭裁判所に相談するのは手続きのことだけにして、相続の内容に関しては、弁護士等の専門家に相談しましょう。
上記の他の相談先に、弁護士や司法書士などの士業や一般の企業が運営している相談センター・相談室があります。
前者では、法律の専門家が対応してくれますが、後者では各士業と提携してるところがほとんどで、各分野の専門家が対応してくれます。
これらのセンターは、メールでの質疑応答にも対応しているなど、士業の事務所に比べて気軽に相談をしやすいのが特徴です。
一度、無料相談を受けてみて、自分に合いそうなら依頼しましょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

相続放棄をしても、自分の子に相続権が移ることはありません。
相続放棄をすると、相続権が次の順位の法定相続人に移ります。
例えば、親の相続で子が相続放棄をした場合、子の相続権は次の順位の法定相続人である祖父母(親の両親)に移るのです。
そのため、相続放棄をしても、自分の子に相続権は移りません。
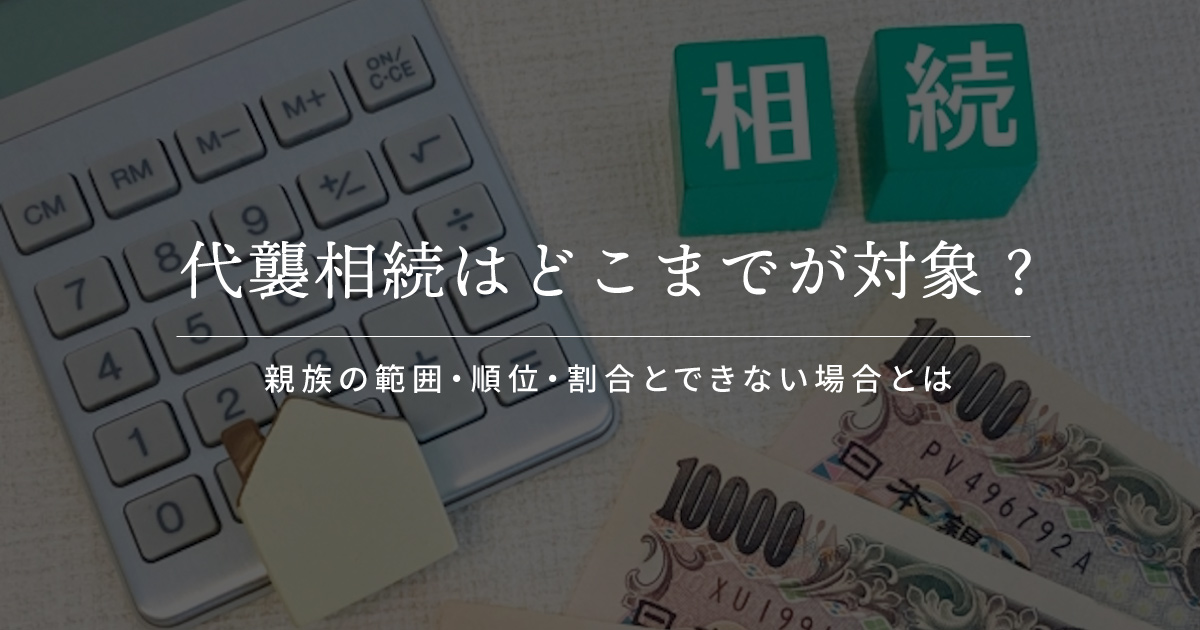
最終的には国に帰属します。
法定相続人には相続の順位があります。
第1順位の法定相続人が相続放棄をすれば、相続権は第2順位の法定相続人に移転するのです。
全ての順位の法定相続人が相続放棄をし、相続人がいることが明らかでない状態になれば、相続財産は相続財産法人とみなされます。
法人化された相続財産は、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が管理することになります。
相続財産清算人によるその後の清算手続きで処分されずに残った相続財産は、国庫に帰属するのです。
「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡と自分が被相続人の相続人であることの両方を知った時という意味です。死亡日とは必ずしも一致しません。
例えば、被相続人が死亡した日と同日に、死亡の事実と自分が相続人であることを知った場合は「相続の開始があったことを知った時」は死亡日と同日です。
しかし、被相続人が死亡した日から数日後や数カ月後に、死亡の事実や自分が相続人であることを知った場合は「相続の開始があったことを知った時」は死亡日よりも後になります。
自分で通知しなければ、基本的に債権者には通知されません。
債権者に対して、自分が相続放棄をした事実を通知する義務はありません。しかし、通知しない場合は、債権者から返済を求められる可能性があります。
債権者から返済を求められた場合、家庭裁判所から発行される相続放棄申述受理通知書を提示し、相続放棄をしたことを証明しましょう。
通知書を提示すれば債権者からの取り立ては止まる可能性が高いです。しかし、債権者から異議申し立てや訴訟を起こされる恐れもあります。訴訟に発展した場合には、専門家に相談することをおすすめします。
通知書を債権者に渡すことは義務ではありませんが、トラブルを避けるためには、相続放棄が完了したらコピーを郵送するなどして、相続放棄したことを伝えておく方が良いでしょう。
準備を始めて相続放棄の申述書が受理されるまで約3カ月かかります。
必要書類の取得と申述書の作成が必要なため、準備だけでも約1カ月はかかるといえます。
必要書類では戸籍謄本や住民票除票などを準備しなければなりません。
被相続人の死亡したときの住所地が遠方であれば、郵送請求になることも時間がかかる要因の1つです。
相続放棄の申述書を提出して約3週間から1カ月で家庭裁判所から照会書が郵送されて、照会書返送後に約3週間から1カ月で受理されることが多いです。
ただし、書類内容や添付書類に不備があればより多くの期間がかかります。
相続放棄をした人により、相続税の基礎控除額が減ることはありません。
相続放棄をすると最初から相続人がいなかったものと扱われるものの、相続税の計算上は相続放棄がなかったものとして計算されるためです。
相続税の基礎控除額は次式により算出します。
相続税基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記のとおり相続人の数に変わりがないと計算されるため、相続税の基礎控除額が減ることはありません。
相続放棄後に新たな債務が発覚したとしても、すでに行った相続放棄の効力には何ら影響を与えません。
相続放棄は、被相続人のすべての債務の承継を拒む手続きです。相続放棄の対象には、放棄時に発覚していなかった被相続人の債務も含まれるのです。
そのため、相続放棄後に新たな債務が発覚したとしても、履行する必要はありません。
債権者から債務の履行を求められたとしても、相続放棄申述受理証明書などを示して、相続放棄をしたから応じられない旨を伝えればよいでしょう。

本記事では、相続放棄の概要とメリット・デメリット、相続放棄の手続き方法、注意点をわかりやすく紹介しました。
相続放棄を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続放棄には期限が設けられており、期限が過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。また、相続後の行為が処分行為に該当した場合、期限内であっても、相続放棄ができなくなります。
相続放棄にはデメリットも多いため、相続放棄を選択する前に慎重な検討が必要です。専門家に相談することをおすすめします。
ファミトラでは、お客様に寄り添って個々のケースに応じた相続対策への提案を行っています。専門家と連携しているため、皆様の様々な疑問への回答が可能です。
相続に関するお悩みや疑問のある方は、24時間メールフォームから無料相談を受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!



家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!



PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。