
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

家督相続を昔の相続制度だと考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、現代の相続においても、家督相続が問題となるケースはあるのです。
そこで本記事では、家督相続の制度概要や現在の遺産相続との違い、現代において家督相続が問題となるケースなどを紹介します。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
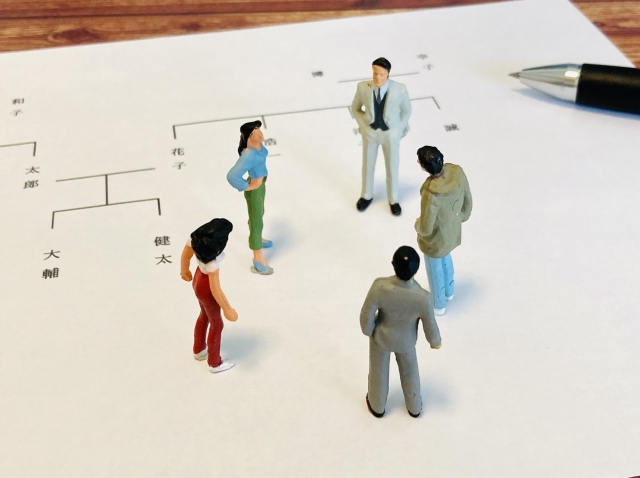
まず、家督相続の概要について解説します。
家督相続がどのような制度か、いつまで使われていた制度なのかを見ていきましょう。
家督とは、明治時代に始まり戦後間もなく廃止された、家制度における家族の代表者(戸主)としての権利や地位のことです。
家制度において戸主には家族の居場所を指定したり、婚姻などの身分行為を許可したりする強い権限が与えられていました。
そのため家督には、単に家の財産に対する権利という意味だけではなく、家の主人として家族を統率する権限、地位という意味もあるのです。
家督相続とは、長男が全ての財産を相続する旧民法の制度です。
「戸主」が死亡したり隠居したりすると、長男が全ての財産を相続して「戸主」となります。
その「戸主」が死亡したり隠居したりすると、次の長男が全ての財産を相続します。
そのため、配偶者や次男、長女、次女、兄弟姉妹など、長男でない人は基本的に相続できない制度です。
男子が生まれず女子しか子どもがいない場合は、長女が家督相続人となり長男も長女もいない場合は、前戸主が家督相続人を指定できるようになっていました。
家督相続の制度が誕生したのは明治時代であり、その内容は江戸時代の相続慣習の影響を強く受けています。
江戸時代後半の武家社会では、長男に一家の財産やあらゆる権限を承継させる相続慣習が根付いていました。
「家」を後世に安定的に承継し存続させるという観点からは、家の財産や権限を1人に集中させることが望ましかったためです。
長男が戸主として家のあらゆる権限を承継する家督相続は、こうした江戸時代の相続慣習を背景に誕生しました。
家督相続の対象は、戸主が持つ権利・義務であり、家の財産だけではありません。
例えば、戸主が持つ主な権利は以下のとおりです。
また、戸主の持つ主な義務としては、家族に対する扶養義務があります。
このように家督相続は、単なる家の財産を承継する制度ではなく、一家の主人としての権限、立場を承継させる手続きなのです。
家督相続は旧民法上の制度です。旧民法が相続制度で効力を発揮していた、昭和22(1947)年5月2日まで使われていました。
昭和22年5月2日までに亡くなった方には家督相続の制度が適用され、民法改正以降に亡くなった方には家督相続は適用されません。
昭和22年まで、すなわち戦前は「家」制度が当たり前であり、家のトップである「戸主」が財産を相続していました。
しかし、「家」中心の生活から「個人」中心の生活に移行し、それに沿って民法が改正され、相続についての制度が大きく変更されました。
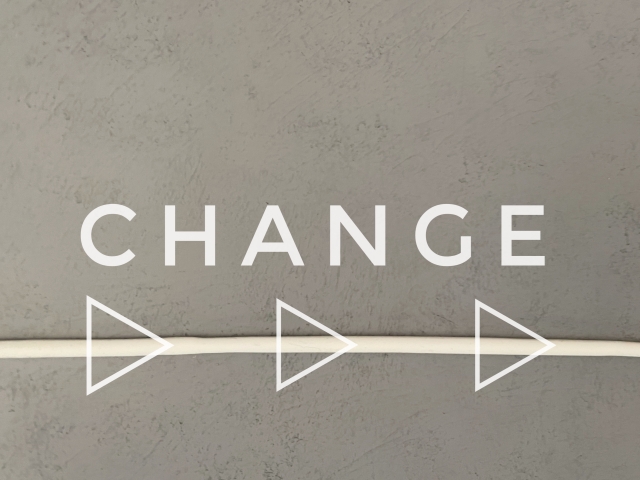
家督相続の廃止により、配偶者と子供(直系卑属)や両親(直系尊属)などによる分割相続が基本になりました。
また、分割相続が基本となったことから、相続人間の相続分も別途定められました。
家督相続廃止後の相続人や相続分などの主な相続制度の変遷は、下記のとおりです。
| 相続順位 | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 | 代襲相続の有無 |
|---|---|---|---|
| 第1順位 | 3分の1 | 直系卑属(3分の2) | あり |
| 第2順位 | 2分の1 | 直系尊属(2分の1) | なし |
| 第3順位 | 3分の2 | 兄弟姉妹(3分の1) | なし |
| 相続順位 | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 | 代襲相続の有無 |
|---|---|---|---|
| 第1順位 | 3分の1 | 直系卑属(3分の2) | あり |
| 第2順位 | 2分の1 | 直系尊属(2分の1) | なし |
| 第3順位 | 3分の2 | 兄弟姉妹(3分の1) | あり |
| 相続順位 | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 | 代襲相続の有無 |
|---|---|---|---|
| 第1順位 | 2分の1 | 子ども(2分の1) | あり |
| 第2順位 | 3分の2 | 直系尊属(3分の1) | なし |
| 第3順位 | 4分の3 | 兄弟姉妹(4分の1) | あり(再代襲相続はなし) |

家督相続では、長男が全ての財産を相続することになっていました。しかし、現代の遺産相続では、それぞれの相続人が相続できる割合が決められています。
法定相続分と呼ばれ、具体的な割合は以下の表のとおりです。
なお、表にある「直系尊属」とは、父母や祖父母など、本人より前の世代のうち、血が繋がっている直系の親族のことです。
| 相続人 | 配偶者の有無 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 子ども | あり | 子ども:1/2、配偶者1/2 |
| 子ども | なし | 1 |
| 直系尊属(子どもがいない) | あり | 直系尊属:1/2、配偶者:2/3 |
| 直系尊属(子どもがいない) | なし | 1 |
| 兄弟姉妹(子ども・直系尊属がいない) | あり | 兄弟姉妹:1/4、配偶者:3/4 |
| 兄弟姉妹(子ども・直系尊属がいない) | なし | 1 |
| 配偶者のみ | ー | 1 |
なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が1人でない場合は、特定の1人が単独で相続するのではなく、均等に分けることになっています。
例えば、相続人が配偶者と2人の子どもである場合には、子どもの法定相続分1/2を2人で均等割して、1人あたりの相続分は1/4となります(1/2÷2)。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

ここでは、家督相続と現在の相続制度との違いを、以下の4つの観点から解説します。
それぞれの違いについて見ていきましょう。
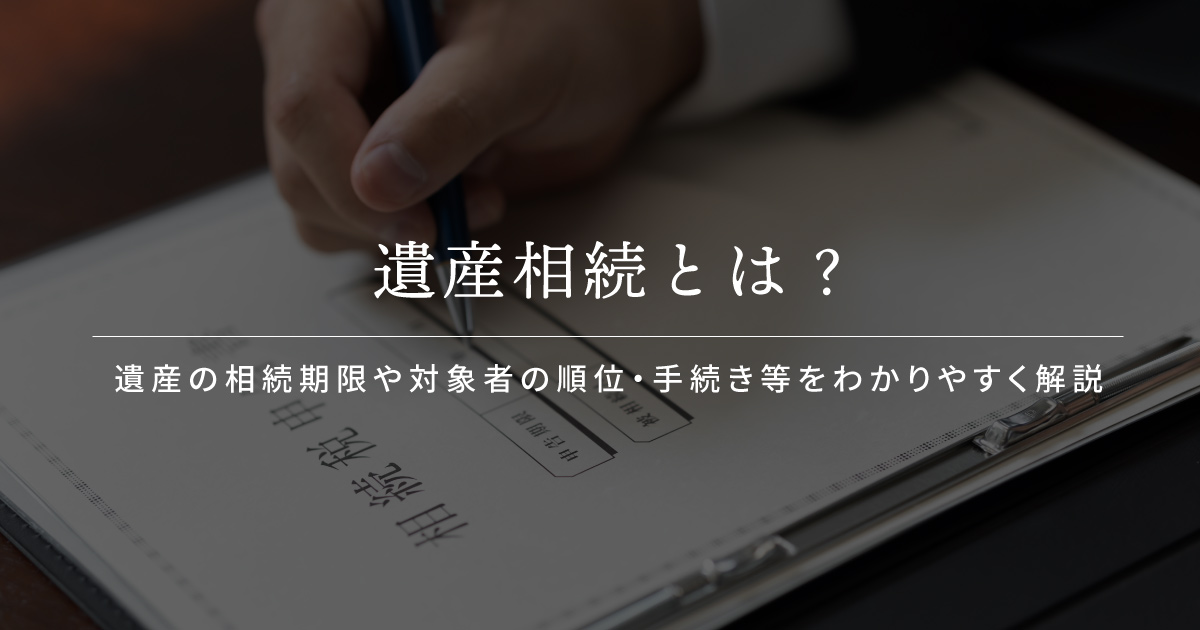
家督相続では、原則、長男が家督相続人になります。場合によっては長女が家督相続人になることもありました。しかし、現代の遺産相続では、配偶者がいれば必ず相続人になります。
また、子どもが複数人いれば、長男のみならず全ての子どもが均等に相続できます。子どもがいなかった場合は、直系尊属や兄弟姉妹も相続人になるのです。このように、家督相続と遺産相続とでは、相続する人が全く異なります。
現代の遺産相続は、被相続人が亡くなった時に相続が開始されます。
一方、家督相続では、被相続人の死亡時以外にも相続が開始されるタイミングがあります。
主なパターンは、以下の3つです。
その他に、離婚や国籍喪失により相続が開始される場合もあります。
現代の遺産相続では、負の遺産が残る可能性も大いにあるため、相続放棄が認められています。一方、家督相続では、原則、相続放棄が認められていません。
つまり、家督相続とは、負の遺産がある場合でも長男が相続をし、断ることができない制度です。

現代の遺産相続における相続人の順位は、子ども・直系尊属・兄弟姉妹の順です。配偶者がいれば、他の相続人と同じ順位となります。
一方、家督相続の順位は、次のように規定されていました。
| 第1順位 | 第1種法定推定家督相続人:被相続人の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親などが近い者。 |
| 第2順位 | 指定家督相続人:被相続人が生前、または遺言によって指定した者。 |
| 第3順位 | 第1種選定家督相続人:被相続人の父。父が死亡している場合は母。父母が死亡している場合は親族会が選定した者。 |
| 第4順位 | 第2種法定推定家督相続人:被相続人の直系尊属。(直系尊属とは、父母や祖父母など、本人より前の世代のうち、血が繋がっている直系の親族のこと) |
| 第5順位 | 第2種選定家督相続人:被相続人の親族会が選定した者。 |
現代の遺産相続では「相続」を登記原因として登記手続きを行います。しかし、家督相続においては「家督相続」を登記原因として手続きを行います。
旧民法では、相続手続きが戸主の地位を承継させる家督相続と、戸主以外の家族の財産を承継させる遺産相続の2種類に分かれていました。
そのため、戸主以外の家族の財産を承継させる場合の登記原因は、「遺産相続」となっていました。両者の区別をつける意味で、家督相続の登記原因は「家督相続」とされていたのです。
また、現代の遺産相続の開始原因は、被相続人の死亡のみです。一方、家督相続の開始原因には、戸主の死亡の他にも、隠居や国籍喪失などがありました。
このように家督相続の開始原因には複数の種類がありましたが、登記原因としては、「家督相続」の1つのみとなります。
なお、現代の遺産相続の登記手続きでは、相続の発生を証明するために被相続人の戸籍謄本を提出する必要がありますが、この点は家督相続においても同じです。
現代の遺産相続では、相続手続きによって承継されるのは、被相続人が生前保有していた財産のみです。他方で家督相続においては、戸主の権限が承継されることになります。
つまり、家の財産のみならず、家族の身分行為に対する権限なども承継されるのです。
具体的には、家族の婚姻や養子縁組に対する同意権、家族の居所指定権などが承継されます。
また、現代の遺産相続では、原則として被相続人の保有していた全財産が承継されます。しかし、家督相続においては、一部の財産が承継対象から除かれていました。
例えば、前戸主が隠居する際に留保した財産(ただし、確定日付のある証書によることが必要)や、前戸主が隠居後に取得した財産などです。これらの財産は、遺産相続により、戸主以外の家族にも承継されることとなっていました。

実は、今でも不動産の相続において、家督相続が適用されるケースがあります。
その一例が、相続登記がされずに放置された不動産の名義変更をしようとする場合です。
相続登記がされずに放置されていた不動産の名義変更をするには、登記簿上の名義人から現在の所有者までの相続関係を証明しなければなりません。
原則として、家督相続が適用されるのは、旧民法が効力を持っていたときに亡くなった人が持っていた財産となります。
したがって、旧民法が効力を持っていた期間に相続が発生し、相続登記がされなかった不動産の名義変更をしようとする場合、家督相続を適用して相続関係を明らかにする必要があります。
厳密には、旧民法と新民法の間は、応急措置法という別の法律が適用されていました。
応急措置法とは新民法と旧民法の矛盾を解消するために制定された法律です。
応急措置法上の相続制度は、旧民法とも新民法とも異なるため、注意してください。
父親の相続手続きで、実家の土地建物の所有名義は父親だと思っていたところ、実は昭和10年に亡くなった祖父のままであったことが発覚したとします。
このケースでは、昭和22年5月2日以前の相続であるため、祖父の相続については旧民法が適用されます。祖父が戸主で父親が長男であれば、実家の土地建物の所有権は家督相続により父親が承継することになるのです。
そのため、父親の相続手続きの前提として、実家の土地建物について家督相続を原因とする父親への所有権移転登記を行うことになります。
このように、現代においても不動産の相続においては、家督相続の登記がなされることがあるのです。
前述した父親の相続手続きを具体例として検討しましょう。
前述の事例では、父親が実家の土地建物の所有権を家督相続により取得しています。
このようなケースでは、実家の土地建物の所有権は、父親の相続人の間で遺産分割協議をして取得者を決めることになります。
他方で、祖父には子どもが3人おり、父親は長男ではなかったとします。この場合、父親は戸主として家督相続を受ける立場にはありません。
そのため、父親が実家の土地建物の所有権を家督相続により取得した可能性は低く、そもそも父親の相続財産にならない可能性があるのです。
このように、過去の相続が家督相続によるものかどうかが、現在の遺産相続にも大きな影響を及ぼす可能性があることを認識しておきましょう。
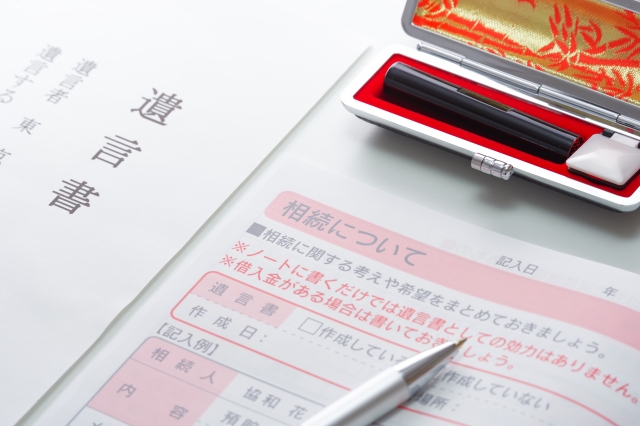
家督相続は旧民法上の制度ではありますが、現在でも1人で相続できるケースが3つあります。
それぞれのケースについて見ていきましょう。
遺言書に記載がある場合は、1人で相続することが可能です。
遺言書は相続において大きな効力を持つため、遺言書に「〇〇に全ての遺産を相続させる」という記載があれば、その人が1人で相続できます。
家督相続では長男しか相続できませんでしたが、遺言書であれば長男以外の人を指定することも可能です。しかし、遺言書に記載があったとしても、必ず相続分全てを取得できるわけではありません。
相続人は相続分について最低限の割合を保障されているため(遺留分)、他の相続人から請求を受けたら必ずその分は支払わなければならないのです。
詳しくは後ほど解説するので、ぜひチェックしてみてください。
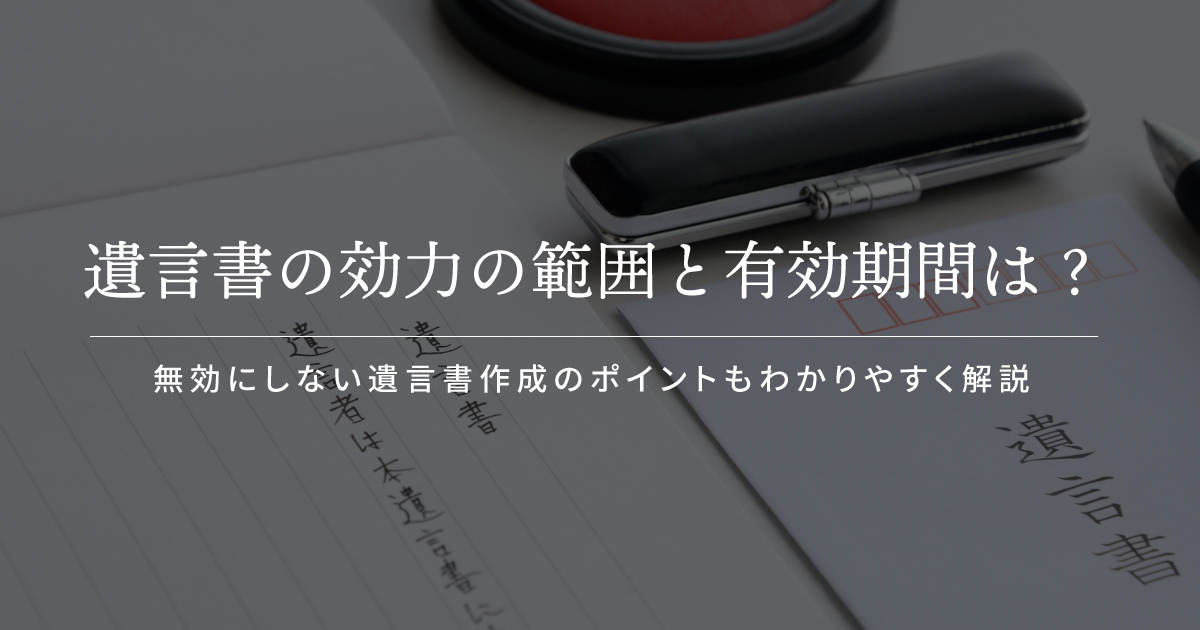
家族信託をしている場合でも1人で相続することが可能です。
家族信託は生前に財産を家族に託して、あらかじめ決めておいた方法にしたがって管理や処分をしてもらう仕組みのことです。
家族信託を行う際の契約で、家族に託した財産を誰が承継するのか決めることができます。
例えば、土地を長女に相続させたい場合は、長女と家族信託契約を結びます。契約で自分が亡くなった場合には、長女がその土地を相続する旨の記載をしておくのです。
全ての財産でなくても一部の財産を1人に相続させることもできるため、柔軟な対応ができます。

他の相続人全員の同意があれば、1人で相続することが可能です。
被相続人が亡くなると「遺産分割協議」で、誰がどの割合で何を相続するのかを話し合います。
特に異論がなければ、法定相続分通りに相続されます。しかし、相続人全員の同意があれば、法定相続分とは異なる割合での相続も可能です。
そのため、相続人全員が同意していれば、1人での相続もできます。
なお、被相続人の生前に相続人が同意している場合は注意が必要です。
生前の同意は生前の相続放棄とみなされ、無効となる可能性が高いです。必ず被相続人の死後に行われる「遺産分割協議」にて同意を得てください。
1人で相続する場合には「遺留分」も確認する必要があります。
「遺留分」とは、それぞれの相続人が受け取れる最低限の遺産取得分です。
例え、遺言書で「1人に相続する」と書かれていても、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分の範囲にあたる財産は取り戻すことが可能です。
そのため、遺留分を取り戻したい相続人がいると、「遺留分侵害額請求」をされ、遺留分はその相続人に支払わなければなりません。
遺留分は遺言書であっても侵害できないため、遺留分を返還しないと訴訟を提起される可能性もあります。
訴訟すると確実に遺留分を受け取れるため、問題が大きくなる前に請求に応じるのが無難だといえるでしょう。
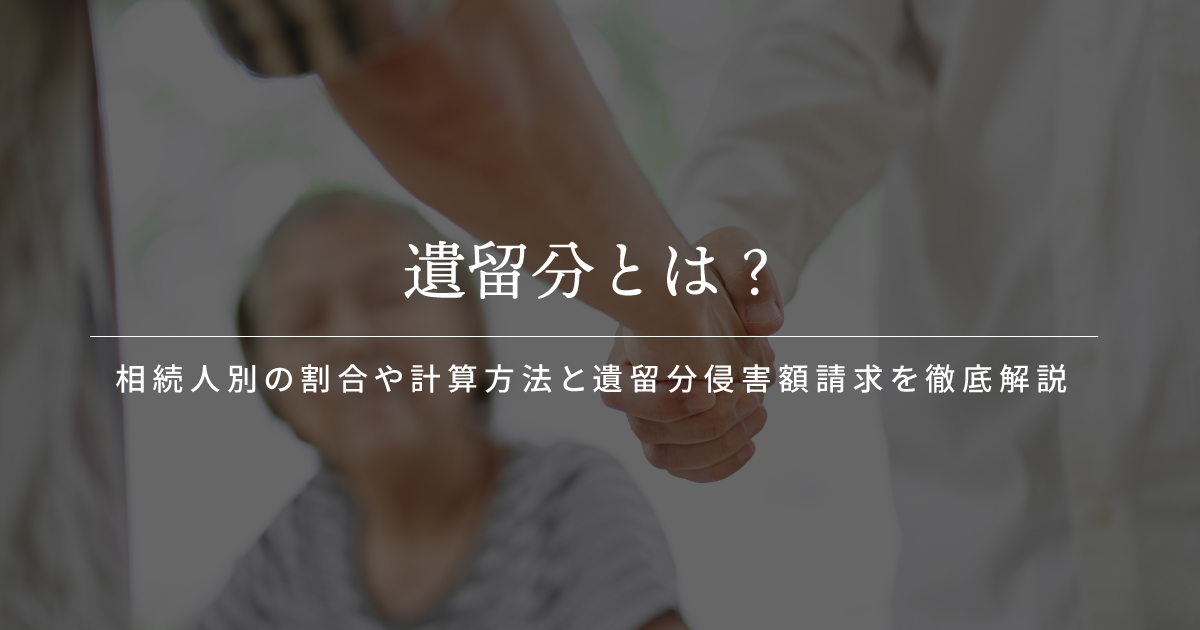
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

もし、相続人に単独での承継を主張してくる人がいる場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。対処法の鍵は「遺言書」です。
遺言書がなぜ重要になるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
まずは、遺言書が残されているかを確認してください。
遺言書はどのように財産が相続されるのかを決める力を持っているため、遺言書の有無が大切になります。
遺言書の有無により対応方法が大きく変わります。以下でそれぞれの対応方法を確認しましょう。
遺言書がない場合は、勝手に1人で相続内容を決めることはできません。
主に、以下の2つの方法で決着をつけることが考えられます。
それぞれの方法を見ていきましょう。
話し合いで決着をつけるのが1番無難な方法です。
相続における話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれます。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要です。誰か1人でも合意しなければ協議は終わりません。
もし、他の相続人が1人に相続させることに賛成していても、誰か1人でも反対すればその決定は認められません。
話し合いで決着がつきそうになければ、遺産分割調停で決着をつける方法も考えられます。
遺産分割調停は、調停委員が間に入って相続分を調整する制度です。
しかし、調停委員による調整では納得しない人もいます。その場合は遺産分割審判に移行し、裁判所が分割方法を決めます。
多くの場合では、法定相続分に則った割合で相続するように決められます。そのため、1人が全て相続する結果になることはほとんどありません。
一方、遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に沿って相続されます。
遺言書の内容は、家督相続を認める場合とそれ以外の場合があるため、1つずつ確認しましょう。
遺言書の内容が、家督相続を認める内容の場合があります。
遺言書の内容は原則としてそのまま認められるため、家督相続と同様の内容で相続することになります。
しかし、先述したように、遺留分と呼ばれる相続人が受け取れる最低限の遺産取得分があります。そのため、財産の全てを相続した人に対して「遺留分侵害額請求」が可能です。
遺留分に関しては遺言書よりも優先されるため、最低限の遺産は取得できます。
遺言書の内容が、家督相続を認める内容でない場合の対応方法を見てみましょう。
遺言書に家督相続以外の内容が書いてある場合は、遺産分割協議にて遺言書の内容に沿った分割を主張しましょう。
しかし、遺産分割協議では折り合いがつかない場合も考えられます。
その際は、遺言書がない場合と同じく、遺産分割調停を利用して調停や審判を受けることになります。

今は利用ができません。 明治時代(1868年7月16日から1947年5月2日まで)には「家督相続」と「遺贈相続」の2つの相続がありました。
「家督相続」は家族の主である家長の身分の相続、「遺贈相続」は家長以外の家族の財産の権利と義務の相続です。
第2次世界大戦後に改正された民法(1948年1月1日施行)が施行されると、家督相続と遺贈相続は廃止されました。しかし、相続時点の法律に従った相続は今でも適用されます。
家督相続は、家長の身分と関連する権利と義務(財産)が正当な長男に引き継がれる相続方式を指します。家督相続の原因は家長の死亡に限らず、隠居、国籍喪失なども含まれます。
家督相続が起こると、前の家長が有する不動産(もしあれば)は新しい家長に引き継がれますが、家督相続の登記が必要です。
「家督」とは、明治時代(1868年7月16日から1947年5月2日まで)の日本において存在した、家族の主となる人(家族の代表者)のことを指します。
家督は家族の財産や権利を継承することができ、「家督相続」という形で法律によって規定されていました。
1948年1月1日に施行された改正民法以降は、家督相続制度は廃止されましたが、遺産相続時の法律は今も適用されています。
隠居とは、戸主が生存中に家督を譲り、隠居の意思によって相続が開始することを指します。隠居前に取得した財産は家督相続、隠居後に取得した財産は遺産相続となります。
隠居者が隠居後に売買を原因として登記した不動産は家督相続の登記を受けられませんが、所有権保存の登記を受けた不動産については家督相続または遺産相続の登記を受けることができます。
旧家などでは相続登記や保存登記がされていない場合もあるので、隠居後の日付と財産の取得日の確認が重要です。
家業や先祖代々の土地を長男に継いで欲しいというケースです。
家督相続には、家の全ての財産や権限を長男に集中して承継させることで、家の維持継続を図るという目的がありました。
そのため、現代においても家の財産などを分散させたくない場合には、家督相続のような相続の必要性が認められるでしょう。
具体例としては、家業や先祖代々の土地を長男に継いでもらいたいケースがあります。
これらのケースで現代の法定相続分通りの相続を行うと、相続人間で財産が共有されることになってしまい、意図した相続を実現できません。
戦後の新憲法の施行から、新民法が施行されるまで(昭和22年5月3日から同年12月31日まで)の間、身分関係や相続関係について臨時的に適用された法律のことです。
家督相続は、戦後の新憲法の内容(個人の尊厳や両性の平等)に違反する制度でした。新憲法下での新民法が施行されるまでの間、憲法違反を是正するために施行されたのが、応急措置法です。
応急措置法では、相続に関して家督相続を適用しないことや、新しい相続人、相続分などが定められていました。

本記事では、家督相続の内容や現在の遺産相続との違いなどを解説しました。
相続に関連する制度は時代に応じて変化するため、家督相続以外にも理解しておくべき制度や手続きは数多くあります。
そのうちの1つが家族信託です。家族信託を効果的に利用すれば、相続手続きよりも柔軟に、自ら望む形で次世代に財産を承継できるのです。
ファミトラでは、次世代への資産承継に関する相談を無料で行っています。家族信託を利用した、お客さまのニーズに応える財産承継をご提案しています。
次世代への財産承継で後悔しないためにも、まずはお気軽に相談してください。

家族信託に精通した専門家が、お客様の相談を受け付けております。
ファミトラでは、家族信託に限らず相続対策や成年後見制度にまつわるご相談など幅広く対応することが可能です。

さまざなお客様のケースに対応してきた経験豊富な家族信託コーディネーターが、お客様一人ひとりのご状況に合わせて親身にサポートいたしますので、「まずはお話だけ…」という方もお気軽にご相談ください。
\ 24時間いつでもご相談可能 /
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。