
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

相続における「法定相続人」という言葉についてご存知でしょうか。法定相続人は相続手続きをする上で必ず登場する言葉であるため、相続が始まる前に理解しておくことが望ましいです。
本記事では法定相続人についてわかりやすく解説します。法定相続人の範囲や順位、法定相続分の割合など、相続に必要な内容を具体的に紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利のある人で、その順位や範囲は民法で定められています。
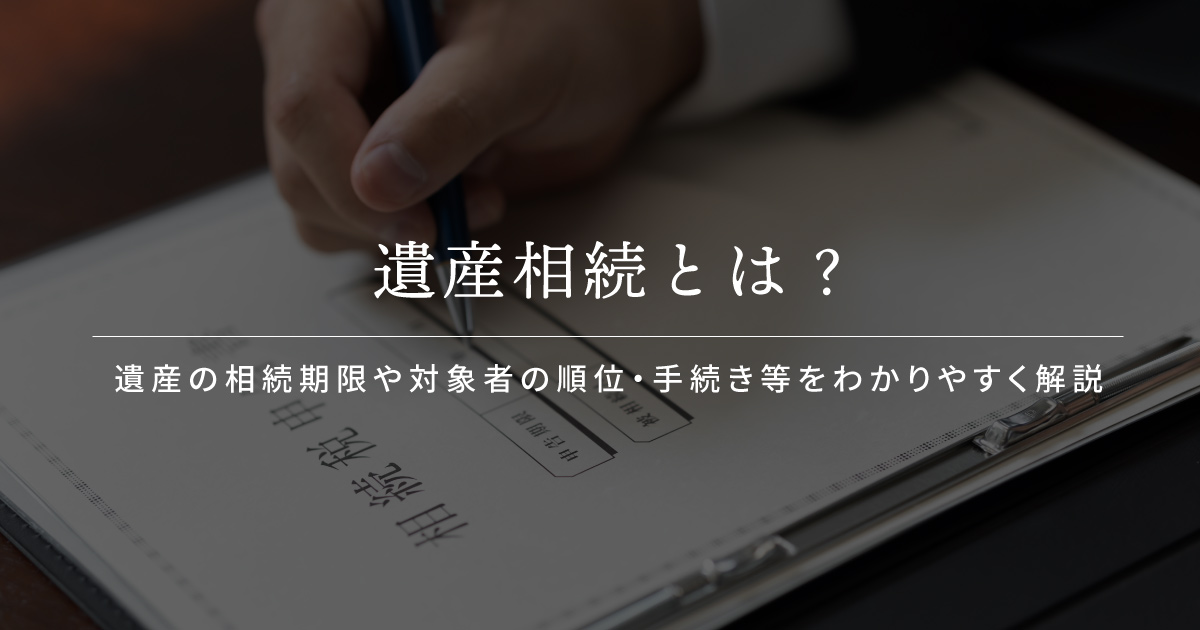
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続する権利がある人で、実際に遺産を相続する「相続人」とは異なります。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
血族とは被相続人と血の繋がった人のことです。相続人になれる順位や相続分は民法のルールに従います。
法定相続人と推定相続人との違いは、被相続人が存命しているか死亡しているかにあります。
法定相続人は、被相続人が死亡した際に相続の権利を持っている人です。
一方、推定相続人は被相続人が存命している状況で、仮に相続が発生した状況を想定し、相続できる人を指します。
法定相続人は実際に相続手続きを開始しますが、推定相続人はまだ仮の状態であると理解すると良いでしょう。
法定相続人とは、被相続人が死亡した際に相続の権利を持っている人であり、相続人は実際に相続する人です。
例えば、被相続人の息子が相続放棄をした場合、相続の権利はあるため法定相続人ではあるものの、その権利を放棄し実際には相続しないため、相続人ではありません。
法定相続人は権利、相続人は実際の状況を表していると考えるのが良いでしょう。
受遺者とは遺言書によって相続をする人です。
遺言書は相続ではとても強い効果を持つため、受遺者と法定相続人を比べると受遺者が優先されます。
ただし、全ての財産を受遺者に遺贈するとした場合でも、法定相続人も民法で保証された最低限の相続を受けられます(遺留分)。
全ての財産が受遺者に相続されるわけではありません。
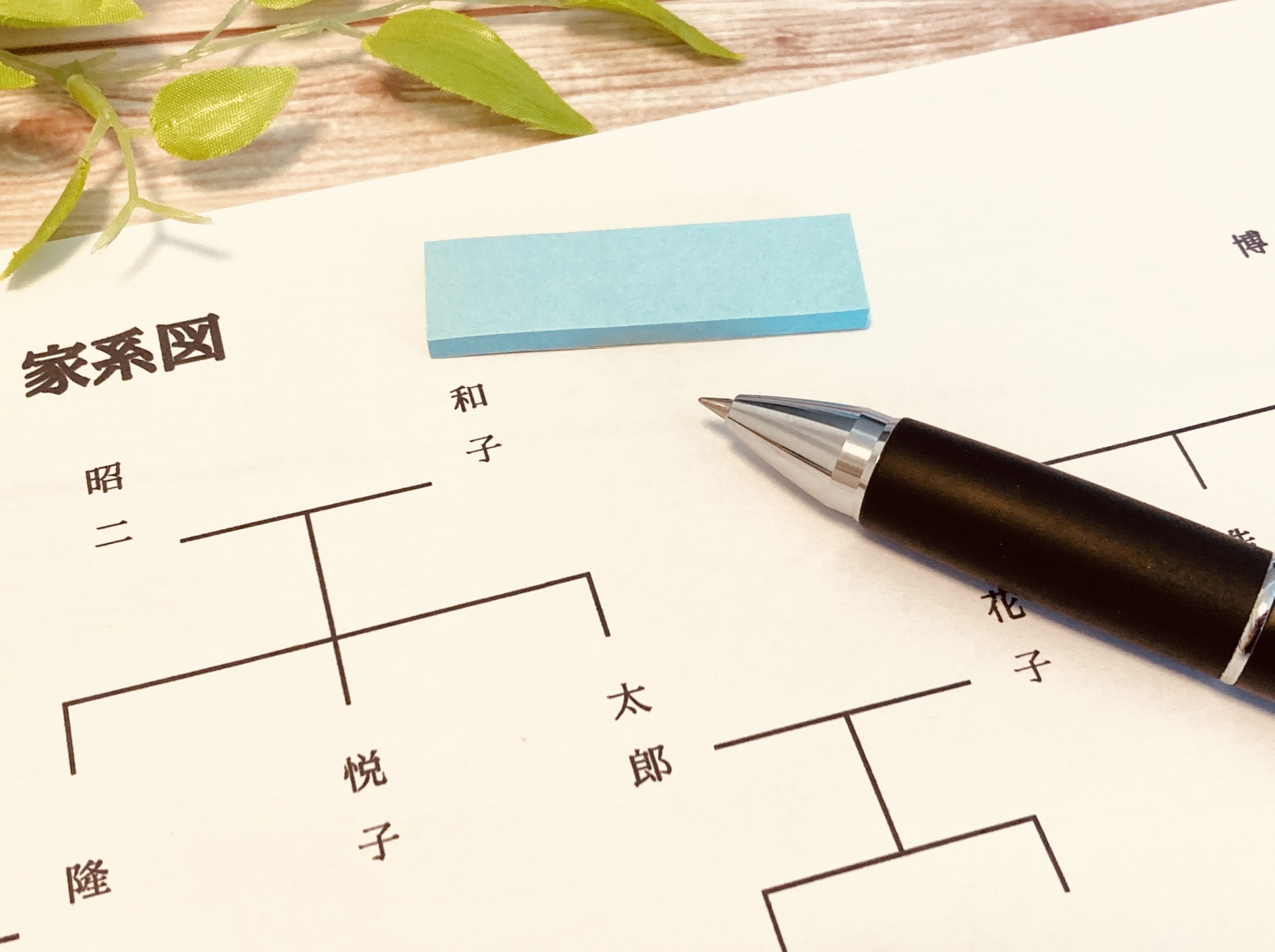
法定相続人の範囲は民法で以下のように定められています。
それぞれどのような人のことを指すのかについて見ていきましょう。
配偶者がいれば、常に相続人になります。
配偶者とは法律上の婚姻をしている人に限り、事実婚の相手は含まれません。
血族も法定相続人になりますが、順位が決まっています。
第一から第三順位まであり、被相続人に近い人ほど順位が上になります。
第一順位:直系卑属
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
順位が上の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
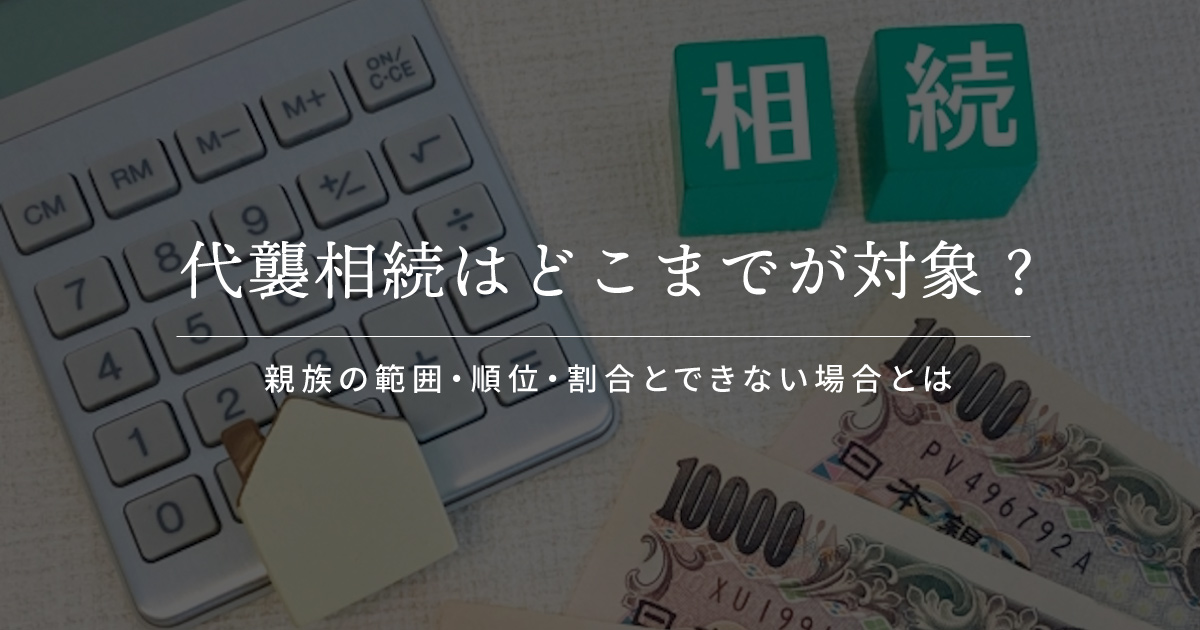
直系卑属とは、被相続人から見て血が繋がっている後の世代のことです。
「直系」とは、血が直接の親子関係で繋がっている系統のことです。これに対して、兄弟など横に繋がる系統を傍系といいます。
「卑属」とは、被相続人よりも後の世代の血族を指します。具体的には、子どもや孫、ひ孫などの子孫のことです。
弟や妹は後の世代ですが、被相続人と同順位として扱われるため、卑属ではありません。被相続人の子どもや孫、ひ孫などが直系卑属になります。
子どもには養子も含まれることに注意してください。
直系尊属とは、被相続人から見て血が繋がっている前の世代のことです。
被相続人から見て親、祖父母、曽祖父母などが直系血族にあたります。
「尊属」とは、被相続人から見て前の世代の血族を指します。直系尊属には養父母も含まれることに注意してください。
家系図などで自分から直接の流れで遡れるのが直系尊属になります。被相続人の父母はもちろん直系尊属です。
被相続人の祖母である父の両親は直系尊属ですが、母方の祖父母も被相続人から見れば直系尊属にあたります。
代襲相続とは、本来の相続人が死亡したり相続権を喪失したりすることにより、代わりとなる相続人を決めることです。
代襲相続人とは、代襲相続が発生することで代わりに相続人になる人のことです。
例えば、親の相続を行う場合、本来の相続人である子どもがすでに死亡していると、その子ども、すなわち被相続人の孫が代襲相続人となります。
以下では、代襲相続が発生する条件や範囲について詳しく見ていきましょう。
代襲相続が発生する条件は以下の通りです。
被相続人より先に法定相続人が死亡している場合は、法定相続人が相続できないため代襲相続が発生します。
また、法定相続人が相続廃除もしくは相続欠格になる場合も代襲相続が発生します。
相続廃除とは、相続人に非行などがある場合、被相続人が家庭裁判所に申請することで相続権を剥奪することです。
一方、相続欠格とは、一定の事情を満たすことで相続人として認められなくなり、相続権を失うことを指します。
代襲相続人になれる範囲は以下のとおりです。
例えば、3人の子どもを持つ親が亡くなったとき、3人の子どもはいずれも法定相続人となります。
しかし、そのうち長男がすでに亡くなっている場合、長男の子ども、すなわち被相続人の孫が代襲相続人となるのです。
また、被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続権を有する場合、被相続人の甥姪が相続人になります。

法定相続人に該当するかどうかは民法の要件に当てはまるかどうかで決まります。
親類とは、血縁や婚姻で繋がっている人のことです。
以下の人は親類でも法定相続人ではありません。
また、法定相続人でも以下の人には相続権がありません。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

本来は先の順位の血族であり相続人になれる人であっても、相続権がないケースがあります。
ここでは3つのケースについて1つずつ詳しく見ていきましょう。
相続人は、欠格事由があれば何らかの手続きを経ずに法律上当然に相続権を失います。同時に受遺者にもなれません。
相続の欠格事由は次の5つです。
相続廃除とは、相続権を持っている人を相続から外す制度です。
ただし、廃除は相対的なもので廃除された人の子どもや孫は代襲相続ができます。
廃除されるのは遺留分を持つ推定相続人に限られます。なぜなら、それ以外の人に財産を渡したくなければ、遺言でその旨を書けば良いためです。
廃除事由は以下のとおりです。
廃除の手続きは被相続人の生前に行う場合と、遺言で行う場合とで異なります。
相続放棄とは、法定相続人が相続財産や被相続人の権利義務などを一切継承せず放棄することです。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとして扱われるため、遺産分割協議は相続放棄した人を除いた相続人で行うことになります。
相続欠格の場合や相続廃除された場合と異なる点は、相続放棄をすると代襲相続ができない点です。
相続放棄をした人は相続人でないものとして扱われるため、当然ながらその子どもや孫なども相続人として扱われることはありません。
なお、全ての子どもが相続放棄した場合、直系尊属(親など)が相続人となり、全ての直系尊属が相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続人になります。

家族が死亡し相続が発生したら、まずは誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。
法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で確認します。
転居や結婚などで転籍しているときは、最初に現在の戸籍謄本を取り寄せ、転籍前の戸籍をたどっていかなければなりません。
被相続人の元配偶者との間の子どもや、認知した子どもも法定相続人になるため、過去の戸籍謄本を全て確認する必要があります。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せるには、本籍地のある市区町村に対して請求します。本籍地がどこか不明な場合は、本籍地が書かれている住民票を取得してください。
出生までの戸籍謄本を遡って請求する場合は、最新の戸籍から順番に取得し、必要に応じて転籍してきた市区町村をたどって請求する必要があります。
市区町村への請求は、窓口と郵送の2つの方法があり、市区町村がコンビニ交付を導入していればコンビニでも取得できます。
郵送で申請する場合は、市区町村の役所・役場のホームページから取得できる戸籍謄本取得申請に必要事項を記入し、「定額小為替証書」と切手が貼ってある返信用封筒を同封してください。
手数料は、戸籍謄本が450円、除籍謄本や成改製原戸籍謄本が750円です。
戸籍謄本のコンビニ交付を導入している市区町村でも、亡くなった人の戸籍謄本はコンビニで取得できない場合がある点に注意してください。
例えば、東広島市や府中市では、亡くなった人が含まれる戸籍に存命の人がいなければコンビニ交付ができないとされています。
一方、亡くなった人が含まれる戸籍に存命の人がいれば、コンビニ交付は可能です。
コンビニ交付ができない場合は窓口か郵送を利用することになります。
参考:東広島市|お亡くなりになった人の住民票や戸籍等の証明書の取得について
参考:府中市|コンビニ交付|亡くなった人の証明書も取得できるの?
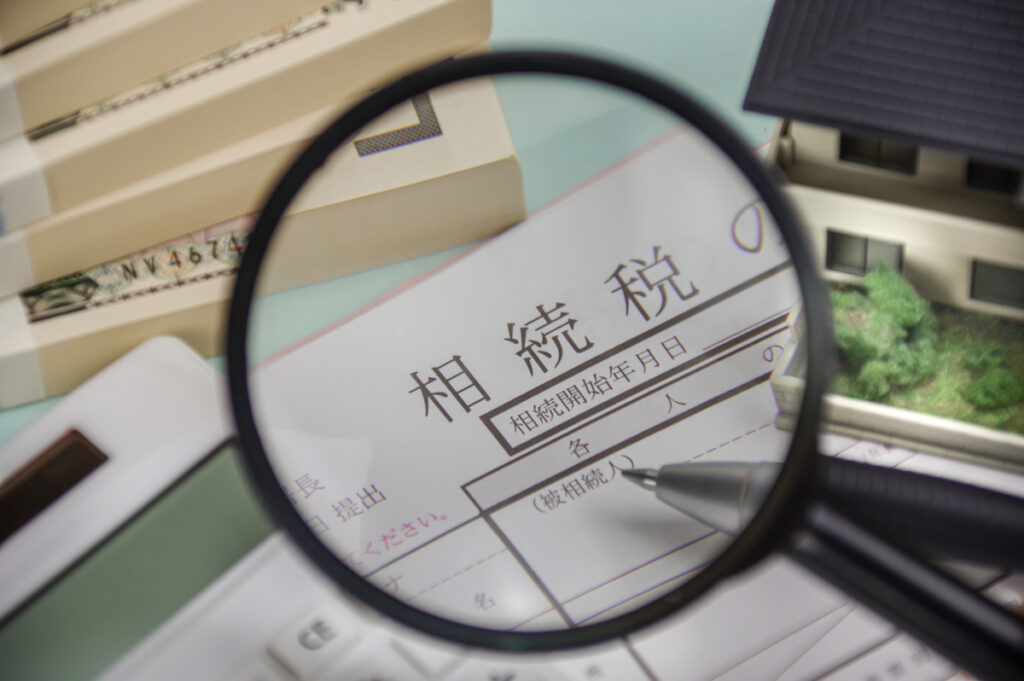
被相続人の財産は、相続人同士で遺産分割協議を行い分け方を決めます。相続財産の分け方を決めるときに目安となるのが「法定相続分」です。
法定相続分は民法で決められており、相続する人によって割合が異なります。
同順位の相続人が複数いる場合は、同順位の相続人同士で均等に分けることが原則です。
ただし、法定相続人が法律で厳格に決められているのに対し、法定相続分はあくまで目安です。必ずしもその通りに相続財産を分ける必要はありません。
ここでは、法定相続のパターンと相続割合について解説します。
被相続人の配偶者と子どもが相続人のとき、法定相続分は、配偶者 1/2、子ども 1/2 です。
子どもが複数人いる場合は、相続財産の1/2をさらに子どもの人数で均等に分けます。
例えば、相続財産の評価額が合計1億円であり、法定相続人が配偶者と子ども2人(長男・長女)の合計3人である場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者がおらず子どものみが相続人の場合、子どもが全て相続します。子どもが複数人いる場合は、相続財産を子どもの人数で均等に分けます。
財産6,000万円、子ども3人(長男・次男・長女)の場合、法定相続分は次のとおりです。
相続の開始時点で子どもがすでに亡くなっているときは「代襲相続」が発生し、被相続人の孫が相続人となります。孫も亡くなっているときは、ひ孫が再代襲します。
被相続人の父母や祖父母を直系尊属といいます。被相続人に子どもや孫、ひ孫などがいない場合、被相続人の直系尊属も相続人となります。
被相続人の死亡時に父母がいる場合は父母が相続人に、父母も死亡している場合は祖父母が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
父母が2人とも健在の場合、相続財産の1/3を、頭数の2で割ったものがそれぞれの法定相続分です。
相続人が、配偶者と被相続人の父母で、相続財産が1億2,000万円のケースで相続分を計算してみましょう。
なお、被相続人に配偶者がいない場合、被相続人の父母のみが相続人となります。
被相続人に子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。兄弟姉妹が2人以上いるのであれば1/4 を均等に分けた金額が法定相続分となります。
例えば、相続財産が1億円、相続人が配偶者と被相続人の兄、弟である場合、法定相続分は次のとおりです。
相続が開始した時点で被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていると「代襲相続」が発生し、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が相続人になります。
相続時にすでに子が死亡していた場合、孫(被相続人の子の子)がいれば、孫が代襲相続します。
被相続人に配偶者がいる場合、相続人になるのは配偶者と孫です。相続分は、配偶者が相続財産の1/2、孫は相続財産の1/2を頭数で割った額になります。
配偶者と孫が2人いて、相続財産が1億2,000万円の場合、相続分がどうなるのか計算してみましょう。
配偶者と亡くなった子の兄弟(子)1人、孫(亡くなった子の子)2人が相続人で、相続財産が1億2,000万円の場合の相続分を計算すると以下のとおりです。
子が相続放棄をした場合、子は最初から相続人ではなかったことになり、その子(孫)に代襲相続は発生しません。
以上をもとに、相続財産が1億2,000万円、被相続人に配偶者がおり、子が相続放棄した場合の相続分を計算してみましょう。
被相続人に相続放棄をした子以外に子がおらず、直系尊属や兄弟姉妹がいない場合、配偶者が全額の1億2,000万円を相続します。
被相続人に直系尊属がおらず、相続放棄をした子に兄と弟(いずれも被相続人の子)がいる場合、相続分は以下のようになります。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

相続では遺留分を考慮する必要があります。
遺留分とは、法定相続人に対して認められる遺産を留保できる割合のことで、遺言によっても奪えません。
誰に遺留分が認められるのか、遺留分の対象となる財産や遺留分の割合、計算方法について解説します。
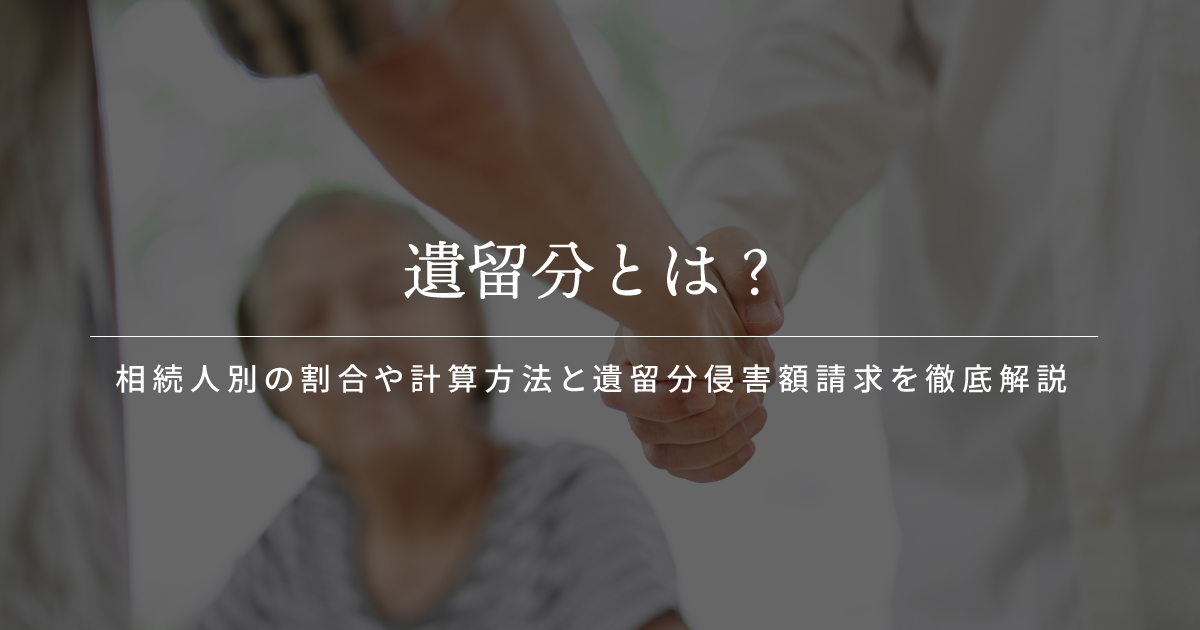
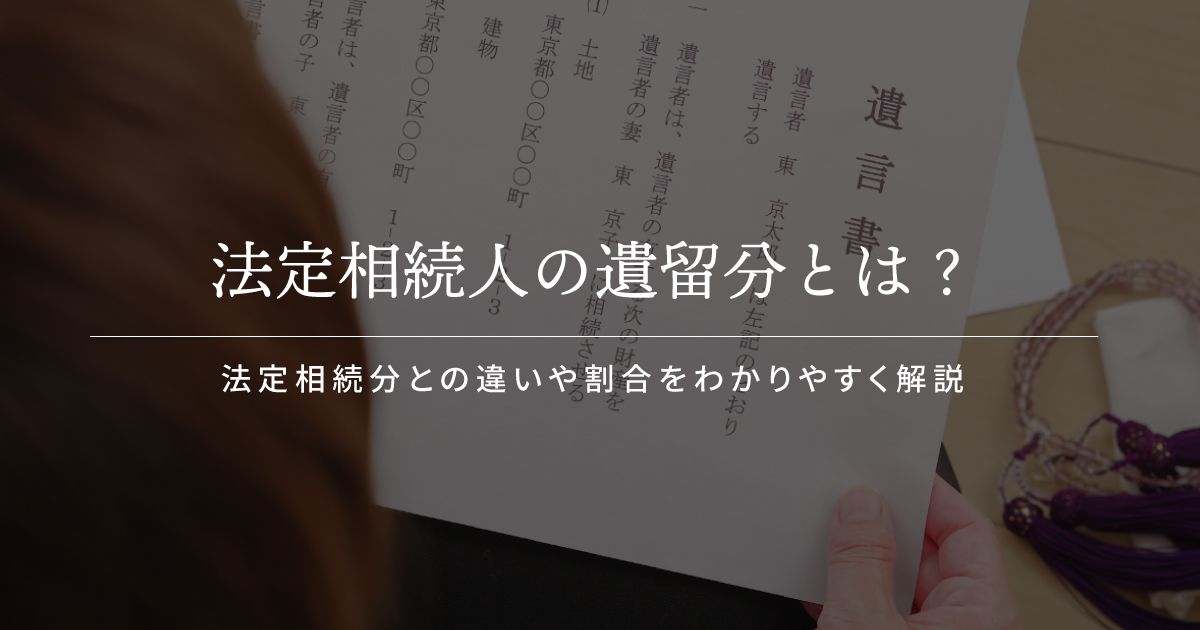
遺留分が認められる相続人は、配偶者・直系卑属・直系尊属です。
兄弟姉妹や甥姪は相続人ではあるものの、直系卑属や直系尊属にはあたりません。
そのため、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められないのです。
遺留分の対象となる財産は、民法1043条で以下のように定められています。
なお、贈与された財産は全てが遺留分の対象となるわけではなく、以下の4つが贈与された財産にあたります。
これらを合わせた財産が遺留分の対象となります。
基本的に法定相続分の1/2、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3が遺留分の割合です。
例えば、配偶者の遺留分は法定相続分である1/2のさらに1/2であるため、1/4です。
ただし、全ての場合で1/2や1/3が当てはまるわけではありません。
正確に計算するには、総体的遺留分と個別的遺留分を計算する必要があります。
総体的遺留分とは、全体として遺留分が認められる割合です。
直系尊属のみが相続人の場合は相続財産全体の1/3、それ以外の場合は相続財産全体の1/2です。
その中から、それぞれの相続人の遺留分を計算することを個別的遺留分といいます。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を掛けることで算出できます。
例えば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、どちらも直系尊属ではないため総体的遺留分は1/2、法定相続分は配偶者・子どもともに1/4であるため、遺留分は1/8ずつとなるのです。
遺留分を侵害された場合、法定相続人は遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求とは遺留分を取り戻すための請求であり、侵害された分の財産を金銭で取り戻すことができるのです。
遺留分侵害額請求をしなかった場合、遺留分を放棄したとみなされ遺留分を取り戻すことができません。遺留分を取り戻したい場合は、遺留分侵害額請求をするようにしてください。
なお、遺留分侵害額請求を起こす前に話し合いで解決できれば、わざわざ裁判所に対して請求を起こす必要がありません。
そのため、遺留分侵害額請求を起こす前に、遺留分にあたる財産を得られるように他の相続人と協議することをおすすめします。

相続が発生したとき、最初に相続人になる人と相続人の数を確定させることが非常に重要です。
相続人全員がそろわないと遺産分割協議が行えません。
本来なら遺産分割協議に参加すべき相続人が1人でも遺産分割協議に参加していなかった場合は、その協議は無効になるためです。
法定相続人を確定する際に誤りや漏れが起きやすいケースは、下記のような場合です。
このような場合は、相続手続きに詳しい司法書士など士業の方に相談することをおすすめします。
ここでは、それぞれのケースについて解説します。
代襲相続とは、相続の開始時点で本来相続人となる子どもや兄弟姉妹が亡くなっているときに、その人の子どもや孫が相続人になることです。
代襲相続人の法定相続分は、本来財産を相続するはずだった人と同じ額となりますが、代襲相続人が複数いるときは、法定相続分を均等に分けることになります。
相続時にすでに被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続により兄妹姉妹の子が相続人となります。
代襲相続は甥姪の代までで、兄弟姉妹の孫以降は相続人になりません。
代襲相続による法定相続分は、基本的に亡くなった兄弟姉妹と等分で、代襲相続人が複数いる場合は、さらに頭数で割ったものが相続分となります。
相続財産1億2,000万円で、相続人が被相続人の兄と弟の子2人(なお、兄と弟、被相続人はいずれも両親が同じ)だった場合の相続額を計算してみましょう。
兄:1億2,000万円×1/2=6,000万円
弟の子1:1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円
弟の子2:1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円
なお、兄弟姉妹、甥姪には遺留分がない点にも注意が必要です。
養親と養子との間に法律上の親子関係をつくることを養子縁組といいます。養子になった子は、実子と同様に相続人となります。
相続財産1億2,000万円で、相続人が配偶者、実子2人、養子1人の場合の相続分を計算してみましょう。
配偶者:1億2,000万円×1/2=6,000万円
子1:1億2,000万円×1/2×1/3=2,000万円
子2:1億2,000万円×1/2×1/3=2,000万円
養子:1億2,000万円×1/2×1/3=2,000万円
被相続人に離婚歴がある場合、子どもの有無に注意しましょう。
特に以下の3つのケースは要注意です。
この場合、嫡出子に相続権があります。
離婚しても養子縁組は解消されないので、養子には相続権があります。
離婚と同時に養子縁組を解消していれば、元養子に相続権はありません。
再婚相手の配偶者が法定相続人となります。
再婚相手との間に子どもがいれば、養子縁組した子どもを含めた子どもたちにも相続権があります。
このように、相続の際には戸籍の調査が重要になります。
法定相続人が妊娠していた場合、注意する必要があります。
胎児は、民法で無事に生まれてくることを条件に相続権が認められています。ただし、死産や流産または堕胎した場合、始めから相続権がなかったものとされます。
しかし、胎児は遺産分割協議に参加できません。この場合、生まれてくるまで遺産分割協議は出来ません。
無事に生まれた場合、遺産分割協議を行いますが、幼児は会議に参加できないので、特別代理人が会議に出席します。
特別代理人は、幼児と利益相反関係にない者が選ばれます。
母親は同じ遺産を分けることになるので、利益相反行為の関係にあり、幼児の特別代理人にはなれません。
男性が被相続人となった際、内縁関係のパートナーとの間に子どもがいる場合、戸籍上の子どもかどうかが重要です。
戸籍上、被相続人の子どもでない場合は、子どもが相続人になることはできません。
しかし、被相続人の死亡後、子どもなどが「死後認知」の訴えを起こすことで、被相続人との親子関係を確定させることができます。
これにより、相続分の請求が可能になるため、内縁関係のパートナーとの間の子どもも相続できるようになります。
ただし、内縁関係のパートナー自身には相続権がないことには注意してください。
もし、法定相続人のなかに行方不明者がいる場合、行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。
行方不明者が見つからず遺産分割協議ができないと、被相続人の口座を解約したり不動産を売却したりできなくなってしまう可能性があります。
そのため、行方不明者がいるときは、親族の中にその所在に心当たりがある人がいないかをはじめに確認しましょう。
もし、行方不明者の所在地や連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せて現住所を調べるなどの手段を取る必要があります。
それでも所在がわからないときは、家庭裁判所へ財産管理人の選任を請求し、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
また、行方不明者の生死が不明な場合は、失踪宣告や認定死亡の手続きが必要です。
相続欠格や相続廃除となった法定相続人は相続権を失います。相続権を失うため遺留分を請求する権利も失うことになるのです。
しかし、法定相続人が相続欠格や相続廃除となった場合、その相続人に子どもや孫がいれば、代襲相続が発生します。
代襲相続の対象となる人がいなければ、同順位の人の相続割合が増えます。
例えば、被相続人の3人の子どものうちの1人が相続欠格者である場合、本来であれば3人の子で均等に相続財産を分けるところ、2人の子で均等に分ければ良いため、1人あたりの相続割合が増えるのです。
もし、代襲相続の対象となる人がおらず同順位の人もいなければ、相続順位が下の人に権利が移ります。
相続放棄をした人は、相続人から除外されます。また、相続放棄した人の子どもや孫は、代襲相続できません。
一方で、相続税を計算するときは、相続放棄をした人も相続人として数えられます。
そのため相続人の中に相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額や生命保険の非課税金額が減ることはありません。


相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、基本的に法定相続人同士で行うことが原則となっています。
ただし、状況によっては、法定相続人ではない人が遺産分割協議に参加することがあります。また、相続人ではない人が財産を相続できる場合もあります。
ここでは、遺産分割協議において想定される様々なケースについて解説します。
遺言書では、友人や内縁の妻など、法定相続人ではない人に財産を譲ると定めることも可能です。
そのため、法定相続人以外の人に財産を譲る旨が書かれていた場合は、その人も遺産分割協議に参加することになります。
また、遺言書の内容は、遺産分割協議で引き継ぎ方を決める法定相続よりも優先されます。ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって遺言内容と異なる引き継ぎ方を決めることも可能です。
ただし、被相続人の配偶者や子ども(代襲相続人も含む)、直系尊属(両親や祖父母など)には「遺留分」を請求できる権利を持っています。
法定相続人がいない場合、被相続人と生前に関係の深かった人が「特別縁故者」として財産を相続できることがあります。
特別縁故者になれるのは、被相続人の介護をしていた法定相続人以外の親族や被相続人と生計を共にしていた人、内縁の夫または妻などです。
特別縁故者もいない場合は、最終的に国庫に帰属することになります。
法定相続人であっても、未成年者については遺産分割協議に参加できません。
そのため、未成年者の法定相続人は、親などが法定代理人となって遺産分割協議に参加します。
ただし、親も同時に相続人であるときは、未成年者の法定代理人になれないことがあります。
未成年者と同時に相続人となった親が代理人を務めると、利益相反の関係となり、未成年者にとって不利な遺産分割となる可能性があるためです。
親が代理人になれないときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
そこで選任された特別代理人が、未成年者の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
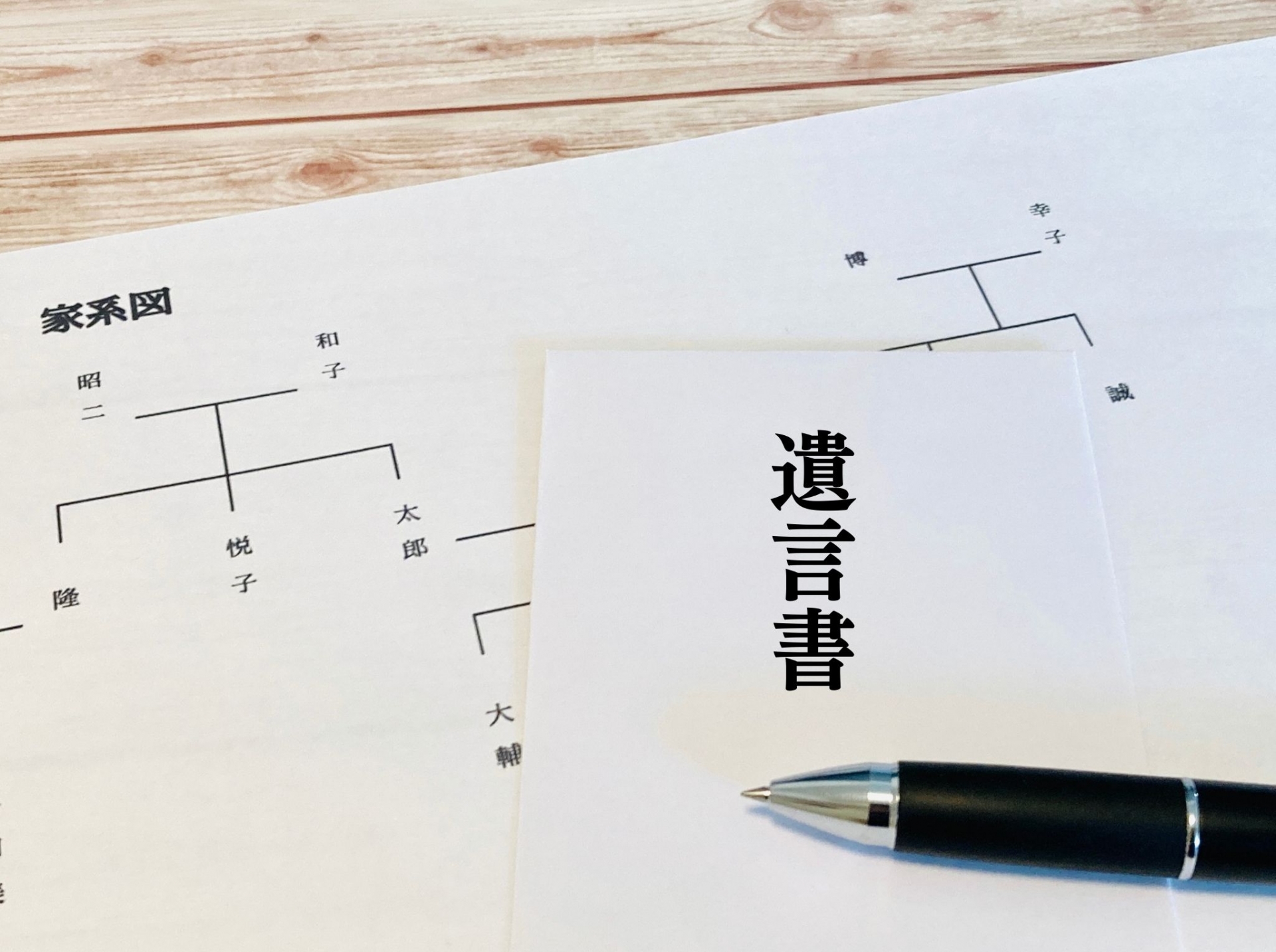
遺産分割協議でのトラブルを避けるためには遺言を作成するか、あるいは遺言の役割も担う家族信託を組成するのがおすすめです。
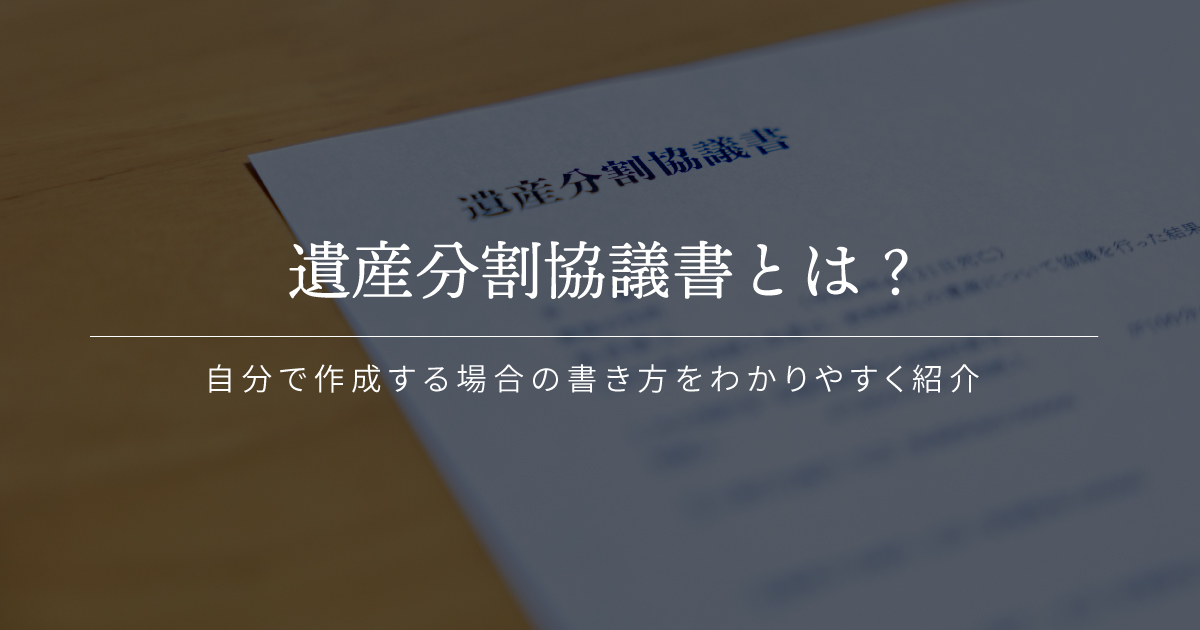
法定相続分と異なった相続をさせる場合、遺言は最も有効な手段です。
遺言に強い効力が認められているのは、遺言が被相続人の最後の意思表示だからです。たとえ遺留分の侵害があったとしても、遺留分侵害額請求をしなければ、侵害された相続人は遺留分を確保できません。
このように、非常に強い効力を持つ遺言ですが、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能です。
遺言作成のメリットとして、以下の3つが挙げられます。
遺言がない場合、遺産分割協議を行いますが、全員の合意が必要なため、1人でも遺産分割協議に反対の人がいると、遺産分割が終わらない可能性があります。
遺言がなければ、相続は法定相続人間で行いますが、遺言があれば法定相続人以外の人にも、遺産を残せます。
遺言がなければ、相続人が被相続人の意思に関係なく遺産を分割しますが、遺言では遺産の承継先を指定できます。
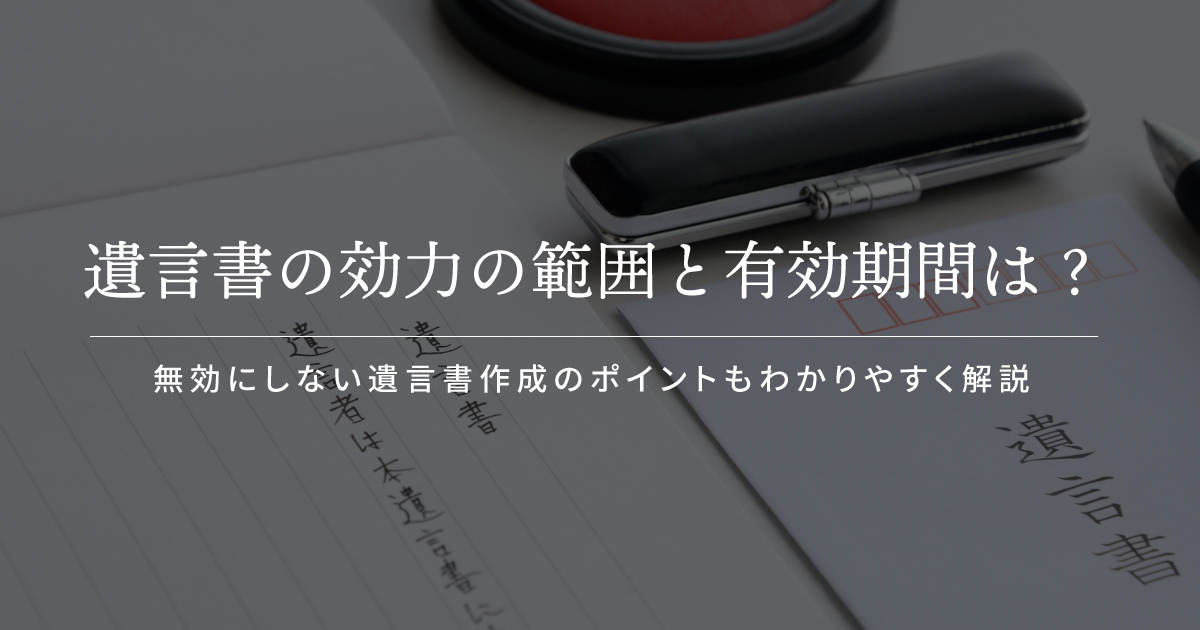
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。③はほとんど使われていないので、ここでは①と②の解説をします。
①は、本人が自筆で作成するものです。手軽に作成できる、費用がかからないなどのメリットがありますが、一般の方が作成するので無効になる場合が多いというデメリットがあります。
②は、公証人が民法に則り作成するので無効になることがほとんどないのがメリットです。一方、費用と公証役場まで出向いて作成しなければならないというデメリットがあります。
おすすめなのは②の公正証書遺言です。理由としては、無効になる可能性が低いこと、家庭裁判所による検認が不要なことなどが挙げられ、費用や手間を考慮してもメリットが大きいといえるでしょう。
遺言書の作成には手間がかかるため、なるべく避けたいと考える方もいるでしょう。
そこで有効利用できるのが家族信託です。
あらかじめ信託契約を結ぶことで、自身の死後、特定の承継人に財産を渡すことができます。
生前は自身が利益を受けつつ、死後には指定した承継人に承継されるため、遺言と同等の効果を発揮できるのです。
そのため、遺言ではなく家族信託で資産承継することも選択肢の1つとして考えてみてください。
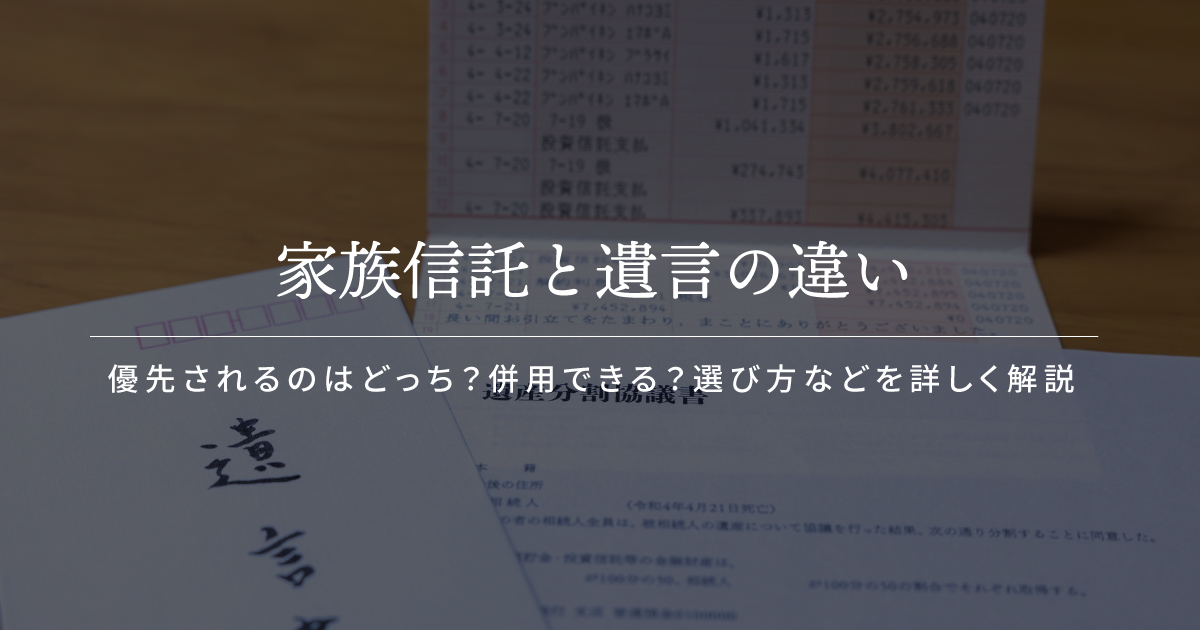
生前贈与とは、生きているうちに本人の財産を他の方へ贈与することです。無償で自身の財産を第三者に与える行為です。
事前に相続対策をしなければ、相続時に被相続人から財産を受け取れるのは相続人に限られます。それではお世話になった相続人以外に財産を渡すことができません。
生前贈与を活用すれば、同居して介護などでお世話になった長男の嫁などにも財産を渡すことが可能になります。事実婚の相手や認知していない婚外子も同様です。
ただし、贈与では原則として贈与税が贈与を受けた者にかかる点には注意が必要です。年間110万円以下の暦年課税による贈与であれば、贈与税は課税されません。
生前贈与では、相続開始前の7年(令和5年以前の贈与については3年)以内に被相続人から受けた贈与については、贈与額の100万円を超える額について相続税の課税額へ加算される点にも注意しなければなりません。

法定相続人に関する相談はどの専門家にしたら良いのでしょうか?以下、各専門家の特色とどのような場合にどの専門家に相談すれば良いのか解説します。
訴訟をはじめとする法律の専門家です。他の専門家より報酬が高めですが、相続に関して争いが起きそうな場合などは、弁護士に相談するのがおすすめです。
登記に関する専門家です。相続財産に不動産が含まれている場合、司法書士に相談するのがおすすめです。
税務の専門家です。相続税の算定に不安がある場合は、税理士に相談するのがおすすめです。
官公庁へ提出する書類作成の専門家です。訴訟や登記の代理権はありませんが、報酬が比較的低額なので、相続人間で争いがない場合や相続財産に不動産が含まれていない場合などにおすすめです。

最後に、法定相続人に関するよくある質問を紹介します。
被相続人の再婚相手の連れ子は法定相続人になれません。
また、死亡時の配偶者の連れ子も同様に、法定相続人にはなれません。
ただし、例外として被相続人の再婚相手の連れ子であっても、養子縁組をしている場合は相続人の対象です。
法定相続人になれるかどうかは重要であるため、戸籍を確認するなどして関係を明らかにしておくことをおすすめします。
法定相続分に反した遺言も有効になるため、原則としてこれに逆らうことはできません。
しかし、最低限の保証として民法では遺留分を定めています。
ただし、遺留分を侵害されたとしても当然に財産が相続できるわけではありません。
遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることで初めて遺留分の財産が受け取れることを理解しておくと良いでしょう。
法定相続人が被相続人に生前贈与を受けていた場合、その金額が「特別受益」になります。
「特別受益」の金額は、相続財産の一部として扱われます。
そのため、被相続人から生前贈与を受けていた法定相続人の相続額は、確定した分から特別受益の金額を引いた額になります。
養子がすでに亡くなっている場合、養子の子どもが法定相続人になれる場合があります。
養子の子どもが法定相続人になれるのは、養子縁組をした後に養子の子どもが生まれた場合です。
一方、養子縁組をする前に養子の子どもが生まれた場合、法定相続人にはなれません。
法律で決められているわけではありませんが、判例によりこのような扱いが一般的になっています。
基本的には、どの相続人にも遺留分が認められているため、原則としては実子の相続人の資格を奪えません。
しかし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合は、実子の相続人の資格を奪える可能性があります。
手続きとしては、家庭裁判所に対し相続廃除の申し立てを行い、家庭裁判所により廃除の審判がなされた場合には、実子の相続人の資格を奪えます。
相続時に親が亡くなっていれば、孫は直系卑属なので代わって相続をします。さらに、孫も相続時に亡くなっている場合は、ひ孫が代わって相続をします。
このように、相続時に相続人が亡くなっている場合、代わりに直系卑属が相続することを代襲相続といいます。
被相続人の兄弟が法定相続人となっていて、すでに兄弟が亡くなっている場合、甥姪が代襲相続しますが、兄弟姉妹と甥姪が死亡している場合、それ以上の代襲相続は発生しません。
夫が死亡し、子どもがいない場合、相続人は①妻と夫の両親、②妻と夫の兄弟姉妹の2つのケースが考えられます。
①と②では妻の相続分が代わってきます。
夫の遺産額6,000万円で考えましょう。
①のケースで夫の父母が健在の場合、妻が2/3、夫の父母1/3となります。
妻:6,000万円×2/3=4,000万円
夫の父:6,000万円×1/3×1/2=1,000万円
夫の母:6,000万円×1/3×1/2=1,000万円
②のケースで夫の弟と妹が健在の場合、妻が3/4、夫の弟と妹が1/4となります。
妻:6,000万円×3/4=4,500万円
夫の弟:6,000万円×1/4×1/2=750万円
夫の妹:6,000万円×1/4×1/2=750万円
法定相続人の調査は義務付けられているわけではありませんが、調査しておくことがおすすめです。
ほとんど関わりのなかった人物が法定相続人であることが発覚することもあるため、法定相続人の見落としがないように、調査することをおすすめします。
調査の際には戸籍謄本を取り寄せますが、その手間が面倒だと感じる方もいるでしょう。
しかし、相続の手続きでは被相続人と相続人全員の戸籍謄本の提出が必要であり、どちらにせよ戸籍謄本を取り寄せることになります。
法定相続人の調査も兼ねて戸籍謄本を取り寄せておくことがおすすめです。
法定相続人と相続税の関係で気を付けなければならないことは、主に以下の2点です。
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により得た財産が「1億6千万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
また、以下の人が相続人となる場合、相続税額が2割加算されることに注意してください。
以前は、不動産を相続放棄した場合、後順位の相続人が管理するまで、自己の財産と同一の注意をもって管理することが必要でした。また、相続人が1人しかいない場合はその相続人が、相続人全員が相続放棄をした場合は最後に相続放棄をした相続人が、不動産を管理しなければなりませんでした。
しかし、2023年の民法改正により、「現に占有している者」に限り、相続放棄後にも管理する義務が発生することになりました。したがって、相続財産である家に住んでいる相続人は、相続放棄後も不動産を管理する義務を負います。
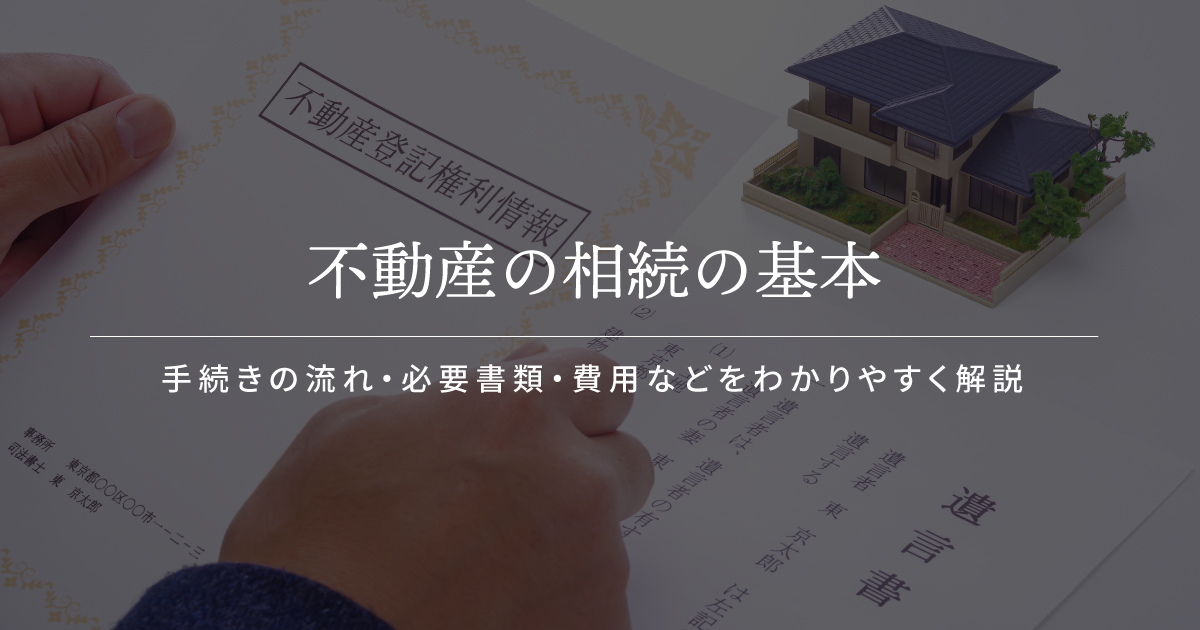
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

法定相続人の人数や相続割合は、家族および親族の構成により異なります。
遺産分割協議を進める際は、自身の家族および親族がどのような構成であるのかを把握した上で行うことがおすすめです。
しかし、遺産分割協議が始まると、相続人の意見がまとまらず親族が分裂してしまうケースもあります。
そのような事態を防ぐために遺言を用いたり、二次相続以降も指定できる家族信託を用いたりすることも検討してみてください。
ファミトラでは、家族信託に関するご質問に対し、家族信託の専門家がお答えしています。
無料相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!



家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!



PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。