
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中

成年後見制度で必要になる登記手続きについて解説します。
成年後見開始時においては、登記の申請は不要です。しかし、変更または終了時には、登記申請が求められます。
この記事では、登記の申請方法や必要書類も解説します。
成年後見の登記が気になる方は、是非とも参考にしてみてください。

姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!



成年後見制度は、判断能力の衰えた本人(成年被後見人等)を守るための制度です。
認知症などを患い、意思能力や財産管理能力が衰えてしまった方がいる場合に、成年後見制度は利用されます。
具体的な保護内容は、本人の財産管理と身上保護です。
成年後見制度では、成年後見人が選任され、本人に代わって財産管理や契約の締結をします。
判断能力が低下すると、詐欺などの被害にあう危険が高くなるためです。
成年後見制度は2種類あり、法定後見制度と任意後見制度の2つです。
任意後見制度は本人が元気なうちに本人の意思により契約が締結される一方で、法定後見制度は本人の意思能力が衰えてから手続きを開始します。
なお、法定後見制度は、本人の能力に応じ、後見・保佐・補助の3つに分類されます。

登記とは権利関係を公示するための仕組みです。
登記制度がなければ、取引などがスムーズに進みません。
たとえば、AからBへ不動産の売買があったとします。売買契約があった時点で、所有権はBへ移転します。
ただし、不動産の権利は目に見えません。
誰の目にも見える形で、Bに権利がある事実を証明させる必要があります。
契約書の提示があれば、Bが権利者である旨は証明されるでしょう。
しかし、逐一当事者に契約書を確認しなければいけないとすると、取引が円滑に進みません。
Bが権利者である旨を登記簿に記録し、誰もが閲覧できるよう公示させておけば、当事者に確認せずとも、権利者は一目瞭然になります。
権利関係を第三者にも分かるよう公示し、円滑な取引を実現させるのが、登記制度の意義です。
登記の代表例は、不動産登記・商業登記です。
その他、円滑な取引を実現すべく、成年後見制度にも登記が採用されています。
不動産や法人と同じく、成年後見に関する情報は、登記されます。
成年後見制度に関わる登記は4つです。
法定後見開始の登記と任意後見開始の登記を「後見登記」といいます。
後見登記は、後見開始の審判(または任意後見監督人の選任審判)がされたタイミングで、登記が行われます。
ただし、後見登記は裁判所の嘱託でされるため、当事者の申請は不要です。
一方、変更登記と終了登記は、当事者の申請が求められます。
本人や成年後見人に、氏名や住所の変更があった場合、変更登記を申請しなければなりません。例えば本人が自宅から入所施設へ移る場合、住所変更登記を申請します。
また、本人の死亡などで成年後見が終了した場合は、終了の登記申請が必要です。
変更登記・終了登記ともに、複雑な申請にはならないことが一般的です。専門家に依頼せずとも、個人でも対応できる場合もあります。ただし、不明な点があれば、司法書士に相談しましょう。
成年後見登記の目的は、取引の円滑化です。
登記という形で成年後見に関する事実を公示・記録しておくことで、成年後見人は、自らが成年後見人である旨を容易に証明できるようになります。
法務局が発行する登記事項証明書を提示して、第三者に権限を証明できるためです。
本人に代わり不動産の売買契約や介護施設への入所契約を締結する場合、成年後見人は登記事項証明書を提示するだけで、スムーズに取引できます。
成年後見人である事実が登記で公示されることで、取引相手の信頼が得られ、成年後見制度はより機能します。
成年後見登記制度とは、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し「登記事項証明書」を発行してもらうことにより、登記情報を証明・開示する制度です。
法定後見制度や任意後見制度では、例え成年後見人等が変更されたとしても、あらかじめ決めておいた権限や契約に沿った保護・支援が継続されることが重要です。
そのためには、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを記録しておく必要があります。
登記自体は東京法務局後見登録課で行われます。証明書交付については東京法務局以外にも全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課でも請求することができます。
なお、全国各地には法務局・地方法務局の他に出張所や支局もありますが、出張所や支局では成年後見登記の取り扱いはしていませんので注意しましょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
任意後見制度とは、本人の意思能力があるうちにあらかじめ任意後見人となる人と契約をしておきます。その後、本人の意思能力が不十分になったとき、任意後見人が契約内容に沿った保護・支援をする制度です。
契約は公正証書にて行い、公証人(※)がその作成と登記を担当します。
任意後見契約において登記される内容は、任意後見人の氏名や住所、代理権の範囲や任意後見監督人の氏名や住所などで、任意後見開始前と後で異なります。
任意後見開始前は、本人を保護・支援する任意後見受任者の氏名や住所、代理権の範囲などが登記されます。任意後見開始後は、任意後見受任者が任意後見人となり、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を登記します。
また、任意後見契約が解除により終了した場合などでは「終了の登記」、本人や任意後見人の住所の変更があった場合などでは「変更の登記」をする必要があります。これらの登記申請は、任意後見人や親族などが行います。
※公証人:法的知識と法律実務経験を有している、国の公務である公証事務を行う公務員
法定後見制度とは、本人の意思能力が低下・喪失したあとに、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を保護・支援する制度です。
法定後見制度の登記手続きは、本人や親族などによる後見等開始の申し立てがなされたあと、家庭裁判所が法務局に依頼して行います。
また任意後見制度と同様、本人が亡くなった場合は「終了の登記」、本人や成年後見人等の住所の変更があった場合などでは「変更の登記」が必要です。これは、法定後見人や本人の親族などが登記申請を行います。
法定後見制度を利用する場合には、本人の住所地の家庭裁判所に後見等開始の審判の申し立てを行います。申し立ては本人や配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などが行えます。
ここでは、後見等開始の審判の申し立てに必要な書類や申請書類提出から、登記されるまでの流れについて解説します。
後見等開始の審判の申し立てには、主に次のような書類が必要です。
申立書類一式には、申立書や申立事情説明書、財産目録、親族関係図などが含まれます。申立書等の書式については、本人の住所地の家庭裁判所によって異なる場合があります。
そのため、該当する家庭裁判所の窓口か、ホームページから書類をダウンロードして取得することが必要です。
本人に関する資料には、健康状態がわかる資料や収入・支出に関する資料などがあります。必要に応じて提出しなければならない書類も異なるため、家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家に相談しながら準備すると良いでしょう。
必要書類が全て揃い、提出書類確認シートによる書類確認が終わったら、本人の住所地の家庭裁判所に連絡し、面接の予約を行います。
申し立ての際には原則として面接が実施されており、事情を詳しく説明するために申立人や成年後見人等候補者が家庭裁判所を訪れます。
面接の所要時間は1~2時間程度です。開始時刻は後見申し立てが午前10時か午後2時、保佐・補助申し立てが午前9時30分か午後1時30分と時間が異なっています(東京家庭裁判所本庁後見センター)。
面接日が決まったら、準備しておいた書類を家庭裁判所に郵送します。
書類は、予約した面接日の3日前(土日祝日を除く)までに到着するよう郵送する必要があるため、早めに準備しておきましょう(1週間前とする家庭裁判所もあります)。
申立人や後見人等候補者との面接が行われるのは家庭裁判所です。
申立人は本人の意思能力や生活状況・財産状況、本人の親族らの意向などについて、候補者は候補者の適格性に関する事情について確認されます。
また、必要書類を提出し面接が終了したあと、鑑定や調査官調査、親族照会などの審査が行われることがあります。鑑定は、申立書類として提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に依頼して行われ、鑑定が必要かどうか判断するのは裁判官です。
鑑定や調査の後、家庭裁判所により成年後見等の開始の審判が行われます。
家庭裁判所では、成年後見等の開始の審判がされるとともに、成年後見人等や必要に応じて監督人の選任も行われます。保佐開始や補助開始の場合には、同意権や代理権も定められます。
審判の内容の通知は書面です。本人や申立人、成年後見人等に(審判書)知らされます。
審判に不服がある場合、申立人や利害関係人は書面が届いてから 2 週間以内に不服申立てを行うことができます。しかし、成年後見人等の人物について不服申立てを行うことはできません。
また、2週間以内に不服申立てが行われない場合は、審判の内容が確定します。
後見等開始の審判が確定すると行われるのが、家庭裁判所から東京法務局に審判内容の登記依頼です。2週間程度で後見等登記の手続きが完了し、成年後見人あてに登記番号が記載された「登記番号通知書」が送付されます。
その後は、東京法務局の後見登録課や全国の法務局・地方法務局の本局で登記事項証明書を取得できるようになります(申請書に登記番号を記入する欄があるため、申請には登記番号が必要です)。
なお、後見等について戸籍に記載されることはありません。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

成年後見人に関する登記は、誰もが閲覧できるわけではありません。
誰でも閲覧できるとなると、個人のプライバシーがないがしろにされるためです。
成年後見登記の閲覧ができるのは、以下に該当する者です。
本来、登記は誰でも閲覧できるのが原則です。
不動産登記も商業登記も、閲覧者に限定はありません。
情報を第三者に公示し、取引の円滑化を目指すのが登記制度だからです。
しかし成年後見登記に関しては、例外的に閲覧者が限定されます。
閲覧者を限定しないと、プライバシーの公開を嫌い、成年後見制度の利用を控える人がでてくるためです。

成年後見人等の登記に関する証明書には、後見開始前は「登記されていないことの証明書」後見開始後は「登記事項証明書」があります。これらの証明書を準備する場合、どこに請求すれば良いのでしょうか。
ここでは、成年後見人等の登記に関する証明書の申請方法や必要書類、証明書手数料について解説します。
成年後見登記事項証明書の取得手段は、3つあります。
法務局の窓口で取得する場合、支局や出張所では扱っていないため注意が必要です。
郵送を利用する際の送り先は、次のとおりです。
〒102-8266東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課
オンラインを希望する方は、法務省のサイトを参考にしてください。
成年後見登記事項証明書の種類は、次の6つです。
成年後見登記事項証明書は、成年後見制度の類型ごとに発行されます。
ただし任意後見制度は、任意後見監督人の選任前と選任後で、登記事項証明書の種類が異なります。
なお、登記されてないことの証明書は、自らが被成年後見人等でない旨を証明する際に発行するのが一般的です。
後見等開始の審判の申し立てをする際には様々な書類が必要です。その中に「登記されていないことの証明書」があります。
「登記されていないことの証明書」は、法定後見や任意後見を受けていないことを証明するための書類です。同一人について重複して後見手続が行われないようにする趣旨です。
申請の際には、法務局の窓口やホームページで申請書を取得し、必要事項を記入して東京法務局の後見登録課や全国の法務局・地方法務局の本局に提出します。
なお、証明書手数料は、紙の証明書は1通につき300円(窓口・郵送・オンライン請求)、電子データの証明書は1通につき240円(オンライン請求)が必要です。郵送やオンライン請求は、東京法務局後見登録課でのみ取り扱っています。
次に、後見開始後の登記事項証明書の申請方法について解説します。
登記事項証明書は、成年後見人等が本人(成年被後見人等)のために代理で手続きする場合などに必要となる書類です。
例えば、本人の代わりに成年後見人等が賃貸契約を締結する場合、相手方に本人の代わりに契約できる権利を有することを証明する必要があります。
登記事項証明書はそのような時に、成年後見人等が法律上正当な立場であることを証明するものであり、実際に本人を保護・支援するための重要な書類となります。
申請は本人(被後見人等)、後見人、後見監督人などの当事者や本人の配偶者、四親等内の親族、委任を受けた代理人などが申請可能です。
申請書の提出方法や提出先は、前述の登記されていないことの証明書の場合と同じです。
登記手数料は窓口や郵送による請求よりもオンライン請求のほうが割安になります。窓口や郵送で申請する場合は550円、紙の証明書(オンライン請求)は380円、電子データの証明書(オンライン請求)は320円となっています。
成年後見登記事項証明書の申請における必要書類は、誰が申請するかで異なります。
申請対象となりえるのは、次の3者です。
上記の他、郵送で申請する方は、返信用封筒も必要です。
申請者が個人でなく法人である場合は、代表者事項証明書(発行から3カ月以内)も、追加で求められます。
なお、本人確認書類の具体例は、次のとおりです。
郵送で申請する場合は、本人確認書類は写しでも構いません。
列挙した本人確認書類を用意できない場合は、法務局に問い合わせてみてください。代替の書類を案内してもらえる可能性があります。
成年後見登記に関する証明書(登記事項証明書や登記されていないことの証明書)の申請方法の詳細については前述したとおりですが、証明書を取得する際の注意点があります。
ここでは、注意点としてマイナンバーカードが必要になるケースと証明書の有効期限について解説します。
証明書(登記事項証明書や登記されていないことの証明書)の申請や変更登記・終了登記については、インターネットにより登記・供託オンライン申請システムを利用して手続きすることができます。
ただし、証明書の交付請求については、申請の公的個人認証サービスを利用できるマイナンバーカードが必要です。
なお、窓口や郵送による方法と比べるとオンライン申請の手数料は割安に設定されています。
証明書(登記事項証明書や登記されていないことの証明書)の有効期限について、特に規定はありません。ただし、証明書の提出先によって、発行から一定期間内(発行から3カ月以内など)の証明書という条件が付けられることがあります。
また、紙の証明書の提出を求められる場合が多く、電子データの証明書でも対応が可能かどうかは提出先によって異なります。
そのため、証明書を申請する前に、提出先に詳細を確認しておくと良いでしょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
前述のとおり、後見等開始の審判の際には家庭裁判所から法務局への依頼により登記が行われます。
一方、登記内容を変更する場合や本人の保護・支援を終了する場合は、成年後見人等や本人の親族が登記の申請をしなければなりません。
ここでは、変更登記や終了登記の手続きについて解説します。
変更登記は次のような場合に必要です。
変更登記をする場合には、変更登記申請書と変更内容に応じた書類を添付して、東京法務局後見登録課の窓口へ提出または郵送で申請します(東京法務局後見登録課のみで取り扱っています)。
なお、変更登記は成年後見人等だけでなく、本人(成年被後見人等)の四親等内の親族や利害関係者が申請することもできます。
一方、終了登記は次のような場合に必要です。
終了登記をする場合には、終了登記申請書と後見等終了の原因となった事項を証明する書類を東京法務局に提出します。
変更登記と同様、申請は東京法務局後見登録課の窓口に直接提出するか、郵送するかのどちらかとなります。終了登記は、成年後見人等だけでなく、本人(成年被後見人等)の四親等内親族や利害関係人が申請することもできます。

ここでは、成年後見後見人の登記に関係する費用についてまとめます。
変更登記の申請と終了登記の申請がありますが、費用が発生するのは、変更登記のみです。
変更登記の申請には、1,400円分の収入印紙が必要です。終了登記の申請には費用はかかりません。
ただし、変更登記、終了登記ともに、申請には必要書類の添付が必要です。必要書類の取得費用は、自己負担となります。
変更登記について
| 必要書類 | 必要書類の取得費用(1通) | |
|---|---|---|
| 住所変更 | 住民票の写し or 戸籍の附票 | 200~300円 300円 |
| 氏名・本籍変更 | 戸籍謄本の原本 | 450円 |
| 成年後見人の死亡 | 戸籍謄抄本 or 死亡診断書 | 450円 2,000円~1万円程度 |
終了登記について
| 必要書類 | 必要書類の取得費用(1通) | |
|---|---|---|
| 被後見人の死亡 | 戸籍謄抄本 or 死亡診断書 | 450円 2,000円~1万円程度 |
なお、成年後見の登記で当事者の申請が求められるのは、変更・終了の登記のみです。後見開始の登記は裁判所の嘱託によってされるため、申請そのものが不要であり、費用は問題になりません。
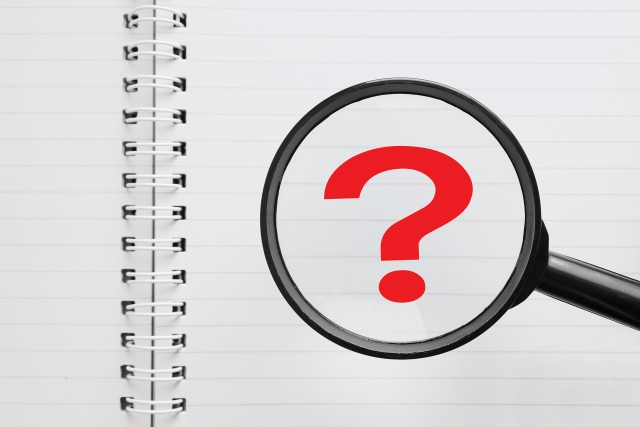
ここでは、成年後見制度の登記に関して、よくある質問に回答します。
成年後見制度利用の事実は、登記に登録されます。しかし、戸籍には登録されません。
過去、成年後見制度利用の事実は、戸籍に登録されていました。
しかし現在、本人のプライバシーが考慮された結果、戸籍への登録は廃止されています。
戸籍ではなく登記への記録により、プライバシーが守られ、成年後見制度がより使いやすくなりました。
登記事項証明書は、成年後見人が、本人に代わり契約を締結する際に利用できます。
不動産の売買、介護施設への入所など、成年後見人が本人に代わり契約する場面があります。そのようなときに、登記事項証明書は役に立ちます。
成年後見人が、登記事項証明書を提示することで、代理権の証明が容易になるためです。
また、登記されていないことの証明書は、自らが被成年後見人でない旨を証明する際に利用可能です。
成年被後見人である事実が、法律上の欠格事由に該当する場合があります。証明書の提示で欠格事由に該当しない旨を証明できます。
成年被後見人がDVやストーカー、児童虐待などの被害をうけている場合、加害者からの登記事項証明書の交付または閲覧を拒否するよう申請できます。
申請には、申請書の提出が必要です。
申請書の記載事項は、次のとおりです。
申請書の提出先は、次のいずれかです。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。


今回の記事では、成年後見登記制度や登記事項証明書の申請方法について解説しました。
成年後見登記制度のおかげで、成年後見人と第三者との取引が円滑に進むようになっています。登記事項証明書の発行で、成年後見人の代理権限を容易に証明できるためです。
しかし、成年後見登記制度が整備されたとはいえ、成年後見制度にも限界があります。成年後見制度で、成年後見人に与えられる権限は、あくまで財産の管理に限定されるからです。
より柔軟に本人の財産を活用したい方は、家族信託も選択肢に含めると良いでしょう。家族信託は、成年後見制度では実現できない財産の利用も可能です。
家族信託が気になる方は、ぜひファミトラにご相談ください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!



家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!



PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
編集者ポリシー
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。